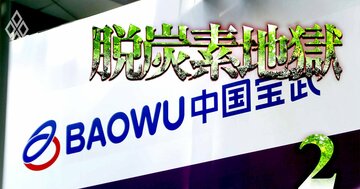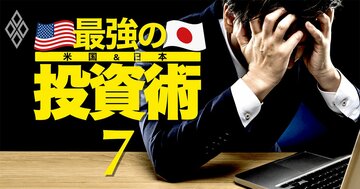写真提供:野村総合研究所、Kazutoshi Sumitomo
写真提供:野村総合研究所、Kazutoshi Sumitomo
ウィズコロナで経済が回復しつつあるが、油断は禁物だ。回復の過程には波乱が待ち受けている。特集『総予測2022』の本稿では、トップエコノミストの木内登英氏と河野龍太郎氏に2022年の波乱要因について議論してもらった。(ダイヤモンド編集部編集委員 竹田孝洋)
22年中米国でインフレが
続く公算あり
――2022年の世界経済や日本経済の波乱要因を挙げてください。
木内 一つ目は、世界、特に米国における物価の高騰です。いずれ落ち着いてくると考えていますが、長引くと景気を犠牲にして利上げをしなくてはいけなくなります。
 きうち・たかひで/1987年野村総合研究所に入社。2004年に野村證券に転籍し、07年経済調査部長兼チーフエコノミスト。12年日本銀行審議委員に就任。17年7月より現職。 写真提供:野村総合研究所
きうち・たかひで/1987年野村総合研究所に入社。2004年に野村證券に転籍し、07年経済調査部長兼チーフエコノミスト。12年日本銀行審議委員に就任。17年7月より現職。 写真提供:野村総合研究所
二つ目は、これもまた米国を中心とした金融政策の正常化です。FRB(米連邦準制度理事会)の利上げの過程で、新興国市場を混乱させるとともに、米国内ではハイイールド債や証券化商品など高リスク資産の金融市場が不安定になる懸念があります。そのとき、円高が進行し、日本にとっては逆風になります。
三つ目は中国です。中国共産党は民間企業への統制を強化しています。その一つの帰結が不動産不況です。これは世界経済に大きな影響を及ぼすと思います。
河野 波乱要因となる項目については同じ意見です。ただ、見方が少し違います。
22年中は世界的に供給制約によるインフレが続くとみています。新型コロナウイルスの変異株の登場で経済の正常化にまだ相当な時間がかかるためです。
FRBの利上げが前倒しされることで金融市場が動揺するのはその通りだと思います。コロナ感染拡大で苦境にある新興国からの資金流出が続く可能性もあります。
中国は構造政策を継続するとみられますが、これは短期の成長を犠牲にします。FRBによる超金融緩和と中国の経済成長が新興国経済をサポートしてきましたが、双方が変化することは新興国経済の下押し要因となります。
――米国のインフレ高騰はFRBを量的緩和縮小、利上げ前倒しに追い込みました。22年に入って上昇はさらに加速するのでしょうか。