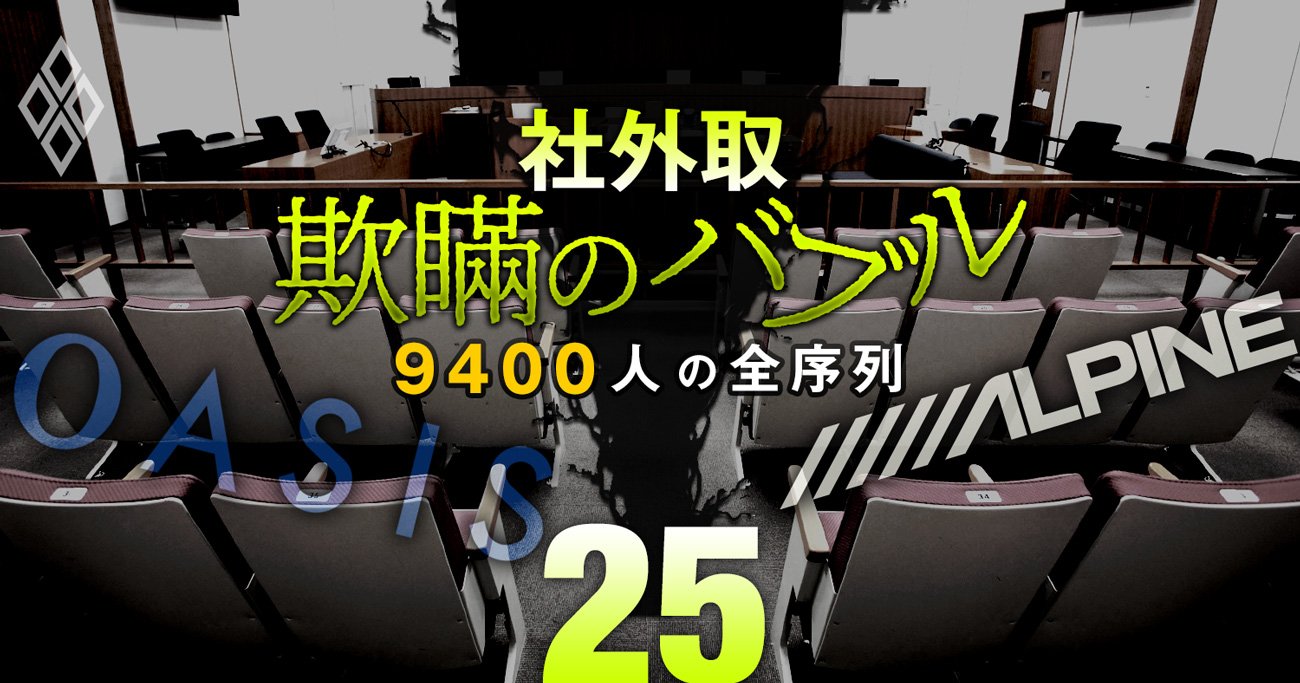 Photo:Bloomberg/gettyimages
Photo:Bloomberg/gettyimages
親子上場企業の経営統合を巡り、海外大物アクティビストと統合会社の法廷闘争が泥沼化している。アクティビスト側は少数株主を無視した姿勢を問題視する。特集『社外取「欺瞞のバブル」9400人の全序列』の#25では、親子上場企業に巣くう“追認”社外取のガバナンス不全を指摘する。実は、この訴訟は単なる「企業対投資家」の構図のゴタゴタではない。日本にある200の親子上場会社の形を変える可能性を秘めているのだ。(ジャーナリスト 大西康之)
ジリ貧の親会社が子会社と統合
“物言う株主”「少数株主を無視」
「多数決」か「少数株主」か――。
海外投資家が注目する裁判が繰り広げられている。原告は香港の「物言う投資家」オアシス・マネジメント、被告は電子部品・車載機器メーカーのアルプスアルパインだ。
「アルプス電気とアルパインが合併した際、子会社であるアルパインの企業価値が不当に低く評価され、少数株主の権利が守られなかった」というのがオアシスの主張である。
大株主である親会社が優位な立場にある上場子会社で、少数株主の利益を守るのは社外取締役の大切な役割だが、アルパインの社外取が物申した痕跡はどこにもない。
カーオーディオ、カーナビなどを手掛けるアルパインは1967年にアルプス電気と米モトローラの合弁会社として設立された。
78年に両社が合弁を解消し、その後アルパインは88年に東京証券取引所第2部に上場、91年には東証1部にくら替えしている。上場後もアルプス電気が40.4%を出資する「親子関係」にあった。
電子部品メーカーのアルプス電気が完成品メーカーのアルパインを子会社に抱える珍しいグループ構造だ。2011年上期の時点で、アルプス電気の連結営業利益73億円のうち、約半分の31億円をアルパインが稼いでいた。
孝行息子のアルパインに支えられる形で連結ベースの利益を確保してきたアルプス電気だが、財務体質では子会社に見劣りするようになっていく。
完全子会社化直前の18年3月期、アルプス電気の自己資本比率は44.8%。これに対しアルパインは70.1%。アルパインの方がはるかにキャッシュリッチだ。
事業の将来性もアルパインの方が上と見られていた。アルプス電気は家電向け電子部品が主力だったが、日本の家電メーカーが衰退する中、スマートフォン部品やゲーム部品に軸足を移した。
しかし、主力のアクチュエーターはミネベアミツミなどとの厳しい競争にさらされ、大きな成長は見込めない。
一方、アルパインのカーオーディオ、カーナビもスマホに市場を奪われているが、これらの技術は将来、自動運転やコネクテッドなど「CASE」と呼ばれる技術革新につながる可能性がある。
ジリ貧のアルプス電気は、キャッシュリッチで将来性のあるアルパインを取り込むことで延命を図ろうとした。これが19年に実施された経営統合である。問題はそのときの株式交換比率だった。
アルパインは18年12月に開いた株主総会で1:0.68の株式交換でアルプス電気の完全子会社になることを決議した。
ところが19年1月29日、両社の持ち株会社アルプスアルパインは「19年3月期の営業利益が(従来予想より)160億円少ない500億円になる」と業績予想を下方修正した。
旧アルパインの車載情報機器事業の通期の営業利益は前期比6%増の見込みだったので、下方修正分は旧アルプス電気の変調によるものだ。
これにオアシス最高投資責任者(CIO)のセス・フィッシャー氏がかみ付いた。
現在、オアシスとアルプスアルパインが激しく争う法廷闘争には注目した方がいい。なぜなら、これはアルプスアルパインに限った問題ではないからだ。
訴訟の行方によっては、また政府や東京証券取引所を巻き込んだ議論によっては、日本に200社以上ある親子上場の在り方を大きく変えていくかもしれないのだ。
次ページからは、“物言う株主”がスポットライトを当てた、株の持ち方や組織の形態、経営陣の人選から出世のメカニズムも含めたいびつな親子上場の構造とともに、物申せない“追認”するだけの社外取など関係者の実名も基に親子上場ガバナンスの問題点を明らかにする。







