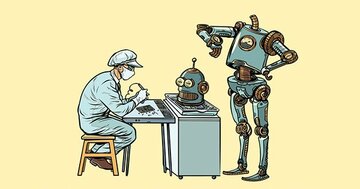ハードモードの人生から生まれた懐の深い物語
このように、『フランケンシュタイン』は、実に多様な読み方ができる物語なのだが、メアリー・シェリーは弱冠20歳(執筆開始時は18歳)でこの傑作を世に出している。彼女は一体何者なのだろうか?
ヒントの一つは彼女の出自にある。彼女の母は18世紀末に女性の権利を求めて精力的に活動し、フェミニズムの創始者の一人として有名なメアリー・ウルストンクラフト、父は社会改革を力強く訴えた無政府主義の先駆者で無神論者の作家、ウィリアム・ゴドウィンなのである。母はメアリーを出産した後すぐに亡くなるが、彼女が残した著書『女性の権利の擁護』はメアリーの幼少期からの愛読書だったという。また、自宅には父を慕う当代一流の知識人たちが多く集い、知のサロンになっていたことも彼女に知的な刺激を与えたはずだ。
その中の一人、ロマン派の詩人のパーシー・ビッシュ・シェリーと、才気煥発なメアリーは恋に落ちる……まではいいのだが、パーシーが妻帯者だったため、メアリーは10代のうちに不倫、駆け落ち、生活苦、子どもの出産と死……と、人生の辛酸をなめることになる。パーシーとは後にめでたく結婚するが、幸せもつかの間、29歳の若さで先立たれてしまう。控えめに言って、ものすごくハードモードな人生である。
『フランケンシュタイン』は、この激動の人生から生まれた。1816年の夏、18歳のメアリーはパーシーと一緒に、詩人バイロンが侍医ジョン・ポリドリと共に滞在していたスイスの別荘を訪れる。悪天候で館に閉じ込められて暇を持て余した彼らは、バイロンの発案で怪談の創作に挑む。「ディオダティ荘の怪奇談義」として文学史上のエポックになっているこの夜、メアリーは哀しい怪物の物語を着想するのだ。ちなみにポリドリもこの夜を契機にヴァンパイア小説の元祖といわれる『吸血鬼』を書き上げている。
このような簡単な紹介だけではメアリーの人物像はとても語り尽くせないが、少なくとも、彼女が若くして知性と教養を土台にした合理的な思考力と、物事をさまざまな立場から理解する深い洞察力を持ち得た背景は分かっていただけたのではないだろうか。
SFは、社会で自明とされている常識を疑い、マイノリティーの視点を大切にする文学ジャンルである――と『SF思考』で繰り返し指摘した。『フランケンシュタイン』は、まさにそうした特色を備えた良質なSFといえる。「人間とは何か」という問いは文学ではおなじみのテーマだが、メアリーはこの問いを「人間とモノはどう違うのか」「創造主と被造物はどんな関係にあるべきか」という関係性にフォーカスすることで解像度を上げた。だからこそ、200年たっても古びることなく新たな論点を提起し続ける物語になれたのではないだろうか。