
加藤嘉一
第1回
人々は往々にして、簡単に「中国」と「民主化」という二つの言葉をくっつけて語ろうとする。しかし、「中国の民主化」とはどういうことなのだろうか。本連載は、人々が陥りがちな“希望的観測”や“制度的優越感”を可能な限り排除したうえで、検証していく。
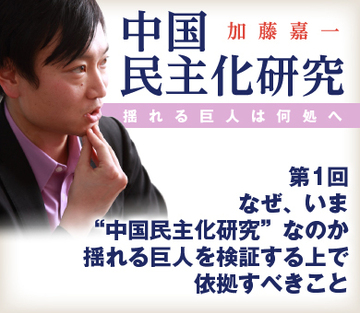
第20回
香川真司選手が試合後に残した“悔しさと楽しさが入り混じった”笑みと“現実を知りました”という言葉の意味が、私には痛いほどよく分かる。祖国を飛び出して10年、私も香川選手と同じような感覚を、何度も味わってきたからだ。

第19回
人生二度目のイギリス訪問となった今回は、昨年度に引き続きロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで開催される中国関連の学術フォーラムに、スピーカー、パネリストとして出席することが主目的であった。

第18回
オバマ大統領の演説を生で聞いたのは初めてのことだった。歯切れの良さ、強弱のつけ方、トーンの上げ方・抑え方、聞いている人を巻き込む力……、すべてが洗練されていた。私はただ立ちつくし、前方にいるオバマ大統領の勇姿を見つめるばかりだった。

第17回
1月15日正午、米シカゴ、オヘア空港から電車に乗る。これからあと4年間、同氏はアメリカ合衆国の大統領として国をリードすることになる。そんなオバマ氏の足跡を遡るために、私はこの場所へ来た。

第16回
成人式を迎えられた皆さん、おめでとうございます。これを一つの節目と能動的に認識し、益々ご健勝いただければと、一人の日本国民として願っています。自らの経験を踏まえ、語ること通じて、新成人となる皆さんと8つの言葉を共有したい。

第15回
年末年始は、私にとって1年の間で最も静かに過ごす時間である。人には会わず、話もしない。ただひたすら座禅を組み、坂道ダッシュをするか読書に励み、疲れてきたらまた座禅に戻る。こうして1年を振り返り、これからの1年に挑んでいくための気力と体力を養う。

第14回
今回は2012年最後の原稿となる。「加藤さんの通信簿をつけてみましょう」というキャプテンからの要望に応じる形で、自分なりに5(満足)、4(納得)、3(次第点・合格)、2(まだまだ)、1(問題外)という基準で採点してみたい。

第13回
今回の衆議院選挙は、「日本版価値観という生き方」を模索するためのプロセス、即ち、日本人自身が、どういう社会を求め、どういう生活を欲し、どういう世界を築いていくかというテーマに対して、答えを探していく過程であると思う。

第12回
12月5日、米経済誌「フォーブス」が「世界で最も影響力のある人物」の番付を発表した。我が祖国、日本のリーダー野田佳彦首相は60位だった。世界第三の経済大国に符合しない地位にある現状は否定できない。
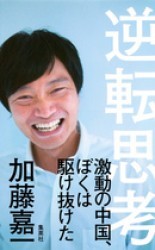
第11回
ここ数日間、ハーバード大学、マサチュッセツ工科大学、タフツ大学の三大学で、日本の政治・経済を専門とする、或いは東アジアの国際関係から日本の外交的、安全保障的プレゼンスをウォッチしている複数の教授と議論してきた。
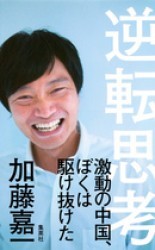
第10回
「Regional Studies(地域研究)をもっとしっかりやらないといけない」。最近、日本と米国を代表する中国問題研究家それぞれから、同じ問題意識をご教授いただいた。中国を多角的、立体的、重層的なアプローチで分析することが必要になるのは言うまでもない。

第9回
「日本は素晴らしい国だ」。先日もこの言葉をかけられ、身震いした。日本・日本人に対する同情である。世界は日本を「何がしたいのか分からない国」だと見ている。この状況をどうすれば変えられるのだろうか。私は3つの力が必要だと思っている。

第8回
11月6日、火曜日、朝7時――。米ボストンの自宅玄関を出る。投票所が閉まるのは20時だ。身は寒さで震えている。気温は5度くらいだろうか。これから13時間にわたって繰り広げられる米大統領選挙の現場をこの眼に焼き付けておきたかった。

第7回
10月16日~23日、尖閣諸島に関する国際会議に出席するために台湾を訪れた。今、尖閣諸島をめぐる攻防が北東アジアで繰り広げられており、関係各国の領土ナショナリズムも高揚している。私は緊張感を持って台湾に降り立った。

第6回
アジア出張が多い私にとって、北京を拠点としていた頃に比べて、今は移動により長い時間がかかるし、時差もある。アジアはボストンとの時差が約12時間、全く逆ということだ。自己管理を徹底するだけでなく、柔軟に対応していく器用さも求められる。

第5回
ケネディースクールには世界各国から学生が学びに来ている。皆、公共政策に関心を抱き、教室やキャンパス内で、とにかく意見を主張しまくる。他人の主張にも耳を傾ける。そこには、「徹底的に議論すること」が唯一の使命であるかのような空気が漂っている。

第4回
マイケル・サンデル ハーバード大学教授は渡米前からぜひ会ってみたい人だった。今回、幸運にも生の講義を聴講する機会を得た。テーマは「Who Built It? Is the American Dream of Individual Success a Myth?」(「個々の成功というアメリカンドリームは神話なのか? 一体誰が、何がそれを創っているのか」)である。

第3回
私は、語学にはこだわっている。誰にも、特に自分には負けたくない。今回、約10年間過ごした中国を離れ、アメリカで一定期間生活してみようと思った理由のひとつに、己の語学力を根本から見つめ直してみたいという昔からの渇望があった。

第2回
太平洋の向こう側が荒れている。私は現在、米ボストンに身を置いている。「真実はいつも現場にある」をモットーに執筆・言論活動に取り組んできた人間として、いまの自分の置かれた状況は、とてつもなく歯がゆい。
