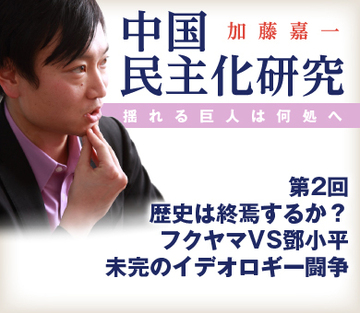加藤嘉一
第19回
M氏との北京での対話で氏が「習仲勲を祝う真の目的は胡耀邦の歴史的地位を復活させるため」だと述べたことは前回述べた。加えてM氏は、「トウ小平の歴史的地位を“総括”することが真の目的だ」と話した。この言葉に、私は興奮せざるを得なかった。
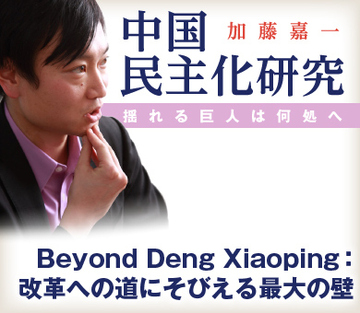
第18回
10月、中国では習近平の実親である習仲勲の生誕百周年を大々的に祝っていた。一部から習近平の実親をあからさまに持ち上げたことを「権威主義的だ」と懸念する声が上がった。しかし、真の目的は他にあると、ある共産党幹部が話してくれた。
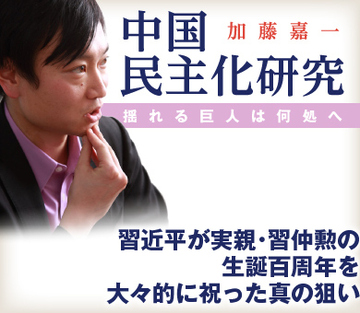
第17回
11月9〜12日、中国共産党第十八期中央委員会第三回全体会議(三中全会)が北京で開催された。国家リーダーが変わる党大会が実施された後の三中全会は、どのような政策を打ち出そうとしているのかを占う上で、極めて重要な会議とされてきた。
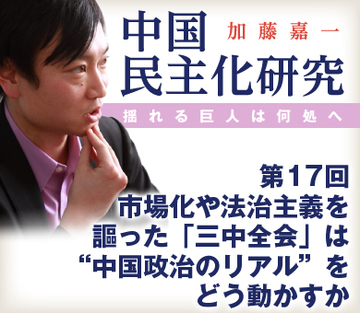
第16回
前回コラムでは、習近平総書記率いる共産党指導部は、工農階級の権益を優先的に守ろうとする「革命党」だと述べた。本稿では、前回に引き続き、銭教授の論考を引用しながら、“紅老衛兵”たちの価値観や行動規範を具体的に検証していきたい。
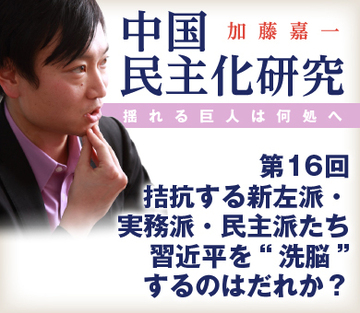
第15回
「永遠に党についていく」。このような文言がいま、北京の街に溢れている。常務委員入りした劉雲山氏の、党の威信を高める「群衆路線教育実践活動」のためだ。そしてこれは党の先進性と純潔性を訴えるプロパガンダとして機能している。
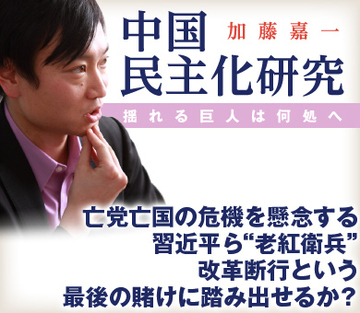
第14回
中国の将来を考えるとき、中国共産党自身がどのような自己改革を実現していくかがキーポイントになると、私は考えてきた。しかし、中国共産党はいまだに「工農階級」を代表するという、昔のままの統治理念を掲げたまま、今日に至っている。
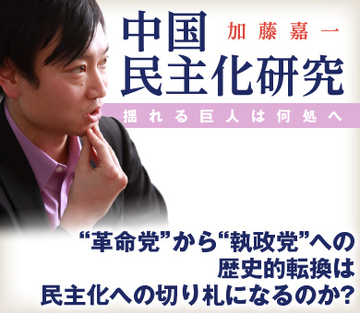
第3回
尖閣を買ってくれた野田首相に感謝する――。中国公安部のある幹部が私にこう語った。そこには反日のニュアンスは感じられず、起こってしまった危機から何を得るかという残酷なまでに強かな姿勢だった。一方のわれわれ日本人は、何を学ぶべきなのだろうか。
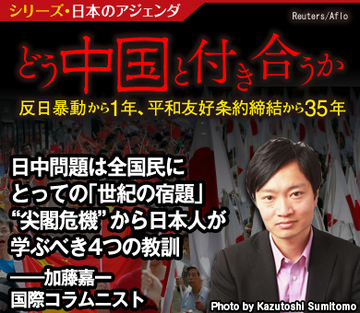
第13回
“薄煕来事件”は習近平政権が展開する「反腐敗闘争」の一環として処理し、法治主義が成熟してきていることのプロパガンダとして利用された。なぜ共産党指導部は「反腐敗闘争」を大々的に展開するのか、そして、それは「中国民主化」を促すのだろうか。
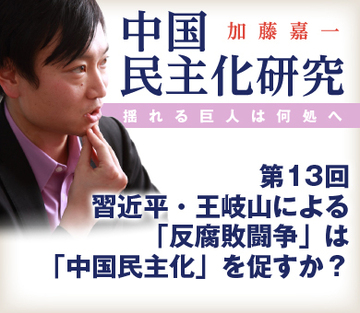
第12回
党籍も含めたすべての政治的地位を失い、完全失脚に追い込まれた薄煕来氏。しかし、今でも社会的弱者からの薄煕来支持は根強く残る。薄煕来氏によって揺れる中国共産党と中国社会。民主化へはどのような影響があるのだろうか。
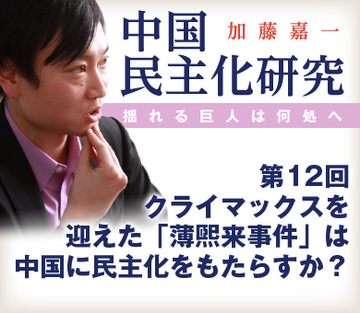
第11回
前回コラムで詳述したように、中国共産党指導部が“工農階級”の欲求ばかりに迎合し、“中産階級”の真っ当な権益を軽視しる現状は、民主化という観点からはネガティブと言わざるを得ない。本稿では、“共産党”と“民主化”の相関性を考えてみたい。
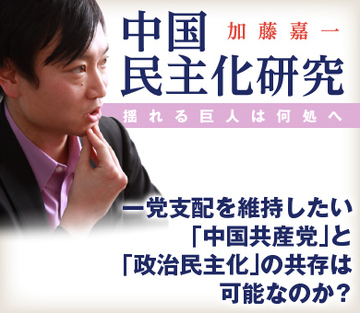
第10回
2003年当時、北京大学から国貿という北京で最も発展している場所まで地下鉄で行くのには約1時間半を要した。しかし今は約70分。料金は5元から2元に値下げされた。なぜか?ここには、中国社会が抱える伝統的なロジックが隠されている。
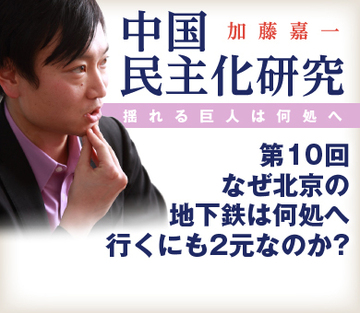
第9回
3月17日、北京人民大会堂。李克強氏は国務院総理として初めて国内外の記者の前に姿を現し、自ら記者会見を主催した。記者会見における李克強氏のパフォーマンスはダイナミック、且つ確かな理論武装に裏打ちされた、切れ味の鋭いものであった。
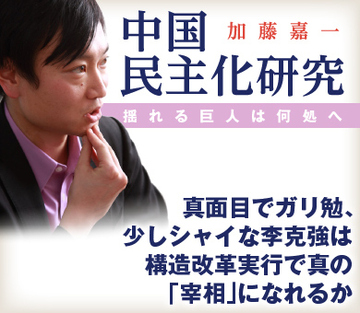
第8回
習近平総書記の口から出てきたスローガン、「中国夢」(チャイニーズドリーム)。「中国夢」は習近平・李克強政権がこれからの10年間で最重要視すべき「公正」というファクターを促進するのか、或いは阻害してしまうのか。
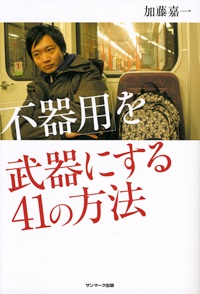
第7回
「安定、成長、公正、人権」という優先順位をつけ、政策を実行し、党をガバナンスし、国家を統治した胡錦濤氏。襷を受け取った習近平氏は、これからの10年間、安定・成長・公正・人権という4つの軸をどのようにリバランスしていくのだろうか。
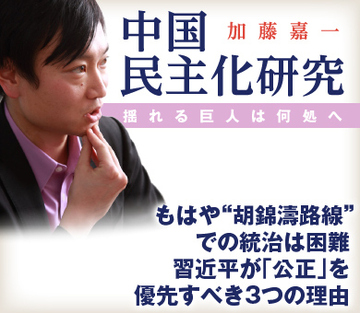
第6回
政府は人民から何らかの「信任」を得なければならない。中国では、その信任が「ガバナンスにおける結果・業績」に相当する。胡錦濤・習近平の20年間は、少なくとも4つの要素が「信任状」を理解するための軸になると考える。
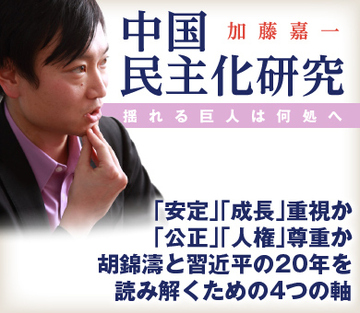
第438回
先週末、米カリフォルニア州サニーランドで、2日間にわたってオバマ米大統領と習近平国家主席による米中首脳会談が行なわれた。両国リーダーによる会談は、今後の世界情勢を見通すうえで、極めて大きなインパクトを持つ。

第5回
「現代政治システムとかけ離れた中国政治は、今後“良いリーダー”を提供し続けることは可能なのか?」これは今回は本連載で度々取り上げてきたフランシス・フクヤマ氏が最新の著書の最終ページ提起した問題である。今回はこの点について考えていきたい。
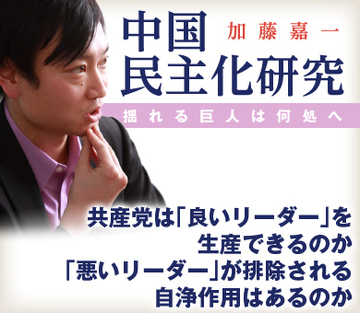
第4回
本連載では政治学者フランシス・フクヤマ氏の学説に言及してきた。今回、フクヤマ氏が「現代政治システム」構築の必要十分条件として掲げる3つの要素が昨今の中国社会でどのように機能しているのかを考えてみたい。
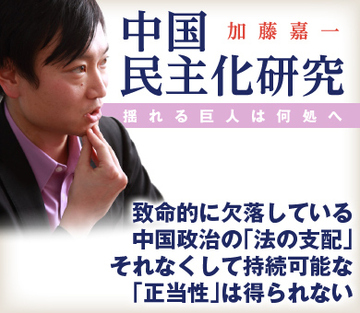
第3回
2012年10月、かつて「共産中国の崩壊」を説いたフランシス・フクヤマ氏の『政治秩序的起源—従前人類時代到法国大革命』(広西師範大学出版社)が中国共産党18党大会が開催される直前に出版された。これは、何を意味しているのか?
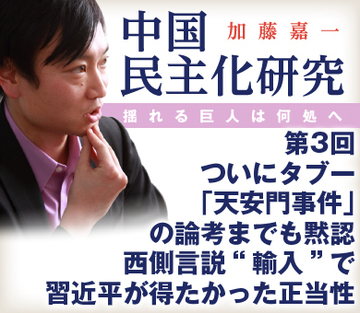
第2回
政治学者のフランシス・フクヤマ氏は1989年に『The End of History』(歴史の終焉)という論文を執筆し、1992年には『The End of History and the Last Man』を出版した。1989~1992年と言えば、国際政治システムを歴史的変化が襲った時期である。