トヨタ自動車
関連ニュース
予告
トヨタ・ソニーEV参戦が呼び水、戦略物資に豹変した「半導体&電池」争奪ゲームの内幕
ダイヤモンド編集部
脱炭素とデジタルトランスフォーメーション(DX)という産業界のメガトレンドに米中対立の激化も相まって、主要国・地域による半導体と電気自動車(EV)向け車載電池の争奪戦は熾烈を極めている。半導体とEV電池は、グローバル競争を勝ち抜く上で不可欠の「戦略物資」となったのだ。くしくも産業界で半導体不足が表面化する中、日本政府は台湾TSMCの半導体工場の誘致に成功した。トヨタ自動車のEV大攻勢に続き、異業種のソニーグループがEV参入を決めるなど、EV電池の投資競争はさらに加速することは間違いない。1月17日から配信の特集『戦略物質 半導体&EV電池』では、産業競争と経済安全保障という二つの側面から、戦略物資としての価値を高める半導体とEV電池の最前線の動きを追った。

予告
日本企業が悶絶するインフレ2022、資源高と悪い円安が招く「コスト上昇ラッシュ」の惨状
ダイヤモンド編集部
鉄鋼、原油、銅、小麦……。ありとあらゆる資源が、世界で高騰している。そこに追い打ちをかけるのが円安による日本の「買う力」の低下だ。グローバルインフレと円安の中で、日本企業がいかに呻吟しているかをレポートする。

トヨタと三菱商事も乱入!東電・ENEOS・東京ガスが戦々恐々「再エネ争奪戦2022」
ダイヤモンド編集部,堀内 亮
脱炭素を実現するために、ありとあらゆる企業が環境に優しい「グリーンエネルギー」を欲しがっている。電力、ガス、石油元売りといったエネルギー企業にとって、異業種とのグリーンエネルギー争奪戦を勝ち抜けるかどうかが2022年の命運を決することになりそうだ。

日本を襲う想定外の「新型インフレ」、29業種の資源高リスク
新村直弘
世界経済が新型コロナウイルスの猛威から回復する中で表面化した資源高。その構造を読み解くと、日本がこれまで想定していなかった“新型”インフレへの「扉」が開いた可能性がある。

中国ロックダウンで混乱、世界供給網に再び打撃
The Wall Street Journal
中国全土でのコロナ感染拡大を受け、主要メーカーの工場閉鎖や港湾施設での滞留、労働者の不足といった問題が相次いでいる。

日本製鉄、トヨタに強気の“反撃“で号砲!鉄鋼3社2022年「値上げ」レース
ダイヤモンド編集部,新井美江子
2021年は鉄鋼業界にとって、「顧客優位、鉄鋼劣位」の関係を覆すための“反撃開始”の年となった。中でも最大の取り組みが鋼材価格の値上げであり、22年も引き続きタフな価格交渉は続く。まさに、顧客と対等な取引関係を奪還するための正念場となるが、鉄鋼3社は一様に値上げを実現できるわけではなさそうだ。

ジャスト・イン・タイム神話が崩壊?2022年のサプライチェーン予測
坂口孝則
2021年のサプライチェーンは、世界の景気高揚によって需要が急増し、半導体や部材などの入手が困難になった。自動車やゲーム機などが市場に供給できなくなり、サプライチェーンが注目された。本稿では21年のサプライチェーンを振り返りつつ、22年のサプライチェーンの課題を予測する。

日立・ソニー・三菱“常勝の構図”に異変!電機7社、2022年は「成長投資格差」が鮮明に
ダイヤモンド編集部,千本木啓文
日系電機メーカーにとって2021年は、勝ち組と負け組の分岐点といえる年だった。22年以降は、リスクを取って成長投資を行ったかどうかで企業の明暗が分かれるだろう。電機業界では事業ポートフォリオを早めに入れ替えた日立製作所やソニーグループ、三菱電機が優等生とされてきたが、それらの企業にも“異変”が起きている。東芝、NEC、富士通も含めた電機業界における真の勝者・敗者を明らかにする。

20業界天気予報、2022年は自動車・航空・製薬・ビールにリストラの嵐!?再編・業績は?
ダイヤモンド編集部
2022年の主要20業界の天気予報はどうなりそうなのか。ダイヤモンド編集部の担当記者が、リストラ実行度、再編機運、業績の「三大指標」を目安に業界の行方を大予想。22年に浮き上がる業界と沈む業界を大胆に先読みした。
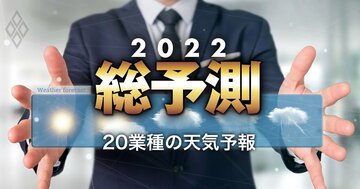
トヨタがEV大攻勢でも、2022年は「ガソリン車大増産」が自動車産業の主戦場になる理由
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
2021年の自動車産業は電気自動車(EV)一色だったといっていい。世界の主要自動車メーカーはこぞって強気なEV投入計画をぶち上げており、その極めつきはトヨタ自動車のEV大投資計画である。ところが22年の自動車業界では、早くも「EV一辺倒からの揺り戻し」が起きそうな気配になっている。その理由はどこにあるのか。22年の自動車業界の明暗を分ける鍵を大胆に解説していこう。

日本企業の生死を分ける2022年「8大潮流」、脱炭素揺り戻し・半導体欠乏・デジタル敗戦…
ダイヤモンド編集部
主要国では、ウィズコロナ時代の「エネルギー・技術」覇権争いが活発化しています。コロナ変異株の状況、脱炭素バブル、世界の保護主義化、デジタルの社会実装――。世の中を左右する“変数”が多く不透明な時代にこそ、ビジネスパーソンには「着眼大局、着手小局」の実践が求められることになりそうです。ビジネスの「大きな潮流」を把握しておけば、仕事やキャリアに生かせる具体的な戦術が立てやすくなるはず。日本企業を動かす「8つの潮流」についてダイヤモンド編集部の業界担当記者が徹底解説します。
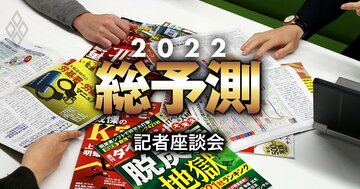
トヨタ「ランドクルーザー」がフルモデルチェンジ!世界中で高い人気を誇る理由
Esquire
世界中で高い人気を誇るトヨタ「ランドクルーザー」が、パワーアップして帰ってきました。今回、そのパワフルな雄姿をご覧いただきながら、その魅力をお伝えいたします。

マツダが9月販売台数「半減」の緊急事態、実はさらに深刻な実態とは
ダイヤモンド・アナリティクスチーム,加藤桃子
コロナ禍から企業が復活するのは一体、いつになるのだろうか。上場100社超、30業界を上回る月次業績データをつぶさに見ると、企業の再起力において明暗がはっきりと分かれている。前年同期と比べた月次業績データの推移から、6つの天気図で各社がいま置かれた状況を明らかにする。今回は、2021年7~9月度の自動車編だ。

日本脱落と米中覇権争い、時価総額「トップ100」企業が示すビジネスの主役
野口悠紀雄
株価時価総額ランキングが示すのは、ビジネスモデルを変えていかない限り企業価値は上がらないことだ。90年代に世界をリードした企業は消え、ファブレスや無人企業、どの産業にも分類できない企業が上位を占める。

トヨタ系サプライヤーで明暗、デンソーは減収なのに豊田織機は2割超増収のなぜ
ダイヤモンド・アナリティクスチーム,笠原里穂
コロナ禍からの企業業績の回復は、勝ち組と負け組の格差が拡大して「K字型」に引き裂かれていくという二極化の議論が強まっている。そこで、上場企業が発表した直近四半期の決算における売上高を前年同期と比べ、各業界の主要企業が置かれた状況を分析した。今回はデンソーやブリヂストンなどの「自動車部品/産業車両」業界5社について解説する。

トヨタが強気のEV新戦略を発表、わずか半年で目標を引き上げた理由
佃 義夫
トヨタが2030年にバッテリーEVを350万台販売するという新戦略を発表した。これまで同社はEV否定派というレッテルを貼られていたが、強気の目標を立てることでそのイメージを払拭したい考えだ。

イーロン・マスクがテスラ株を1兆円も手放せる「カラクリ」とは?
竹内一正
米電気自動車企業テスラのCEOであるイーロン・マスクが、今年の11月からテスラ株を次々と手放すニュースが世界中で話題になった。11月24日まででその売却総額は約100億ドル。日本円にして約1兆1300億円に上る。そんなとんでもないことができる背景には、テスラのCEO報酬制度があった。イーロン・マスクについての著書を数多く執筆する経営コンサルタントの竹内一正氏がくわしく解説する。

トヨタC-HR、スタイルとスポーティな走りを楽しめる「異端」のSUV【試乗記】
CAR and DRIVER
C-HRは、コンパクトSUVの人気が高まりはじめた2010年代前半、他メーカーにはない個性的なデザインと、欧州でも通用する走行性能を兼ね備えた、独自の世界戦略クロスオーバーを生み出そうという企画から始まった。最初に披露されたコンセプトモデルから雰囲気を変えることなく市販車に仕上げた容姿は、登場から間もなく5年を迎える現在でも目を引く。

トヨタ・日産は四半期増収でも「調達難とコロナ打撃」の厳しい実態、コロナ前比で判明
ダイヤモンド・アナリティクスチーム,笠原里穂
コロナ禍からの企業業績の回復は、勝ち組と負け組の格差が拡大して「K字型」に引き裂かれていくという二極化の議論が強まっている。そこで、上場企業が発表した直近四半期の決算における売上高を前年同期と比べ、各業界の主要企業が置かれた状況を分析した。今回はトヨタ自動車、ホンダなどの「自動車」業界5社について解説する。

EV不毛の地ニッポンで「トヨタのEVシフト」は本物なのか?
鈴木貴博
これまで自動車のEV化について「後ろ向き」だと批判されてきたトヨタが、「EVへの巨額投資にかじを切った」と報道されました。豊田章男社長は「これでもEVに前向きでないと言われるなら、どうすればご評価いただけるのか」と胸を張られていましたが、このトヨタのEVシフト、本当に評価できるのかどうかを検証してみたいと思います。
