記事検索
「数学」の検索結果:1481-1500/2840件
#16
2021年入試の“大イベント”だった、センター試験から共通テストへの移行。実際の試験問題の傾向や難易度はどうだったのか。初年度に出題された内容を分析し、2年目となる来年の傾向を読み解く。

【中学受験への道】第106回
首都圏「私立中高一貫校」のICT教育の現状、全121校をリサーチ
英語など語学力も含む「国際教育」と並んで保護者の関心が高いのがデータサイエンスをはじめとしたICT関連の能力を身に付けるための「情報教育」である。首都圏私立中高一貫校121校から寄せられたアンケート結果も交えながら、中高一貫教育のメリットを生かしたカリキュラムがあるのかなど、志望校選びのチェックポイントを見ていこう。

#14
実力・人気共に国内トップ私立大学群である「早慶上理」(早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学)を五つの独自指標で徹底比較!偏差値だけでは分からない“序列”の実態に迫る。

#12
1986年、奈良県に開校した西大和学園は、東大・京大合格者数を急増させて片田舎の無名校から一気に全国レベルの有名進学校に上り詰めた。同学園が運営する大和大学は2014年に開学。20年には大学院を持たない稀有な理工学部を設置した。西大和学園創始者で大和大学学長の田野瀬良太郎・元衆議院議員にその野望を聞いた。

【スポーツ・音楽・タバコ】産業を「大きい順」に並べられますか?
人々を熱狂させる未来を“先取り”し続けてきた「音楽」に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだという経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽やアーティストの分析を通じて、ビジネスや人生を切り開くための道を探った一冊だ。バラク・オバマ元米国大統領も、この「ロックな経済学(ROCKONOMICS)」というコンセプトに強い関心を示しており、本書に熱い絶賛コメントを寄せているという。本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

第14回
“昭和の街”として甦った西武園ゆうえんちに刀が吹き込んだ“持続可能な仕組み”
2020年に開業70周年を迎えた西武園ゆうえんちは、「心あたたまる幸福感に包まれる世界」をコンセプトにリニューアル工事を進めてきた。そして2021年5月19日、ついにグランドオープンを迎えた。コロナ禍にもかかわらず、客足は予想を上回り好調だという。リニューアルを指揮したのは、USJを再建したことで知られる森岡毅氏率いる株式会社 刀である。『苦しかったときの話をしようか』などの著者としても知られる森岡氏は、西武園ゆうえんちをどうやって立て直そうとしているのか? そこには刀ならではの知恵が散りばめられていた。

GDP0.1%以下の規模で世界を動かす「史上最高の娯楽ビジネス」とは?
人々を熱狂させる未来を“先取り”し続けてきた「音楽」に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだという経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽やアーティストの分析を通じて、ビジネスや人生を切り開くための道を探った一冊だ。バラク・オバマ元米国大統領も、この「ロックな経済学(ROCKONOMICS)」というコンセプトに強い関心を示しており、本書に熱い絶賛コメントを寄せているという。本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

#7
コロナ禍で行われた2021年入試は少子化、学習の進捗遅れや感染拡大地域を敬遠する動き、経済的な問題、そして共通テスト初年度……さまざまな要因が複雑に絡み合い、異例ずくめのものとなった。特に早稲田大学の看板である政治経済学部や国際教養学部、青山学院大学の国際政治経済学部などの志願者数激減は耳目を集めた。来年もこの流れは続くのか?21年入試から、22年入試の必勝法を探る。
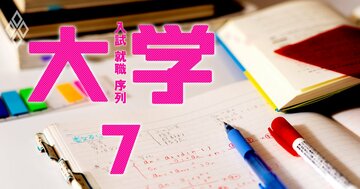
「モノ」より「体験」で儲けるコツは、ロック音楽が教えてくれる
不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”し続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽やアーティストの分析を通じて、ビジネスや人生を切り開くための道を探った一冊だ。バラク・オバマ元米国大統領も、この「ロックな経済学(ROCKONOMICS)」というコンセプトに強い関心を示しており、本書に熱い絶賛コメントを寄せているという。本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

ネットフリックス、アマゾンから予想される「音楽ビジネス」の未来とは?
不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”し続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽やアーティストの分析を通じて、ビジネスや人生を切り開くための道を探った一冊だ。バラク・オバマ元米国大統領も、この「ロックな経済学(ROCKONOMICS)」というコンセプトに強い関心を示しており、本書に熱い絶賛コメントを寄せているという。本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

#6
量子コンピューターのクラウド公開をきっかけに興味を持ち、「量子星占い」という自作アプリを開発したエンジニアが、東京大学の量子コンピューター研究室の技官に転身した。本人の意志があれば、誰でも量子エリートに成り上がれる時代が到来した。
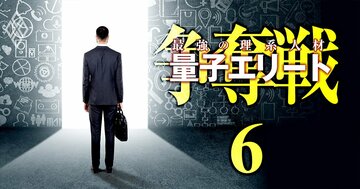
「ストリーミング」が経済にとって最高の実験室だと言えるワケ
不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”し続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽やアーティストの分析を通じて、ビジネスや人生を切り開くための道を探った一冊だ。バラク・オバマ元米国大統領も、この「ロックな経済学(ROCKONOMICS)」というコンセプトに強い関心を示しており、本書に熱い絶賛コメントを寄せているという。本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

「週刊ヤングジャンプ」での連載開始から15年、圧倒的な人気を誇る歴史漫画『キングダム』。テレビアニメ化、実写映画化され、最新61巻までの累計発行部数は、8000万部(電子版を含む)を突破している。6月12日から「上野の森美術館」で開催される『キングダム展-信-』を前に、作者である原泰久氏にインタビューすると、大学時代、大学院時代に身に付けた理系的思考が『キングダム』制作につながっていると明かしてくれた。

ロックな経済学者が明かす、音楽レーベルがアーティストを「搾取」してしまうワケ
不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”し続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽やアーティストの分析を通じて、ビジネスや人生を切り開くための道を探った一冊だ。バラク・オバマ元米国大統領も、この「ロックな経済学(ROCKONOMICS)」というコンセプトに強い関心を示しており、本書に熱い絶賛コメントを寄せているという。本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。
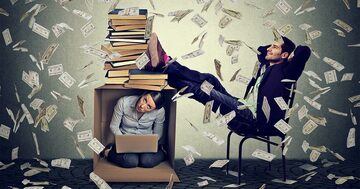
#4
金融3メガの最後の1社がついに動きだした。三井住友フィナンシャルグループがグループ総出で量子人材育成に乗り出す。JPモルガン、ゴールドマン・サックスなどの海外勢や、IBM・慶應義塾大学と組んで先行して活用法を模索する三菱UFJフィナンシャル・グループ、みずほフィナンシャルグループに追い付けるか。

デイヴィッド・ボウイが予言した「モノが売れない時代」の新しい稼ぎ方
不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”し続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽やアーティストの分析を通じて、ビジネスや人生を切り開くための道を探った一冊だ。バラク・オバマ元米国大統領も、この「ロックな経済学(ROCKONOMICS)」というコンセプトに強い関心を示しており、本書に熱い絶賛コメントを寄せているという。本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

“ロックな経済学者”が教える「儲け・人気」を最大化するポイント
オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』(アラン・B・クルーガー著、望月衛訳)がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽関連のデータ分析と関係者へのインタビューを通じて、経済的な成功や人生における幸福への道を解明した驚異的な一冊だ。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロッコノミクス=ロックな経済学)」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? 本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

「わかる」が「できる」に変わる、超簡単な復習方法
勉強前にたった1分、瞬読トレーニングを取り入れるだけで成績が上がる右脳のはたらきが覚醒、読むスピードが速くなり、一度で見る情報量がアップ。あとは、イメージに変換する力と、自分の言葉で言い換えるアウトプット力を磨けば、勉強効率が劇的に変わる。
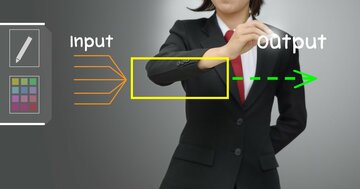
ロングテール説は怪しい。「ニッチ市場が勝つ」って本当ですか?
オバマ政権で経済ブレーンを務めた経済学者による『ROCKONOMICS 経済はロックに学べ!』(アラン・B・クルーガー著、望月衛訳)がついに刊行となった。自身も熱烈なロックファンだというの経済学の重鎮アラン・B・クルーガーが、音楽関連のデータ分析と関係者へのインタビューを通じて、経済的な成功や人生における幸福への道を解明した驚異的な一冊だ。バラク・オバマ元大統領も、以前から「Rockonomics(ロッコノミクス=ロックな経済学)」というコンセプトに強い関心を示しており、「何十年も積み重なってきた経済の問題を解くカギがここにある!」と熱い絶賛コメントを寄せている。ますます不透明性が高まるいま、「人々を熱狂させる未来」を“先取り”する存在であり続けてきた音楽に目を向けることで、どんなヒントが得られるのだろうか? 本記事では同書の一部を抜粋して紹介する。

第277回
分科会の尾身茂会長が、東京五輪の開催について「こういうパンデミックでやるのが普通ではない」と発言した。これにより世論は「正義の味方の尾身」と「悪者の政府」という図式となった。しかし、尾身会長の発言への支持とは別に、分科会のパフォーマンスに対しては厳しく評価せざるを得ない。
