
野田 稔
第9回
W杯開幕直前に代表監督が交代し、日本人の多くは「今度のW杯はグループステージ敗退だな」と感じました。その予想を見事に覆し、セカンドステージに進出。そんな日本チームの良さは何だったのかについて考えてみましょう。

第8回
60歳を過ぎると、これからの自分の人生に対する悩みや不安だと思う人は多いのではないでしょうか。自分にとって楽しめることが見つけられれば、日々充実するでしょう。決まり切った「当たり前の人生」などありません。今、やりたいことが見つからない人は、好きだったことや趣味、特技を「働き」のタネにしてみてはいかがでしょうか。
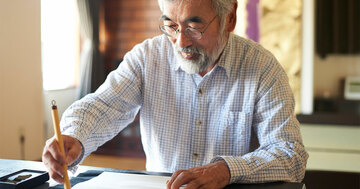
第7回
会社の役職に固執し、今の仕事だけして何の準備もしないまま定年・再雇用終了を迎える人もいれば、早期退職勧奨を断れない状況に陥る人もいることでしょう。第2の人生で後悔しないようにするにはどんな点に気を付けたらいいのか、今回は会社員人生で「負け残る」か「逃げ勝つ」かの分かれ道について考えてみましょう。

第6回
定年後再雇用されたり、第二の職場を見つけたりすれば、それなりに出勤する場所は確保できます。それでも多くの場合、以前と比べて就業時間は短くなるでしょう。家にいる時間はどうしても長くなるわけです。この「家にいる時間」をどう充実させるかが、実は定年後の一大課題なのです。

第5回
前回はボーイスカウトなどの、ボランティア団体で認められるための、「セカンドキャリアの人間基礎力」について書きました。人間関係形成力やフットワークの軽さ、腰の低さといった態度に関するものを中心に示しました。今回は、そういった組織で仕事を進めるために必要なスキルにはどのようなものがあるかをお伝えします。

第4回
地域とのつながりを確保するために、人間関係を作ることだけが主目的になってしまうと、人は打算的になってしまいます。では、どうすれば地域の活動に自分自身が溶け込み、心地よい居場所を作ることができるのでしょうか。

第3回
5年前に継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止する制度改正が行われ、「65歳までの継続雇用制度の導入」に加え、「定年制の廃止」「65歳までの定年の引き上げ」のいずれかの措置を実施する企業は増加傾向にあります。しかし、定年が65歳になったり70歳まで働けるといっても、定年後再雇用は本当に魅力的なのでしょうか。

第2回
会社というコミュニティに属していると認識することは決して悪いことではありません。当然のベースでしょう。ただ、その狭い世界だけに閉じこもって、他のコミュニティに一切関わらないまま定年を迎えるとなると、その先の展望はかなり厳しくなります。では、どんなことをすればいいのでしょうか。

第1回
今回から新連載「定年前5年の過ごし方」を始めます。50代になると安心・安定を求めて「守りに入る」人が多くなるのではないでしょうか。ところが「守りに入る」ことは実は定年後を危うくするのです。それはなぜでしょうか。

第24回
30代になると「1年は速い」と感じる人が多いことでしょう。なぜなら、10代や20代の頃は自身に訪れる環境変化に対応していく中で多くを学び、成長しているものの、30代になるとそうした環境変化が起こらなくなるからです。では、人はどうやって自分の人生に変化を起こすことができるのでしょうか。

第23回
技術の進歩と細分化が進むにつれ、想定外の変化も頻繁に起こっています。自分自身の広く浅い知識では稼げず、とはいえ、何らかの分野を深く究めても、今度は想定外の変化が起こった途端に無用の長物になってしまうというリスクがつきまといます。このジレンマをどう解決すればいいのでしょうか。

第22回
世の中で光る存在となっている若者は、人生の先取りをしています。ところが今の30代のビジネスパーソンの多くは、自ら光り輝こうとはせずに自分の人生に遠慮し、組織人として上司の小さな期待に応えようと、妙な忖度をしているように思います。

第21回
今回は、通勤について考えますが、通勤時間をどのように有効に過ごすかといった堅苦しい話ではありません。通勤を人生の貴重な一部としてとらえた時に、いかに楽しむかという話をします。

第20回
自分の評価と周りの評価、あるいは組織の評価とのギャップに悩むビジネスパーソンは少なくありません。これはスポーツの世界でも同じ。そこで今回は、昨年、巨人を自由契約となり、所属が未だに決まっていない村田選手の事例を取り上げ、組織の事情についてお伝えします。

第19回
前回から「修羅場体験」について語っています。今回は皆さんが企業の中にいて、いかに「修羅場体験」を積むべきかについて考えてみることにしましょう。
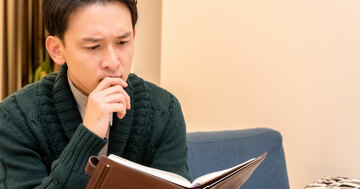
第18回
前2回にわたって、最先端のトレンドに追いつき、さらに自らリードするための方法について考えてきました。今回は、引き続き、特に「応用力」をいかに発展させていくかについて見ていきます。
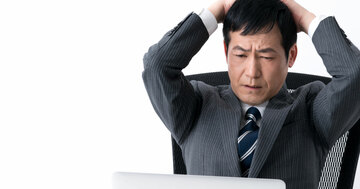
第17回
今回は、超速でその道のプロになっていくためにどんなことが必要なのかについて考えてみましょう。

第16回
「学び」には様々なものがあります。今回は短期間で最先端をキャッチアップし、さらにリードしていく、そんなビジネスパーソンになるための方法論について考えてみましょう。
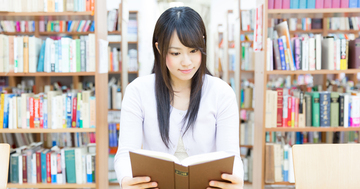
第15回
MBAには多様な人材が集まっています。今回は自衛官、中国人留学生にスポットをあてMBAでどんな効用が得られたのかについてお話しします。

第14回
今回も3人の現役経営者に話を伺います。様々な意味での「学び直し」のためにMBAに進学しましたが、実際に学びつつある彼らは今、MBAという学びの場をどう捉え、何を感じているのでしょうか。
