
田坂広志
第2回
「あの人、頭は良いんだけど……」と陰で言われる人に足りないもの
残念な人、一流の人、その差は紙一重 ――あなたの成長を阻む「7つの壁」を打ち破り、人生を拓くための「7つの技法」とは。 田坂流「成長の思想」をまとめた最新刊『なぜ、優秀な人ほど成長が止まるのか』より、本文の一部を紹介する。

第1回
なぜ、「勉強ができる人」は「仕事ができない人」になってしまうのか
残念な人、一流の人、その差は紙一重 ――あなたの成長を阻む「7つの壁」を打ち破り、人生を拓くための「7つの技法」とは。 田坂流「成長の思想」をまとめた最新刊『なぜ、優秀な人ほど成長が止まるのか』より、本文の一部を紹介する。

第57回
才能の開花を妨げるのは、我々の「深層意識」や「無意識」の中にある、自分の能力と可能性を限定してしまう「自己限定」の意識に大きな原因がある。

第56回
人の心の中には「様々な人格」が存在し、その人格に付随する「様々な才能」が眠っている。その「隠れた人格」を表に引き出すことができるならば、自然に、それに付随する「隠れた才能」が開花し始める。

第55回
仕事ができる人は、様々な人格を切り替えながら仕事に処する「多重人格のマネジメント」を無意識に行っている。そうした能力は、実は、日々の「メール応対」「電話応対」による修業で身につけることができる。

第54回
自分の中にある「複数の人格」を自覚し、置かれた場面や状況によって「異なった人格で対処する」ということを意識的に行えば、自然に「様々な才能」が開花していく。

第53回
「自分の中に様々な人格を育て、場面と状況によって、適切に使いわける」という「多重人格のマネジメント」が、我々の中の「様々な才能」を開花させる。

第52回
AI革命が進む21世紀の高度知識社会においては、現場分権型で水平型の組織が基本となる。その組織においてリーダーに求められるのは、「統率型リーダーシップ」ではなく「支援型リーダーシップ」であり、3つの力が極めて重要になる。

第51回
「マネジメント力」は、人工知能革命の後も、人間に残された重要な仕事であると、多くの識者が指摘している。だが、実際はその管理業務の多くを人工知能が代替していくことになる。そのとき重要になるのは、「こころのマネジメント」と呼ぶべき成熟したマネジメントである。

第50回
活躍する人材に必要な能力の1つが「対人的能力」だ。それは、広義の意味でのコミュニケーション力だが、その大半は「ノンバーバル=非言語的」、つまり言葉を使わないコミュニケーションだ。

第49回
「職業的能力」を磨くために、我々が知っておくべき大切な技法が「私淑の技法」だ。優れた能力を持っている人物を、心の中で「師匠」と思い定め、その人の仕事をする姿から、言葉を超えて、直接、その技術や心得を学ぶことだ。

第48回
実社会で活躍する人材になりたければ「職業的能力」を磨かなければならないが、それは、ただ「経験」を積んだだけでは身につかない。そのためには、科学的な「反省」の技法が求められる。
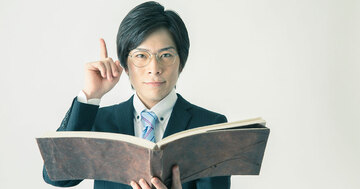
第47回
急速に進化する人工知能は、ついに人間の勘まで代替するようになってきた。人工知能が普及し、本格的に活用されるようになると、学歴社会は崩壊し、東大卒の人材でも淘汰される時代がやってくる。

第46回
いま、東大卒に「活躍する人材」が少なくなったと言われるが、今後、東大卒の半分が失業する時代がやってくる。なぜなら、「人工知能革命」という荒波がやってきたからだ。

第45回
世の中には「東大神話」という言葉がある。「東大を出れば、世の中で活躍できる」といったものだ。しかし、それは、文字通り「神話」であり、「真実」ではないことを意味している。

第44回
いま、我が国のエリート官僚が、何かを隠しているのか否か、ある言葉を言ったのか否かが、連日のように報道されている。その真偽以前に、大きな問題を感じるのは、これらのエリート官僚や政治家の言葉が、極めて軽いことである。

第43回
優れたリーダーは、聴衆を前にして、一挙手一投足や立ち振る舞いをもメッセージにする。だが、ロシアのプーチン大統領でも、過去のダボス会議で聴衆に緊張と虚勢を伝えてしまった。それほど難しいものだ。

第42回
優れたプロフェッショナルの話者は、必ずと言っていいほど、「矛盾した二つの人格を持っている。それは、米国のアル・ゴア元副大統領や、ドイツのアンゲラ・メルケル首相のスピーチを聴くと分かる。

第41回
世界が金融危機に見舞われていた2010年のダボス会議で、フランスのサルコジ大統領は、「世界の金融業は、貪欲だ」と批判した。しかし、金融業も多い聴衆からの拍手は、まばら。だが、彼は胆力で聴衆を呑み込み、聴衆の拍手を引き出した。

第40回
彼の声が響くと、もう、ダボス会議の聴衆は、彼の話に惹き込まれていく。彼とは、トニー・ブレア・イギリス元首相。なぜ、彼のスピーチは、これほどまでに、聴衆の心を掴むのか。そこには奥義が隠されている。
