小林祐児
部下は帰宅、管理職はサービス残業…部下より「時給」が安くなる罰ゲーム管理職の悲哀
残業禁止やパソコンの電源オフで従業員の労働時間を削減するーー表面的な問題解決のためにこのような「上から蓋」の改革を行ったとて、管理職へのしわ寄せが増えてしまい、真の解決にはならないだろう。そこで、労働や組織の研究者である筆者は、組織全体の役割や業務量を調整する「ワークシェアリング・アプローチ」を提案。その具体的な施策とは?※本稿は、小林祐児『罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法』(インターナショナル新書)の一部を抜粋・編集したものです。

忙しすぎる「罰ゲーム管理職」が今すぐ仕事を頼むべき相手とは?
権限の小さい現場管理職は、無駄な稟議書、煩雑な承認プロセス、お伺いや根回しといった業務に圧迫され、組織メンバーの自律性は失われていく一方だ。その状況を打開するためのキーワードは「権限委譲」。管理職が役割をシェア・移譲すべき3人のキーパーソンについて、組織や人事の研究者である筆者が解説する。※本稿は、小林祐児『罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法』(インターナショナル新書)の一部を抜粋・編集したものです。

管理職はもはや罰ゲーム!「忙しすぎる雑用係」に仕立て上げられる恐怖の構造
管理職になると市場価値が下がり転職に不利だとして、「管理職になりたくない」とこぼす若手が増えているという。実際、その多忙さに忙殺されてスキルアップもままならないという管理職経験者の声も多い。労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行う筆者は、日本型組織とそこで働く管理職の「役割」の特殊さにこそ元凶があると語る。※本稿は、小林祐児『罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法』(インターナショナル新書)の一部を抜粋・編集したものです。

2020年に新型コロナウイルスの流行が始まって以降、感染防止対策の一つとして日本企業はテレワークの活用を推進してきた。しかし、長引くコロナ禍で、多くの企業がテレワークを継続する難しさに直面している。「結局出社した方がいい」と結論付けてしまう企業も出てきているようだ。本当の意味で日本企業にテレワークを定着させるには何が課題となるのか、考えてみよう。

サントリーホールディングスの新浪剛史社長が、「45歳定年制」の導入について提言し、話題となっている。発言には多くの批判が集まっているが、雇用問題として捉えるならば、「企業はなぜ45歳の社員に『区切り』をつけようとするのか」という問題を考えなければならない。この問題の背景を考えると、現状を変えるためには、「40歳以降のキャリア」を考えるだけでは不十分であることが分かる。

新型コロナウイルス感染拡大を背景にリモートワークが広く普及し、働き方は大きく変わった。さらにコロナ禍でリストラが加速する。日本企業で安定したキャリアを築いてきた中高年が窮地に立たされる可能性がある。そもそも日本の中高年のキャリアにおける問題点はどんなところにあるのか。データを基に解説する。

コロナ禍で急速に普及したテレワーク。さまざまなメリットが期待されているが、その一つが「介護との両立」である。介護離職の問題が顕在化する中で介護と仕事をどう両立させるかは、日本企業にとって大きな課題だ。しかし、テレワークの普及がそれを可能にすると結論付けることはできない。むしろテレワークによって高まるリスクがあることが調査データから分かった。

外国人留学生を採用する企業が増える中、課題となっているのは「定着率」だ。入社後の早期離職に悩む企業は少なくない。人材の定着に向けて、取り組みの工夫、強化が必要になってきている。

#8
日立製作所や資生堂、富士通など大手企業が相次いで採用を試みている「ジョブ型雇用」。こうした新たなトレンドは、ビジネスパーソンの「給料」にどんな影響を与えるのか。

コロナ禍におけるテレワークの急速な拡大により、再燃した「働かないおじさん問題」。筆者は、こうした言説はあまりに表面的で扇情的だと見ている。今回は「働かないおじさん問題」が盛り上がる背景に潜む日本企業の課題に目を向けてみたい。

コロナ禍で進む在宅勤務が「女性活躍」にマイナスに作用しかねない理由
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「在宅勤務」に切り替える企業が増えている。こうした動きがウイルス収束後も定着すれば、働く場所が就労の足かせとなってきた「女性」たちの働き方に、一見ポジティブな影響を与えるようにみえる。しかし、実際の家庭で起こっている問題は複雑だ。

新型コロナウイルスの感染拡大により、日本の経済、社会は大きな影響を受けている。これからの日本の雇用や働き方がどうなるのだろうか。今回は、過去のデータをひもときながら、今後の日本の変化を考えてみたい。

テレワーク拡大を妨げる同調圧力、2万人緊急調査から見えてきた課題
緊急事態宣言の対象地域が全国に広がってから10日が過ぎた。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク実施に踏み切る企業も少なくないが、実際のところ、出社抑制にはまだまだ課題も多い。どうすれば、テレワークを拡大できるのか。

新型コロナ感染拡大でオンライン化する就活、2つの落とし穴とは
企業が新型コロナウイルス感染拡大への対応に追われる中、今年の採用活動が本格的にスタートした。説明会や面接がオンライン対応に切り替えられるなど、異例の事態となっている。混乱の中で就活に挑む学生たちが、最も危惧すべきこととは――。

入社後の「こんなはずじゃなかった」を招く就活・採用の問題点
就活・採用に関する情報はネット上にあふれているが、それでも入社前の企業イメージと入社後の実態との間にギャップが生じてしまうことは多々ある。就活・採用の時点で防ぐことはできないのだろうか。データを元に考察してみたい。

現在の就活市場において、重要な役割を担っているのが「インターンシップ」だ。日本では採用直結型のインターンは認められていないため、あくまでも「自社のファン作り」を目的とする企業が多い。しかし、実際にインターンはどのくらい「ファン作り」に貢献しているのだろうか。調査結果を元に考察する。

学生の約半数がインターンシップに参加しているという。企業説明会のようなワンデー・インターンなども増えており、その意義に疑問の声もあがっているが、実はこのインターンが、入社後の評価や定着率に大きな影響を与えているという調査結果がある。

多くの企業で、アルバイトの問題行動が動画系SNSを通じて拡散され、「バイトテロ」などと呼ばれて問題視されている。「こうしたことは前からあった」「問題を起こすのは一部の従業員だけ」と言わず、客観的なデータを基に原因と対処法を考えよう。
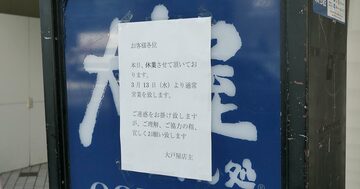
長時間労働について議論する際、しばしば指摘されるのが「会議、打ち合わせの多さ」だ。では、日本企業の会議は仕事のパフォーマンスにどれくらい寄与しているのか。実態調査を行うと、利益よりもムダが想像以上に多い実態が浮かび上がってくる。

日本企業には職場の多様性が求められており、若手、女性、外国人の活躍を促す風土づくりが進められている。しかし、表向きには出て来なくても、そうした風潮への抵抗感は根強い。調査でわかった、ダイバーシティ抵抗勢力の素顔とは。
