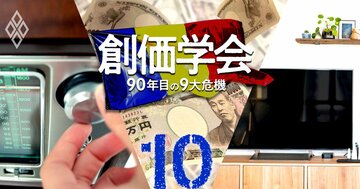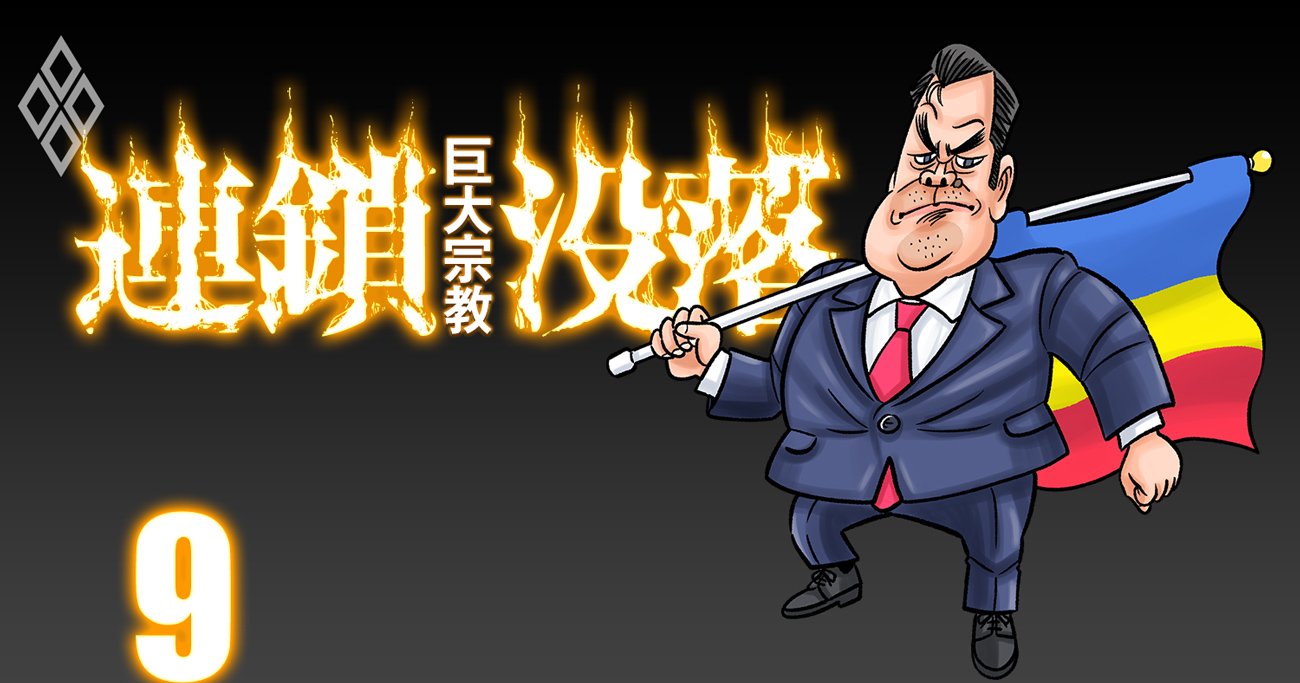 Illustration by Yuuki Nara
Illustration by Yuuki Nara
創価学会の名誉会長、池田大作氏が創立した宗教系大学、創価大学。かつては学会活動こそが学生の本分とされた学風も様変わり。特集『巨大宗教 連鎖没落』(全20回)の#9では、こと就活においては普通の大学化が進む、令和の創価大生の実態をレポートする。(ダイヤモンド編集部特別取材班)
かつての創大生の“本分”は
学会活動と池田大作氏への帰依
俺たち創大生にとって就職活動は『折伏(しゃくぶく)戦』なんだよ」――。
バブル経済の崩壊が始まった1991年、創価大学に入学した男性は、「学生部」と呼ばれる創価学会組織の会合に顔を出した際、創大OBが就職活動に突入した4年生たちにそんなげきを飛ばしている姿を今もなお鮮明に覚えているという。
「折伏」とは、悪人や悪法を議論で打ち砕き、屈服させるという意味の法華経における仏法用語だ。転じて自らが信じる信仰に導き、帰依させることをいう。この文脈では創価学会の教えを広め、入会に導くことを指す。
「俺たちが仏法を語る場とのご縁を紡ぐ戦い、それが就職だ。だから会社の知名度とか、給料が安いとか、そんなことを創大生が言ってはいけない。全ての目的は『広宣流布(布教)』『創立者(池田大作氏)』のため。そこを外さなければ、おのずと就職先は決まる!」
続くOBの言葉に、創大入学の目的が入試偏差値に見合わない大手企業への就職力にあった男性は、おのれの俗物性を深く恥じたと振り返る。
 Illustration by Y.N.
Illustration by Y.N.
実際に創大は、大企業や官公庁に人材を今日に至るまで数多く輩出してきた。男性の在籍当時でいえば、大林組や竹中工務店といった大手ゼネコン、三菱UFJ銀行や三井住友銀行といった金融に強いとされるのが内外での評判だったという。
しかも、当時の創大生の“本分”は「学会活動」にあるのが学内の常識で、就活のみに血道を上げる学生は肩身が狭かったという。とりわけ、この男性が創大に入学した91年は、学会が宗門から破門された年で、学内の関心は学会でいうところの「宗門問題」に集約されていた。
キャンパス全体がピリピリした雰囲気で、学生が集う食堂「ロワール」やA棟「1Fテラス」といった場では、学生同士で「おまえの今の話にどれだけ『創立者』という言葉が出てきた」「『創立者』という言葉を語れないなら何をするにもただのエゴだ」といった激論があちらこちらで交わされる時代だった。
つまり、当時の学生の学会活動の源は、信心というより「創立者」たる池田氏への帰依に尽きる。「学園」と呼ばれる系列校出身者を軸に、大学からの入学者も、学内外で事あるごとに「創大生としてなすべきこと」、つまり「創立者をお守りする」ことをたたき込まれるのだ。
法曹界や外務省職員も数多く輩出していることで知られる創大だが、これらの進路も創大生たちの間では、「創立者をお守りするために進んだ進路」として捉える向きが多い。
弁護士になっていわれなき誹謗中傷から創立者をお守りする、外交官になって海外で創立者の素晴らしさを流布していく、という考え方が根底にある。同様に、大手企業への就職も「創立者をお守りする」という志がなければ、学内では誰も評価しないというわけだ。
とりわけ、学会員の間では「学会と創立者を内側から守る」立場である学会本部職員への就職は、内心では熱望していても口に出せるようなものではなかったという。「おまえは先生のおそばにいられるだけの人間なのか」と、周囲から日頃の行いを責め立てられるのが常だからだ。