早川幸子
第224回
医療制度改革関連法の成立により2022年から、現在医療費の窓口負担が1割だった後期高齢者の一部の負担が、2割に引き上げられることになった。是非を巡りさまざまな議論がなされているが、その引き上げの“実態”はどうなのか。
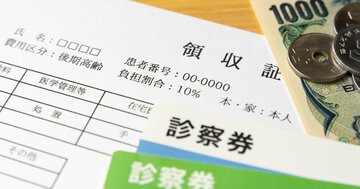
第223回
ようやく加速してきた新型コロナウイルスのワクチン接種。だが、ちまたでは副反応への危惧を訴える声もいまだ強い。それでは、ワクチン接種により健康被害が出た場合の補償制度はどうなっているのだろうか。

第222回
ついに3回目の発令となった緊急事態宣言。沈静することを知らないコロナ禍で、失職したりコロナに感染して休職したりしたときどうすればいいのか。実は、必ず押さえておきたい国民健康保険と国民年金のある制度がある。

第221回
新社会人にぜひとも覚えてもらいたいのが「高額療養費」という制度だ。また、会社員になって自分で保険料を納めるようになると、親の扶養に入っていたときにはなかった「傷病手当金」ももらえるようになる。このふたつは、健康保険の給付のなかでも特に重要なものなので、押さえるべきポイントを解説しよう。

第220回
コロナ禍であぶりだされたものの一つが、アルバイトで生計を立てている学生のたちの窮状だ。減収で学費や生活費もままならなくなれば、当然、国民年金保険料の支払いも厳しくなっているはずだ。コロナ禍で、学生納付特例も臨時の特例措置が設けられ、令和3年分も引き続き特例が継続されることになっているので、忘れずに手続きをしたい。

第219回
例年、確定申告の申告期限は3月15日まで。しかし、今年は新型コロナウイルスの影響を考慮し、4月15日まで延長されている。昨年1年間に、大きな病気やケガをして医療費が高額になった人は、確定申告をして医療費控除の手続きをすれば、払い過ぎた税金が戻る可能性がある。「忙しくて、まだ手続きが済んでいない!」という人も、これからでもまだまだ間に合うので、忘れずに申告しよう。
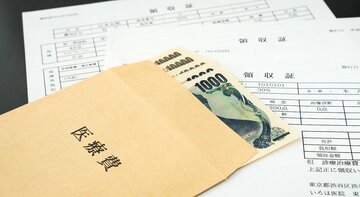
東日本大震災から、間もなく10年がたつ。災害は、けっして他人事ではない。3月11日が1週間後に迫った今、防災の一つとして、改めて災害時の医療体制について確認しよう。

第217回
昨年1年間に、大きな病気やケガをして医療費が高額になった人は、医療費控除の申告をすると、払い過ぎた税金が戻る可能性があるので、忘れずに手続きしたい。だが、その前に確認しておきたいのが、健康保険の高額療養費の請求漏れだ。

第216回
新型コロナの感染拡大を抑える最大の防御策は、人と人との接触を極力減らすことにある。病院や診療所については、「感染が怖いから」と受診をためらう声もあるようだ。そのため、昨年は、多少、具合が悪くても医療機関を受診せずに、市販薬などを購入して、自分で治療した人も多いのではないだろうか。こうしたケースで、利用できる可能性があるのが、「セルフメディケーション税制」だ。

2021年の幕開けは、新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大を受け、緊急事態宣言の再発令から始まった。病院の病床数もひっ迫しており、いつ医療崩壊してもおかしくない状況だ。万全な感染対策のもと、安全に働けることを祈るばかりだが、万一、業務中に新型コロナにかかった場合は、正社員だろうと、非正規雇用だろうと、雇用形態に関係なく、すべての労働者が労災保険の給付対象になることを覚えておきたい。

第214回
年末はパートや派遣など非正規雇用で働く人々の契約更新時期も迫ってくる時期だ。今回は、コロナ禍によって生活が困窮した時に使える医療分野の制度について、改めてまとめておきたい。

第213回
長引くコロナ禍で、体調が悪いにもかかわらず、経済的理由で医療にかかれない「受診控え」が全国的に報告されているという。その実態と救済制度である「無料低額診療事業」について解説する。

第212回
会社員は、労働時間や収入などが一定ラインを超えると、社会保険に加入することが義務付けられているが、副業をすると保険料や給付に影響が出るのだろうか。今回は、おもに副業をした時の健康保険の保険料や給付について見ていきたい。

第211回
11月に入り、心配されるのが季節性インフルエンザの流行だ。今年は新型コロナウイルスとの同時流行も懸念されている。年齢や性別を問わずに、ワクチン接種はインフルエンザ予防に有効な手段であるが、問題はその費用だ。

「コロナの陽性となって入院したら、たくさん医療費がかかるのではないか?」「感染して仕事を休んだら、収入が減ってしまうのではないか?」と不安に思う人もいるだろう。こうした不安を手っ取り早く解消できそうなのが、民間の医療保険への加入だが、果たして本当に必要なのだろうか?

新型コロナの影響で、自らの意思に反して失業し、雇用保険を受給しながら暮らしている人もいる。ただし、病気やケガの療養中ですぐに働くことができない人は、そもそもこの雇用保険の基本手当(失業手当)を受給することができない。もし、基本手当をもらっている最中に病気やケガで就職活動ができなくなったら、どうすればいいのだろうか。

コロナ禍による雇用不安が広がっている。会社員やパート職員など、企業や団体から給与をもらって働いている人は、失業と同時に健康保険も失うので要注意だ。失業を機に健康保険に未加入となり、それがきっかけで生活が困窮していった事例も耳にする。失業中の人が、できるだけ負担を抑えて健康保険に加入する方法を考えてみよう。

第207回
6月26日、厚生労働省から「厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について」が発表され、コロナの影響で休業し、収入が激減した会社員の健康保険料についても配慮されることになった。納める保険料が減れば、当面の負担は抑えられる。だが、落とし穴もある。

前回の本コラムで、「令和2年7月豪雨」の被災者は、健康保険証がなくても医療を受けられることをお伝えした。被害の拡大と共に被災者が医療を受ける際の対応もフェーズが一段階アップし、災害救助法が適用された市町村の住民で、一定要件を満たした被災者は医療費の自己負担分が免除されることになった。

日本では、毎年、どこかで地震や津波、水害などの大規模災害が発生しており、いつ自分や家族が「被災者」になってもおかしくない状況だ。今回の九州豪雨のように大きな災害が起きると、避難することに必死で健康保険証や所持金を持ち出せない人も多い。そこで、知っておきたいのが、災害時の医療費の支払いについてだ。
