
江幡吉昭
富裕層――資産を多く持つ彼らは“憧れ”を抱かれることも多い存在だ。しかし、資産があるからといって「いいことばかり」ではない。富裕層ならではの問題が多数存在する。“資産があるからこそ”の悩みとは何か。長年、富裕層の資産管理に携わってきた筆者が解説する。
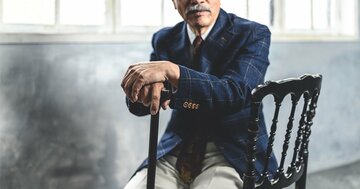
資産を子どもや孫など次の世代にどう残していくのか。特に、資産額の大きな富裕層にとっては重要な問題だ。やり方を間違えると、子どもたちの間でトラブルになったり、資産の額を減らしてしまったりするかもしれない。長年、富裕層の資産管理をサポートしてきた筆者が、老後の資産管理や相続の準備において「絶対やってはいけない」ことをお伝えする。

8月5日、日経平均株価が急落し、先週末の終値から4451円下げて3万1458円で取引を終えた。翌6日は急反発するなど、株価は荒れ模様だ。株価の暴落に直面して怖くなった人もいるかもしれない。しかし、ベテランの投資家ほど、こうした暴落時はチャンスと見る。過去の株価急落の局面を振り返り、今やっておくべきことを確かめよう。

「老後2000万円問題」が話題になってから約5年。さまざまなメディアで取り上げられたこのワードも今日ではあまり耳にしなくなった。しかし、状況はさらに深刻になってきているといえるかもしれない。金額だけでいえば、「2000万円では足りない」というのが筆者の見解だ。

新NISAで投資への関心が高まる中、投資先として人気なのが、米国株や米国株が約6割を占める「オルカン」です。メディアでも評価の高いオルカンを選んでおけば安心、と思っている人もいるかもしれません。ただ、投資の世界に絶対はありません。それは歴史が証明しています。

経営者会や勉強会といったさまざまな「異業種交流会」が開催されている。参加したことがある人もいるかもしれない。しかし、一流のビジネスリーダーは、そうした交流会には参加しない。なぜか。

お金持ちは、「運がいい」。運なんてどうしようもないと思われるかもしれないが、そうしたお金持ちの行動には、「運を悪くしない」共通点があると感じる。特に、4つのことを「しない」のだ。

50兆円超に上る「タンス預金」。今年7月に行われる1万円札の刷新には、こうしたタンス預金をあぶり出す目的もあるといわれている。旧札でのタンス預金を持ち続けることには、どんなリスクがあるのか。取るべき対策とは。

メジャーリーガー大谷翔平選手の通訳を務めてきた水原一平氏が、違法賭博をきっかけに大谷選手の多額の資金を着服したと米複数メディアが報じた。大谷選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、水原氏を解雇したと明かした。報道によれば、水原氏はスポーツ賭博に大金をつぎ込んだという。近年広まりつつある“スポーツベット”と呼ばれるスポーツへの賭け事。ハードルが低く、これをきっかけに誰しもギャンブル沼にハマる可能性がある。

東京の不動産価格が上昇している。一方で、昨年の出生数が過去最少を更新するなど深刻な少子高齢化が進む中、「日本の不動産に未来はない」という声も少なくない。本当にそうなのだろうか。今、日本の不動産は買いなのか否か――。データ、世界の都市との比較を基に考えてみたい。

高齢化が進む中、「シニア再婚」をする人も珍しくない。そんなシニア再婚をした夫婦、家族でしばしば問題になるのが「相続」だ。特に資産額の大きい富裕層ではトラブルに発展しやすい。

インフレが進む中、資産を守るために株や債券、金などさまざまな金融商品に分散して投資をしようと考える人が少なくありません。しかし、過去のデータを見ると、超長期で投資をするなら「株一択」であることが分かります。知っておきたい「超長期投資の鉄則」とは。

富裕層といえども、多額の資産をきちんと守れている人ばかりではない。時に、一般人には想像できないスケールの「大失敗」をすることも富裕層の特徴といえよう。富裕層の投資での失敗例から学べる、資産形成の鉄則についてお話ししたい。

富裕層はなぜ日本株を買い続けるのか?株価上昇だけでない「あと2つの理由」
日本株はじめ世界の株は、引き続き底堅く推移している。コロナ以来、私はインフレ対策のために資産運用をすべき時代に移行したと申し上げてきた。特に富裕層に関しては「もうかるので資産運用しましょう」ではなく、「インフレ下の資産ヘッジのために運用すべきだ」と考えている。そこでインフレ下の資産運用として、現在の3万3000円前後の水準でも日本株投資を選ぶべき二つの理由について解説する。

親が認知症に…実家を売って老人ホームに入れたいが断られた→こんな時どうする?
高齢化が進み、親の介護費用が大きな課題となっています。認知症になれば実家売却などが難しくなります。こうしたリスクに備えて、財産管理を家族に委ねる家族信託が徐々に広がりつつあります。今回は家族信託のメリットとデメリットについて解説します。

情報弱者をカモにする不動産「サブリース契約」あまりにエゲツない“中抜き”の実態
アパートなどを所有者から一括して借り上げて入居者に貸すサブリース会社をめぐるトラブルがいまだに絶えない。今回はトラブルに巻き込まれた2人の不動産所有者のケースをもとに、サブリース契約の3つのデメリットについて解説したい。

少し前に話題になったサブリース。サブリースとは本来、転貸借全般を指す用語ですが、一般には収益不動産の一括借り上げのことをいいます。マンションやアパートなどの賃貸不動産の所有者が、空室リスクなどを避けるため、いったんサブリース会社に不動産を貸して、サブリース会社に客付けやら管理やらの面倒なことをやってもらおうというもので、多くの不動産オーナーが利用している仕組みです。ところが2019年、大手サブリース会社で問題になったのは、当初約束した家賃を、数年後強制的に『当初家賃から引き下げられた』所有者が全国で相次いだという事例です。所有者に銀行借り入れがある場合、家賃を引き下げられると「借入との収支がマイナス」になってしまう方も多く存在しています。あれから数年がたち、現在、全国のサブリース物件所有者の人たちには何が起きているのでしょうか。

日本株は連日上昇し、日経平均株価は3万円どころか、一時は3万1000円を超える勢いです。とはいえ、米債務上限問題や長引くインフレ、そして米地銀の相次ぐ破綻など、リスクは多い中、「どうも買うに買えない」という人が多いのではないでしょうか。そんな中、富裕層である企業経営者は「日本株は買いでしょう」とおっしゃる方が非常に多いです。その理由はどこにあるのでしょうか。買いの要因自体は複数ありますがここでは2つに絞ってみたいと思います。

#11
富裕層への課税強化が進んでいる中、「超」が付く富裕層は今後、どのような節税策を取るのか。富裕層の資産管理の専門家は、「王道」といえる海外移住へ回帰するとみる。特に、日本との距離が近い、モノや情報の調達が早い、日本より税金が安いという「近い・早い・安い」がそろったシンガポールに、さらに集まるだろうと見立てを語る。その際に「ドンキ」ことディスカウントストアのドン・キホーテが鍵を握るというのだが、なぜだろうか。

#7
数年来議論されていた「生前贈与」が2023年度の税制改正で大きく変更された。しかし変更の詳細に関しては少々分かりづらい部分も多い。そこで、富裕層の資産管理を手掛けるプロフェッショナルが、分かりやすく3点に絞って整理・解説する。
