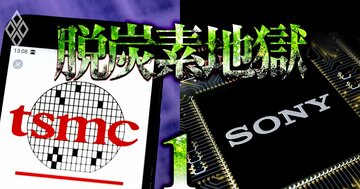Photo by Masato Kato
Photo by Masato Kato
日本の半導体復活の切り札として、最先端半導体の国産化を目指すラピダス。設立に奔走し同社会長に就任した東哲郎氏は、半導体製造装置大手の東京エレクトロン出身。過去40年以上にわたって日本の半導体産業が“凋落”するさまを間近で見てきた歴史の証人だ。特集『半導体 最後の賭け』の#12では、巨額の国家予算を投じて最先端半導体メーカーを立ち上げる意義と、その勝負の行く末を問う。(聞き手/ダイヤモンド編集部 村井令二)
日の丸半導体の“敗戦”を知る
レジェンドの最先端半導体構想
――東さんは半導体産業で40年以上の経験があります。1980年代に世界一だった日本の半導体産業が「敗戦」した歴史をどう見ていますか。
僕が東京エレクトロンに入ったのは77年。それから十数年は日本が半導体で急激に成長した時期に当たります。日本の国家戦略は「コンピューター産業で後れを取るな」という方針でした。富士通、NEC、日立製作所などアプリケーションを持っている会社が「キーパーツ」のメモリー(DRAM)に続々と参入し、シェアが50%くらいまで高まって世界一になりました。
ところが、日本が「メモリーで一番だ」と言っている同じ頃、米国ではすでに、今でいうところのAR(拡張現実)やVR(仮想現実)の開発に乗り出して、着々とコンピューター技術を強化していました。
ちょうどこの時期に、米インテルはDRAM事業から撤退してマイクロプロセッサーに大きく戦略を転換します。そこからインテルは再び強くなり、日本陣営はどんどん落ちていったのです。米国は大きな事業転換をしていたのに、日本ではメモリーで頂点を極めた後の展望が全くなかった。それが負けた要因の一つ目でしょう。
もう一つ大きかったのは自前主義。僕の言葉で言うと、身内主義というべきものです。
日本の半導体企業は、垂直統合型の組織から(設計、製造を切り分ける)水平分業型への転換に乗り遅れた。水平分業とは、“コア”に集中して、それ以外をやらないと明確化することですが、日本企業は、社内の身内に全部をやらせるという安易なオペレーションを続けてしまったので、いつまでもコアが定まらなかった。
一方、「コア事業の明確化」に成功したのが台湾積体電路製造(TSMC)です。彼らは製造に徹して、顧客と競合する事業は絶対にやらない。今思えば、日本企業の場合は、最終製品もやるし半導体もやると中途半端でした。やらない事業を明確にして日本の得意分野をつくり上げていくという発想が全くなかったのです。
――当時、日立製作所や東芝などではたくさんの事業がある中で、半導体は一つの部門という位置付けでした。
その通りで、総合電機メーカーの組織の中で、半導体部門の位置付けは高くなかったように思います。会社の中には、半導体だけではなくいろいろな事業があったので(浮き沈みの激しい)半導体は(力を入れて投資を)やらなくてもいいのではないかという考えがトップに潜んでいたのではないでしょうか。
――確かに、その後、総合電機メーカーは半導体事業を次々に切り離していきました。一方で、86年の日米半導体協定は実ビジネスにどのような影響を与えましたか。
日本の政府は米国との難しい交渉で妥協しすぎたと思います。しかし、日本が負けた要因はそれだけではない。その後の日本企業は、半導体の先端技術は輸入すればいいという考え方に傾いてしまいました。それまで「半導体は産業のコメ」という位置付けで強化してきたのに、非常にふがいなかったと思います。
――回路線幅2ナノ(ナノは10億分の1)メートルの最先端半導体の製造拠点を日本に確保するというラピダスの構想は、どのように実現したのでしょうか。
日本の半導体の“敗戦”の歴史をつぶさに見つめてきた東氏。国家の半導体戦略の一環で、最先端半導体の国産化を目指すラピダスを立ち上げた理由はどこにあったのか。巨額の国家予算を注ぐ意義はあるのか。次ページでは、ラピダスが実現するまでの経緯を振り返るとともに、今後の戦略を余すことなく明かしてもらった。