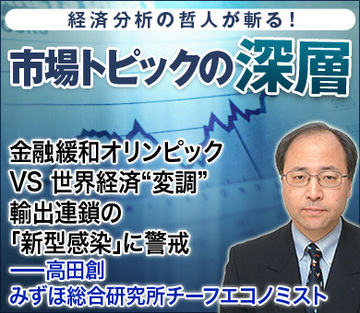熊野英生
第94回
日銀は強烈なサプライズを与える追加緩和に打って出た。今後、アベノミクスの焦点はQQE(量的・質的金融緩和)を主役とする「第1幕」から、成長戦略を主役とする「第2幕」に移る。ここで焦点になるのが、労働市場の流動性向上だ。
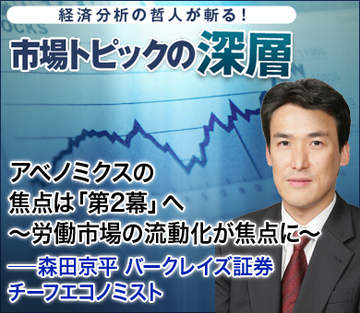
第93回
デフレ脱却を急ぐために、日銀は2年以内に2%の消費者物価上昇を目指すという。しかし、2%の消費者物価上昇率を達成すれば、デフレを脱却できるのだろうか。単に消費者物価を上げるのならば、消費税率を引き上げればよい。

第92回
2009年半ば以降日本株だけが出遅れ、「失われた3年」の状況にあった。第二期安倍政権は、そこからの脱却に止まらず、1990年代以降初めて「失われた20年」からの転換も視野にできる状況にある。安倍政権が「持っている」のは何故か。
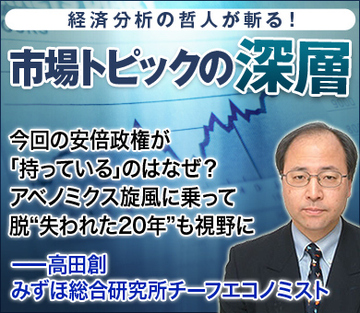
第91回
日銀新総裁の題は、いつ、どの程度の追加緩和を行うかである。ベースマネーの増減に強く影響するのが、市中金融機関が日銀に預ける超過準備預金だ。この準備金には、前回の量的緩和と現行の包括的な金融緩和の間で顕著な違いがある。
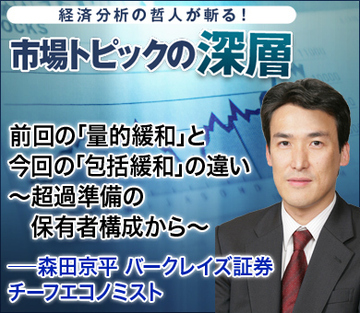
第90回
孫のために高齢者が使う金額は、年間約1.6兆円。孫への利他的消費を増やすよう支援すれば、景気刺激効果は大きい。2013年の税制改正大綱には、孫への教育資金の贈与を非課税にする案が盛り込まれた。これは素晴らしい仕組みなのか。

第89回
アベノミクスへの期待から、円安・株高が続いている。当面は、3月の期末までに株式市場と為替市場における「失われた3年」を取り戻す動きが、日本の市場の最大のテーマとなる。今まさに、マインド改善の絶好のチャンスが訪れているのだ。
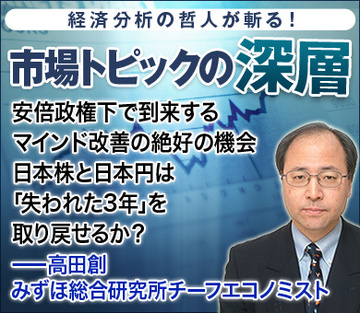
第89回
先日開かれた日銀の金融政策決定会合では、ついに2%の物価安定の目標が導入された。今後の焦点は目標の実現性に移る。日本の金融政策については、どれだけ緩和するか」と同時に、どのように緩和が効く経済をつくるかも問われる。
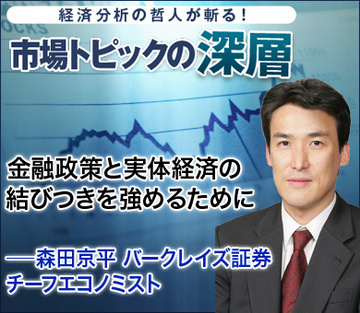
第88回
金融危機以降の日本株は、他国の株式と較べて明らかに出遅れていた。それが生じた過去3年は、日本の株式市場の「失われた3年」であっただけに、ここ2ヵ月の株高はこれまでの出遅れの調整の側面が強い。その脱却が2013年の課題になる。
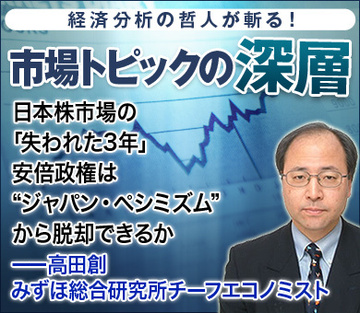
第87回
金融政策に関わる市場の焦点は、物価の位置付けに向かっている。日銀が今月21~22日の決定会合で、中長期的な物価の安定について検討する、としているからだ。自民党が掲げる「2%の物価目標」の妥当性について、考察してみよう。
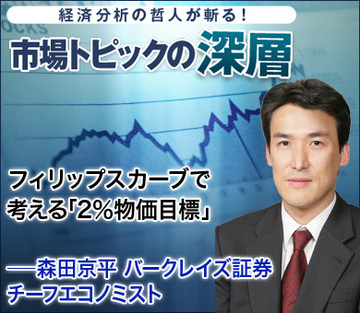
第86回
安倍首相の提唱するリフレ政策の先にあるものには、危なさを感じる。金融関係者の間でも、そう感じている人が少なくない。「リフレ」という目新しいラベルが貼られているが、その内容は金融緩和と財政拡張を推進させるものだ。

第85回
11月下旬、ニューヨーク・ワシントンへ出張した。そこで現地市場参加者のコメントとして最も新鮮に聞こえた言葉が、「日本人は運用がうまい」というものだった。特に債券についてのコメントだが、その背景にはどんな理由があるのか。
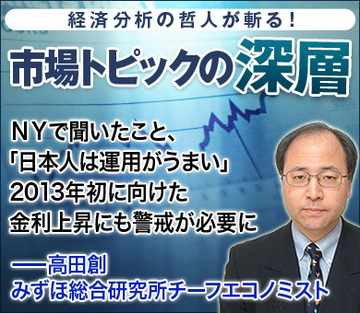
第84回
大震災後の日本の貿易収支が赤字に転じていることは、よく知られている。こうした中、1つの象徴的な出来事が起きた。日本と韓国の経常収支の逆転だ。これが定着するとは言い切れないが、中長期的に円高トレンドが変わる可能性もある。
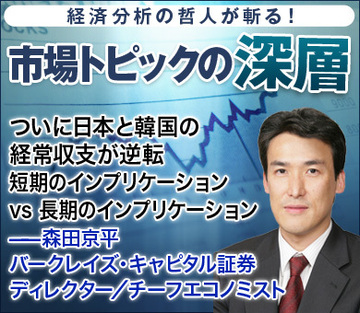
第83回
大規模な金融緩和や日銀法改正まで踏み込んだ安倍晋三・自民党総裁。市場はそれに反応して、円安・株高が続く「リフレ相場」となっている。筆者は、この流れはそれほど長くは続かないと見ている。日銀には期待に応える手段がない。
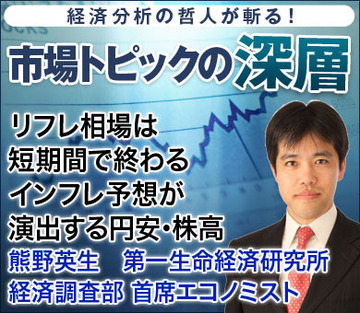
第82回
2012年の日米債券市場の最大のリスクは、オバマ大統領が再選されないことだった。ロムニーが大統領になった場合は、金利上昇が起きると見る向きが多かったためだ。足もとでは、むしろ「金利が上がらないリスク」が顕在化し始めた。
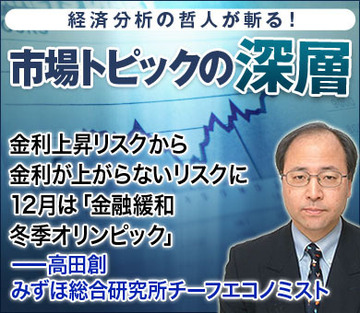
第81回
日銀は2ヵ月連続となる追加緩和に打って出たが、さらなるリスク資産の買い入れが求められている。リスク資産の買い入れは、損失発生のリスクを高め、結果的に国民負担につながる。この機に、中央銀行の自己資本の毀損をどの程度重視すべきかを考えたい。
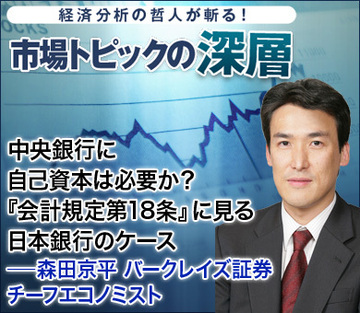
第80回
足もとで日銀は必死に資産買入基金残高を増やしているが、インフレは起きないというのが金融関係者の大方の合意である。一方で政治家からは、「小出しではダメだ」と怒られる。日銀は何をすれば、非難されずに済むのだろうか。
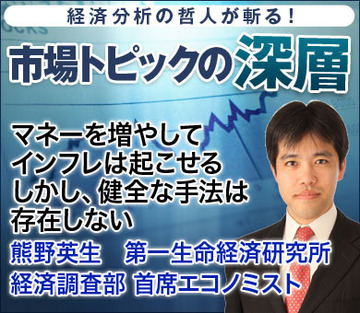
第79回
金融緩和は行なわれたものの、実物経済では製造業を通じた輸出連鎖が経済の収縮を強めている。そんななか、世界中が「政局化」し、世界的に「決められない政治」状況になっている。これは、1930年代の世界大恐慌時の環境に似ている。
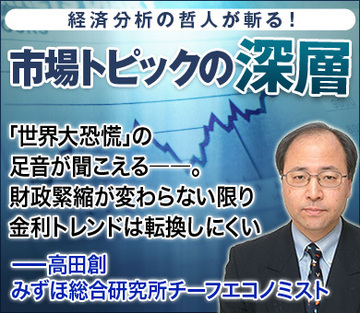
第78回
マクロ経済の先行きが見通しにくくなっている背景には、政治がある。政治家の間でも意見が分かれる財政・金融政策の行方をどう読むべきか。財政政策を「波の高さ」と「波の拡がり」、金融政策を「又は」と「及び」に注目して考えたい。
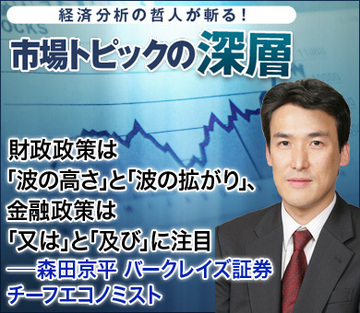
第77回
日本経済が景気後退に陥るリスクが高まっている。景気シナリオを考えるときの焦点は、米国経済の行方だ。ひとえに年始からの「財政の崖」をうまく乗り切れるかどうかにかかっているが、気がかりなのは「日本化」の兆候が見えることだ。
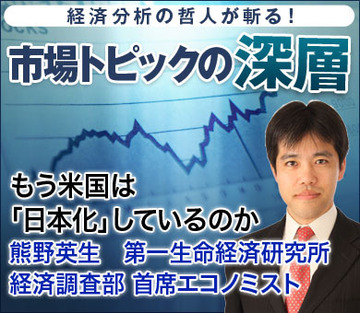
第76回
9月は、日米欧の中央銀行が同時に金融緩和のかつてない技を競い合う「金融緩和オリンピック」だった。金融緩和に伴い、長期金利上昇と市場の「リスクオン」の環境が続いており、実体経済では予想を上回るペースでの減速が生じている。