
三谷宏治
第134講
ミケランジェロの『創世記』、至高のステンドグラス『薔薇窓』、狩野永徳の襖絵。分解しては決してわからないものがあります。あるがままでしか味わえぬ価値があります。

第133講
愛用しているカゴメの野菜生活、紙パックの容器が、丸みがあって持ちやすくなっていました。問題は実は、そこではありません。新しいリーフ型では、ストロー穴の位置が手前の真ん中に来ています。なぜなのでしょう?

第132講
大ヒットを記録している映画『オデッセイ』の原作『火星の人』で、火星にひとり取り残された主人公・ワトニーは、生き延びるために何をどうハカったのでしょうか。

第131講
人間がハカる対象は、森羅万象に及びます。自然も社会も、感情も能力も、ヒトはすべてをハカろうとしています。その目的はさまざまですが、いくつかの共通点があります。

第130講
ハーレーで過失ゼロのもらい事故の後、自分が加入していた保険会社M社との長く面倒な交渉ごとのお話です。保険会社との戦いはまだ、終わっていませんでした。

第129講
2008年1月末、公道上、バイク(ハーレーVRSCD ナイトロッド07年式)で転倒しました。時速約60km。片道3車線道路(国道246号線)の左車線を通行中、右前方の車がいきなり車線変更し、私の前に躍り出ました。

第7回
三谷宏治氏の書斎大公開!本の開架、分類、面陳まで、知をオープン化する書斎術
本の収納・管理は、本好きを悩ませる永遠の課題。無類の本好きとして知られる三谷宏治氏は、どのように理想の書斎をつくり上げたのか? 本棚のサイズからデスク周りの環境、家族との共有法、分類・並べ方まで、長年試行錯誤して辿り着いた、三谷流書斎術を大公開!
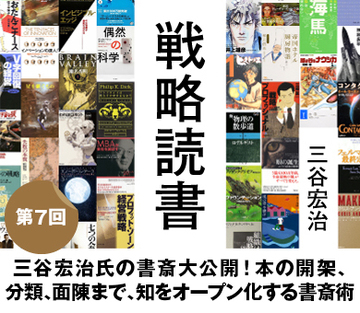
第6回
新しい視点や言葉を与えてくれるベストセラーやリベラルアーツ本の戦略的「斜め読み」
新しいテーマを切り拓き、新奇な知識や視点を与えてくれるベストセラー作品。自分にとって新しい言葉や思考法を与えてくれるリベラルアーツ本。直接仕事につながらないように思える本はどのように読むのが効果的か?
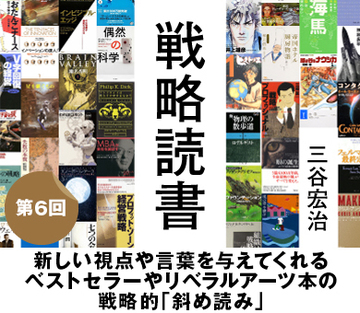
第5回
仕事と関係ない本を未来につなげる戦略的読み方とは?
仕事と直接関係ないジャンルの本はどう読めばいいのか?「非ビジネス系」の本から得た学び、力、信念を、本業につなげるには?BCG、アクセンチュアで経営コンサルタントとして活躍した三谷氏が、仕事と一見関係ないSF小説を読み続ける理由とは?
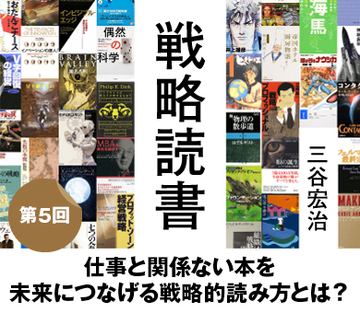
第4回
フレームワークはたくさん知ってもムダ!ビジネス書を使うには「ファクト」を集めよ
フレームワークは使いこなせなければ意味がない。使いこなすためには、ひとつのフレームワークを何度も使って自分の「技」にすること。「読書ポートフォリオ・マトリクス(RPM)」で考える、ビジネス書を実際に使いこなすための効果的な読み方。
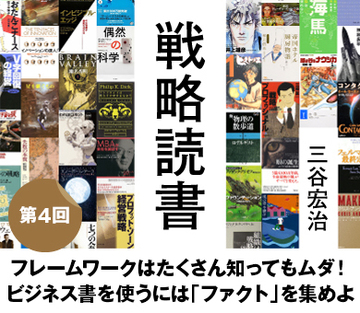
第128講
1969年の映画「イージー・ライダー」で無法者・無頼漢の象徴となったハーレーダビッドソン。1980年代後半に導入された、「従業員参画型経営」と「大人のユーザーコミュニティの構築」により、ハーレーは、性能への自己満足でなく、社会的な自己実現のためのツールとなりました。

第3回
本は戦略的に読み方を変えろ!ビジネス基礎は古典の「熟読」が一番効率的
「粗読み」「斜め読み」「熟読」「重読」…目的が変われば、読み方も変わる。本からの学びを最大化するためには、どのような読み方の戦略が有効なのか?「読書ポートフォリオ・マトリクス(RPM)」で考える、「ビジネス基礎」の最も効果的な読み方を解説。

第2回
「何を」「いつ」「どう」読むか?コモディティにならないための「戦略読書」のススメ
『経営戦略全史』等で著名な三谷宏治氏が、30年にわたって編み上げたコモディティにならないための「戦略読書」。オリジナル人材になるために、「何を」「いつ」「どう」読むかを工夫する戦略的な読書法とは?
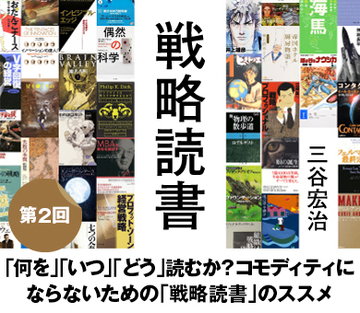
第1回
みんなと同じ本を読んではいけない!読書には「戦略」が必要だ
みんなと同じ本を読むと、みんなと同じ発想しかできなくなる。人の体が食べものからできているように、人の精神・思考もまた、読むものからできているのだ。三谷宏治氏が、30年にわたって編み上げた自分の独自性をつくるための「戦略読書」とは?
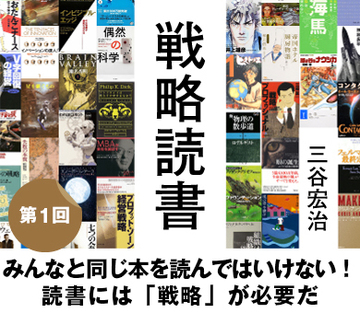
第127講
ビジネス力を本気で上げたいのならば、「何を読むか」や「どう読むか」の前に、「どんなバランスで読むか」をちょっと気にしてみませんか?「ビジネス系か非ビジネス系か」、「基礎か応用・新奇か」。その2軸で自分の読むものを意識的に配分(バランス)することで、きっと世界が変わります。

第126講
過去数十年にわたり、交通事故の発生件数や死亡者の数は減少を続けていますが、その中で唯一、増えているのが高齢者の関わる事故です。これまで高齢者の起こす交通事故は、圧倒的に男性によるものでした。しかし、最近目立つのは女性による事故です。

第125講
発見し、選択し、探究し、組み合わせる。それが正しく発想するためのステップです。そして、そこで「3つの技」を働かせましょう。それが「比べる」「ハカる」「空間で観る」です。今回は「比べる」ことでの大発見を紹介します。

第124講
二子玉川は、いま、東京で最も注目されている街かもしれません。駅東口に拡がる、二子玉川RISE(ライズ)開業のためです。二子玉川RISEの開発の中核を担っているのが東急電鉄です。30年にも及ぶこの再開発に東急電鉄がこだわったのはなぜでしょうか。

第123講
アメリカではDIYが非常に盛んで、市場規模はホームセンター全体で1600億ドルあまり、20兆円に達します。日本の5倍以上であり、各家庭にはツールキットから電動ノコギリまで、あらゆる道具が揃えられています。

第122講
「窓」という住宅設備は、省エネルギー上は最悪なパーツです。欧米やアジア各国では1970年代以降、窓の断熱性能が強く求められるようになりました。地震に強い日本の家も、こと窓(の断熱性)に関しては、欧米・アジアに比べて35年遅れの緩さなのです。
