
野地 慎
再びドル円相場は1ドル160円を超えた。円安の主因について個人も含めた実需の円売りを挙げる向きが多い。しかし、実需ベースの売買動向を分析してみると前回160円を超えた4月の場面では、円買い介入を考慮しても大幅な円売り超過とはなっていない。
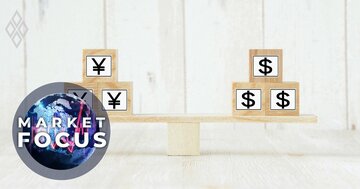
日本の円と主要国のみならず新興国も含めた外国通貨との金利差は依然大きい。過去最高水準に積み上がった投機筋の円の売り持ちに加えて、新NISAを契機に膨らんだ個人の売り持ちが膨らんでいる。これが相場が逆に動くきっかけがあればリスクオフの円買いが起きる可能性を高めている。

インフレ率下げ止まりを背景に上昇してきた米国の長期金利。4月の雇用統計の発表を機に物価の沈静化期待で低下し、水準を切り下げた。今後も沈静化が続くかどうかのカギを握る2つのポイントにつき解説する。

米国の3月のCPI(消費者物価指数)の前年同月比の上昇率が市場予想を上回ったことで利下げ開始の後ずれ見通しが強まり、金利は上昇した。移民増加が中立金利上昇をもたらし、景気拡大にも寄与したことで景気は堅調に推移している。ただ、移民増加は労働需給を緩和させインフレ圧力を和らげ、最終的には金利低下をもたらす。利下げ軌道に大きな変化はない。

日本銀行がマイナス金利を解除した。17年ぶりの利上げである。しかし、今後、さらなる利上げとなるとその道のりは険しく、円相場の上昇余地は限られるだろう。その要因を検証していく。

日経平均株価が急上昇している。インフレが継続するなか、低い実質金利の継続が見込まれること、株価は名目値の伸びを反映することを考えれば、インフレが株価上昇をもたらしているといえる。

2024年のFRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ幅についてFOMC(米連邦公開市場委員会)のドットチャートでは0.75%。市場はそれ以上の利下げ幅を織り込もうとし、10年債金利は低下するが、そのたびにFOMCメンバーのけん制発言などで再び上昇することを繰り返している。実際に、利下げ時期や水準がどうなるのかを検証してみた。

これまで米国の個人消費の強さを支えた、大型の財政出動による過剰貯蓄も底を突き始めた。個人消費は減速し、インフレも鈍化していきそうだ。FRBも景気減速前の利下げを意識しつつある。2024年にかけて米国の長期金利はさらに低下していきそうだ。

米国の長期金利は5%を天井に低下している。カナダやユーロ圏も長期金利は低下しており、インフレ低下で利下げ期待が高まりつつある。しかし、米国は長期金利低下が株価上昇をもたらし、それが消費拡大につながる構図がある。そのため、このまま金利低下局面にすんなりと入りそうにはなさそうだ。

米国10年国債利回りは5%台に乗せた。この水準は長期の中立金利に比べて明らかに高い。ゆえに短期の中立金利の上昇がもたらした水準といえる。短期の中立金利低下は米家計の過剰貯蓄が使い果たされることと株価の下落によってもたらされるだろう。

ドル高は通常であれば原油安要因だ。しかし、今は産油国の減産継続もありドル高と原油高が共存している。それは米国や欧州へのインフレ圧力となり、追加利上げの公算を大きくする。さらなる利上げは2024年に世界経済の大幅後退の可能性を高める。

長期金利の指標である米10年国債利回りの今夏における上昇は実質金利上昇による部分が大きい。一方、日本は物価上昇による期待インフレ率が高まる中、実質金利上昇は望みがたくドル高の要因となっている。円高への反転は米金利低下主導でしか望めず、2024年が最後の円高局面となる可能性もある。

日本銀行は10年国債の指し値オペの利回り水準を0.5%から1.0%に切り上げるYCCの柔軟化を決定した。これは、0.5%が天井のままでは期待インフレ率上昇による実質金利低下で円安が急速に進みかねない事態になることを予防することが狙いだ。日銀は期待インフレ率上昇に見合う長期金利上昇は認めざるを得ないと判断している。

昨年は円安要因として貿易収支の赤字が挙げられることが多かった。しかし、今年に入ってはあまり聞かなくなった。現在のドル円相場は日米の実質金利差が左右する。年初からの日本の実質金利の顕著な低下が円安のドライバーとなっている。

FRBは6月のFOMCでは利上げを見送ったが、年内の追加利上げを示唆している。しかし、インフレ率が低下する過程での政策金利高止まりは実質金利上昇を招く。それは過度に景気を冷やすことになりかねない。

米国ではサービス価格を中心にインフレ高止まりが続いている。それゆえ、FRBは6月も利上げを継続しそうである。ただ、年後半には量的引き締め策の効果が表れ、株価は下落基調になるだろう。逆資産効果でようやくインフレが抑制されることになりそうだ。

インフレ抑制のために、日本以外の主要国の中央銀行は利上げを継続してきた。ここにきて利上げを停止する動きも出始めた。結果として、日本銀行の政策修正見送りの公算が大きくなっている。それでも円が買われる理由について解説する。

SVB(シリコンバレー銀行)の破綻に端を発した金融不安は足元和らぎ、市場は平静を取り戻している。株価も反騰している。しかし、金融機関の融資姿勢は厳格化しており、利上げの代替効果をもたらしつつある。

米国のインフレ高止まり懸念で、米長期金利は上昇した。現在の水準はインフレ継続を織り込んでいる。しかし、FRB(米連邦準備制度理事会)が追加利上げ幅を拡大すれば、インフレ沈静化は十分に可能である。

FRB(米連邦準備制度理事会)は1月31日と2月1日のFOMC(米連邦公開市場委員会)で0.25%の利上げを決定し、前回に続き利上げ幅を縮小した。インフレの今後の動向を左右するのは雇用との見方が多いが、インフレ収束の予兆が表れる統計は別にある。
