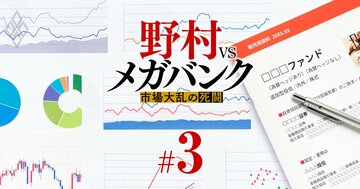岡田 悟
市況悪化で減収減益が相次ぐ証券業界。相場操縦事件で裁判が続くSMBC日興証券は事件の影響を引きずり、最終赤字は244億円と過去最悪となった。昨年の為替や金利の変動も生かし切れておらず、いばらの道は続く。

#14
生前贈与のルール改正時期が2024年に決まり、金融業界が沸いている。23年中の「駆け込み贈与」需要が見込めることに加え、富裕層や事業者向けの「相続時精算課税」制度の使い勝手が向上するからだ。両制度の利用を促すことは顧客資産に食い込む好機。税制改正をビジネスチャンスとして狙う金融業界の動向を追った。
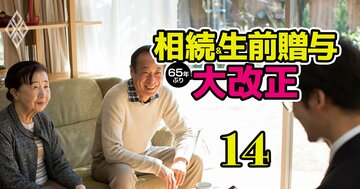
日本最大の金融グループである三菱UFJフィナンシャルグループ傘下のインターネット証券事業で、次の一手が見えない。ネット証券の勝ち組2社に他のメガバンク2社が出資を決めたが、傘下のauカブコム証券は口座数が伸び悩み、低空飛行が続く。SBIホールディングスが株式の売買手数料の無料化を仕掛ければ、ひとたまりもないと危惧する声が上がる。
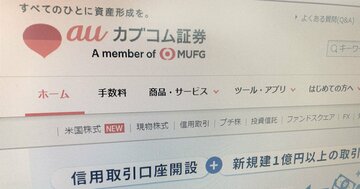
#50
年初から厳しい市場環境だった2022年。証券業界トップとして、23年の相場をどう見ているのか。苦難の歴史を経て拡大してきた海外戦略の行方は?かつて米国トップも務めた野村ホールディングスの奥田健太郎グループCEOに話を聞いた。

#41
年初からマーケット環境が悪化したものの、少額投資非課税口座(NISA)の拡充が決まり明るい日差しが差し込む証券業界。2022年は仕組み債だけでなく、「顧客本位の業務運営」を象徴する商品として販売されてきたファンドラップにも金融庁はクレームをつけた。国内個人営業は23年も引き続き我慢の1年となるのだろうか。

#4
携帯電話事業の巨額赤字で資金繰りに窮した楽天グループは、虎の子の金融グループ解体の引き金を引いたのか?楽天傘下の楽天証券に19.99%を出資したみずほフィナンシャルグループは虎視眈々と「楽天経済圏」を自陣に引き寄せる絵を描く。楽天の“大義なき”金融子会社の上場計画は、後戻りできないところまで来ている。

#9
大手製造業にとって円安は増益要因となることが多い。しかし、円安が原材料費や海外拠点のコストの高騰などを助長し、減益要因に働くケースも出てきた。日本銀行が12月に打ち出した長期金利の見直しで円安是正が進めば、その構図も変わるかもしれない。時価総額上位で対ドルの為替感応度が判明した超大手企業50社をリスト化。為替変動による業績への影響度合いを明らかにした。

#7
かつて貿易で世界を席巻した日本だが、2022年に進んだ円安は国民生活をむしばみ始めている。日本は世界最大の「対外純資産国」の地位を失い、過去にため込んだ資産を食いつぶして生きていくしかないのだろうか!?目先の相場の動きにとらわれず、円安を生み出した構造要因に加え、円安が定着すると生じる経済への影響などについて、みずほ銀行チーフマーケット・エコノミストの唐鎌大輔氏に聞いた。

#6
「弱い円」が定着すると、資産運用法も変えざるを得なくなる。そこで投資信託選びのプロであるファンドアナリストに、円安や円高の両シナリオに加え、投資を始める年齢や経験、熟練度別におすすめの投資信託46銘柄を厳選してもらった。

#2
空前の円安で海外事業の利益が膨らみ、過去最高益を更新する大手メーカー。だが、トヨタ自動車やコマツの従業員の年間平均給与を見ると…!?海外進出を強化してきた日本企業が“国内還元”できないのには、企業会計上の“落とし穴”がある。内部留保を巡る解決策も提案されているが、実現に向けたハードルは高い。
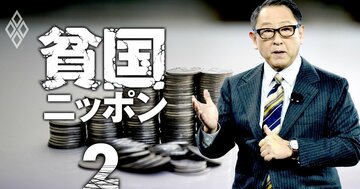
米国の仮想通貨交換業大手FTXトレーディングが、経営破綻した。顧客資産の流用など創業者によるずさんな内部管理が原因とみられ、暗号資産全体の価格が暴落するなど影響は大きい。日本でも、コインチェックで個人情報の取り扱いなどに不備があることがダイヤモンド編集部の取材で明らかになった。日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)の廣末紀之会長(ビットバンク社長)に話を聞いた。

相場操縦事件で当時の副社長らが逮捕・起訴されたSMBC日興証券。近藤雄一郎社長は11月4日、役員報酬6カ月カットの処分を発表し「(再建の)道筋をつけて身を引く」と表明した。かつて四大証券の一角を占めた日興は2009年以降、三井住友銀行(SMBC)の影響下にあるが、これまでも不祥事を繰り返してきた。

年明け以降の市場環境の悪化で投資銀行ビジネスが世界的に打撃を受けている。とりわけ注目が集まっているのがスイスの名門であるクレディ・スイスだ。昨年までの巨額損失に加え、経営陣の不祥事や交代が繰り返されていたが、再建策を3カ月示さずにいたことで市場の疑心暗鬼が加速し株価が下落。強固な財務とは裏腹に、健全性が懸念される展開となってしまった。

みずほフィナンシャルグループが、楽天証券に2割の出資を決定。メガバンクグループによるインターネット証券の囲い込みが進むが、独自性の強いネット証券のビジネスモデルまで失われてしまうのだろうか。

証券取引等監視委員会は9月28日、SMBC日興証券の元副社長が逮捕、起訴された相場操縦事件について、同社への処分を金融庁に勧告した。勧告はさらに、相場操縦とは無関係のはずの、三井住友銀行と日興の間で顧客の意に反した情報共有があった点にも言及。2社の持ち株会社である三井住友フィナンシャルグループの責任論が強まっている。

#7
金融緩和が終幕を迎え、インフレが襲う世界経済。株式、債券、M&Aアドバイザリーだけでなく、未知の領域に踏み出す野村ホールディングスの戦略に込めた狙いは?ホールセール部門長のスティーブン・アシュレー氏に話を聞いた。

#6
幾多の大リストラを経て軌道に乗った野村ホールディングスの海外ビジネスだが、米系投資銀行には遠く及ばず、日系メガバンクにも肉薄される。非従来型のビジネス強化をうたうが、未知の領域で成功できるだろうか。

#5
“癒やし系”とも評される営業スタイルへの大転換に対し、2025年3月期の収益目標は極めて大きい。富裕層シフトと“顧客本位”の人材育成をどのように実現するのか。野村證券で国内個人営業部門を率いる杉山剛専務に聞いた。

#4
証券会社にとって垂涎モノの銀行預金にリーチしたのは、大手証券会社が進める地銀との提携である。だが高齢化と人口減少が進み、「金の卵」となるかは疑問だ。そして、SBIホールディングスが進める地銀提携の危うさも浮き彫りになった。

#3
市況の悪化が証券会社の業績を直撃。そして「顧客本位の業務運営」という“錦の御旗”の下で販売を進めてきたあの商品にも金融庁がメスを入れた。悪名高い仕組み債のカラクリと共に、個人営業で稼ぐ困難さを探る。