田上貴大
7月8日、金融庁の幹部人事が発表された。氷見野良三長官は1年で退任となり、後任には中島淳一総合政策局長が昇格した。新たな幹部の顔触れを見て、早くも「次の長官」予想が始まる中で、トップ人事を巡る“ひずみ”も浮き彫りになった。

#3
みずほフィナンシャルグループが、3度目の大規模なシステム障害を起こした。顧客不信を招いたにもかかわらず、前期決算はV字回復と好調だ。だが実は、みずほはいつ発火してもおかしくない時限爆弾を二つ抱えた状況にある。

#15
EY、PwC、デロイトトーマツといった四大会計事務所が、続々と弁護士法人の立ち上げに乗り出した。新興組の彼らは、会計士や税理士、コンサルタントなどグループ内に抱える他分野の専門家を武器に、“総合格闘技”で五大法律事務所の牙城を崩しにかかる。

#11
大手法律事務所では、弁護士が働いた分だけ企業に費用を請求する「タイムチャージ」が一般的だ。業界トップに君臨する五大事務所の弁護士の時給は幾らなのか。顧問弁護士の料金相場とともに、知っておきたい弁護士の金回りを公開する。
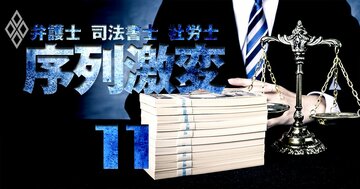
#6
弁護士業界に巨額の利益をもたらした過払い金の返還請求バブルが終焉。コロナ禍に伴う交通事故の減少で、売り上げ減に陥る法律事務所も現れた。アディーレ法律事務所やベリーベスト法律事務所など、過払いマネーで急成長した準大手・中小事務所のこれからの戦い方を探った。
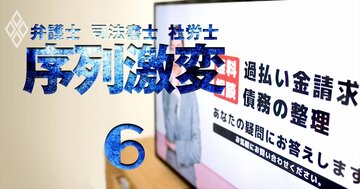
3度目の大規模なシステム障害を起こしたみずほ銀行とみずほフィナンシャルグループに対して、第三者委員会がまとめた調査報告書が、6月15日に公表された。報告書では、頭取が自行のATM障害をインターネットニュース経由で知るなど、衝撃の事実がつまびらかにされた。最たる「汚点」は、企業風土に問題があると“再び”指摘されたことだ。

ESG(環境・社会・企業統治)やSDGs(持続可能な開発目標)の流れが日本企業に到来している。メガバンクが投融資目標を打ち出す中、りそなホールディングスも負けじと「りそならしい」独自戦略を掲げる。その狙いを、南昌宏社長に聞いた。

#14
成果を重視した評価体系への傾倒や、若手人材の抜てき、所属する事業部にひも付いた「背番号」の廃止など、総合商社が次々に人事制度の抜本的改革に着手している。各社の新人事制度から、これからの商社パーソンの「出世の条件」を探った。
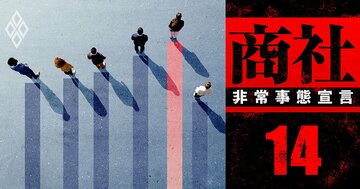
#13
金融ビジネスは今や、商社の重要な収益源の一つだ。リース子会社を舞台に繰り広げられる三菱商事と三菱UFJ銀行の主導権争いの行方や、新興の金融事業者に出資を続ける伊藤忠商事の狙いなど、商社が金融領域に侵攻するさまを明らかにする。

#10
国内外を飛び回り、時には相手の懐に飛び込んで事業を成立させる――。コロナ禍に伴う移動制限やテレワークの増加は、こうした昔ながらの商社パーソンの働き方を激変させた。現場の最前線で働いている、若手・中堅社員の本音や不安をお届けする。

#5
コロナ禍が商社業界に襲い掛かり、五大商社の明暗を分けている。最新決算から「コロナ耐久力」を独自に算出したところ、ランキング上位に食い込む専門商社の存在や、大手商社が落ちぶれる様子が浮かび上がった。
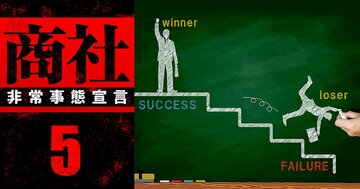
2021年3月期決算において、三菱UFJフィナンシャル・グループ(FG)が最終利益で三井住友フィナンシャルグループを追い抜き、業界首位に返り咲いた。このタイミングで三菱UFJFGは、過去最高水準の「純利益1兆円」を目標に掲げたが、幸先の良くないスタートとなり、亀澤宏規社長は危機感をあらわにする。

新型コロナウイルスの感染拡大は、会計士の仕事に劇的な変化をもたらした。監査現場で非対面のリモート化が進み、AI(人工知能)などデジタル技術の導入が加速する。それらのテクノロジーを駆使し、会計士はコロナ禍で誘発される不正会計を見破らなければならない。その一方で企業側からは、高騰する監査報酬に不満の声が上がり始めている。コロナ監査を巡る企業と監査法人の“攻防戦”の最前線をレポートする。
![「会計士vs企業経理部」コロナ禍が招く不正とカネの超攻防戦が勃発![編集長セレクト]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/360wm/img_06dd9ecde66a400b4df1a35f5e00b155300149.jpg)
社長として、ユニゾHDの規模拡大やEBOを実現させた一人の男がいる。名前は小崎哲資。みずほの副社長からユニゾHDに移った小崎氏の原動力は、みずほの総帥にまで上り詰めた男との権力闘争に敗れたことを機に、古巣に対して芽生えた怨嗟とみられる。
![全てはメガ銀で権力闘争に敗れた男の「怨嗟」から始まった…ユニゾ危機の前日譚[見逃し配信]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/0/d/360wm/img_0d13d29a023b981b9b0bd025679b3078305124.jpg)
#4
過去の金融危機の反省から、銀行業界は健全性を高める努力をしてきた。昨年来のコロナ禍では、ためた資本余力を生かして、銀行は企業からの融資要請に応えられるか否かが試されている。融資増減率と健全性の二つの観点から、“貸せる銀行”と“貸せない銀行”をあぶり出した。

三菱UFJ銀行で4月、新たな頭取に半沢淳一氏が昇格した。国内最大規模を誇りながら、銀行単体で見ると、経営の効率性を示す経費率で競合の三井住友銀行に劣っている。現状を打開するためにどうコスト構造を変えていくのか。半沢頭取に直撃した。

#9
社長として、ユニゾHDの規模拡大やEBOを実現させた一人の男がいる。名前は小崎哲資。みずほの副社長からユニゾHDに移った小崎氏の原動力は、みずほの総帥にまで上り詰めた男との権力闘争に敗れたことを機に、古巣に対して芽生えた怨嗟とみられる。
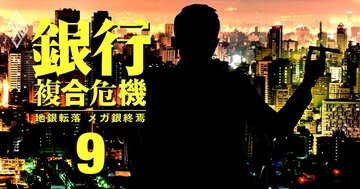
#8
みずほ銀行が大規模なシステム障害を再発した。メガバンクとしてあるまじき同じ失敗を繰り返すみずほは、収益力で3番手という現状からの脱却が一層困難になった。歴史を振り返ると、システム障害の「元凶」はユニゾ問題と通底する旧行問題だった。

#7
かつて外資のハゲタカファンドが日本に上陸し、バブル崩壊後の不良債権市場で暗躍した。現在、不良債権が静かに増加の気配を見せる中で、外資ノンバンクが日本の債権回収会社を買収。不良債権投資に着手しながら、「地銀買収」の意欲を見せている。

#6
コロナ禍に伴う企業の業況悪化が、与信コストの増加をもたらし、地銀の収益力に暗い影を落とそうとしている。今後、全国的に不良債権が急増したタイミングで赤字に転落しやすい地銀はどこなのか。独自の試算で地銀の体力を推し測った。
