宮原啓彰
#1
「生成AIによって、士業における従来の常識は一変する」。資格学校の関係者はそう口をそろえる。AI時代に負けない、もしくは逆用できる老若男女になるには、今以上に三つのスキルの習得が必要となるという。自分の価値を保てる三つのスキルと共に、どの資格から挑戦すべきか迷っている人のための「資格ステップアップチャート」をお送りする。
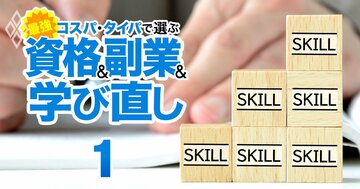
予告
ChatGPT時代の「資格・副業・学び直し」大全!雇用も流動化の時代に自分の価値を高めるには?
「自分の価値を高めたい」――。社会人にせよ、学生にせよ、夏休みは、それまでの人生を変えられる貴重な自由時間となる。自らの価値を高める手っ取り早い手段といえば、資格と副業、そして学び直しだ。だが、そのいずれもChatGPTに代表される生成AIの登場によって、市場環境が一変しつつある。また、6月に閣議決定された「骨太方針2023」では「リスキリングの強化」や「成長産業への人材移動」がうたわれた。新時代に対応できるスキルは何か?コスパ・タイパを重視した“自分磨き”の第一歩が踏み出せる裏ワザやノウハウを伝授する。

#26
少子化により厳しい経営環境が続く学習塾業界において、ひときわ業績好調なのが中学受験を主力とする早稲田アカデミーだ。売上高は12期連続、営業利益は2期連続で過去最高を更新中だ。今年5月に示された、新たな中期経営計画でもさらなる成長をうたう。だが、その足元がすくわれかねない誤算が起きている。

#20
医療保険において、がん治療に特化した商品ががん保険だ。その種類は大きく二つに分かれる。多額の一時金をもらえるタイプと、治療法に合わせて保険金が支払われるタイプだ。トップに立ったのは、両方を追求できる“欲張りタイプ”の商品だ。片やワースト商品となったのは、がん保険の代名詞、アフラック生命保険が昨年投入した新商品。その理由とは?

#18
円安で人気を集めているのが、外貨建て保険だ。ランキングは2商品が拮抗する結果となった。だが、高いリターンが期待できる一方、当然ながら為替リスクがあるため、加入には細心の注意が必要だ。保険のプロ27人が厳選した、外貨建て保険ランキングをお届けする。

#16
保険料を国内外の株式や債券などで運用し、その実績に応じて保険金や解約返戻金の額が変動する保険商品が「変額保険」だ。他の投資商品と異なるのは、運用成果とは無関係に「最低保証金額」が定められた死亡保障が付いてくる点だ。インフレに強いことから注目を集めているが、デメリットを知らなければ痛い目に遭いかねない。保険のプロ27人が厳選した変額保険ランキングと共に、人気商品の特徴を解説する。

#13
死亡保障に医療保険、資産形成……。それぞれの分野でベストな生命保険商品がランキングで分かっても、その組み合わせ方は家族構成や年齢、年収によって異なる。そこで保険のプロが、属性に応じた生保商品のトータルプランを伝授する。
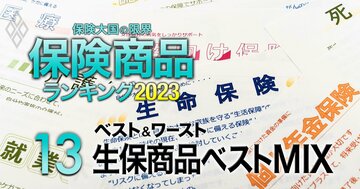
#6
相続やそれに伴う骨肉の争い“争族”対策に頭を悩ませる人は少なくない。そんな人には、生命保険を活用した相続術が強力な武器になる。商品の中には、初めから生前贈与を目的に設計されたプランも存在する。知っているようで意外と知られていない生命保険の相続活用術を伝授する。

#4
病気やけがの治療費を保障する「医療保険」。毎年のように生命保険各社が新商品の投入やリニューアルを繰り広げる激戦区において、商品選びには最新の情報を知ることが不可欠だ。そこで、保険のプロ27人が厳選した医療保険ランキングと共に、人気商品の特徴を解説する。

#2
死亡時や高度障害時のリスクに備えられる死亡保険は、家族持ちならば、真っ先に加入を検討すべき生命保険商品だろう。その一つ、「収入保障保険」は、必要な保障が割安な保険料で得られる合理的な仕組みを持つ。そこで、保険のプロ27人が厳選した、収入保障保険ランキングをお届けする。

#24
中学受験の過熱ぶりから、有名中学受験塾の席を確保するべく、小学校1~2年から通塾する子どもが増えている。どんな塾を選ぶべきか、そして親はいかにあるべきか、中学受験塾に詳しい教育家の西村則康氏と小川大介氏の対談をお届けする。

#17
首都圏で難関校に強い塾といえば、SAPIXをまず思い浮かべるはず。だが、特定の難関校を見れば、SAPIXより強い塾もある。そこで、男女御三家や筑駒、灘中など首都圏と関西の難関26校について、共学、男子校、女子校別に、最新2023年入試を含めた過去16年間の塾別合格者数を大調査。特定の難関校に強い塾に加え、現在どの塾がどの難関校の合格実績を上げようとしているのかを明らかにする。
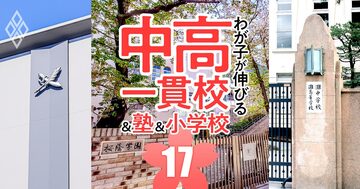
#15
わが子にピッタリな塾はどこなのか。街にあふれる塾を前に頭を抱える親は多い。そこで首都圏の主要27塾について最新2023年入試結果を含めた16年間の合格実績を大分析。子どもの学力が伸びる塾の真の「合格力」を明らかにする。

中学受験が過去最高の受験者数、受験率、過熱の「負の象徴」とされる入試トラブルも
『週刊ダイヤモンド』4月15・22日合併号の第1特集は「わが子が伸びる中高一貫校&塾&小学校」です。小学生たちの戦いが激しさを増しています。2023年の中学入試において、首都圏の受験者数、受験率は過去最高となりました。西の激戦区、関西の受験率も14年ぶりに10%超です。今春、桜が咲き誇る中高一貫校の校門をくぐった子どもたちのうち、第1志望の学校に進学できたのは、3割ほどにすぎないとされます。問題は、この史上空前の“中受ブーム”が24年以降も続くとみられていること。学校間の競争も激化し、入試トラブルも起きる中、入って後悔しない「志望校」と「塾」はどこか、中学受験以上に過熱する小学校受験を含め、その選び方や勉強法をお届します。

#12
年々、受験率が上がる中学受験。比例して、受験費用が家計に重くのしかかる世帯の比率も増えているはず。そこで、「課金ゲーム」とさえ呼ばれる中学受験にかかるお金を徹底解剖する。
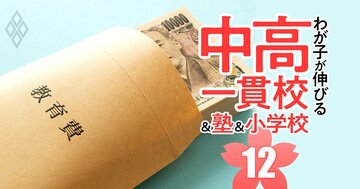
#11
急増する民間学童保育施設。3月には、やる気スイッチグループやウィズダムアカデミーなどが参画する初の業界団体が発足した。設立代表理事の遠藤奈央子氏に民間学童の選び方を聞いた。
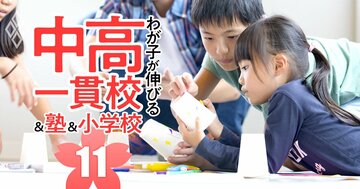
#3
わが子の塾選びに悩む親は多い。つい塾の広告に躍る難関校の合格実績から判断しがちだ。しかし、子どもの学力や志望校を鑑みて、その塾が最適とは限らない。「難関校よりも中堅校に強い」「特定の中学校に強い」など、塾それぞれに強みがあるからだ。そこで関西と東海の主要塾について、最新2023年入試を含めた過去16年間分の合格実績を大分析。子どもを伸ばせる塾の「合格力」を明らかにする。併せて灘中の合格者数で番狂わせが起きた関西塾業界の最新動向を見る。

#1
過去最高の受験者数と受験率を更新し続ける首都圏の中学受験。だが2023年入試ではコロナ禍が終息するに伴い、新たな動きが起きている。史上空前の“中受”ブームに沸く首都圏の最新入試動向について、23年最大の話題、「芝国際ショック」と共に分析する。

予告
中学受験が史上空前の大ブーム!わが子が伸びる中高一貫校&塾&小学校選びの最新事情
小学生たちの椅子取りゲームが激化の一途だ――。2023年の中学入試では、首都圏の受験者数は5万2600人(首都圏模試センター。私立・国立受験者)と、これまでのピークだった昨年を上回り、受験率(同)と共に過去最高に達した。西の激戦区、関西の受験率(日能研関西データ)も14年ぶりに10%を超える異常事態だ。問題は、この史上空前の“中受ブーム”が来年以降も続くとみられていることだ。学校間の競争も激化し、入試トラブルも起きる中、入って後悔しない「志望校」と「塾」はどこか。中学受験以上に過熱する小学校受験を含めて、その選び方や勉強法を余すところなく伝授する。
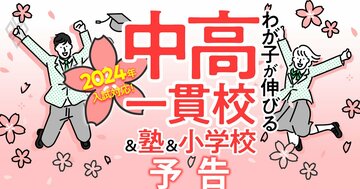
税理士になるには、通常、税理士試験で合計5科目の合格が求められるが、そのうち3科目を占める税法科目の合格を一部免除できる方法がある。科目免除制度だ。大学院修了によって、税法3科目のうち2科目を免除申請できるのだ。だが、その大学院選びを誤ると後悔することも。大学院の入試難易度と共にその選び方を伝授する。
