高口康太
米国の制裁でファーウェイに大打撃、苦境を表す2つの数字・2つの言葉
米国トランプ政権の厳しい制裁を受け続けている中国ファーウェイ。業績はまだ堅調ながら、先行きは厳しい。事態の深刻さを、経営トップが年次イベントで、2つの数字と2つの言葉を使って吐露していた。
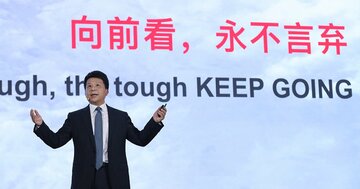
外食のコロナ禍、キャンセル率5割も…データが語る壮絶ダメージ
新型コロナウイルスで深刻な打撃を受けているのが外食産業だ。緊急事態が緩和された現在でも、休業や営業時間を大幅短縮したままの飲食店はまだまだ多い。業界が受けたダメージの甚大さは、データで見ると一目瞭然だった。

#6
「情報銀行の第一人者」が見通す個人情報のゴールドラッシュ――。CRM(企業が顧客を管理)からVRM(顧客が企業を管理)へと移行する情報銀行の未来。そして情報銀行の担い手はどこになるのか?金融機関か、それともITベンダーか。

#5
NTTドコモや丸井と提携したメルカリは、自社アプリで売買された商品だけではなく、dポイント導入店などパートナー企業で購入した商品の「見える化」を進めている。“データ経済圏”を商品開発などにつなげる狙いだ。メルカリ再加速の切り札になるか。

#4
みずほ銀行とソフトバンクが出資するJ.Scoreが、個人情報を売買する情報銀行ビジネスに参入した。売られた個人情報は英会話教室やスポーツジムの会員獲得といったマーケティングに活用されるという。ダイレクトメールよりも高い成約率になるとの期待もあるが……。

#3
GAFAやBATといった巨大企業がデータを独占する米中、そして情報ポータビリティを義務化した欧州に続く、情報ビジネス「第三の道」と呼ばれるのが、個人データを取引する日本の情報銀行だ。その仕組みはまさに身もふたもないものだった。

#2
中国が急ピッチで整備を進める社会信用システムは、『1984年』的な監視社会をつくると批判されている。しかし、その監視の目こそがビジネスの安定化、高速化を実現しているという。個人情報を巡る監視とビジネスの裏腹な関係とは?

#1
中国での売り上げを伸ばし、存在感をにわかに高めている資生堂。躍進を後押しするのが中国EC大手、アリババグループとの提携だ。アリババのビッグデータを活用することで激変した資生堂の「商品開発」の作法を探った。

予告編
個人情報は「守らず売る」時代へ、データ売買ビジネスの金脈を掘る【予告編】
個人情報は「守る」から「売る」へ――。日本発の情報流通スキームである「情報銀行」はまだ一般のなじみは薄いが、現金報酬など直接的なメリットを“ニンジン”として、ユーザーに情報を「売」らせる画期的なビジネスだ。より多くの個人データを提供するユーザーほど、より多くの恩恵にあずかれる新たなデータ売買社会、その最前線を追う。

#3
新型肺炎は中国と世界の経済にどのような影響を与えるのか? 筆者は取材のため、中国のエレクトロニクス産業の中心地である広東省深セン市に飛んだ。特集『断絶!電機サプライチェーン』(全8回)の#3は、機能停止した巨大都市の現地ルポ。執筆は帰国後、某所に隔離されて行った。
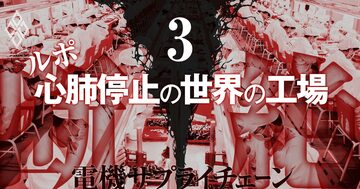
マスクが買えない!新型肺炎の感染拡大が懸念される中、日本の店頭からマスクが消えてしまった。またたく間に中国人によって買い占められたマスクは、その後どのように流通しているのか。そしてなぜ中国人は買い占めに走るのだろうか。中国を熟知するジャーナリストによる、皮膚感覚あふれる「マスク問題」ルポ。

中国シャオミ日本上陸、ソニー・シャープを超える成長戦略の凄み
中国のスマートフォンメーカー、小米科技(シャオミ)が12月9日、日本参入を宣言した。ハイスペックのスマホをはじめ、ウェアラブル端末や旅行用キャリーケースなどを引っさげていよいよ上陸したシャオミ。その成長の理由はどこにあるのか?

アリババ香港上場、調達した1.2兆円の「使い道」を深読みする
香港上場で1.2兆円を調達した中国アリババグループ。この巨額資金を、アリババは何に使うのだろうか?上場目論見書を手がかりに、巨大企業の戦略を探ってみた。

中国アリババが技術と物流の限界に挑む!「独身の日」真の注目点
かつて世界最大の商戦日は、米国のブラックフライデーだった。近年、それに取って代わったのが中国のインターネット通販商戦、双十一(ダブルイレブン)。巨大市場の消費者がアパレル製品を、家電製品を、化粧品を買いまくる。

#4
気鋭のジャーナリスト、高口康太氏による中国5G最前線レポートの最終回は、今最も注目すべき中国スマートフォンメーカー、OPPO(オッポ)の経営幹部インタビューです。気が付けば世界5位に付けているOPPOは、5G時代にどのような戦略を描いているのでしょうか?

#3
次世代通信規格、5Gの時代はあらゆるものがコンピューターにつながる時代といえる。この局面で最も重要な技術が、コンピューターの頭脳である半導体。従来、半導体を手掛けてこなかった中国のハイテク企業が次々とこの技術分野に参入している。

#2
従来の4G通信よりも格段に性能が上がる次世代通信規格、5G。これを使っていったい何が可能になるのか? 中国ではすでに、政府と企業向けの5G導入事例が百花繚乱だ。ファーウェイ(華為技術)とアリババ・グループという中国を代表するハイテク2社が開発したものを中心に、日本に先駆けて進む5Gの事例を紹介しよう。

#1
次世代通信規格の5Gが2020年、いよいよ日本で始動する。これより一足早い10月末、中国で主要通信事業者が5Gの商用サービスをスタートさせた。その中国では5G開始にあたって、官民で異様な盛り上がりをみせている。なぜこれほど盛り上がるのか。その理由を図解で解説する。

予告編
中国5G、早くも始動!気鋭のジャーナリストが最速現地リポート
次世代通信規格の5Gが2020年、いよいよ日本で始動する。これより一足早い10月末、中国で主要通信事業者が5Gの商用サービスをスタートさせた。5G時代にどのようなイノベーションが起こるのかは、お隣の国を見れば先取りできるのだ。
