猪熊建夫
第171回
東京都の南西部・町田市にある私立の玉川学園。幼稚園から大学院まで展開する一貫校だ。「全人教育」と「個性尊重」を教育理念として掲げる。のびのびとした校風を背景に、多くの文化人や芸能人を輩出してきた。
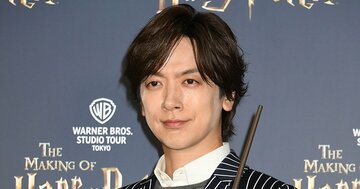
第170回
南西を長崎半島、南東を島原半島に接する諫早(いさはや)市。長崎県の交通の要衝だ。そこにある長崎県立諫早高校は、附属中学校を持つ併設型中高一貫校だ。略称は「諫高(かんこう)」だ。
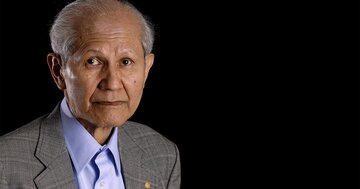
第169回
東京都港区三田といえば、慶応義塾大の所在地として知られる。都立三田高校はそのすぐ北側にある。戦前は高等女学校だったが、「良妻賢母」教育はせず実務型の教育に徹した。文化人として活躍した卒業生が多い。

第168回
山に囲まれた盆地にある長野県諏訪市。県立諏訪清陵高校の校風は「自治・質実剛健・勤勉努力」だ。地域の気候・風土の影響を濃厚に受け継いでいる。

第167回
東京の下町・墨田区にある男女共学の中高一貫校だ。1913年に日本大学最初の付属校として誕生した。個性が突出した魅力あふれる文化人などを多数、輩出している。

第166回
京都市南区にある京都府立の高校だ。旧制京都二中の後継校として、120余年の校歴を受け継いできた。1915年に開かれた第1回全国中等学校野球大会(現在の甲子園大会に相当)の優勝校、という栄冠を背負っている。

第165回
「栃木県」という県名の由来になった栃木市(栃木市の名の由来となった「栃木町」が、最初の県庁所在地だったため、県名にもなった)にある、県立の伝統校だ。校内には明治から大正時代に建てられた三つの建物が、国の登録有形文化財として残されている。略称は「栃高(とちたか)」だ。

第164回
人材の豊富さと個性の多様性が持ち味の慶応義塾高校(横浜市港北区日吉、略称は「塾高」)。学業だけではなく趣味もハイソで、音楽科や美術科などは設置されていないのに第一級の芸術家や文化人になった卒業生も数多い。

第163回
慶応義塾の創設者である福沢諭吉は『学問のすゝめ』という啓蒙書を著した。慶応義塾高校(塾高、横浜市港北区日吉)の卒業生で、その教えに従って学者・研究者になった者も多数、出ている。

第162回
神奈川県横浜市にある私立男子高校だ。通称「塾高」で、慶応義塾大学の1、2年生が通う日吉キャンパスと同じ敷地にある。ほとんどの生徒が慶応大に進学できるため、人気がすこぶる高い。

第161回
山形県の県庁所在地である山形市にある県立高校だ。全国の県庁所在地にある「旧制一中」のひとつに数えられる。この10月29日には創立140周年記念式典を開く。

第160回
福岡市早良区にあるキリスト教系の私立中高一貫校だ。100余年の校歴があり、福岡県を代表する伝統校の一つだ。男女共学で、略称は「西南」(せいなん)だ。
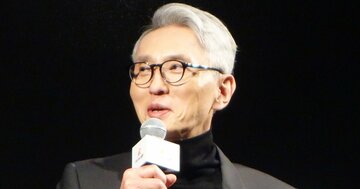
第159回
「あの歌手も、この俳優も青山」といわれるくらいに文化人や芸能界で著名な人物を多数、輩出している。青山学院高等部の、その華やかなイメージを作りだしている卒業生たちを紹介しよう。

第158回
東京・渋谷区の青山といえばおしゃれで、トレンディーな街として知られる。その青山通りに面して、高等部は青山学院大と同じキャンパスの中にある。受験勉強にとらわれない自由な高校生活を満喫できるため、趣味も豊かな生徒が多い。「柔和で素直」なのが、青山学院高等部(以下、青学高等部)の校風だ。

第157回
「しゃくじい」高校という。東京・練馬区にある。東京府立第十四中学校を前身とする都立の伝統校だ。「文武二道」を掲げ、「スポーツの石神井」と呼ばれている。

第156回
「文武両道」を体現している高校だ。北海道のほぼ真ん中に位置し、札幌に次ぐ第2の都市・旭川。ここに前身の北海道庁立上川中学校が設立され、戦後の学制改革によって道立北海道旭川東高校となった。通称は「旭東(きょくとう)」、あるいは「東高(とうこう)」だ。

第155回
「文武両道」を体現している高校だ。北海道のほぼ真ん中に位置し、札幌に次ぐ第2の都市・旭川。ここに前身の北海道庁立上川中学校が設立され、戦後の学制改革によって道立北海道旭川東高校となった。通称は「旭東(きょくとう)」、あるいは「東高(とうこう)」だ。

第154回
東京都港区で、女子だけの12年間の一貫教育を続けている聖心女子学院。文化人、学者・研究者、スポーツ選手などとして活躍しているOGに焦点を絞ってみよう。

第153回
東京港区の閑静な住宅街の一角に、ひっそりとたたずんでいるのが、聖心女子学院だ。初等科(小学校)から高等科(高校)までの12年一貫教育を基本とした、カトリック系の伝統校だ。
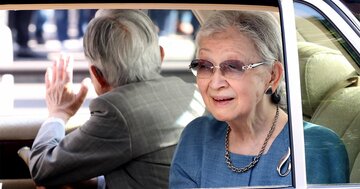
第152回
千葉市中央区の県庁近くにある県立高校だ。前身の旧制中学の創立以来、140余年の伝統を誇る。2008年度から中学校を併設し、中高一貫教育になっている。
