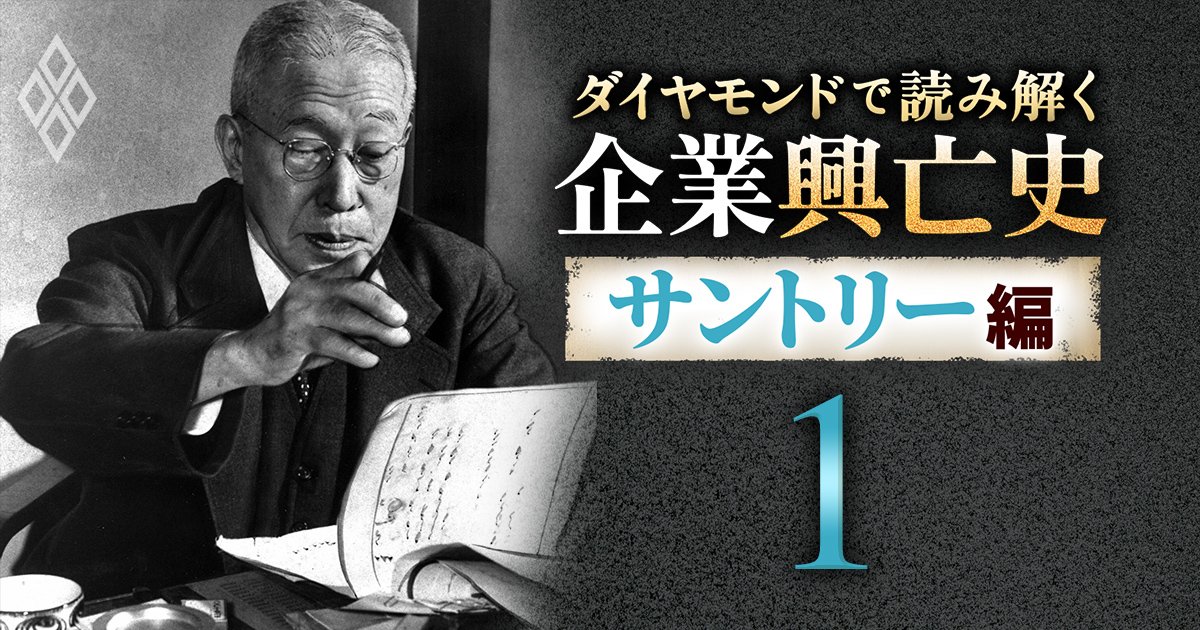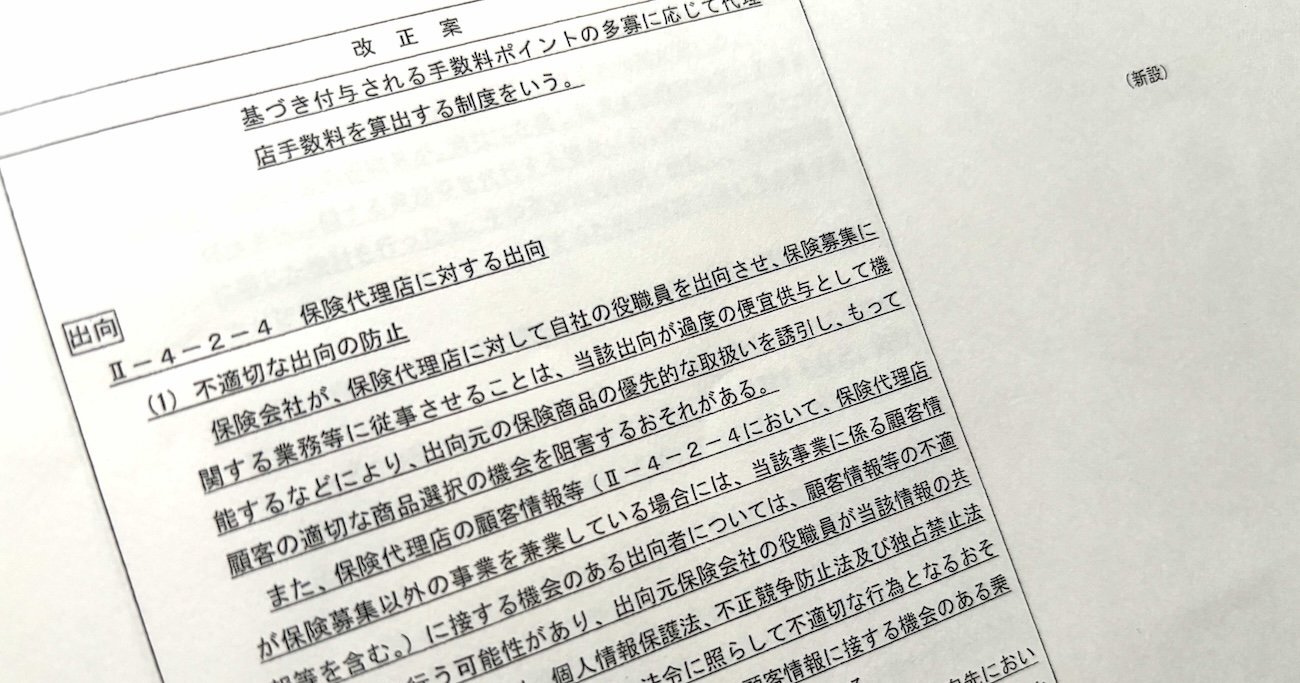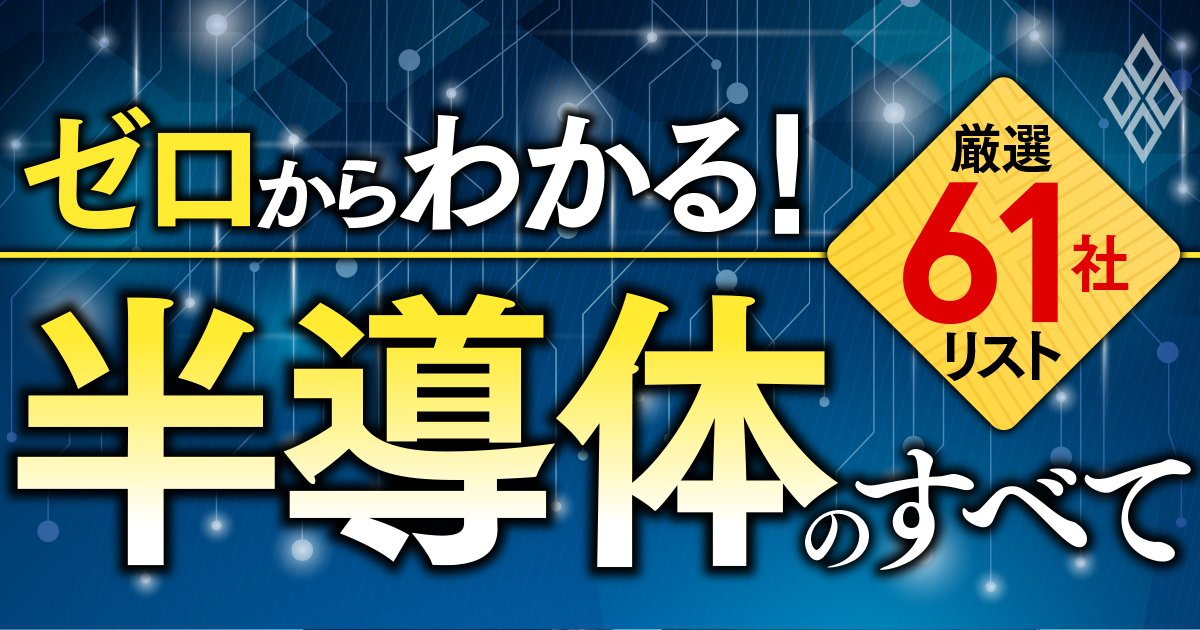Photo:Howard Kingsnorth/gettyimages
Photo:Howard Kingsnorth/gettyimages
長時間の残業がつらくても、真面目に働き出世すれば、それに見合った給料が得られる。そんな日本のサラリーマンの成功ストーリーが、崩壊しつつある。国際比較すると、日本は「給料があんまり上がらない国」というのが現実なのだ。特集『安いニッポン 買われる日本』(全24回)の#17では、日本企業の経営幹部の給料が中国、韓国、さらにはフィリピンやタイをも下回るという、日本の給料の実態をデータで浮き彫りにする。(ダイヤモンド編集部副編集長 杉本りうこ)
韓国が肩を並べ、中国にも抜かれ…
他国より昇給率の低い日本
日本の企業の平均賃金が低いことは、本特集でOECD(経済協力開発機構)のデータを使ってすでに解説した(関連記事 本特集#1『日本人は韓国人より給料が38万円も安い!低賃金から抜け出せない残念な理由』)。今回は組織・人事コンサルティングのマーサージャパンのデータを使い、企業における昇給と給料の関係を分析する。
マーサーは世界約140カ国で企業の報酬(給料)調査を行っており、一般社員から経営層まであらゆる職階の実際の給料データを1500万人分集積している。今回はこのデータのうち、日米中など15カ国の企業の給料(基本給、諸手当などを合計した年間の支給実績額の中央値)を比較できるよう、グラフ化した(次ページにグラフ)。
日本は非管理職のスタッフレベルでは、給料は決して低くない。金額は704.2万円で、15カ国中では米国、ドイツ、オーストラリアに次ぐ4番目に位置している。なおこの金額は、働く日本人の実感からするとかなり高額だ。それは(1)手取り額ではなく、中長期インセンティブなどあらゆる報酬を含めた企業側の支給額であること、(2)調査対象の企業における大手企業の比率が高いことが理由だ。
ところが課長レベルになると、スタッフレベルでは日本を下回っていた韓国に、ほぼ肩を並べられる。給料の上昇カーブが、韓国の方が急なのだ。中国もカーブが急だ。課長から部長になる間にほぼ倍増の勢いで昇給し、日本の部長の給料を追い抜いてしまう。