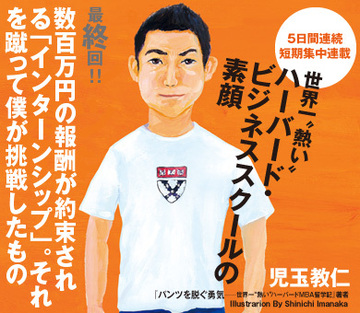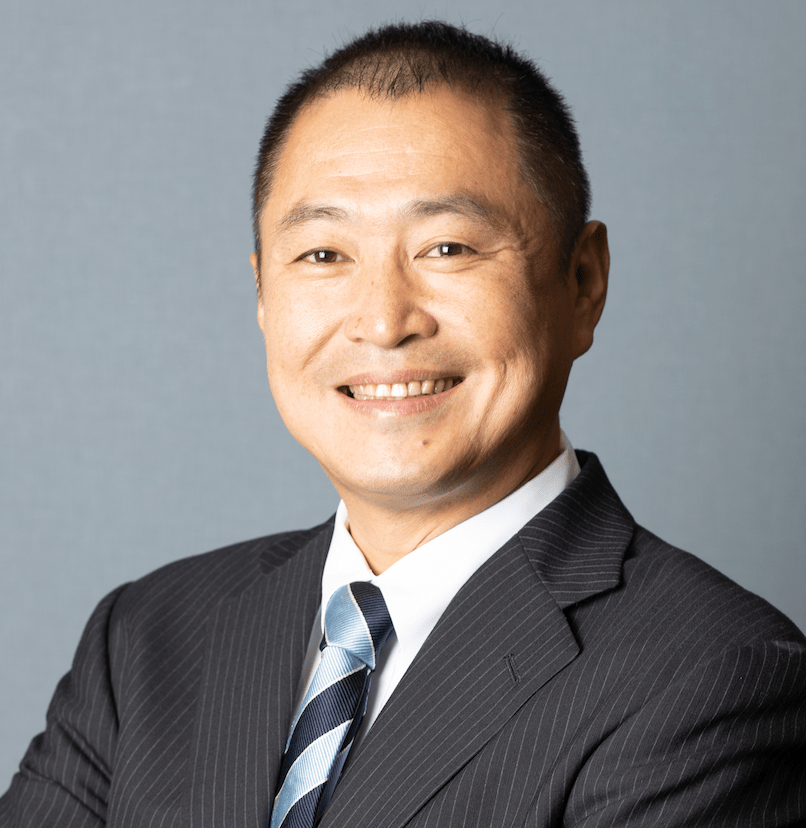
児玉教仁
第15回
最初が肝心!会議でメンバーの本気を引き出すコツ
アジェンダを告げる際に気をつけたいのは、周りを巻き込むことである。会議の運営上は、最低限、議題を共有できればよいが、そこで「皆で議題を作る・合意する」という巻き込むプロセスを入れれば、参加者の本気度合いがぐっと変わってくる。

第14回
よい会議は、理想と現実のギャップを埋めていく
アイスブレークで打ち解け、「すごいチームに所属した」というプライドをメンバーが共有できたら、いよいよ実際の会議に入る。これまで述べてきたように、あうんの呼吸では何も伝わらない。よい会議は、「いけてない現状」と「何となくわかっている理想の姿」との間にあるギャップを埋めるための、具体的な道筋を示すものだ。ここでは、3つのステップで進めていく方法を紹介する。

第13回
G7でダントツ最下位!ステレオタイプな価値観が「事故」を招く
たとえば、ガタイがいい人に「何かスポーツでもやっていましたか?」と聞く。実はこれは、「体格が良い=スポーツ経験あり」という決めつけによるステレオタイプ化で、たとえ褒めたつもりだったとしても、それ自体が問題となることがある。会社からお茶の間まで、日本にはびこる「ステレオタイプ化」の根はけっこう深い。男女格差指数にいたってはG7でダントツの最下位でもあり、注意が必要だ。

第12回
「まだまだ勉強中ですが」へりくだった挨拶は逆効果
ビジネスパーソンは忙しい。誰もがたくさんの仕事を抱えている。会議の中身を充実させることは大事だが、なにより、この会議体が一番大事だと思えるようにする必要がある。そこで、まずは相手や仲間をとにかく褒めて意欲を高め、「すごいチームに所属した」というプライドをもってもらうことがポイントとなる。
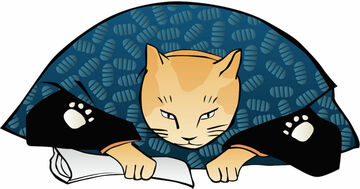
第11回
言いづらいけど迷惑…偉い人の「表敬訪問」
シリコンバレーやエストニアなど、注目の集まる海外地域で働く日本人に共通する悩みは、日本の本社や取引先のお偉いさんから、現地企業との顔つなぎを頼まれることだ。生き馬の目を抜く世界では、単なる「情報交換」のようなふわっとした目的の訪問など、無視されて当たり前。いくら社長や役員が表敬訪問したいといっても、そう簡単にアポは取れないからだ。

第10回
相手の心をつかむ人は、アイスブレークがうまい
雑談を通して相手のことを知ろうともせず、いきなり本題に入るのは失礼に当たる。とはいえ、会ったばかりの人と、いきなり込み入った話をするのは難しい。自然な流れで雑談に入るには、とっつきやすい「つなぎ」があると便利である。

第9回
「名乗りを上げぃ!」武士の時代から進化してない日本人
日本人の自己紹介は丁寧すぎる。「我こそは、○○家家臣、○○家嫡男、○○○である!」と、まるで戦国武士の名乗りのようで、必死に身分を紹介しようとしがちである。それが悪いとは言わないが、組織名やタイトルの棒読みで回りくどい印象を与えるのは損だ。

第8回
第一印象でなぜか損する、日本人のもったいなさ
日本人は、特にビジネスの場では、「丁寧な言葉遣い」や「礼儀正しい振る舞い」で相手への敬意を示し、プライベートで友人たちと過ごすときとは違う顔を見せる。この厳密なまでの「公私の区別」は世界でも珍しく、日本人がビジネス上でオフィシャルな感じを出そうとすればするほど、海外の方からすると理解しづらいものとなってしまう。

第7回
存在感がないのはNG!会議で生き残る方法
映画に誘われたとき、「今週末は、ちょっと……」と語尾を濁せば都合が悪いことが伝わる。「箱根か草津に行かない?」と言えば、おのずと温泉に入ることが前提になっているとわかる。言葉に全部出さなくても察し合える――これは日本ならではの高文脈のコミュニケーションであり、グローバルでは通用しない。

第6回
「時間の無駄」と指をさされる、日本の会議の問題点
日本の会議では物事が決まらない、せっかく集まっているのに何も決まらないのは、時間の無駄遣いではないか、と海外の方から指摘されることは多い。方向性はもちろん、具体的なアクションプランにまで落とし込まれていなければ、物事を決めたとみなされない。

第5回
「察してくれないあなたが悪い」が通用するのは日本だけ
ところ変われば習慣も変わる。カルチャーギャップからすれ違いが起きることも少なくない。本連載では、折に触れて、ありがちなエピソードをコラムとして紹介する。

第4回
「英語が下手」なのは単なる個性、ネイティブレベルは必要ない
前回、グローバル・モードにシフトするためには、「思想」「伝達方法」「ビジネスの進め方」の3つを押さえる必要があるとご紹介した。逆に言えば、英語が多少苦手でも、このモードの切り替えができれば、ビジネスはできるということだ。

第3回
きれいな英語表現を覚えても、ビジネスで失敗する理由
前回、「日本人は空気を読むのが得意というけれど、私たちが得意とするのは、あくまで日本ローカルの空気。そのままグローバルに出ても、無意識に地雷を踏むことがある」と紹介した。では、どのような点に注意すればよいのだろう。

第2回
英語研修では身につかない、日本人に決定的に足りていないスキル
リモートワークがスタンダードになるにつれて、コミュニケーションや会議の進め方が変わりつつある。日本的なあうんの呼吸に頼れなくなったとき、新しいビジネスの作法は、空気を読み合う「ローカル・モード」から、誰でも明確にかかわりあう「グローバル・モード」に近いものとなっていく。

第1回
なぜ日本のビジネスパーソンはオンライン会議が苦手なのか
企業によっては在宅ワークが3カ月近くに渡り、オンライン会議もすっかり日常化している中、情報伝達、会話のやり取り、仕事の進め方が変わりつつある。

第4回
高校時代、英語で赤点の常連だった著者は、ハーバード・ビジネス・スクールで、グローバルで活躍するために必要な本物の英語力を知った。それは人としてのコミュニケーションの本質なのだ。それはたとえば忘年会の幹事でも磨かれるものなのだ。
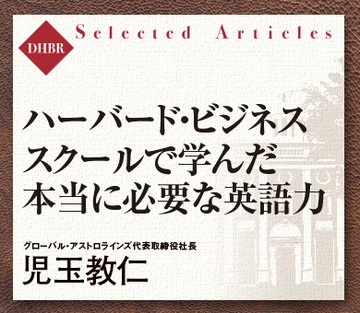
第3回
言葉が通じないからと言って、言いたいことを諦める。英語が苦手な人がよく経験することだろう。しかし、ハーバード・ビジネス・スクールで本当の英語力を学んだ筆者は、これを完全に否定する。英語力より先に伝える覚悟を身につけるべきだと。そしてそれは、英語力とは違い、一日で身につけられるという。
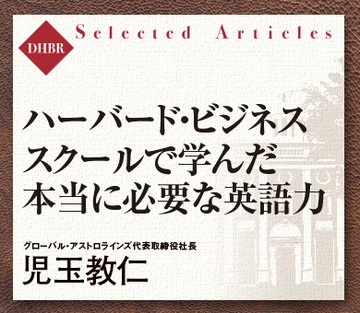
第2回
英語の勉強法はかずかずある。しかし「本当に必要な英語力」を伸ばそうとするなら、「英語で大声で叫ぶこと」。単純なようで幼稚に見えるこの方法が絶大な効果を発揮する。
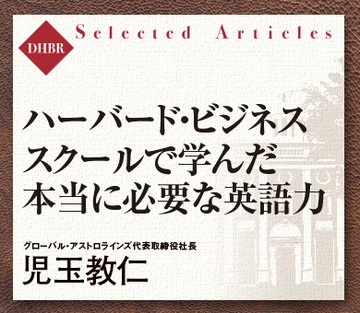
第1回
高校時代に赤点をとり英語が苦手だった著者が、ハーバード・ビジネススクールの面接試験に挑む。そこは本当の英語力とは何かを教えられる場だった。
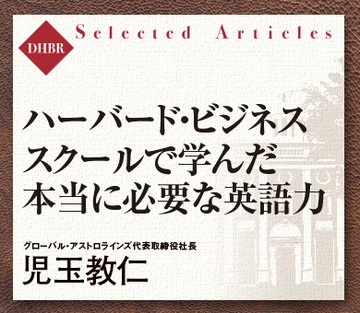
最終回
数百万円の報酬が約束される「インターンシップ」。それを蹴って僕が挑戦したもの
世界最高峰のMBAと言われるハーバード・ビジネススクールの素顔を紹介する本連載。最終回の今回は、MBA生たちのインターシップについて。一流企業から100万円単位の報酬を約束されるインターンシップ。しかし、それを蹴って著者が挑戦したのは、アメリカを代表するジャンクフード、バッファローウィングの全米調理選手権だった。