
王 青
9月5日、埼玉スタジアムで行われたサッカーワールドカップのアジア予選で、日本に0-7で敗れた中国。実は中国では、この結果が大変な騒ぎになっている。中国代表に対し激怒する人々、ネットにあふれる批判、さらには対日感情も変化の兆しがあるという。サッカー日本戦の結果が、中国社会に与えた衝撃とは?

「患者の息子が医師をメッタ刺し」「血の海で倒れる女医」…中国でなぜ医師が患者に殺されるのか
7月下旬、中国の大学病院で診察中の医師が刃物を持った男に襲われ、殺害されるという衝撃的な事件が起きた。日本人からすると信じられないできごとだが、実は中国では、医師が患者やその家族に襲われるこうした事件が後を絶たず、「世界で最も医師が殺される国」となっている。なぜ、中国の医療現場では、医師と患者の関係がここまで悪化しているのか?中国の医療制度の深刻な現状を解説する。

長年、日本と中国の介護ビジネスに携わってきた筆者は、今年6月中旬に中国・上海で開催された中国最大級の国際介護福祉展「AID」(旧称:China Aid)を訪問した。コロナ禍後、久しぶりの中国訪問で、多くの地元介護事業者と対話する機会を得た。本記事では、改めて感じた中国と日本の介護事業者間のギャップ、そして中国市場で介護ビジネスを展開しようとする日本企業の課題についてレポートする。

廃棄物ソーセージ、毒入り粉ミルク、石油燃料入り食用油…中国の食品安全問題はなぜ無くならないのか?
7月上旬、中国で発覚した石油混入食用油問題。国民の怒りが爆発し、食の安全への不信が再燃した。中国ではこれまでも何度となく食品安全問題が明るみに出ている。廃油を食品に再利用する、毒入り粉ミルク、水でかさ増しした肉、廃棄物で作ったソーセージ……中国は世界第2位の経済大国になったはずなのに、こうした問題がなくならないのはなぜなのか?

カフェの男性店員が女性客をビンタ!でもネットは「よくやった、いい気味だ!」中国で起こる異常事態の背景とは?
店員が客を平手打ち。手に持ったコーヒーの粉を客に投げつける……上海の人気コーヒーチェーン店で立て続けにトラブルが起き、動画がSNSで拡散され、大きな反響を呼んだ。もしこれが日本であれば、客に手を上げた店員は相当世間に責められることになりそうだが、中国でのコメントの多くは店員を擁護し、客を責めるものだった。なぜ人々は店員の味方をするのだろうか?実はこの背景には、急成長する中国のコーヒー市場と、過酷な労働環境という二つの問題が潜んでいる。

中国・蘇州で、日本人学校のスクールバスが刃物を持った男に襲われる事件があり、犯人の男に立ち向かった中国人女性が亡くなった。この他にも中国では、外国人を対象にした無差別殺傷事件が起きている。背景にあるのは、中国社会の閉塞感や経済不況、そして今も続く反日教育だ。中国では今も反日ドラマや映画がたくさん放映されているほか、SNSも閉鎖的で海外の情報に触れることが難しい。さらに昨今は「日本人学校はスパイを養成している」といったデマ動画が拡散されSNSで人気を集めている。このデマ動画の元となった動画を撮影した男性に、話を聞くことができた。

【靖国神社に落書き、放尿男】「日本は弱腰」「山口組に期待」中国での意外すぎる反応
東京・千代田区の靖国神社で、石柱に放尿するような動きをしたあとに落書きをして立ち去る男……こんな動画が中国で拡散、話題になっていた。日本で上がっているのはもちろん怒りの声だが、中国では賛否両論、さらには日本人からすると意外な反応も起きている。この男はいったい何者で、どんな狙いでこうした行動に走ったのか。

「反日商法」で中国ミルクティーの売上高が400倍!→ヤラセが即バレで批判殺到のお寒い事情
今年のゴールデンウイーク、中国からの海外旅行先で一番人気は日本だったという。しかし同じ頃、中国では「反日」「愛国行為」を打ち出したことにより、ミルクティーで有名なある飲料メーカーの売り上げが400倍と激増するという事態が起きていた。日本人の目から見ると不思議としか思えない「愛国行為」とは……。

中国・上海の公園で「親の代理婚活」が名物化!収入、学歴…個人情報をチラシでばらまく深刻な事情
中国・上海の人民公園では週末になると自然発生する「親の代理見合い」が名物になっている。公園に親たちが集まって、子どもの代わりに結婚相手を探すのだ。親たちはなぜ公園に通い続けるのか。筆者は数年ぶりに週末の人民公園を訪れこの名物イベントが徐々に様変わりしているのを目の当たりにした。少子化や高齢化、世代間ギャップ……ここには中国社会のさまざまな社会課題が凝縮されている。

中国Z世代「10年働けば年収2000万円」の豪語が「生まれる時代を間違えた」の絶望に変わったワケ
若者が控えめになった、おとなしくなった――こう聞いたら、あなたは「いいことだ」と思うだろうか、それとも「大丈夫か?」と不安になるだろうか?日本の若者は昔に比べて謙虚でおとなしい人が増えている印象があるが、中国では今、約2.6億人いると言われるZ世代の行動や思考、特に就職やお金に対する考え方が大きく変わりつつあることが注目を集めている。どう変わったのかというと……。

中国と日本の経済は「逆転」した?3年ぶりに上海を訪れた私が見た“驚きの光景”
先日、3年ぶりに中国を訪れて驚いた。以前とはまったく異なる光景が広がっていたのだ。街に人がいない。景気が悪い。社会に活気がない……そんな中国から見ると、現在の日本は「中国よりもはるかに活気がある」と感じるようで、多くの中国人が「中国と日本は何もかも逆転した」と口を揃える。そう言われても、日本に住んでいる筆者はこのような実感がなかったが、実際に上海を訪れ、現地で話を聞いているうちに、その意味が分かった気がした。中国経済はバブルが弾けてしまったのではないだろうか。そう、かつての日本のように……。

「汚染水の天罰」「祝杯だ」中国SNSで能登震災に心ない投稿…日中友好の美談まで改ざんの豹変も
元日に能登半島地震、翌2日に羽田空港でのJAL機炎上事故と、新年早々大きな災害が相次いだ日本。中国でもその様子は詳しく報じられているが、ネットでは災害を喜ぶような心ない声が目立つ。

台湾では「日本はライバル」と聞くけど…外国人“介護人材”の獲得競争は日本のボロ負けだ
日本と同じく高齢化が急速に進む台湾は、高齢者の介護人材不足という問題を抱えており、外国人労働者に頼ることでこの問題を解決しようとしている。一見、日本と同じような解決方法に見え、台湾の人たちもしきりに「この点で、日本は我々のライバルだ」と言うのだが、実態を知れば知るほどまったくライバルではないと思えてしまう。というのも、台湾がリードしすぎていて、日本は勝負のスタートラインにすら立てていないからだ。

白い防護服、手にニラ…中国・上海のハロウィンが日本人の想像を絶する「悲壮さ」だった理由
渋谷区長が「来ないで」と発言、厳戒態勢の中行われた今年の東京のハロウィーンは例年よりもあまり盛り上がらなかった。その一方、大変なにぎわいで、11月に入ってからも中国で話題沸騰中なのが、上海で行われたハロウィーンの様子である。ハロウィーンを通じて、中国の若者たちが発信したメッセージとは?

中国人の爆買いは「もう死んだ」…日本への団体旅行解禁でも期待外れに終わる理由
8月10日、中国政府は日本を含む海外への団体旅行をついに解禁した。コロナ前のように中国人観光客が大勢やってきて、“爆買い”が復活するのではないか、とインバウンド効果に期待する声は大きい。しかし、中国からの個人・団体旅行客をよくアテンドし、買い物の同行もしている筆者は「団体旅行客が急増することはないし、爆買いも復活しないだろう」と予想する。その理由とは?

中国で「汚染水で海水が2色に」のデマがトレンドに…処理水問題で中国人が大荒れする内情
東京電力の福島第一原発処理水の海洋放出をめぐって、中国から強い反発が起きている。中国では処理水ではなく「汚染水」と呼ばれ、SNSは、今や連日この件一色。「微博(ウェイボー)」や検索エンジン「百度」では、人々の最大の関心事となっており、毎日のように注目ランキングの上位を占めている。「汚染水が放出された現場、海水が二色になった」「福島原発事故の影響で、日本のがん患者数が年々増加」などのタイトルが付いた記事のアクセスが急上昇している。おそらく多くの日本人が思っているよりも、中国人の反発はかなり激しい。尖閣諸島問題の頃と同じくらいという声もある。なぜこうした事態になっているのだろうか?

母の悲痛「バレーボールをやらせなければ…」天井崩落11人死亡、中国全土が涙と怒りに震えた理由
7月23日、普段と何も変わらない日曜日の午後。ある衝撃的なニュースが中国全土に走った。黒竜江省チチハルにある中学校の体育館の天井が突然崩落し、中にいた生徒ら11人が生き埋めとなり死亡したというのだ。このニュースは瞬時に拡散され、中国のほとんどのSNSプラットフォームでアクセスランキングの1位となった。夏休みの真っただ中に、一体何が起こったのか。

中国のメディアやSNSでは、最近、日本の若者の就職率や株価について、また、バブル期や「失われた30年」を振り返るような記事に注目が集まっている。背景にあるのは、経済の低迷と、雇用状況の悪化だ。状況が悪化するあまり、就職や働き方にまつわる新語や珍現象が数々登場しているという。
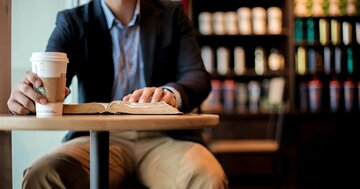
最近、中国人富裕層が日本に移住し、日本の不動産を爆買いしているという記事をよく目にするようになった。「日本が買い占められるのではないか」と心配や不快感を抱く日本人も少なくない。確かに、コロナ禍を経て中国から日本へ移住する人が増えている。しかしその中心は、富裕層ではなく「中間層」で、不動産購入どころか家族と一緒に賃貸住まいをしている人も多い。今回、2022年に中国から日本にやってきた2組の家族に直接会い、話を聞くことができた。

ある中国人が羽田空港で体験したことをまとめた動画が、中国で大きな反響を呼んでいる。「感動した」「泣けた」と大絶賛なのだが、日本人の感覚では「そんなにすごいこと?」と疑問に思うような内容だ。これに限らず、日本に来た中国人は、意外なところに喜び、感心する。しかし逆に、日本人が思う「おもてなし」が逆効果になっている場面も珍しくないという。
