
鈴木明彦
日銀の次の利上げは4月までにと予想する声が市場では広がるが、日銀には金利正常化ペース加速の思惑から長期金利上昇に拍車がかかり、国債減額が計画通り進まない懸念がある。次の利上げは、消費税減税の議論が長期金利や為替の動向に与える影響にも注意を払いながら、早くて7月ということになりそうだ。

日本銀行は12月の金融政策決定会合で政策金利を0.75%に引き上げたが、今後も金利正常化を進め、早ければ2026年7月には政策金利は中立金利の推計値下限の1%に達するだろう。それで打ち止めの可能性もあるが、その後は手探りながら最終ゴールは「1.25~1.75%」になるのではと予想する。

日銀は12月の金融政策決定会合で、今年1月以来の政策金利引き上げを決める可能性が高い。その後の利上げシナリオを展望する上で注目は、植田総裁が中立金利の水準でどのような見解を示すかだが、1.5%台半ばを中心に想定し、27年度まで半年から1年ごとをめどに利上げを進めると考えられる。

日銀の追加利上げ見送りの背景には「積極財政・緩和維持」を掲げる高市早苗新政権の発足があったとみられるが、日銀ももともと10月ピンポイントではなく、来年1月までの間での追加利上げがメインシナリオだ。高市首相に利上げを納得させるには、利上げの必要性を強調するよりも、利上げによる景気下押し懸念を取り除くことが重要だ。

高市早苗氏が自民党総裁に就任したことで市場では「サナエノミクス」への期待が高まり、10月の利上げ観測を後退させた。しかし、その見立てはあまりに短絡的ではないか。本稿では、「デフレ脱却」というスローガンの意味が歴代政権でいかに変容してきたかを解き明かし、高市氏の経済政策と日銀の現在の方針が、巷で言われるほど対立していないという意外な事実を論証し、政治が不安定な局面だからこそ、日銀が10月の利上げに踏み切るべきなのかについて解説する。

3%以上の物価上昇が続く中、政策金利据え置きを続ける日銀に対して「ビハインド・ザ・カーブ」に陥っているとの批判も出始めた。たしかに日銀は物価高や円安への対応での利上げには消極的だが、トランプ関税の景気への影響などを注視しながら、金融政策正常化に向けて「10月利上げ」を目指すと考えられる。

トランプ米大統領が8月1日実施で新たな相互関税率「25%」を提示したが、日本経済への影響は今後の日米交渉の行方や企業の価格転嫁戦略、為替動向などが鍵になる。ただ、日銀の金融政策正常化の基本姿勢は維持されており、支店長会議などが予定される10月の金融政策決定会合で利上げ再開を決める可能性は十分ある。

日本銀行が5月の金融政策決定会合で政策金利を据え置いたのは、トランプ関税の不確実性の中、目先の利上げにこだわらない一方、いつでも利上げが再開できるよう金融政策正常化の道を残すためだ。早ければ次々回の展望レポートが出る10月決定会合で、次の利上げの可能性が高まる。

トランプ政策の不確実性があるものの日銀は半年ごとをめどに利上げという基本シナリオは変えず次の利上げは7月の可能性が高い。国債買い入れ減額も同時に進み、政策金利が中立金利水準の1.5%程度になると見込まれる2~3年後には、長期金利は2%台後半になる見通しだ。

日銀が1月の金融政策決定会合で利上げを決定、植田総裁は「展望レポート」で示した経済・物価の見通しに沿って推移し、先行き、見通しが実現していく確度が高まっていることを最大の理由として挙げた。いわば日銀は、展望レポートを基本にした政策判断をするという正攻法のもとで金融政策の正常化を進める姿勢といえる。だが、「半年ごとに一度の利上げ」シナリオには“齟齬”が生まれる可能性がある。

日本銀行は12月18、19日の金融政策決定会合で政策金利を据え置いた。12月の利上げ見送りの背後には、円高リスクの懸念や金融市場の安定性を重視した日銀の思惑が透けて見える。日銀が12月に利上げを見送った理由を掘り下げるため、植田総裁が示した表向きの理由を分析するだけでなく、市場や為替に対する影響、米国との金融政策のタイミング差が日本経済に及ぼすリスクについて検討するとともに、利上げに賛成票を投じた少数派の意見を紐解き、これが日銀の政策決定に与える影響や1月以降の金融政策に焦点を当てる。

日本銀行は、12月の金融政策決定会合で追加利上げを決める可能性が高い。前回10月会合で植田和男総裁が「(利上げ判断まで)時間的余裕がある」という姿勢を変えたことで示唆はされたが、物価の下振れリスクに加え円安加速で対応を余儀なくされないためにも年内利上げを急ぐとみられる。

日本の消費者物価は近年2%を超える上昇を見せているが、これは一時的な要因によるもので、長期的には0~2%程度に落ち着くと考えられる。過去に日本で物価が安定していた理由や、企業の価格転嫁姿勢の変化が物価上昇を促すものの、2%を超える物価上昇の持続は難しい理由を解説し、日銀が物価目標を見直し、新たな基準とする可能性を展望する。

日本銀行は政策金利を中立水準まで徐々に引き上げ、金融政策の正常化を進めている。今や正常化を進めるという基本方針においては政策委員全員で共有されている。これから注目すべきは正常化の有無ではなく、正常化後に日銀が目指すべき姿だ。2%の物価安定目標が続く可能性を展望し、日銀によるアンケート調査で設定された質問・回答選択肢から日銀が目指そうとしている正常化後のあるべき金融政策の姿を推理する。

岸田政権の政策継承を掲げる石破新政権の誕生は日本銀行の金融政策正常化にもグッドニュースといえるが、円安修正で物価の上振れリスクが減って「時間的余裕」が生まれたことや10月には解散総選挙が予定され、利上げ再開は早くて今年12月か来年1月というのがメインシナリオだ。

7月末の利上げ決定直後に株価が急落し、日本銀行は事実上追加利上げの中断を余儀なくされた。しかし、日銀保有の長期国債残高の縮小は続き、非伝統的金融政策の出口戦略は前進している。筆者は、金融市場の落ち着きを確認しつつ、今年12月または来年1月には0.5%への利上げがあるとみる。その後も中立金利に向けて数回程度の利上げが想定される。

日本銀行の7月利上げは円高急伸や株価乱高下などの混乱を招いたが、国債買い入れ減額計画実施を含め金融正常化に本格的に踏み出したことは間違いない。株価下落も実体経済の弱さを反映したものではなく、市場が落ち着くのを見て早ければ12月にも追加利上げの可能性がある。

日本銀行は7月の金融政策決定会合で今後1~2年の国債買い入れの減額計画を決め、実施に踏み出すが、買い入れ額は現在の月6兆円を4兆円程度減らし、月2兆円程度にする可能性が考えられる。同時の追加利上げの予想も市場にはあるが、7月かどうかはともかく、利上げが秒読み段階にあることは間違いない。

6月13~14日の金融政策決定会合では、長期国債買入れを減額していく方針が決まり、7月30~31日の次回会合では、今後1~2年程度の減額が具体的に決まることになった。しかし長期国債の買入れ減額の決定は、すでに1年半にわたって続いていたことの追認に過ぎず、日銀も金融政策の変更とは考えていない。だからといって、7月会合での「追加利上げ」を日銀が諦めているわけではない。日銀が長期国債買入れの減額方針を発表した経緯を整理するとともに、7月会合での追加利上げの可能性は長期金利の上昇次第であると指摘する。
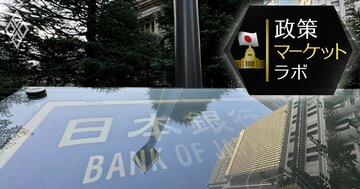
日本銀行は2%の物価安定目標の達成には至っていないと判断しているが、消費者物価は2%の上昇を続け、10年続けた異次元金融緩和も終了させた。さすがの日銀もデフレ脱却というスローガンを使いづらくなり、今では「賃金と物価の好循環」という新たなスローガンが生まれた。物価の上昇が先行している以上、賃上げしても実質賃金が増えることはないと指摘するとともに、日本経済が目指すべきは賃金と物価の好循環ではなく、「価値と所得の好循環」であることを提言する。
