
長井滋人
高インフレに対する金融政策対応で、先進国と新興国の明暗が分かれている。欧米先進国の中央銀行は、高インフレを一過性と認識して対応が遅れた。その後、先進国中銀は引締めに転じたが、インフレは中銀の予測を何度も裏切って下げ渋り、後手に回った引締めは予想を超えて長期化して終わりが見えない。一方、新興国では順調にインフレ率が低下を続けている。経済構造や高インフレに対する金融政策における先進国と新興国の違いを解説するとともに、先進国中銀がインフレ退治で成功するために、従来の常識を見直す必要があることや、結果として金融市場に構造変化をもたらす可能性を指摘する。

欧米先進国・中央銀行が利上げの動きを続けており、市場が戦々恐々としている。利上げ継続の背景にはインフレ対応が後手に回るという危機感があるが、金融引き締めが行き過ぎると景気が予想以上に悪化するリスクも高まる。金融政策の効果が波及する時間差(ラグ)がインフレと景気では異なることや、金融「引き締め過ぎ」リスクが最も高いのがユーロ圏であることをインフレの内容から解説するとともに、資産価格下落に伴う金融不安の展開もあり得ることを指摘する。

米国政府は次世代戦略産業の生産過程を国内に呼び戻す「リショアリング」を推し進めている。昨年夏の関連法案成立後、巨額の補助金支出の影響が早くも統計に出始めている。しかし、事はそう単純ではない。

資源価格と円安の落ち着きに加え、供給サイドのインフレ圧力が後退してくることから、インフレ率は年後半から一旦は急速に低下する見込みだ。しかし、本当の勝負はその後だ。一旦低下したインフレは、企業の賃上げと価格戦略の変化によって再び上昇に転じることは間違いない。今回の値上げラッシュが一過性ではないことを日銀短観の調査結果などから指摘するとともに、値上げラッシュ後に2%インフレ目標達成のカギを握るのが企業の「値上げ力」にあることを解説する。

中国の景気回復は、先進国が利上げや金融不安で苦しむ中、世界経済を支える救世主として期待が高まっている。実際、今世紀に入ってから、金融危機など先進国が原因で世界経済が急減速した際には、中国が常に大胆な景気刺激策を打ち、成長加速と輸入の増加を通じて世界経済の回復を助けてきた。しかし、今回の場合、中国の景気回復があっても、世界経済への波及効果に過度な期待はできない。中国当局の景気刺激策や潜在成長率などから、中国の「輸入力」が中長期にわたって減衰する可能性が高いことを示し、中国の輸入力の低下が米中覇権争いに影響を及ぼす展開を論じる。

米国のシリコンバレー銀行(SVB)に始まる銀行不安は、海を越えて欧州にまで波及し、世界経済を大きく揺るがしている。足元では、欧米当局のスピーディな対応もあり、銀行システム全体に及ぶシステミックな金融危機には発展する可能性は、今のところ小さいとみられるが、今後もFRBやECBの利上げが続けば、SVBショックが今後どの程度収束するかに止まらず、金融システムの綻びが他にも新たに出てくる展開もあり得る。金融システムの不安定化に発展するトリガーとして警戒すべき点として銀行の与信基準の動きを指摘するとともに、与信基準のタイト化が不動産市場に波及するシステムや、考えられる最悪の結果を明快に解説する。

米欧の雇用指標が予想以上に底堅い。その結果、多くの国が景気後退を回避して軟着陸するのではないかとの楽観も広がっているが、雇用が減少しなければ景気後退はないと決め付けるのは早計だ。

米国で金融引締めが長期化すると、景気への悪影響は米国に止まらず、全世界に及んでいく。中でも心配なのは、新興国における金融政策運営への影響だ。今後FRBが引締めを続け、その後も利下げになかなか転換しない場合、新興国は身動きが取れない状況が続き、世界景気は一段と悪化することも懸念される。新興国の中銀がFRBの利下げを待たずに利下げに踏み切るケースを取り上げるとともに、新興国におけるインフレの波及経路を解説し、新興国が米国よりも早く利下げに踏み切る可能性を論ずる。

コロナ禍は経済活動に不可逆的な変化をもたらした。特にリモートワークの普及は、柔軟な働き方の選択肢として定着する見込みで、コロナ後の経済の生産性上昇に大きく寄与するとの期待も高まる。ただ、リモートワークへの転換が可能な職種や産業は高付加価値のサービス業などに限られる。

供給サイドのインフレ要因は後退しているが、欧米先進国の中央銀行はタカ派的な姿勢を崩していない。今後の利上げ停止の時期や、その後に続く据え置き期間や利下げ転換時期について、市場の見方は大きく分かれ、大きな不確実性要因となっている。中央銀行のタカ派姿勢が変わらない理由を説明するとともに、市場の信認を失った欧米先進国の中央銀行が、再び信認を失ってしまうリスクを明快に解説する。

今年(2023年)の世界経済を展望すると、先進国を中心に多くの国が景気後退入りすることに議論の余地は殆どなく、今後の焦点は、景気後退がマイルドに止まるのか、深刻化するのかという点だ。今年の景気後退が多くの国で不可避となる理由に加え、景気後退時の様子を明快に指摘するとともに、景気後退後の次の景気拡大の様子を大胆に展望する。

中国経済は2010年代に平均8%近い高成長を遂げたが、今後10年間は4%台にまで大きく減速する見込みだ。ここで不動産バブルの処理に失敗すると、一段の失速は避けられない。不動産市場の過熱は著しい。住宅の新規販売価格の対所得比率は、全国平均で8.5倍。これは、サブプライム危機前の米国の5.8倍を大きく上回る危険な水準だ。

コロナ発生直後の世界経済の落込みは、国際金融危機の時を遥かに上回り、大恐慌に匹敵する規模だったが、世界各国が大胆な金融緩和と財政発動に躊躇なく踏み切ったことで、世界経済のV字回復が可能となった。しかし、有効であった財政政策は、短期間で慌てて発動したものだけに完璧なものではなく、事態が落ち着くに連れて政策検証も徐々に始まっている。財政政策を検証する上でのポイントを解説するとともに、財政政策と金融政策の組み合わせ(ポリシーミックス)のあり方と新しい形を考える。

英国史上最短の45日で終わりを迎えたトラス政権。政権交代をもたらしたポンドと国債価格の急落、その後の戻しの振れ幅はすさまじく、わずか3週間で国債の価値が30%も下落したことになる。

米連邦準備制度理事会(FRB)は、インフレ抑制を最優先に、金融引締めを一段と強化し、景気後退入りも辞さない姿勢を明確にしている。景気後退を招いても、利下げに転じることで対処可能とFRBは考えているようだ。しかし、利下げで景気後退が収まる保証はない。実体経済の悪化が、株価や住宅価格といった資産価格の大幅な調整を招き、金融市場・システムの不安定化を招く展開もありえる。実質長期金利が急ピッチで上昇している状況を整理するとともに、実質長期金利の上昇がシステミックリスクにつながる展開の可能性を論ずる。
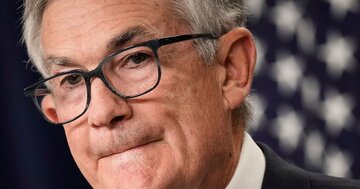
中国の経済成長は、22年に3.2%、23年も4.9%と、5.5%の成長目標には程遠い低成長が続く見通しだ。現在の中国の成長伸び悩みは、より深刻な構造的な問題がもたらす長期的な成長率低下だ。英経済調査機関の在日代表が、成長会計アプローチで中国の長期成長の行方を分析するとともに、米中対立下の中国経済の先行きを見通す。

相場を動かす要因は、金利差や対外収支の変化、地政学リスクなど様々で、局面によって主役も入れ替わる。しかし、その中で一貫してドル高基調は続いている。ドル高が今後どれだけ続くかは、ドル円相場の帰趨に止まらず、世界経済の成長の持続性という意味でも鍵を握っている。昨年から今年、そして来年におけるマクロ経済要因を整理し、ドルが下落に転じるシナリオとドル高が続くシナリオを考える。

ウクライナ戦争の経済的ダメージは欧州において飛び抜けて深刻だ。パイプライン経由の天然ガスを中心に、欧州連合(EU)全体の消費エネルギーの24.4%をロシアからの輸入に依存していることが大きい。このアキレス腱ともいうべきガス供給が、ウクライナ支援へのロシアの対抗措置として例年の7割以上も削減されている。この影響を重くみた当社は7月に2023年のユーロ圏の成長見通しを2.5%から1%へ大幅に引き下げた。

高インフレに収束の兆しがみられず、米国だけでなくユーロ圏でも中央銀行が利上げの大幅前倒しに追い込まれているなかで、市場は利上げによる景気後退への懸念を強めている。最悪の展開として恐れられているのがスタグフレーションだ。スタグレーションが発生するリスクを正しく恐れるためには、スタグフレーションの歴史を振り返り、過去に何が起きたかを知ることが有益だ。50年代以降の長期にわたり米英仏の成長とインフレの関係を検証し、われわれがスタグフレーションに直面する可能性を考察する。

リスク・ヘッジの手法のひとつに、株式と債券の双方に投資することによるポートフォリオ分散がある。相場のサイクルによって株式と債券のウェイトを調整し、投資全体のリターンの変動を小さく出来る。しかし昨年から株安と債券安が同時に起こり、ポートフォリオ分散効果が機能しなくなっている。分散効果が機能しなくなった理由をマクロ経済の視点から解説し、機能が回復する可能性を考察する。
