
長井滋人
米国経済の先行きを巡る悲観論が急速に後退している。米連邦準備制度理事会(FRB)は9月に予想を上回る利下げを決めたが、市場が織り込む今後の利下げペースはかなり緩やかだ。悲観論が後退している背景として雇用・消費の改善などを指摘し、9月下旬に改定された過去数年分のGDP(国内総生産)の大幅上方改定が、米経済の「底堅い成長」の構図を示していることを解説する。

中国の国内需要の停滞に歯止めがかからず、5%前後という今年の成長目標達成に黄信号が灯る。金融緩和は小出しで財政政策においても過去の経済危機で救世主となったインフラ投資はボリューム感に欠ける。9月下旬に突然公表された一段の金融緩和は当局の焦りを示す。中国経済停滞の背景に「新たな成長モデル」の問題を指摘するとともに、個人消費主導の成長を遂げるために必要な改革案を大胆に提示する。

移民対応が米大統領選の争点、過度の移民制限は経済的なダメージが大きい
米国大統領選挙でのトランプ氏への高い支持率の背景にあるのが、近年の移民急増に対する社会的な不満の高まりだ。米国議会予算局が年初に公表した推計では、米国への移民流入は2022年に260万人、昨年は330万人と、10年代の平均90万人と比べて急増した。

世界貿易の趨勢的な伸び悩みが続いている。世界各国の財輸入(実質ベース)は、コロナ禍による大幅減と反動増という振幅が収まった後、小幅ながらマイナス基調が続いている。世界貿易停滞の原因を景気循環だけでなく、所得弾力性の低下という構造的な要因からも読み解き、所得弾力性が低下している理由として経済グローバル化の一服や貿易障壁の増加を解説。その上でトランプ前米大統領が再選した場合の米国の保護主義の高まりというリスクを指摘する。

米欧中央銀行の今後の利下げペースを巡る不確実性は相変わらず。市場は毎月の物価・賃金指標で一喜一憂する状況が続く。ここまで個々の経済指標が注目されるのは、中央銀行が物価や賃金の落着きをデータの実績で確認しないと動かないという極めて慎重な政策運営姿勢を貫いているためだ。中央銀行が「データ次第」で政策運営を続ける理由を整理するとともに、今後の中央銀行が経済予測に基づく政策運営に回帰していくことを警告する。

金融市場は利下げが先延ばしされるリスクで頭が一杯のようだ。FRBが物価安定に万全を期すために、引締めの手を緩めない構えを続けており、米雇用統計も堅調な結果を示している。米雇用は経済指標が示す表面上の結果ほど実際は強くないことや、米雇用に構造変化が生じている可能性を紹介し、FRBが今後、金融政策の転換時期と市場との対話という2つの難問と戦うことを指摘する。
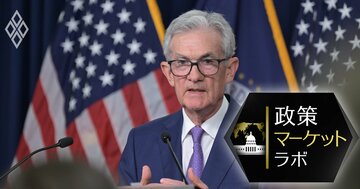
インドの消費市場拡大を阻む中産階級の発展の遅れ、経済発展の鍵を握る格差是正
成長に陰りが見える中国に代わって、同じく14億人の人口を抱えるインドが世界経済に巨大な消費市場を提供することへの期待が高まる。ただ、消費をけん引する中産階級の発展は中国と比べて極めて遅れている。

米大統領選が近づき、トランプ氏が再選するリスクが意識されている。第2次トランプ政権が取り得る各種政策を基に2つのシナリオを策定し、経済モデルから得られた今後数年間の米経済の行方を紹介するとともに、米経済に大きな影響を与える”移民政策”の変化が米経済に与えるインパクトを解説する。

世界経済はソフト・ランディングとなる蓋然性が高まっているものの、その後は世界貿易の減速を主因に勢いがつかない状況が見込まれている。世界貿易が減速する背景に貿易障壁と各国の産業政策があることを解説するとともに、中国のデフレ輸出とトランプ氏の米大統領再選が世界貿易の悪化を加速させる恐れを指摘する。

悪化した中国の地方財政が不動産市場と景気対策の制約に、財政の主役は中央政府へ
中国の地方政府の財政悪化が著しい。実質的な債務残高のGDP比は2018年の59%から23年には80%に急上昇した。長期化する不動産不況は、地方財政運営も立ち行かなくしている。

コロナ禍はロックダウンによる経済活動の急停止をもたらしたが、その後、急速な需要回復と需給ミスマッチによる高インフレを引き起こすなど、世界経済を何年にも及ぶ混乱に陥れた。そのコロナ禍で注目すべきは米国における起業活発化の動きだ。米国での起業数はコロナ禍後に急増している。米国でコロナ禍後に企業数が急増した理由を平易に解説するとともに、コロナ禍後にスタートした米国・新興企業に対して注意すべき点と、我が国が学ぶべき点を指摘する。

1月の米国・消費者物価指数(CPI)は、総合が前年比+3.1%と市場予想の+2.9%を上回り、コアCPIは前月比+0.7%とサービス価格を中心に前月0.4%から加速した。これを受けて、市場の利下げ期待は急速に後退したが、米CPIの結果はインフレ基調判断を揺るがすものではない。CPIの詳細を分析することでCPIの強さが一時的なものである可能性が高いことを解説し、市場でパフォーマンスを残すために、個々の指標に振り回されて一喜一憂せずに、統計の限界を踏まえてノイズと基調を見極める力が重要であることを指摘する。

米国経済は、これまでの利上げの悪影響で今年前半の景気減速が避けられない見込みだ。しかし市場関係者の多くは、年後半には景気が緩やかながらも回復基調に戻るという「ソフトランディング」を見込んでいる。米国のインフレ、賃金を所得階層別などの多面的な視点に展望し、ソフトランディング・シナリオのリスクとしてトランプ再選による移民受け入れの抑制を提示する。

中国住宅市場は調整長期化へ、時間をかけた“漢方治療”はさらなる停滞につながる
今後数年の中国経済は、4%程度の成長率維持が精いっぱいではないか──。そう悲観せざるを得ない理由は、行き過ぎた住宅市場の調整が長期化することだ。

来年(2024年)のドル円相場では、各国のインフレの展開とそれに対する金融政策面での対応が引続き鍵を握る。市場が現在織り込んでいるのは、米国、ユーロ圏ともに24年春頃には中央銀行が利下げを開始し、その後は似たようなペースで利下げが進むという展開だ。足下で円が買われているのは、日本では利下げがないという点で金利の方向が欧米と逆であることが大きい。ただ、来年の為替予想を左右する各国の成長やインフレ、金融政策の動きを巡る不確実性は非常に大きい。ドル円相場に有意な影響を与えるサプライズの火種が、日米欧の金融政策それぞれにおいて存在することを大胆に指摘する。

米国の女性労働参加率はコロナ禍後に急上昇、経済軟着陸の援軍になるか
女性の社会進出において、米国は先進各国の後塵を拝している。ただ、コロナ禍からの回復局面で、米国女性の労働参加率の上昇は目覚ましい。そして、これがインフレ退治に苦戦している米国経済を軟着陸させる強力な援軍となっている。

5月まで3%半ばで推移していた米国10年国債の利回りが急上昇するなど、米欧の長期金利が高水準で推移している。金利上昇の動きが今後どの程度続くかを判断するには、FRBがどのように長期金利を押し上げているかについて踏み込んだ分析が不可欠だ。イールドカーブの変化が、①短期政策金利の予想経路(パス)と、②タームプレミアム、という2つの変動要因のいずれによるものかを要因分解し、中立金利決定の構造要因やタームプレミアム拡大の原因を考察するなど、金融当局が活用する高度な分析手法を駆使して今後の長期金利の行方を占う。

株式と債券の組み合わせによるリスクヘッジ戦略が揺らいでいる。これまでは株式相場が下がったときの債券高(金利低下)が期待され、株式と債券を6:4の比率で持つのがヘッジ戦略の基本とされてきた。ところが昨年以降は6:4の黄金戦略の神通力が効かなくなり、投資リターンにおいて金融危機以降最大の落込みをみせている。株式と債券の組み合わせによるリスクヘッジ戦略が揺らいでいる理由を各国中央銀行による金融政策の変化から読み解くとともに、インフレ環境の時代に戻っていく今後における新しいヘッジ手段を真剣に考える必要性を指摘する。

バブル崩壊後の日本と同じように、バランスシート不況が中国でも起きつつあるのではないかという議論が盛り上がっている。投機抑制策導入から始まった不動産市場の調整は止まる気配がなく、不動産開発業者の資金繰り難が連日紙面を賑わす。中国のバランスシート不況が現時点では不動産セクターにとどまっているものの、中国当局が不動産バブルの本格処理に及び腰となっている理由を説明し、中国経済の停滞が長期化する理由をバランスシート不況だけでなく、今後の成長モデルの欠如にあることを指摘する。

米国で進む対中貿易の減少、ある先行指標の数字は西側全体への拡大を示唆する
コロナ禍下の混乱で一服していた米中デカップリング(経済分断)の動きが、再び勢いを増している。日米を除く西側諸国でも、デカップリングの動きは表面的な数字より進んでいる可能性はある。
