山本洋子
新日本酒紀行「秀峰岩泉」
大山隠岐国立公園の中央にそびえる大山は、標高1729メートルと中国地方の最高峰で、上質な天然水が湧く。その奥大山の天然水で酒造りをするのが、江府町の宿場町江尾で1877年に創業した大岩酒造本店だ。

新日本酒紀行「平六醸造」
国指定重要文化財の岩手県紫波町の日詰平井邸が、2024年1月、新たに息を吹き返した。16代の平井佑樹さんが、クラフトサケの醸造を開始したのだ。

新日本酒紀行「源流どぶろく 上代」
「鳥取の良いものをなくしてはならない」と、24歳で事業を承継した遠藤みさとさんが率いる上代の「源流どぶろく 上代」は、日本酒ならば純米大吟醸クラスで、クリーミィな食感と優しい甘味が醍醐味。
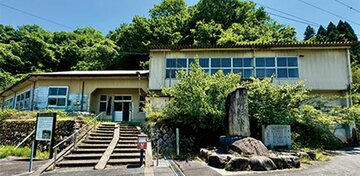
新日本酒紀行「千代の光」
豪雪地である新潟県妙高市は、かつて頚城(くびき)郡と呼ばれ、越後杜氏の一派、頸城杜氏の里で名杜氏を生んだ地。1860年から酒造りをする千代の光酒造は、全ての酒で吟醸酒と同様のきめ細かな造りを行い、端麗辛口が主流の新潟県で、柔らかな甘味とうま味を守る。

新日本酒紀行「雅山流」
酒蔵に生まれ、酒造技術に優れた祖父に小学校3年から酒造りを習っていた新藤雅信さん。山形県米沢市の新藤酒造店10代目だ。新藤家は元庄屋で酒造りを開業し、酒造専業になった今も、8町歩の自社田で酒米の出羽燦々と出羽の里を栽培する。

新日本酒紀行「人気一」
全量木桶仕込みで瓶貯蔵を行い、金属製タンクは一本もない稀有な酒蔵が、福島県二本松市の人気酒造。蔵元の遊佐勇人さんのモットーは「楽しく自由な酒造り」。

新日本酒紀行「玉乃光」
「神話から続く日本の誇るべき酒は純米酒だ」と無添加清酒の名で純米酒を復活させたのが、玉乃光酒造11代目の宇治田福時さん。無添加清酒を復活させて、今年で60年。純米吟醸と純米大吟醸だけを醸す純米吟醸蔵として邁進する。

新日本酒紀行「副将軍」
水戸黄門を示す「副将軍」を酒名に冠した明利酒類は、全国新酒鑑評会で通算15回金賞を受賞する銘醸蔵。清酒以外にも梅酒30種、茨城県産の芋、麦、米焼酎、和ウオッカ、和ジンに醸造アルコール、調味料の製造も行い、経営の柱を幾つも持つ総合酒類メーカーとして成長した。

新日本酒紀行「南郷」
大好きな酒を飲み続けるうちに酒蔵と縁がつながって、蔵を継いで蔵元になった男がいる。それが矢澤酒造店の矢澤真裕さんだ。宿命的な出会いで事業承継を行った。

新日本酒紀行「こんにちは 料理酒」
料理人から圧倒的な支持を得る「こんにちは料理酒」は、大木代吉本店の代表作だ。創業は1865年で、初代代吉さんが醤油蔵から分家し、福島県西白河郡矢吹町で開業。4代目、一也さんがアミノ酸量が3倍以上の無添加料理酒を開発すると、料理人や食品加工業者、自然食品店が大注目した。

新日本酒紀行「A.BIRTH(エーバース)」
「この風景を瓶に詰めたい」と語り、夏は田んぼで米作り、冬はその米で酒造りの人生で夏田冬蔵と自らを名乗った森谷康市さん。業界内外から慕われ、全国から講演会に呼ばれる人気者でしたが、2019年夏の田んぼで倒れ、62歳で帰らぬ人に。残された30ヘクタールの田んぼを、三男の友樹さんが銀行職を辞めて継承した。

新日本酒紀行「木内酒造」
茨城県那珂市で1823年に創業した木内酒造は、日本酒「菊盛」の他、「常陸野(ひたちの)ネストビール」が有名だ。社長の木内敏之さんは、東京駅からのバスツアー考案し、酒に合う地元素材の食を提供する。

新日本酒紀行「富久錦」
全国に先駆け1987年に純米酒宣言を行い、92年に全量純米化した富久錦。播州平野の田園地帯で、1839年に創業した。「酒は土地の風土と思いが造る」が持論。播磨の米と水と人で、播磨の地酒を追求する。

新日本酒紀行「熟露枯」
総延長600mにも及ぶ洞窟は、戦車製造工場として建造された。全て人力で掘られ、岩肌にごつごつした掘削跡が残る壮大な建造物だが、一度も使われないまま終戦を迎えた。この洞窟で、99年から贅沢な大吟醸酒の熟成を試みたのが島崎酒造だ。

新日本酒紀行「稲田姫」
稲田姫とは、ヤマタノオロチ伝説でスサノオノミコトに助けられて妻になった稲と田の女神様。その姫の名の酒を醸すのが鳥取県米子市の稲田本店だ。創業は1673年という老舗蔵。

新日本酒紀行「瀧自慢」
「平成の名水百選」に選ばれた、三重県の赤目四十八滝の近くで酒造りをするのが、「瀧自慢」を醸す瀧自慢酒造だ。仕込み水は滝の伏流水を用い、県産米を主に食に寄り添う酒を造る。

新日本酒紀行「神蔵」
京都御所の東方、鴨川近くに立つ松井酒造は、酒造りが見学でき、その場で飲めて酒が買え、英語もOKとあって国内外の観光客に大人気。

新日本酒紀行「鷹勇」
中国地方最高峰の大山の東北側にある船上山は、平安時代に山岳仏教が栄え、後醍醐天皇の倒幕きっかけの地だ。その麓の琴浦町で、1872年に創業した大谷酒造は、山々からの豊かな伏流水を使い、地元産の山田錦や強力、玉栄などを主に、食事に合う辛口酒を醸す。

新日本酒紀行「東京八王子酒造prototype」
東京で10番目となる酒蔵が、2023年にJR八王子駅から徒歩5分の料亭内に誕生した。花街の面影を残す中町の黒塀通りに面した料亭すゞ香の厨房を改装し、開業したのが東京八王子酒造だ。

新日本酒紀行「十石」
灘と全国一、二を争う日本酒の大生産地伏見で、造り手1人、営業1人の小さな酒蔵が2023年1月に船出した。醸造の場は、月桂冠に酒を納め、21年に休蔵した松山酒造で、幕末まで薩摩藩邸があった土地に明治期に建てられた酒蔵だ。
