広告企画
企業の再生可能エネルギーの調達を巡る悩みが深まっている。「もしトラ」によって脱炭素化のスピードが鈍化するとの観測も出る中、再エネの需給環境の見立てには必ずしも共通解がない。一方で、多くの企業が掲げるカーボンニュートラルの中間目標設定年=2030年までは、あと5年強とタイムリミットが迫る。必要とする再エネを確実に、そして費用対効果をも加味しながら合理的に調達するために、企業が今だからこそ知っておくべきノウハウについて追う。

電通総研が、大胆な変革とチャレンジに着手している。2024年1月、慣れ親しんだ「電通国際情報サービス(ISID)」から社名を変更するとともに、大規模な組織再編を実行。“DX旋風”で好調なシステムインテグレーション(SI)事業に加え、コンサルティングとシンクタンク機能の確立・強化に動いた。「課題設定からシステム実装まで」を標榜するコンサルやSIerは多いが、電通総研は他社にない独自路線で差別化を図る。3月に社長に就任した岩本浩久氏に、戦略の中身を明かしてもらった。

昨今、インターネットを利用する上でのサイバー攻撃などの脅威が高度化し、セキュリティがますます重要になってきている。しかし情報漏洩やウィルス感染などを防ぐために、セキュリティを強化するとそれが逆にスムーズなアクセス環境の邪魔になることも多い。そこで最近出てきたのが「SASE(サシー、サッシー)」というセキュリティモデルだ。今回は一般社員も知っておくべきSASEについて紹介する。

コロナ禍を経てハイブリットワークが進んだ今、社外から社内ネットワークやクラウドに接続して仕事を進めるのは日常となっている。しかし、そんなネット環境の中で問題となっているのが、データ管理などのセキュリティ面と利便性の両立だ。具体的にどんなことが課題で、どのような解決策があるのか。マンガと導入事例で分かりやすくご紹介する。

中小企業が事業拡大時に必ず直面する問題、それは未収金のリスクだ。取引先の倒産や未入金など、売上金の回収ができないと自社の資金繰りが悪化、その結果、連鎖倒産に陥ってしまう企業も少なくない。物価上昇・人件費増加など厳しい環境下で倒産件数も増加している今、取引先を決定する上で気を付けたいポイントをまとめた。

およそ34年ぶりに最高値を更新した日経平均株価。「バブルの再来なのでは?」という声も聞こえてくるが、果たして日本株はまだ上がるのか。以前より日本株を買うべきと主張しているエコノミストのエミン・ユルマズさんと、ストラテジストの白木久史さんが語り合った。

働き手の減少やESG投資への注目を背景に、人的資本経営への取り組みが広まっている。そこで大きな課題となっているのが、人的資本を活かし、生産性を引き出すためのアプローチとしての「従業員のウェルビーイング実現」だ。なぜウェルビーイングが実現すると生産性は上がるのだろうか。そしてそのウェルビーイングはどのように実現すれば良いのだろうか。

ビジネスではスムーズな情報共有やコミュニケーションが欠かせない。さらに応答のスピードが重視される今、多岐にわたる連絡先へのヌケモレといったミスをなくし、常に変化する情報を共有、さらに生産性を上げるような結果を出すには「ビジネスチャット」の導入が効果的だ。社内が活気づき、無駄な仕事が軽減できるなどの結果をもたらすためには、具体的にどのように活用したら良いのか。さまざまな業界での活用法を紹介する。

仕事でメールを使わない日はない。そんな中、現状で問題となっているのが大量のメール処理だ。上席になればなるほどCCで多くのメールが共有され、本当に重要なメールや返信が必要なメールの見落としなどミスが発生してしまう。結果的に生産性が下がり、取引先や部下の不満の元となってしまうこともある。仕事上のコミュニケーションを円滑にするにはどうすれば良いのだろうか。
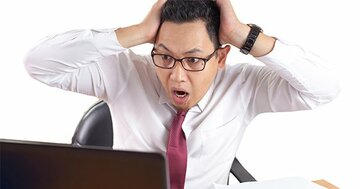
ある個人投資家は「ゲームアプリの会社」だと言い、またある投資家は「Web3の有望銘柄」と評して株を買う。人によって見え方や評価がまったく異なる会社。それが東証グロース市場に上場し、デジタルビジネス・コングロマリットを標榜する東京通信グループだ。

デジタル社会の実現に向けて、データを有効に活用してビジネスに生かすこと、またデータそのものの信頼性を担保することは、人々の暮らしをより豊かなものにするとともに、企業においては競争優位性獲得の観点から重要な課題となる。デジタル社会の実現をリードするデジタル庁の村上敬亮統括官、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するオービックビジネスコンサルタントの和田成史社長、資本市場の信頼性向上をデジタル監査で支えるEY新日本有限責任監査法人の片倉正美理事長が、人口減少時代におけるデータの重要性と、これからの日本が目指すべき方向性=共助のモデルについて語り合った。

年々減り続ける新卒者。大企業との人材争奪戦がさらに熾烈化する中、中堅・中小企業はどうすれば優秀な人材を安定採用できるようになるのか?東京の、とある中堅企業の取り組みからヒントを探った。

ブラックロックの「iシェアーズETF 東証上場シリーズ」は37本のラインアップ。その中から今回は、低コストで米国の社債に投資できる為替ヘッジなしのETF3本を紹介する。同社の鈴木絵里可さんにお話を聞いた。

企業IT動向調査報告書2023*によると、現在、日本の企業では4つの課題解決が急務であるという。セキュリティの保全はもちろんだが、IT人材・人員不足によるIT基盤の「運用管理業務負担の軽減/省力化」「IT基盤の保守/運用管理費の削減」も問題視されている。人材の確保が難しいにもかかわらず、強固なセキュリティ環境を整える仕組みを構築することが求められている今、その解決策を探る。*出典:『企業IT動向調査報告書2023(2022年度調査)』一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(2023年4月)

多くの企業に欠かせないコンタクトセンター。今、そこが抱えている課題は、オペレーターの採用・育成や定着、生産性向上などだが、その解決に大きく貢献すると期待されているのが生成AIだ。この資料では生成AIを導入した富士通グループの「実在のコンタクトセンター」における効果と、活用での留意すべきポイントについて紹介する。

「make brighter tomorrow.」という経営理念の下、メディア・医療分野など社会課題を解決するためのコンサルティングサービスを提供しているグライダーアソシエイツ。同社取締役副社長の荒川 徹氏は、ビジネスの成功には「タイムマネジメント」と「清潔感のあるスーツ」が必要だと語る。そのこだわりと両者をかなえるスーツの管理法について聞いた。

自宅などの社外から、社内のシステムやデータに遠隔接続する「リモートアクセス」に進化が求められている。在宅勤務の定着によってセキュリティ対策などの強化が不可避になっているのだ。サイバー攻撃に屈しない高いセキュリティを担保しつつ、利便性も損なわない遠隔接続体制を構築するためにはどんな知識が必要なのか。企業が今こそ備えるべきセキュリティの“新常識”について詳しく解説する。

企業におけるクラウド活用は増えるばかりだ。それはサーバーなどの機器が不要で、容量の拡張も簡単。また社員にとっても、インターネット環境さえあればいつでも、どこからでもシステムにアクセス可能になるなど、メリットが大きいからだ。しかし、問題も生じている。セキュリティ強化の負担増だ。ITやセキュリティの担当者が無理なく、適切にセキュリティ対策を講じるための「5つの具体策」を紹介する。

ビジネス・採用環境が変化する中、採用における面接の重要性が増している。変化が激しく、不確実な時代に入り事業環境が短期間で大きく変化しているため、その状況に合わせて、採用する人材も見直したり、変化させたりしていくことが求められているからだ。自社にとって本当に必要な人材を採用するにはどうしたら良いのだろうか。

トイレ業界のリーディングカンパニーとして知られるTOTOが、衛生陶器の「製造DX(デジタルトランスフォーメーション)」を急ピッチで進めている。便器などの衛生陶器は製造の難易度が高く、良品を均質に作るためには生産現場の経験と勘が不可欠だ。一般的に、匠の技とデジタル技術は“相性”が悪いとされるが、TOTOはわずか3年で融合に成功した。TOTOがトイレの生産現場で起こす、デジタルイノベーションの奥義に迫る。
