日本郵政
関連ニュース
#1
倒産危険度ランキング2021【ワースト1~100】上場廃止オンキヨー29位、1位は?
ダイヤモンド編集部,大矢博之
新型コロナウイルスの感染拡大で多くの企業が打撃を受け、倒産事情も激変した。そこで上場企業3787社の「倒産危険度(Zスコア)」を総点検。リスクの高い493社をあぶり出した。倒産危険度ランキングのワースト100を紹介する。

現金着服・自爆営業…日本郵政が「社員性悪説」コンプラ指導の非常識【内部マニュアル入手】
ダイヤモンド編集部
『週刊ダイヤモンド編集部』7月31日号の第1特集は「郵政消滅 郵便局国有化 ゆうちょ・かんぽ解散!」です。郵便局長・局員による詐欺・横領やかんぽ生命の不正販売など不祥事が多発しており、経営は信頼の回復に躍起になっています。ダイヤモンド編集部では、日本郵政の社員40万人に向けられた「内部マニュアル」を独占入手しました。それによれば、世間の常識とかけ離れた「コンプライアンス指導」がなされている実態が明らかになりました。
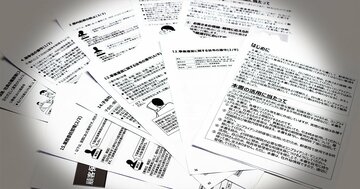
ゆうちょ銀行元幹部が提言、「かんぽスキーム」で郵政出資を50%以下に下げよ
宇野 輝
ゆうちょ銀行の常務執行役をかつて務めた筆者は、遅々として進まない「ゆうちょ銀行の民営化」に危機感を募らせている。そして本稿では、日本郵政が持つゆうちょ銀行株の売却に向けて、5月にかんぽ生命保険が実施した自社株買いのスキームを使うことを提言する。

#15
60万票を集めた全特会長出身の郵政族議員が激白「悪いのは郵便局じゃなくてかんぽ生命」
ダイヤモンド編集部,千本木啓文
2019年の参院議員選挙で、60万票を獲得して、自民党比例代表のトップで再選された柘植芳文氏(元全国郵便局長会会長)は、かんぽ生命保険の不適切販売の問題の根本原因は郵便局ではなく、かんぽ生命にあると言い切った。「もっと謙虚になれ」とかんぽ生命保険の経営者を叱責したという柘植議員に同社への怒りの理由を語ってもらった。

#14
日本郵政の株価は半減!民営化の先輩であるJR、NTTとの「圧倒的格差」とは
ダイヤモンド編集部,千本木啓文
2015年に東京証券取引所第1部に上場した日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の株価は、そろって半値程度まで下落している。3社の株価が上昇に転じる余地はあるのか。民営化・上場を経験した他の旧公社、JR東日本、NTTと比較して、日本郵政の構造問題をあぶり出す。

#13
楽天の無慈悲に提訴準備の運送会社も!「日本郵政×楽天」物流タッグはパンク寸前
ダイヤモンド編集部,村井令二
日本郵政と楽天グループとの物流領域の提携が動きだした。郵便物が減少する中で、日本郵便が望みを懸けるのがeコマース(EC、電子商取引)向けの宅配便市場。楽天という大口荷主を確保したが、業界の争いは厳しい。

#12
日本郵政40万人組織をむしばむ「理不尽序列」、時代錯誤のエリートポストとは?
ダイヤモンド編集部,山本 輝
利用者から見れば「郵便局で働いている人」は誰も同じ職種のように映るかもしれない。日本郵政グループに従事している社員は約40万人に上る。その中には、旧特定郵便局長、旧普通郵便局長、本社幹部、旧郵政省官僚、一般職など、出自もキャリアも全く異なる“人種”が混在している日本郵政グループ社員の「ヒエラルキー」を徹底解剖する。
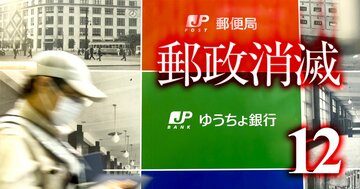
#11
郵政の“生みの親”竹中平蔵氏が民営化批判に大反論「悪いのは、民間人を切った民主党政権」
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
小泉純一郎政権で郵政民営化担当大臣や総務大臣を歴任した竹中平蔵氏は、日本郵政の“生みの親”ともいえる人物だ。民営化から14年。統治不全に陥っている日本郵政グループの「問題の病巣」はどこにあるのか。郵政民営化の旗振り役を直撃した。

ヤマト運輸が宅急便とEC向け配送サービスをあえて切り離す理由[物流業界・見逃し配信]
ダイヤモンド編集部
宅配便市場が驚異的な急成長を遂げる中、ここ数年“ジレンマ”を抱えていたヤマト運輸は、宅急便とEC向け配送サービスを「あえて切り離す」という戦略に踏み切りました。その狙いとは?「ダイヤモンド・オンライン」で会員読者の反響が大きかった週間人気記事1位を中心に、その関連記事をお届けします!
![ヤマト運輸が宅急便とEC向け配送サービスをあえて切り離す理由[物流業界・見逃し配信]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/a/0/360wm/img_a027791fa720da333f357c604ae41bd5206209.jpg)
#9
日本郵政による楽天1500億円救済は矛盾だらけ、郵便局が携帯・カードの「下請け」部隊に
ダイヤモンド編集部,村井令二
日本郵政が楽天グループに1500億円を出資した“ビッグネームの提携”は、矛盾に満ちている。携帯電話の投資負担に苦しむ楽天を日本郵政が救済したという構図で、日本郵政が得られるメリットはあまりにも小さい。

#8
「郵便局2万4000局vs農協」5番勝負、限界集落“最後の生活インフラ”対決の軍配は?
ダイヤモンド編集部,山本 輝
郵便局と農業協同組合(農協)は、共に地方の金融や保険といった社会インフラを支える「最後のとりで」となっている。採算だけで拠点の統廃合が進めば、たちまちその地域住民の利便性が失われかねない。だが一方で、郵便局の非効率な拠点配置を指摘されてきたのも事実だ。農協すらリストラを加速させている中で、「利益追求」と「ユニバーサルサービス提供」の二兎を追わねばならない郵便局はどうあるべきなのか。五つの指標による郵便局と農協の比較に加えて、統廃合必至となる郵便局の“過剰エリア”を炙り出す。

#7
日本郵政マル秘名簿で暴く「特定郵便局長ネットワーク」、腐っても鯛の60万集票マシンの内幕
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
全国に約1万9000ある旧特定郵便局。その大方の郵便局長が全国郵便局長会(全特)に属している。単なる任意団体にすぎない全特が、なぜ日本郵政グループに大きな影響力を持ち得るのか。全特関係者から入手した内部名簿を基に、その“魑魅魍魎”組織の全貌を浮き彫りにする。

#6
ゆうちょマネー220兆円が消失?民営化見直しの肝は「郵便国有化」と「郵便局長の特権剥奪」
ダイヤモンド編集部,村井令二
日本郵政の屋台骨を支えてきた「ビジネスモデル」が揺らいでいる中で、全国一律の「ユニバーサルサービス」を支えるのは一体誰なのか。そのコスト負担を巡り、政治家、本社官僚、地方の郵便局長など利害関係者の“骨肉の争い”が始まった。

#4
郵便局舎・社宅は宝の持ち腐れ!日本郵政が不動産2.6兆円を台無しにする「致命的欠陥」
ダイヤモンド編集部,山本 輝
日本郵政が郵便、銀行、保険の3事業に続く「新たな収益の柱」として期待をかけるのが、不動産事業だ。都市部の一等地に点在する郵便局舎や社宅などを筆頭に、日本郵政グループが抱える不動産は、なんと約2.6兆円にも及ぶ。だが、それらの優良資産を有効活用できずに“持て余している”実態がある。日本郵政グループの不動産事業の死角を検証する。

#3
郵便局長が告発「地方人事に斬り込む増田・日本郵政社長はけしからん!」【全国郵便局長会(全特)座談会・前編】
ダイヤモンド編集部,村井令二
地方の名士出身者が多く含まれる旧特定郵便局長を組織化した全国郵便局長会(全特)は、日本郵政の経営に多大な影響力を持つ。ベールに包まれた全特幹部たちに、匿名で本音を語ってもらった。

#2
日本郵政、豪物流6200億円買収で「杜撰すぎる投資計画」発覚!無駄金使いが止まらない
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
国際物流DHLを傘下に入れたドイツポストを見習え――。2015年に、日本郵政が豪トール・ホールディングスを鳴り物入りで買収した。だがその後、4003億円の減損損失を迫られるなど一度も業績が浮上することなく、一部事業を売却する悲惨な末路を迎えることになった。買収失敗の背景を探ると、あまりにもずさんな日本郵政の「投資計画」があらわになった。

#1
日本郵政「クビになった前社長」に復帰待望論、裏に40万人組織の“多頭権力支配”
ダイヤモンド編集部,千本木啓文
かんぽ生命保険による不適切販売の引責で辞任した横山邦男・日本郵便前社長の復帰を待ち望む声が、日本郵政グループ関係者の間で強まっている。横山氏は、2009年のかんぽの宿問題でも責任を問われ、西川善文・日本郵政社長(当時)の退任とともに古巣の三井住友銀行に舞い戻った過去を持つ。こうしたスネに傷持つ人物の「再・再登板」が取り沙汰されること自体が、経営統治の不全を物語っている。多頭権力支配の闇は、どこまでも深い。

予告
日本郵政を襲う無間地獄、元凶は「経営陣の無能」と郵政ファミリーが牛耳る「既得権益」
ダイヤモンド編集部
創業150年の節目を迎えた日本郵政グループが、未曽有の危機に直面している。2007年の民営化以降、歴代経営陣の無能と郵政ファミリーによる既得権益の温存は、日本郵政の企業統治を著しく劣化させた。こうした長きにわたる経営中枢の混乱は、40万人組織を着実にむしばみ、社員のモラルダウンに歯止めがかからなくなっている。そして放漫経営の果てに、郵便局のサービス劣化や地方切り捨てという「大きなツケ」となって国民に跳ね返ってきている。郵便局を存続させるのか、消滅させるのか――。日本郵政のあり方、存在意義を徹底的に問い直すときが迫っている。

ヤマトHD・佐川急便・日本郵政、四半期2割弱増収となった会社とその要因は?
ダイヤモンド・アナリティクスチーム,笠原里穂
コロナ禍からの企業業績の回復は、勝ち組と負け組の格差が拡大して「K字型」に引き裂かれていくという二極化の議論が強まっている。そこで、上場企業が発表した直近四半期の決算における売上高を前年同期と比べ、各業界の主要企業が置かれた状況を分析した。今回は日本郵政、SGホールディングス、ヤマトホールディングスの物流業界3社について解説する。

#5
楽天&日本郵政提携に早くも亀裂、元凶はアマゾン対抗「物流投資」の押し付け合い
ダイヤモンド編集部,村井令二
3月にタッグを組んだばかりの楽天グループと日本郵政に、早くも不穏な空気が流れている。携帯電話事業の設備投資で資金流出が続く楽天は、宿敵アマゾンジャパンに対抗するための物流投資も必須な情勢。そこで楽天は、日本郵政傘下の日本郵便との物流合弁会社に物流センターを移管することで、その投資負担を軽減させようとしている。だがその考えと提携先の日本郵政の思惑には、大きなずれがある。同床異夢となりつつある提携の実態に迫る。
