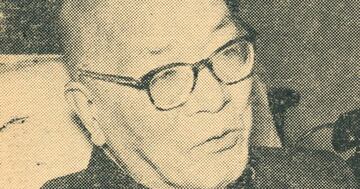深澤 献
第48回
椎名武雄(1929年5月11日〜)が45歳で日本IBMの社長に就任したのは75年。以来92年までの17年間の長きにわたり同社を率い、89〜93年は米IBMの副社長も兼務している。92年に会長に就任して以降は経団連や経済同友会の要職にも就き、IT戦略会議メンバーなども務めることで、日本における外資系企業の“地位”を向上させたことから「ミスター外資」との異名も取る。
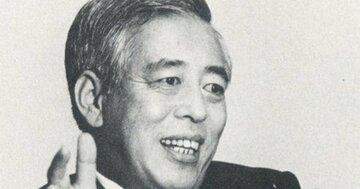
第33回
人と違うことをやり、リスクを取ってでも新しい道を行こうとする若きリーダーたちは、どんな原体験に支えられ、どのように育ってきたのか──。今回は、男性向けスキンケアという新たな市場に挑戦し、メンズコスメブランド「BULK HOMME」を展開するバルクオムの野口卓也さんです。両親共に有名な起業家という家庭に育ちました。

第46回
松下正治は、松下電器産業(現パナソニック)の創業者、松下幸之助の娘婿で、1940年に三井銀行(現三井住友銀行)から松下電器に入社した。その後の20年間は、監査役、取締役、副社長と将来の社長として規定のコースを歩み、61年に幸之助の後を継ぎ49歳で2代目社長に就任した。その正治が会長を務めていた93年に、終戦直後や高度成長期に松下電器が直面した“危機”について語っているインタビューがある。今回はそれを紹介する。
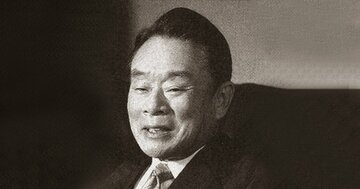
第32回
リスクを恐れず人と違うことに挑戦し、社会を変えたい──。そんな思いで活躍する若きイノベーターたちは、どう育ってきたのか。今回は、中学の終わりに地元、仙台で体験した東日本大震災を機に、食の安心・安全を自身のフィールドに定め、今は農産物の卸売業と小売業を手掛けるLiving Rootsの三浦大輝さんです。

第45回
福沢桃介(1868年8月13日~1938年2月15日)は、慶應義塾在学中に福沢諭吉の次女と結婚、福沢家の婿養子となった実業家だ。慶應卒業後に日露戦争後の株式相場で財を成し、その資金を元手として名古屋電燈の買収を皮切りに全国各地の電気事業に参入。ガスや電気鉄道、紡績、製鋼など多くの事業に携わった。

第44回
老舗百貨店の伊勢丹は、東京・湯島の呉服店に奉公していた初代小菅丹治が、1886年に東京・神田旅籠町で創業した伊勢屋丹治呉服店が発祥である。「帯と模様の伊勢丹」との評判を得た人気呉服店を、百貨店に進化させた“中興の祖”は2代目小菅丹治だ。

第43回
コンピュータ数値制御(CNC)装置や産業用ロボットで世界一のシェアを持つファナック。専務を2年、副社長を1年務めた後、3年後に社長に就任したのが、富士通の計算制御部長だった稲葉清右衛門(1925年3月5日~)である。一代で同社を世界トップ企業に育て上げたカリスマ経営者だ。
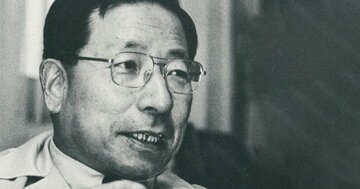
第42回
「元祖グローバル企業」を創り上げた、ソニー盛田副社長の1967年のインタビュー。「日本の経営者は国際レベルか」という特集内で掲載されたものだ。
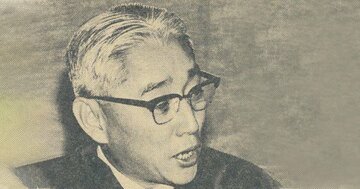
第31回
社会課題に果敢に向き合う若きリーダーの情熱と使命感は、どのように育まれてきたのか。今回は、日本に住む“難民”が、この地で第二の人生を歩むための環境づくりに挑むNPO法人WELgee(ウェルジー)の渡部カンコロンゴ清花代表。類いまれな行動力とコミュニケーション能力の秘密は、少女時代の多様性あふれる環境にありました。

第41回
前編に続いて、日本興業銀行頭取の中山素平と、日産自動車社長の川又克二の対談記事をお届けする。

第40回
1965年1月4日号、新春企画として掲載された、日本興業銀行(現みずほ銀行)頭取の中山素平、日産自動車社長の川又克二の対談記事である。この2人は、29年に旧制東京商科大学(現一橋大学)を卒業し、日本興業銀行に入行した同窓同期という仲だ。

第30回
自らの力で社会を変えたい──そんな情熱や使命感を抱いて活躍する若きリーダーたちは、どんな原体験に支えられ、どう育ってきたのか。今回は、「Z世代」の価値観・視点を生かした学生発イノベーションのプロジェクトを次々に立ち上げるdot代表の冨田侑希さんです。全ての始まりは学習院大学での「起業論」の授業でした。

第39回
大正から昭和初期にかけて大蔵大臣を7度経験し、大胆な財政政策で日本の経済危機を何度も救ってきた高橋是清。その高橋のインタビューが「ダイヤモンド」誌の1930年12月21日号に掲載されていた。インタビューのテーマは「僕の感心した人物」。高橋は第3代日本銀行総裁だった川田小一郎との思い出を披露している。

第38回
堀場雅夫は、京都大学理学部物理学科在学中の1945年10月に堀場無線研究所(現堀場製作所)を創業した。今でいう学生ベンチャーの元祖だ。53歳で会長に退いた後、社是を「おもしろおかしく」と定め、1986年には週休3日制を導入した。
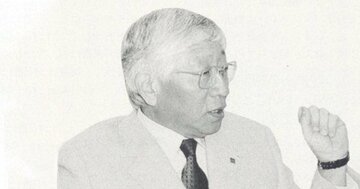
第29回
人と違うことをやる。リスクを取ってでも新しい道を行く──。イノベーターとして活躍する若きリーダーたちは、どう育ってきたのか。今回は、秘書や経理など会社の管理部門の業務をリモートワーク(在宅勤務)で請け負うサービスを展開し、「労働革命で人を自由に」を旗印に新しい働き方を提案するキャスターの中川祥太さんです。

第37回
1899年に創業者の鳥井信治郎が大阪市でワインの製造販売を始めたのがサントリーの始まりである。1907年に「赤玉ポートワイン」、37年に国産ウイスキー「サントリー角瓶」を世に出し、洋酒メーカーとしての地位を築いた。

第36回
1963年9月10日号に掲載された、松下電器産業(現パナソニック)の創業者、松下幸之助(1894年11月27日~1989年4月27日)の手記である。今回の手記は、「名ある経営者が語る“私の経営哲学”」なる企画に寄せられたもの。幸之助の経営哲学はさまざまなかたちで世に出ているが、端的にその要諦と、そう考えるに至った経緯がまとめられている。
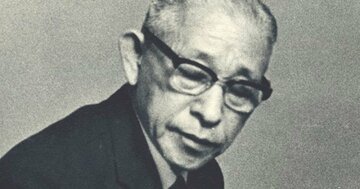
第28回
自分にしかできないことがある、自分ならできる──そんな情熱や使命感を抱いて活躍する若きリーダーたちは、どんな原体験に支えられているのか。今回は、難病などで長期療養生活を送る子供向けのスポーツ体験を提供するNPO法人Being ALIVE Japanを運営する北野華子さん。自身も15年間にわたる療養生活を経験しています。

第35回
キッコーマンの醤油が初めて米国に渡ったのは、1868(明治元)年の第1回ハワイ移民船に積み込まれたときまでさかのぼる。その後は、米国のみならず、中国大陸や東南アジアに日本人が進出するのに伴い、日系人や在留邦人向けに醤油が輸出された。今回紹介するのは、1966年11月28日号に掲載された茂木啓三郎(1899年8月5日~1993年8月16日)のインタビューだ。
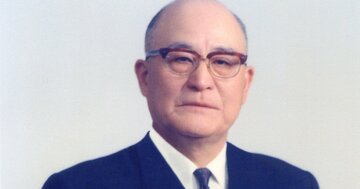
第34回
“日テレ”こと「日本テレビ放送網」。実はこの社名は、壮大な思いを込めて付けられたものだった。その名の通り、設立当初は「日本全国をカバーするテレビ放送網」を目指していたのである。「週刊ダイヤモンド」1951年9月15日号に掲載された、読売新聞社社主で日本テレビの初代社長である正力松太郎(1885年4月11日~1969年10月9日)による「俺はテレビジョンをやる」と題された談話記事には、その熱い思いが開陳されている。