永吉泰貴
#7
連載『スタートアップ最前線』ではこれまで、未上場の急成長スタートアップ、ダイニーにおける違法性の高い退職勧奨の実態を報じてきた。だが、同様の問題は上場企業でも起きている。創業からわずか7年で上場し、DX・AI支援で高成長を続けるジーニーだ。同社は対象者の業務を取り上げた上で虚偽の整理解雇通知を示唆し、法的に会社側が勝てば経歴に傷が付くと告げて自主退職を迫るなど、違法性の高い退職勧奨を敢行していたことが分かった。本稿では、独自に入手した人事部トップと社員との面談記録を基に、その違法性を明らかにする。また、この点について質問書を送付したところ、工藤智昭社長自らが取材に応じ、反省の弁と今後の対応策を語った。

#5
J-STARは、中堅・中小企業を投資対象とするミッド・スモールPEファンドの雄として業界内でも一目置かれている。ところが、その名門ファンドで今年、前代未聞の投資崩壊劇が起こっていた。炎上案件は、医療系スタートアップのMTUである。買収完了からわずか1カ月後、J-STARはMTUの原拓也社長を「重大な疑義」により電撃解任。その背景にある“衝撃疑惑”がダイヤモンド編集部の取材で判明した。本稿では、買収後に明らかになったMTUの事業実態や不正行為に関する疑惑の数々を、投資責任者が周囲に明かした内容とともに公開する。

ゴルフウエアブランド「パーリーゲイツ」などを展開するアパレル大手TSIホールディングスは、数十億円を投じてボストン・コンサルティング・グループ(BCG)に収益構造改革を依頼し、大規模なリストラを進めてきた。だが、コンサルへの巨額支出とは裏腹に、退職勧奨する社員への割増退職金は激減していたことが分かった。本稿では、TSIが2015年以降に実施した3度のリストラの内部文書を独自に入手。その条件を比較し、BCGが助言した今回のリストラにおいて割増退職金がどの程度削られたのか、詳細を明らかにする。

アパレル大手TSIホールディングス(HD)は、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)の助言を基に大規模なリストラを進めてきた。だがその途上、リストラ案の法的リスクを指摘した法務課長が、自らも退職勧奨の対象とされ、「退職強要に当たる」としてTSIとBCGを東京地裁に提訴したことを第1回で報じた。そこでリストラ事件に詳しい東京法律事務所の笹山尚人弁護士に、TSIのリストラがどこに違法性を内包し得るのか、そしてリストラ案を設計したBCGに共同不法行為者としての法的責任が及ぶ可能性について聞いた。

#9
全国の中でも地銀再編が進んできた九州。その流れが及んでいなかった宮崎県でも、ついに再編の兆しが見え始めた。11月14日、宮崎銀行が宮崎太陽銀行の株式を大量取得し、議決権比率8.1%の筆頭株主になったことを公表したのだ。金融庁が昨秋から、地銀トップとの対話で進めている“官製再編”がいよいよ本格化し、経営統合や合併を見込む声が広がる。本稿では、金融庁幹部や関係者への取材を基に、宮崎銀行が筆頭株主となった意味を読み解く。

ゴルフウェアブランド「パーリーゲイツ」などを展開するアパレル大手TSIホールディングス(HD)は、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)の助言を基に大規模なリストラを進めてきた。ところが、リストラ案の法的リスクを指摘したTSIの法務課長が自らも退職勧奨の対象となり、「退職強要に当たる」としてTSIとBCGを東京地裁に提訴していたことがダイヤモンド編集部の取材で分かった。元法務課長が退職に至る詳細な経緯や裁判の焦点を明らかにする。

#7
2025年2月末、ミッド・スモールPEファンドのJ-STARが医療スタートアップMTUを買収したが、わずか1カ月後に当時の原拓也社長を「重大な疑義」で電撃解任した。その背景には、原氏による着服疑惑やセキュリティークラウドサービスの架空疑惑があった。これらの疑惑に加え、MTUが掲げた事業内容と実態の乖離(かいり)を検証する。歯科医院向けポータルや医療クラウドを標榜(ひょうぼう)しながら、実際にはSNS運用支援を中心に展開していた同社。その実態からJ-STARの投資判断の甘さを浮き彫りにする。
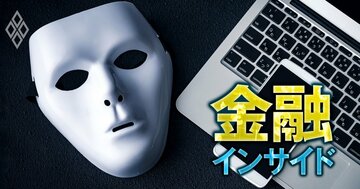
#6
今年5月、ふくおかフィナンシャルグループ傘下のみんなの銀行が開発したフルクラウド型の銀行システムが、三菱UFJ銀行の新設デジタルバンクの基幹システムに採用された。収益面では赤字が続くが、個人向けやシステム外販に加え、BaaS(Banking as a Service)事業を加速させる“第二創業期”を迎えている。本稿では、みんなの銀行の永吉健一頭取に、システム採用の背景や他銀行での需要の見通し、そして「Jカーブ型の成長は必然だ」と語る真意を聞いた。

#7
連載『スタートアップ最前線』ではこれまで、未上場の急成長スタートアップ、ダイニーにおける違法性の高い退職勧奨の実態を報じてきた。だが、同様の問題は上場企業でも起きている。創業からわずか7年で上場し、DX・AI支援で高成長を続けるジーニーだ。同社は対象者の業務を取り上げた上で虚偽の整理解雇通知を示唆し、法的に会社側が勝てば経歴に傷が付くと告げて自主退職を迫るなど、違法性の高い退職勧奨を敢行していたことが分かった。本稿では、独自に入手した人事部トップと社員との面談記録を基に、その違法性を明らかにする。また、この点について質問書を送付したところ、工藤智昭社長自らが取材に応じ、反省の弁と今後の対応策を語った。

ダイニーの退職勧奨は、生成AIの進展に伴うリストラとして注目を集めた。だが、ダイヤモンド編集部が独自に入手した同社のKPIや、山田真央CEOの社内ミーティングでの発言から、noteやメディアで語られていたAIリストラのストーリーは虚構であることが分かった。本稿では、海外投資家からの強い圧力を社内で吐露する山田CEOの姿や、虚構のストーリーに隠されていたリストラの実像、そしてダイニーの事案が他のスタートアップにとっても決して無縁ではない理由を明らかにする。

#5
J-STARは、中堅・中小企業を投資対象とするミッド・スモールPEファンドの雄として業界内でも一目置かれている。ところが、その名門ファンドで今年、前代未聞の投資崩壊劇が起こっていた。炎上案件は、医療系スタートアップのMTUである。買収完了からわずか1カ月後、J-STARはMTUの原拓也社長を「重大な疑義」により電撃解任。その背景にある“衝撃疑惑”がダイヤモンド編集部の取材で判明した。本稿では、買収後に明らかになったMTUの事業実態や不正行為に関する疑惑の数々を、投資責任者が周囲に明かした内容とともに公開する。

飲食店向けにモバイルオーダーを展開し急成長するスタートアップ、ダイニー。同社が6月に実施した大規模な退職勧奨について、山田真央CEOは「弁護士や社労士と連携し、適法に進めた」と説明していた。だがその実態は、対象者にいきなり退職を求め、提示したのは超少額の特別退職金。異例の短期間で退職合意を迫り、拒否すれば「追い出し部屋」へ異動させる違法性の高いプロセスだったことがダイヤモンド編集部の取材で分かった。本稿では、独自に入手した退職合意書や複数の対象者への取材を基に、その全容を明らかにする。

2022年に地銀の大株主リストに名を連ねて注目を集めたのが、元手100万円をわずか6年半で1億円に増やし、23年末に通算獲得利益が85億円に達した個人投資家の井村俊哉氏だ。同氏は既に地銀株を全て売却しているが、その背景には投資先の地銀に対する深い失望と本邦のガバナンス改革への危機感があった。井村氏が「憤りを感じた」と語る地銀の行為や、経営陣との間で交わされたやりとり、金融庁へ制度改革を訴えるに至った真意について、ロングインタビューでお届けする。

#16
日本の上場企業には、年収1億円以上のビジネスパーソンが実に1199人存在する。果たして、どんな顔触れなのだろうか。ダイヤモンド編集部は上場企業3890社を対象に、年収1億円以上の経営陣を調査し、実名で業界別の報酬ランキングを作成。今回は、銀行業界の報酬ランキングを掲載した。その結果、空前の好業績が続く中にあっても、銀行業界の役員報酬の水準は意外なほど抑えられていることが明らかになった。

#4
ダイニーが9月から、リファラル採用を大幅に強化していることがダイヤモンド編集部の取材で分かった。同社はわずか3カ月前、違法性の高い退職勧奨によって社員の約2割を退職に追い込んだばかりだ。本稿では、リファラル制度の改定前後の報奨金額や条件を公開し、一見すると不可解な採用戦略を検証。するとダイニーの突然のリファラル強化策は、他のスタートアップ企業も安易に飛びつきかねない、典型的な迷走パターンであることが分かる。

#3
ダイニーの退職勧奨は、生成AIの進展に伴うリストラとして注目を集めた。だが、ダイヤモンド編集部が独自に入手した同社のKPIや、山田真央CEOの社内ミーティングでの発言から、noteやメディアで語られていたAIリストラのストーリーは虚構であることが分かった。本稿では、海外投資家からの強い圧力を社内で吐露する山田CEOの姿や、虚構のストーリーに隠されていたリストラの実像、そしてダイニーの事案が他のスタートアップにとっても決して無縁ではない理由を明らかにする。

三井住友信託銀行が今年10月に導入する予定の新人事制度で、リテール部門の待遇を大幅に引き下げることがダイヤモンド編集部の取材で分かった。金利ある世界でリテールの重要性が高まる中、なぜ同行はその潮流に逆らい、リテール部門だけを冷遇するのか。独自に入手した新人事制度資料を基に全部門の給与レンジを比較し、その狙いに迫る。

#2
ダイニーが6月に実施した大規模な退職勧奨。その実態は、対象者に異例の短期間で退職合意を強要し、拒否すれば「追い出し部屋」へ異動させる違法性の高いプロセスだったことを第1回で明らかにした。では、退職勧奨を受けた元社員が実際に裁判に踏み切るとどうなるのか。本稿では、退職合意書にサインした元社員が訴訟で主張すべき違法性のポイント、裁判の勝率、勝訴時に得られる損害賠償の具体的な金額について、スタートアップ企業の労務問題に詳しい後藤亜由夢弁護士に聞いた。適法な手続で人員整理を進めたいスタートアップ経営者も必見だ。

#1
飲食店向けにモバイルオーダーを展開し急成長するスタートアップ、ダイニー。同社が6月に実施した大規模な退職勧奨について、山田真央CEOは「弁護士や社労士と連携し、適法に進めた」と説明していた。だがその実態は、対象者にいきなり退職を求め、提示したのは超少額の特別退職金。異例の短期間で退職合意を迫り、拒否すれば「追い出し部屋」へ異動させる違法性の高いプロセスだったことがダイヤモンド編集部の取材で分かった。本稿では、独自に入手した退職合意書や複数の対象者への取材を基に、その全容を明らかにする。

#10
金利上昇でリテール分野が再び脚光を浴びる中、りそなホールディングスはマイナス金利時代から「リテールNo.1」を掲げてきた。しかし、メガバンクが相次いで新サービスを投入し存在感を高める中で、その先行優位は揺らいでいる。潤沢な資本力で攻勢を強めるメガに対し、りそながよりどころとする武器は何か。定評のあるグループアプリ開発の舞台裏から、メガと対照的なリテール戦略の実像、そして新アプリのリリースに向けた課題を明らかにする。
