ダイヤモンド・オンラインplus
介護業界の常識を覆し、ITと営業マインドを取り入れて成長を遂げるケアリッツ・アンド・パートナーズ。夜勤はなく、効率的な労務管理と正社員中心の体制で高いサービス品質を実現。働く人が主役となる「社員ファーストな環境」の職場づくりを進めている。

総合建設事業と総合人材サービス事業、二つの事業ドメインの掛け合わせで多様な事業を創出するハンズホールディングス。グローバル人材を多数受け入れ、社内は多様性にあふれている。障がい者スポーツの支援にも力を入れ、雇用促進と事業成長に貢献している。

東京水道は、日本最大級の水道トータルサービス会社として、東京都民の生活を支える社会的使命を担う。毎年のベースアップや住宅制度、教育ローン支援など手厚い福利厚生で社員に安心を提供。さらに挑戦心を育てる教育カリキュラムや資格取得支援を通じ、未来の技術者を育成している。

パソコン(以下、PC)専門店「ドスパラ」や高性能PCメーカーとして知られるサードウェーブは、急成長するAI事業を軸に、デジタルクリエーション産業を支える取り組みに注力している。その実現に向け、多様な人材が自らの可能性に挑戦できる環境を構築している。

介護業界のデジタル化を原点に、幅広い業界でシステム開発を展開しているケアリッツ・テクノロジーズ。外注に頼らず、社員中心でプロジェクトを遂行する体制で、技術力と知見を社内に蓄積。多彩なバックグラウンドを持ったエンジニア集団が、事業拡大と人材育成を同時に実現している。

医薬品商社大手のアルフレッサは、医薬品や医療機器・診断薬・健康食品など多くのアイテムの安定供給を通じて地域医療・介護に貢献している。近年は社内に専門の部署を立ち上げ、ITシステムやウェブサービスなどのソリューション提供による医療現場の課題解決にも努めている。

長い歴史を持つ名古屋発の専門商社。鉄鋼から情報・電機、生活産業まで幅広い領域で事業を展開し、グローバル拠点は23カ国に及ぶ。地元の製造業との強固な信頼関係を基盤に「三現主義」を徹底。語学研修や早期抜てきを通じて“海外で戦える社員”を育成する。

国際自動車(km〈ケイエム〉)は創業100年を超える老舗タクシー会社。タクシー事業、ハイヤー事業、バス事業という3本柱を持ち、整備事業なども展開する。ホスピタリティと社員第一主義に基づき、働きやすい職場環境を提供。自動運転の将来を見据えた準備も怠らない。

日本の消防車の60%超はモリタ製! 明治時代に開発した日本初のガソリン・エンジン付き消防ポンプを原点に、防災のリーディングカンパニーとして第一線を走り続けると同時に、環境と調和する社会の実現に向けて挑戦を続けているのがモリタグループだ。

自動車分野や半導体分野など、成長分野の生産システムを製造・販売する平田機工。熊本県に本社を置きながら東証プライムの上場企業としてグローバルに事業を展開している。圧倒的な技術力を持ち、自社一貫体制で国内外のクライアントの課題を解決している。

エアバッグ用インフレータで世界トップクラスのシェアを誇り、がん治療薬で医療に貢献する日本化薬。火薬技術を起点に長年培ってきた技術を融合させ、社員の挑戦を後押ししながら社会課題の解決と持続的成長を実現している。目指すのはニッチ市場でのグローバルナンバーワンだ。

創業以来、どんな場面でも「挑戦」を貫いてきたエヌエスティ・グローバリスト(NSTG)。金融不安の時代にリサイクルトナー販売から出発し、サプライ事業を軸に新領域へと歩を進め、今では9つの事業を展開する。大企業にはない機動力と多角的な実績で存在感を高めている。

会社選びには、「どんな人たちと、どのような価値観で共に働くか」が、実はとても大事な視点となる。TSOneは、システム開発を軸に、ITを通じて企業や社会の課題を支える一方、社員一人一人の「つながり」と「成長」、そして「ライフ」までを丁寧に支えていくことを大切にしている。

現場の「力技」で稼働を維持し、デジタル化が遅れる日本の製造業。その危機的状況を打破し、設計から製造までを一気通貫で変革する「デジタルシャドウ」と、PLM短期導入の秘策とは何か。

今後、デジタル通貨のいっそうの普及が予想される中、日本企業はその活用法を真剣に考える必要がある。デジタル通貨はビジネス、そして社会にどのような価値をもたらすのだろうか。

単なるアウトソーシング先ではない、価値創造のパートナーとしてのインドの可能性。そのカギとなる「GCC」(グローバルケイパビリティセンター)の役割を含め、日本とインドによる価値共創の道筋を明らかにする。

50年も前から環境問題に向き合い、いま先駆者としてCEをリードするリコー。同社のCEの現在地点と今後の道筋について尋ねた。

現場を大切にする経営者は、日本にも数多く存在する。その代表が、京セラ創業者の稲盛和夫氏であった。ものづくりの原点は製造現場に、営業の原点はお客様との接点にあると考えた稲盛氏は、「現場主義に徹する」を自身の経営フィロソフィに掲げた。いわく、「現場は宝の山である」と。また、トヨタ自動車や本田技研工業など日本を代表するものづくり企業でいまなお実践されている「三現主義」も、現場で現物をもとに現実の状況を認識して問題解決を図ることを旨としている。こうした現場にこだわり抜く姿勢の先に見えてくるものは何か。それは、顧客中心主義(カスタマーセントリシティ)にほかならない。ペンシルバニア大学ウォートンスクール教授のピーター・フェーダー教授によると、顧客中心主義とは、「選ばれた顧客のニーズに合わせて商品やサービスを開発することであり、その実現には企業と顧客との関係に関する古い考えを捨て、最も重要な顧客への商品開発を根本的に考え直し、新しい独自の方法を見つけること」だと論じている。前出の稲盛氏も、顧客中心主義について「お客様のニーズに対して、いままでの概念をくつがえして、徹底的にチャレンジしていくという姿勢が要求されます」と述べている。ここで重要なのは、「根本的に考え直す」「いままでの概念をくつがえす」という姿勢である。従来の「お客様は神様です」的に、顧客の「御用聞き」に徹してしまっては、本当の意味で顧客ファーストを実践することはできない。そこでは企業が主体となって、課題を抱える顧客の期待を上回る価値提供が求められる。そのためには企業固有の「強み」を再編集、再創造することが必要となる。つまり、現場主義と顧客中心主義は表裏一体の関係であり、どちらが欠けても真の顧客価値を創出することはできないのだ。だが、日々忙殺される経営者がこうした現場主義、顧客中心主義を実践するのは容易ではない。強い信念と自己規律が必要とされる。顧客重視の人間ほど、顧客理解のために現場の重要性をよく知っているからだ。今回インタビューに登場するアビームコンサルティングの社長・山田貴博氏もその一人だった。新卒から30年以上、一貫してコンサルタントの道を歩んできた山田氏は、現場・顧客中心主義の苦労と喜びを知っているからこそ、「現場から離れてしまうことが嫌で、社長就任のオファーを固辞していました」と笑う。成長を続ける同社の社長のバトンを引き継いでから2年半。いまも現場にコミットし続けている。社長になったことで、現場主義、顧客中心主義の意味が大きく変化したようだ。山田氏に、日本発のコンサルティングファームとしての矜持を聞いた。
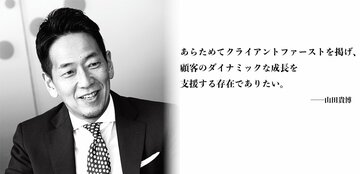
「製造業DX」が広がりを見せている。特に、日本のものづくりを支える中規模および中小の製造業が成果を出せるかどうかは産業全体にとっても重要だ。中規模製造業のDXの現状と課題、その解決策について探る。

Fortune Business Insightsによれば、半導体の市場規模は2025年の7552億8000万ドルから32年は2兆0625億9000万ドルへと成長し、その間の年平均成長率は15.4%に上る。そうした中、世界的半導体メーカーのトップは、どのような戦略でイニシアチブを取ろうと考えているのか。日本テキサス・インスツルメンツ社長のルーク・リー氏に話を聞いた。同氏は現在、日本に加え、韓国・台湾・南アジア地域を統括している。
