ホンダ
関連ニュース
ホンダが「トヨタ超え」10兆円のEV投資!三部社長が見せる旧来トップとの“決別”
佃 義夫
ホンダは2030年度までにEV・ソフトウエアに10兆円を投じる計画を発表した。2年前の計画から一気に2倍に引き上げ、日本の自動車メーカーとしてはトヨタ自動車を抜いて最大規模となる。

日本車EV、米ハイブリッドブームが資金源に
The Wall Street Journal
トヨタやホンダはハイブリッド車で荒稼ぎできるため、電気自動車への積極的な投資が可能になっている。

活況の日本株、急激な円安はリスク
The Wall Street Journal
日経平均株価が34年ぶりに史上最高値を更新することになった理由はまだ健在だが、円安による追加の押し上げ効果を期待すべきではない。

トヨタ、EVからPHEVへのシフト鮮明!EV150万台販売目標は「事実上引き下げ」
ダイヤモンド編集部,宮井貴之
トヨタ自動車の佐藤恒治社長は、5月8日に開かれた2024年3月期連結決算会見で、プラグインハイブリット(PHEV)にシフトしていく姿勢を鮮明にした。背景には、中国で電気自動車(EV)の価格競争が激化していることや、北米でEV販売が減速していることがある。EVへの需要が停滞する中で、ハイブリット車の販売が伸びているのだ。トヨタがPHEVの生産・販売を強化する背景と狙いに迫る。

倒産危険度ランキング2024【自動車24社】4位日産、2位河西工業、1位は?《Editors' Picks》
ダイヤモンド編集部
日産自動車が、経営難に陥っていた自動車内装大手の河西工業を資金支援することが明らかになりました。劇的な円安が追い風となって軒並み好業績をたたき出す自動車メーカー。特集『倒産危険度ランキング2024』から、1月25日に公開した記事をもう一度、紹介します。

「バイク乗りはガラが悪い…」→ホンダが打ち出した販売戦略が秀逸だった
岩尾俊兵
GDPでは中国に抜かれ、人口で劣るドイツにまで抜かれた日本だが、世界に先駆けた取り組みで日本経済をけん引する企業は少なからずある。最新の経営戦略論の中で語られる、日本の製造業の強みとは?

#2
【女子プロゴルフ・スポンサーランキング】PR上手な企業の10位は大和ハウス工業、5位ホンダ、1位は?
ダイヤモンド編集部,堀内 亮
プロゴルフ界で男子ツアーをはるかにしのぐ人気を誇る女子ツアーに対し、大会スポンサーを務めるだけでなく、選手と所属契約を結んでPRを狙う企業が相次ぐ。最もPR上手な企業は、どこか。

予告
名門ゴルフ倶楽部はビジネスに効く「最強サロン」!ランキングと独自取材で“大人の社交場”を徹底解剖
ダイヤモンド編集部,堀内 亮
新型コロナウイルスの感染拡大を奇貨として復活を遂げたゴルフは、その人気に衰える気配がない。もともとゴルフはビジネスとは切っても切れない関係にあり、ビジネスパーソン必須のスキルである。定番のゴルフ場ランキングや、エリートが集う“最強サロン”の名門ゴルフ倶楽部の裏側、プロゴルフの話題などをお届けする。
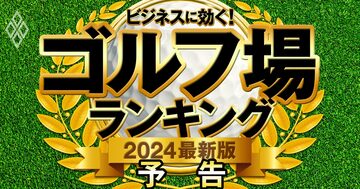
原油相場は半年ぶり高水準で90ドル目指す、米国の量的緩和が価格上昇の引き金に
新村直弘
原油価格が半年ぶりの高水準となり、1バレル当たり90ドルを目指す動きを見せている。今後の原油価格はどのように推移するのか。実は、米国の量的緩和がその行末を大きく左右するかもしれないのだ。

日産の新中期経営計画に感じた「物足りなさ」ホンダ、ルノーとの提携を生かせ!
佃 義夫
日産自動車は、3カ年の新中期経営計画「The Arc」を発表した。年間販売台数を100万台増加させ、営業利益率を6%以上に引き上げることを目指す。だが、一方でホンダ提携の具体策に欠けるなど、やや物足りない面も目立った。

#11
“日本のバフェット”シゲルさんの「長期保有27銘柄」を初公開!トヨタ、商社…
ダイヤモンド編集部,竹田幸平
信用取引を駆使したデイトレードで日本の個別株の売買を行う藤本茂さん(シゲルさん)。だが、実は、中長期保有を前提に運用する投資先もある。そんな、本邦初公開の27銘柄を明らかにする。
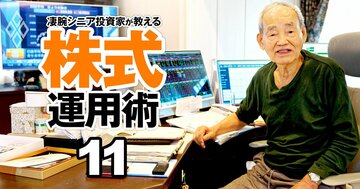
#4
TSMC熊本工場の現地調達率は「まだ25%」、商機を狙う日本のサプライヤー27社の実名
財訊
台湾TSMCの内製化率を高めるという方針の下、ここ数年、日本のサプライヤーが台湾での工場建設に奔走し、日本の半導体産業は一時空洞化の危機に陥った。しかし、TSMC熊本工場の稼働によって、TSMCは日本で新たな半導体エコシステムを構築しつつある。

日産・ホンダは「トヨタの対抗軸」になり得るか?4つの指標で実力を徹底比較
ダイヤモンド編集部,宮井貴之
電気自動車(EV)の劣勢を挽回するため提携の検討を始めた日産自動車とホンダ。トヨタ自動車に対抗できるのか、四つの指標(左表の赤字部分)から提携効果を分析する。

ホンダは新体制で“北米シフト”鮮明に、新型EV「HONDA 0シリーズ」で反転攻勢なるか
ダイヤモンド編集部,宮井貴之
ホンダが4月から役員体制を変更する。貝原典也専務の副社長昇格が目玉で、社長と副社長2人による「トロイカ体制」となる。日産自動車との提携という重責を担う新体制を分析する。

日産・ホンダがEV提携に踏み切った理由、トヨタやBYDを巻き返せる可能性は?
ダイヤモンド編集部,宮井貴之
日産自動車とホンダは、電気自動車(EV)の開発に向け、協業の検討を始めると発表した。部品やソフトウエアの共同開発で価格競争力を高めようとしているが、課題は山積みだ。

#3
トヨタやソニーと緊密関係…TSMC「日本ビジネス」真の狙いを熊本第2工場への巨額投資から読み解く
財訊
台湾TSMCは熊本新工場の開設によって、地政学的なリスクを分散する新たなサプライチェーン構築を可能にした。そして、日本企業との緊密な協力を通じ、競合他社に先駆けて数兆ドル規模のビジネスチャンスをつかむことができるだろう。熊本工場に巨額投資するTSMCの狙いをひもとく。

日産・ホンダ連合誕生で「業界再編」必至!サプライヤー、日仏連合…全てが激変する
佃 義夫
日産自動車とホンダが提携の検討開始を発表した。日産・ホンダの連合は、自動車産業に新たな合従連衡を引き起こす可能性がある。

#16
「EV失速、HV回帰」は日本の自動車株に追い風?日産ホンダ協業で分かった不都合な真実
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
世界の大手自動車メーカーが続々と電気自動車(EV)の投資計画を延期している。EVからハイブリッド車(HV)への揺り戻しにより、トヨタ自動車など日系自動車メーカーに有利との論調が目立つが、本当にそうなのか。「自動車関連16社の株価と業績の関係」と「向こう1年の業界ビッグイベント20」を分析することで、自動車株を左右する“三大テーマ”を抽出する。果たして、EV失速が日本の自動車株上昇のきっかけとなるのか。
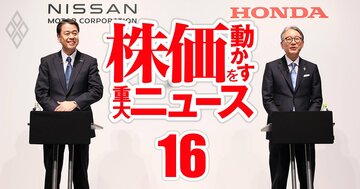
日産・ホンダ・スズキ・トヨタの年収、恵まれた世代は?氷河期世代が不遇の日産・スズキ【5世代20年間の推移を初試算】《Editors' Picks》
ダイヤモンド編集部
3月15日、日産自動車とホンダが戦略的パートナーシップの検討を開始すると発表しました。自動車業界で働く人の待遇は今後、変化するのでしょうか?半導体不足が解消に向かい、円安の恩恵もあって業績が好調な自動車各社。今回は日産自動車、ホンダ、スズキ、トヨタ自動車の4社を取り上げる。4社の中で、それぞれ年齢別に年収を比べた場合、団塊・バブル期・就職氷河期・ゆとり世代のうち、どの世代が恵まれていたか?20年間を10年刻みにして、5世代の年収と主要64社内のランクを初試算した。日産、スズキは氷河期世代が不遇だった。一方、ホンダ、トヨタは?このほか専門家による5年後の平均年収予想も掲載する。

ホンダが日立の“問題児”部品メーカーを引き取った裏事情とは?自動車業界「最大の謎」に迫る!《Editors' Picks》
ダイヤモンド編集部
3月15日、日産自動車とホンダが戦略的パートナーシップの検討を開始すると発表しました。ホンダのサプライヤー政策に迫る記事をもう一度、紹介します。
