
名古屋和希
ポイント経済圏の覇権を巡る攻防が熾烈になっている。台風の目になっているのが、三井住友フィナンシャルグループ(FG)などが展開するVポイントだ。三井住友FGは5月、ソフトバンクと提携し、VポイントとPayPayポイントの相互交換に乗り出すと発表した。ポイント経済圏同士の巨大連合が誕生することになる。Vポイントは先行する楽天ポイントとNTTドコモのdポイントを猛追するが、足元では経済圏の基盤を弱体化させかねない二つの火種がくすぶっている。

根強いコンサルティング需要を背景にコンサルファーム各社の高成長も続いている。では、上場する主要コンサルファームの年収はどうなっているのか。上場している主要ファーム16社の年収ランキングを公開する。野村総合研究所が昨年に続き2位を堅持した一方、トップ5の順位は大きく変動した。

化学業界は脱炭素対応や中国の化学品の供給過剰などを背景に大激変の真っただ中にある。化学メーカーの優勝劣敗も鮮明になる中で、各社の従業員の給与はどうなっているのか。化学大手20社の2024年度の給与ランキングを公開する。10位に住友化学、6位に三井化学が入った。業績の浮き沈みなどを背景に23年度から「序列」も変わった。果たしてトップ5は?

取締役会や役員会のデジタルトランスフォーメンション(DX)を支援するベンチャー、ガバナンスクラウド(東京都港区)がAI(人工知能)の活用に乗り出した。公認会計士で元カカクコム取締役の上村はじめ氏が2021年に設立した同社は、上場する金融機関や商社、不動産会社などに顧客網を広げている。AI活用で、将来的には最適な社外取締役の選任なども目指す。企業統治改革の流れが加速する一方、社外取締役が機能不全に陥るケースなども目立つが、取締役会のDX化は社外取の機能発揮を後押しする可能性がある。

温度センサー大手の芝浦電子を巡る、台湾の電子部品大手、国巨(ヤゲオ)とミネベアミツミのTOB(株式公開買い付け)合戦が長期化している。ヤゲオは8月1日、芝浦電子の株式取得に必要な当局の外為法の審査期間が延び、TOB期間を再延長したと発表した。実は、TOB合戦の異例の長期化は、ヤゲオにとって誤算といえる。「同意なき買収」を仕掛けたヤゲオがはまった落とし穴とは。

デロイト トーマツ グループ傘下のデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA)の前田善宏代表執行役が解任されたことがダイヤモンド編集部の取材で分かった。解任理由は明らかになっていない。昨年6月にトップに就任した前田氏は、M&Aに精通する著名コンサルタント。業績が好調でグループの稼ぎ頭でもあるDTFAを率いる前田氏の“謎”の解任に、グループ内でも動揺が広がりそうだ。電撃解任を受けた新体制を明らかにする。

製造業人材の資格やスキルの管理を支援するベンチャー、スキルノート(東京都千代田区)が事業を拡大している。企業が抱える人材の資格やスキルを全社で一元管理できるようにし、人材育成や技能継承などを後押ししている。すでにJFEホールディングスや川崎重工業、三菱ケミカルグループ、旭化成といった大手製造業が導入している。信越化学工業出身で創業者の山川隆史代表取締役は「日本発で世界を目指す」と宣言する。山川氏に、創業に至った経緯に加え、スキルノートが秘めるものづくり復興の可能性、今後のグローバル展開などを明かしてもらった。

根強いコンサルティング需要を背景にコンサルファーム各社の高成長も続いている。では、上場する主要コンサルファームの年収はどうなっているのか。上場している主要ファーム16社の年収ランキングを公開する。野村総合研究所が昨年に続き2位を堅持した一方、トップ5の順位は大きく変動した。

国内発のコンサルティングファーム、ベイカレントは急速な台頭を遂げてきた。足元で人員数は5000人を突破し、コンサルビッグ4超えも果たした。だが、あまりに急激な成長は組織や社内風土のひずみも顕在化させつつある。第4回の本稿では、ベイカレントの最高幹部の顔触れと序列を明らかにしていく。幹部の序列はその独特な組織体制とも密接で、実は、会長や社長よりも格上の「陰の最高権力者」が社内に存在する。その正体とは。

#1
化学業界は脱炭素対応や中国の化学品の供給過剰などを背景に大激変の真っただ中にある。化学メーカーの優勝劣敗も鮮明になる中で、各社の従業員の給与はどうなっているのか。化学大手20社の2024年度の給与ランキングを公開する。10位に住友化学、6位に三井化学が入った。業績の浮き沈みなどを背景に23年度から「序列」も変わった。果たしてトップ5は?

#27
日本航空(JAL)から非公開化の株主提案を受けている持分法適用会社のエージーピー(AGP)のJALへの抵抗が激しくなっている。AGPは20日、豪金融サービス大手、マッコーリー・グループなどが運用するファンドからTOB(株式公開買い付け)提案を受け、取締役会で正式に協議を始めると発表した。降って湧いたTOB提案は、26日の株主総会前に、JALへの“けん制球”となったものの、実は「勇み足」も犯している。

デロイト トーマツ グループ傘下のデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA)の前田善宏代表執行役が解任されたことがダイヤモンド編集部の取材で分かった。解任理由は明らかになっていない。昨年6月にトップに就任した前田氏は、M&Aに精通する著名コンサルタント。業績が好調でグループの稼ぎ頭でもあるDTFAを率いる前田氏の“謎”の解任に、グループ内でも動揺が広がりそうだ。電撃解任を受けた新体制を明らかにする。

#10
今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。1899年に「鳥井商店」として産声を上げ、創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。「ダイヤモンド」1966年5月30日号に掲載された「ビール5社の優劣格差はどう変わる 麒麟・サッポロ・朝日・サントリー・宝」という当時のビール業界の勢力図をまとめた記事を2回にわたり紹介する。サントリーはビール参入3年目で、先行していた宝(現宝酒造)とシェアが逆転し、業界4位に浮上している。後編の本稿では、シェアトップのキリンビールと同じ宣伝広告費を投じるなどサントリーが取っていた積極的な拡大策の中身を明らかにする。
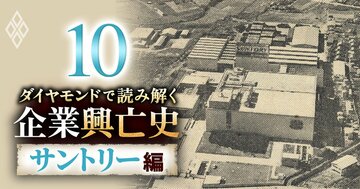
国内発のコンサルティングファーム、ベイカレントは急速な台頭を遂げてきた。足元で人員数は5000人を突破し、コンサルビッグ4超えも果たした。だが、あまりに急激な成長は組織や社内風土のひずみも顕在化させつつある。爆速成長の陰でベイカレントがはまった罠とは。初回となる本稿では、5月27日に社長に就任する予定の北風大輔副社長執行役員の経歴に漂う不可解な点を明らかにしていく。謎多きコンサルタントともいえる新トップの「超華麗キャリア」の実相とは。

#9
今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。1899年に「鳥井商店」として産声を上げ、創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。「ダイヤモンド」1966年5月30日号に掲載された「ビール5社の優劣格差はどう変わる 麒麟・サッポロ・朝日・サントリー・宝」という当時のビール業界の勢力図をまとめた記事を2回にわたり紹介する。前編となる本稿では、キリンのブランド力の高さや商売のうまさを表すキリンの「三つの強み」を明かしていく。
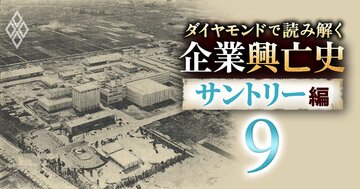
ニデックは工作機械大手の牧野フライス製作所へのTOB(株式公開買い付け)を撤回すると発表した。牧野フライスに対する「同意なき買収」に踏み切ったニデックは、牧野フライスが導入した対抗策の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てたが、却下された。TOB撤回の理由について、ニデックは対抗策による損害の回避と主張している。だが、実はニデックが進めていた買収計画にはある大きな誤算が生じていた。それがTOB撤回の引き金となった可能性がある。ニデックの大誤算とは。

#8
今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。1899年に「鳥井商店」として産声を上げ、創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。今回は「ダイヤモンド」1965年7月30日号の特集「株式未公開の魅力会社」内に掲載されたサントリーに関する記事を紹介。記事では、ビール事業への参入から丸2年で、ビール事業の赤字が累計で40億円に達したと明かしている。64年のビール事業の売上高は40億円ほどで、まだまだ損益分岐点を大きく下回る。一方、祖業である洋酒事業は極めて堅調で、ビール事業の大きな支えとなっている。当時のサントリーの財務や収益の実情をひもとく。
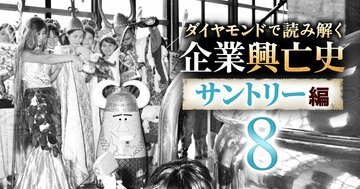
国内発のコンサルティングファーム、ベイカレントは急速な台頭を遂げてきた。足元で人員数は5000人を突破し、コンサルビッグ4超えも果たした。だが、あまりに急激な成長は組織や社内風土のひずみも顕在化させつつある。第4回の本稿では、ベイカレントの最高幹部の顔触れと序列を明らかにしていく。幹部の序列はその独特な組織体制とも密接で、実は、会長や社長よりも格上の「陰の最高権力者」が社内に存在する。その正体とは。

国内発のコンサルティングファーム、ベイカレントは急速な台頭を遂げてきた。足元で人員数は5000人を突破し、コンサルビッグ4超えも果たした。だが、あまりに急激な成長は組織や社内風土のひずみも顕在化させつつある。爆速成長の陰でベイカレントがはまった罠とは。初回となる本稿では、5月27日に社長に就任する予定の北風大輔副社長執行役員の経歴に漂う不可解な点を明らかにしていく。謎多きコンサルタントともいえる新トップの「超華麗キャリア」の実相とは。

ニデックは工作機械大手の牧野フライス製作所へのTOB(株式公開買い付け)を撤回すると発表した。牧野フライスに対する「同意なき買収」に踏み切ったニデックは、牧野フライスが導入した対抗策の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てたが、却下された。TOB撤回の理由について、ニデックは対抗策による損害の回避と主張している。だが、実はニデックが進めていた買収計画にはある大きな誤算が生じていた。それがTOB撤回の引き金となった可能性がある。ニデックの大誤算とは。
