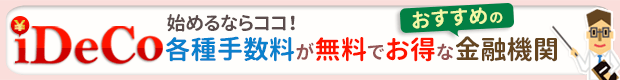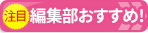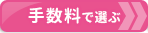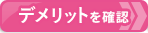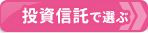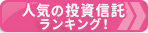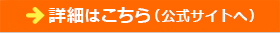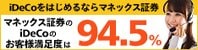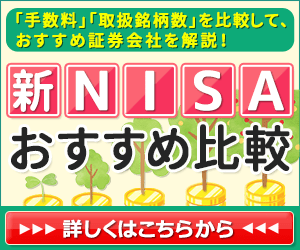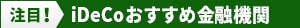今回は、「今すぐiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)に加入したほうがいい人」と「iDeCoへの加入はちょっと待ったほうがいい人」の違いを紹介したいと思います。
iDeCoには、「掛金を拠出するとき」「運用するとき」「受け取るとき」の3つの場面で、大きな節税メリットがあることをこれまで連載で何度もお伝えしてきました。
【※関連記事はこちら!】
⇒「個人型確定拠出年金(iDeCo)」を活用すれば、多くの人が運用利回り15~30%の“天才投資家”に!「iDeCo」のお得な仕組みと節税メリットを解説!
 あなたはiDeCoに入ったほうがいい人? それとも入らないほうがいい人?
あなたはiDeCoに入ったほうがいい人? それとも入らないほうがいい人?
それに加えて、職業や働き方によって「iDeCoに加入すると、さらにメリットが大きくなる人」がいます。
その一方で、「iDeCoにどんなにすごい節税メリットがあっても、iDeCoに入るのはちょっと待ったほうがいい」という人もいます。
では、どんな人ならiDeCoに加入したほうがメリットは大きくなり、どんな人ならiDeCoに加入するのを待ったほうがいいのでしょうか?
「今すぐにでもiDeCoを始めたほうがいい」のはこんな人!
まず、今すぐにでもiDeCoに加入してほしい人を紹介しましょう。大きく分けて3つの働き方に整理できます。
1.公務員
まず加入を検討したほうがいいのは、「公務員」です。恵まれた立場のように思われてばかりの公務員ですが、実は最近、厳しい状態に置かれています。というのは、ここ数年で「退職金水準の引き下げ」が行われているからです。
公務員の賃金は「民間との格差が生じないように」と、民間企業の賃金水準やボーナス水準、退職金水準との比較が常に行われています。そして2012年、国家公務員の退職金水準が著しく高いとの指摘からその見直しを行うための法律が成立し、その後、国家公務員の退職金の段階的な引き下げが行われています。モデル金額で比較すると、見直し以前から現在までで約400万円も引き下げられました(※人事院調べ)。この法律が成立した後、退職金水準の引き下げの流れは、国家公務員だけでなく地方公務員にも広がっています。
公務員としてがんばって働けば、退職金がたくさんもらえる、と期待していた人もいたことでしょう。それが定年直前にするりと400万円が逃げていったようなものです。こうした見直しは今後も継続して行われる可能性があります。
iDeCoの制度変更によって、2017年1月から公務員もiDeCoに加入できることになったのは、「公務員の優遇」ではなく、むしろ「公務員の退職金水準引き下げの穴埋めは自分でしろ」というメッセージなのです。
もしiDeCoで公務員の掛金の上限である月1.2万円の積立を22歳から60歳まで続ければ、元本として547.2万円が貯まります。iDeCoでは掛金の全額が所得金額から控除されますから、税率を20%相当と仮定すれば、掛金の20%が所得税・住民税の減税相当額になり、約109万円は国から取り戻したと考えられます。下げられた分の退職金すべてが戻ってくるわけではありませんが、少しでも取り返すために公務員はiDeCoを使わない手はないでしょう。
2.会社員
「会社員」も基本的にはiDeCoを活用するほうがメリットは大きいと言えます。
会社員として働く限りは、節税をして資産を増やす方法はほとんどありません。住宅ローン減税は、住宅ローンを借り入れて自分の住宅を保有する場合に税負担額を軽減することを認める強力な税制優遇策でしたが、徐々に縮小・終了の方向に向かっています(といいつつ、延期を繰り返すのがまた意地悪なところです)。
一方、iDeCoは自分の老後のための資産形成を行うことで、目の前の所得税や住民税を軽くする会社員にとって魅力的な仕組みです。会社が企業型の確定拠出年金を採用していない限り、基本的に会社員は誰でもiDeCoに加入できますので、税制メリットを活かしつつ老後の資産形成としたいところです(企業型確定拠出年金のある会社でも、会社の企業型年金規約がiDeCo加入を認めている場合はiDeCoに加入できるが、ごく一部の企業にとどまる)。
ちなみに、会社が企業型の確定拠出年金を実施している場合も、約4割の会社では「マッチング拠出」を実施しています。これは会社の確定拠出年金に自分のお金を追加入金できる制度で、iDeCoと同様の税制優遇が受けられます。詳しくは会社の確定拠出年金担当者に確認してみてください。
3.自営業者やフリーランス
国民年金保険料を納めている「自営業者」や「フリーランス」の人々は、実は2017年1月に制度変更される以前からiDeCoに加入することができました。しかも月6.8万円まで積立が可能と、他の職業と比べてとても優遇されています。しかし、自営業者やフリーランスのiDeCo利用者は2017年4月時点でまだ9万人(※国民年金基金連合会調べ)とごくわずかです(国民年金保険料を納めている人は約1700万人いる)。
国民年金にしか加入していなければ、公務員や会社員に比べて老後にもらえる年金額がとても少なくなりますが、自営業者のiDeCo加入率を見る限り、老後資金に対して危機感を持っている人が少なすぎます。
自営業者やフリーランスの場合、国民年金が満額支給されても年間80万円ほどで、生活するには足りないと言われています。会社員のように国民年金と厚生年金を合計して年間200万円ほど支給されるのとでは、老後の経済状況が大きく違ってきます。
しかも会社員の場合、退職金もあればさらに老後の生活資金に余裕が出てきますが、自営業者にはそれもありません。自営業者が少しでも老後に危機感を持っているならば、今すぐにでもiDeCoに加入し、できるだけ活用して老後に備えるべきです。
もうひとつ、自営業者やフリーランスの場合、公務員や会社員などよりもiDeCoの掛金の上限が大きいため、「節税」効果がバカになりません。自営業者は売り上げが増えれば増えるほど税金や社会保険料が増えていくのが悩みですが、iDeCoを活用すれば大きく納税額を減らすことができます。仮に年間81.6万円の満額を積み立てたら、その全額が所得金額から控除されます。仮に税率を20%相当としたなら、掛金81.6万円の20%を節税することができます。つまり、自分の老後に貯蓄しただけで、年間約16万円も支払う税金を減らせるのですから、iDeCoに加入しない手はありません。
「iDeCoに加入するのはやめたほうがいいかも?」なのはこんな人!
ここまで公務員、会社員、自営業者・フリーランスの場合は、iDeCoに加入したほうがいいと説明してきました。その一方で、これから紹介するような方の場合は、iDeCoへの加入はいったん見直したほうがいいでしょう。
1.専業主婦
2017年1月からの制度変更で、新しくiDeCoに加入できる立場として「専業主婦」、つまり国民年金の第三号被保険者が加わりました。iDeCoを紹介する記事などでも「専業主婦でも得」という内容をよく見かけます。しかし、専業主婦のiDeCo加入は要注意です。
というのも、専業主婦の場合、いわゆる「130万円の壁(大企業では106万円の壁)」を超えない範囲に年収をおさえると、国民年金保険料を納めずに済みます。また年収が「103万円(2017年からは150万円に)」の範囲であれば、所得税や住民税がかかりません。
もし、年収が103万円を超えなければ、そもそも所得税や住民税を納めていないので、いくらiDeCoに加入しても税金の軽減メリットは得られないのです。
厳密に言うと、年収103万~130万円の範囲については「税金は払うが年金保険料は払わない」ボーダーラインなので、人によってはiDeCoに加入することで税金の軽減メリットが生じます。しかし、そんなギリギリのところで年収を調整しているパート主婦はほとんどいないと思いますので、ここではあえて考えないことにします。
対して、仕事をしていない専業主婦がiDeCoに加入し、夫の年収から月2.3万円を負担した場合、夫の税金が下がるわけではないので、こちらもメリットを得ることはありません。
したがって専業主婦については、「(会社員時代に積み立てたなど)すでに確定拠出年金の資産があって、iDeCo口座を作らざるをえない」場合はともかく、「今年ゼロからスタートしてみよう」と考えていた方は、じっくりiDeCoへの加入を検討し直してください。iDeCoを活用するよりに、むしろ年収をアップさせることのほうが優先順位は上かもしれません。
2.目の前の家計が安定していない人、特に借金がある人
60歳に向けて老後の財産作りをするならiDeCoは最高の選択肢かもしれませんが、いま目の前の家計すら黒字に保てていない人は、無理に老後の備えをするステージにはありません。まずは毎月の家計のやりくりを安定化させて、コンスタントに黒字できる状態に改善してからiDeCoに加入しても遅くはありません。
特に借金がある人は、基本的にその返済を優先したほうがいいでしょう。税制優遇を考えれば、iDeCoへの積立は20%以上の運用利回りに相当するかもしれませんが、それは掛金の拠出をしたときだけの話です。キャッシング、リボ払い、消費者金融や銀行系カードローンなど、年10%以上の利息がつくローンの残高を抱えている場合、残高がゼロになるまで利息はかかり続けます。iDeCoで20%以上の税制優遇を一度だけ得る前に、まずは年10%以上の利息がかかり続ける借金の返済を終えるべきです。
iDeCoに積み立てたお金は60歳まで解約できないことも考えると、小さな借金を重ねているような人はiDeCo加入を控えましょう。まずは家計の黒字転換が課題です。
3.20代の人
あなたがまだ20代で、毎月の手取りが20万円に達していない場合、今は自分の仕事のスキルを磨いて年収をアップさせることにお金を使いましょう。
手取り16万円の家計から月1.2万円を出すより(企業年金のある会社員の拠出金額の上限金額)、手取り25万円の家計へとキャリアアップするためにお金をかけるほうが長期的には税制メリット以上の価値があります。資格を取れば資格給が出るような仕事の場合、iDeCoに加入することより、資格の勉強と試験代金の支払いを優先させましょう。
また、貯金が100万円にも満たない場合、何か臨時支出が重なるとあっと言う間に借金生活に転落しますので、そうした方もiDeCoへの加入はおすすめできません。
100万円以上の貯金がある場合でも、引っ越し、車を買う、結婚など、今後の人生の大きな節目において使ってしまえば、また貯金をリスタートさせなければなりません。iDeCoに拠出したお金は60歳まで引き出すことができず、現役時代のマネープランには使えませんので、20代にとってiDeCoへお金を拠出することは厳しい制約になります。
ですから、まだあなたが20代なら、まずは毎月の収支を安定させ、貯金ができる体質になることを優先させましょう。それからiDeCoを始めても遅くはありません。
【※関連記事はこちら!】
⇒20代で「iDeCo」を始めるメリット・デメリットは? 会社員なら10年で最大55万円超が節税できるほか、30年以上の時間を味方にすれば運用益も期待できる!
4.年収が下がる可能性のある人
今後、年収が下がる可能性がある場合は、iDeCoへの加入を先送りしたほうがいいでしょう。つまり、数ヵ月だけ積み立てて、その後中断するくらいなら、少し様子をみたほうがいいと言えます。たとえば、
・これから産休に入る人
(共働きで妻が産休に入る場合も含む)
・療養中で病気休職予定の人
・会社を辞めて転職活動する人
などがこれにあたります。
特に、夫婦の共働き家庭でやりくりを成立させているとき、どちらかの年収がダウンすると、家計管理は一気に難しくなります。育休中にお休み前の給与の一定割合を給付金でもらえたとしても、やはり著しい収入ダウンです。
iDeCoの加入はいつでもできます。しかし、iDeCoに積み立てたお金は60歳まで解約できません。不安定な時期にあえてiDeCoに加入するよりは、少し先送りを検討してみてもいいはずです。
どうでしたか? iDeCoには大きな節税メリットがあり、老後資金を蓄えられる心強い存在ですが、誰でもいつでもiDeCoに加入すればメリットが得られるわけではありません。iDeCoに無理に加入した後にむしろ困ったことにならないよう、iDeCoのメリット・デメリットをあらためて理解することをおすすめします。
【※関連記事はこちら!】
⇒iDeCo(個人型確定拠出年金)4つのデメリットとは?はじめる前に必ずチェックしないと失敗する、口座開設や運用商品、解約に関する注意点を解説!
⇒「iDeCo」を始めるなら、おすすめ金融機関はココ!口座管理料が無料になり、投資信託のラインナップが充実している「SBI証券」と「楽天証券」を比較!
1995年株式会社企業年金研究所入社後、FP総研を経て独立。ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士、AFP)、1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)、消費生活アドバイザー。若いうちから老後に備える重要性を訴え、投資教育、金銭教育、企業年金知識、公的年金知識の啓発について執筆・講演を中心に活動を行っている。
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
| 【2026年2月4日時点】 【iDeCoおすすめ証券会社&銀行 比較】 ※どの金融機関でiDeCo口座を開設した場合でも、別途、国民年金基金連合会へ支払う加入時手数料が2829円、国民年金基金連合会と信託銀行へ支払う手数料が合計171円(毎月)かかる。受取時は給付手数料440円(1回毎)を信託銀行に支払う。還付時には、国民年金基金連合会と信託銀行への還付時手数料として合計1488円(1回毎)がかかる。運営機関変更時の手数料は「他の金融機関から」変更の場合で、「他の金融機関に」変更する場合は4400円の手数料が発生する場合がある。下記の金額は掛金を拠出する場合(すべて税込)。 |
| ◆松井証券 ⇒iDeCo詳細ページへ | ||||
| 運営管理手数料※(月額) | 手数料※ | 投資信託 | ||
| 加入時・企業型からの移換時 | 他の運営機関からの変更時 | |||
| 0円 | 0円 | 0円 | 39本 | |
| 【おすすめポイント】「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」対象! 投資信託は39本と最多水準! 運営管理手数料は残高を問わず誰でもずっと無料。投資信託は2020年10月に11本から39本へと一気に拡充され、業界最多水準となった。具体的には、低コストで人気のインデックスファンドシリーズ「eMAXIS Slim」がずらりと並ぶほか、ターゲットイヤー型と呼ばれる「三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド」、「セレブライフ・ストーリー」などの商品が新たに加わった。低コスト投信を厳選した上で、投資対象が広がった形だ。楽天・全世界株式インデックスファンド[楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)]や楽天・全米株式インデックスファンド[楽天・バンガード・ファンド(全米株式)]も取り扱う。投資信託の保有でポイントが貯まる「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」に、イデコで所有している投資信託もカウントされるのも嬉しい。ポイント還元を受けながらお得に投資を継続できる(毎月のエントリーが必要)。2025年11月からオンラインで申込手続きが完結する「e-iDeCo」に対応。氏名・住所や掛金額変更などのオンライン申請が可能になった。 |
||||
| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・One DC 国内株式インデックスファンド(信託報酬:0.154%) ・eMAXIS Slim先進国株式インデックス(信託報酬:0.09889%) |
||||
| 【関連記事】 ◆【松井証券のiDeCo、手数料・メリットは?】運営管理手数料と加入時手数料が誰でも無料でお得!信託報酬が最安クラスの投信が39本もラインナップ! |
||||
| ◆SBI証券 ⇒iDeCo詳細ページへ | ||||
| 運営管理手数料※(月額) | 手数料※ | 投資信託 | ||
| 加入時・企業型からの移換時 | 他の運営機関からの変更時 | |||
| 0円 | 0円 | 0円 | 37本 (セレクトプラン) |
|
| 【おすすめポイント】投資信託の品揃えが豊富! 運営管理手数料は誰でも無料! 運営管理手数料は誰でも0円。「セレクトプラン」は、ほとんどの投資対象で信託報酬が“最安”のインデックス型投信が揃えられており、バリエーションも豊富と、強力なラインナップになっている。人気のアクティブ型投信「ひふみ年金」や「ジェイリバイブ」も用意。2021年1月から申込み手続きを電子化。WEB申込フォームへの入力、必要書類のアップロードが可能になり、iDeCo口座開設の手続きが簡単になった。また、2025年10月からオンラインで申込手続きが完結する「e-iDeCo」に対応。氏名・住所や掛金額変更などのオンライン申請が可能になった。シミュレーションツール「DC Doctor」を提供しており、ポートフォリオ提案から将来予測の比較など、長期にわたるiDeCoの資産形成をサポートしてくれる。 |
||||
| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(信託報酬:0.143%以内) ・SBI・全世界株式インデックス・ファンド[雪だるま(全世界株式)](信託報酬:0.1022%) |
||||
| 【関連記事】 ◆【SBI証券のiDeCo、手数料・メリットは?】 投信のラインナップが豊富!運営管理手数料は誰でもずっと無料! ◆「iDeCo」を始めるなら、おすすめ金融機関はココ! 運営管理手数料が無料になり、投資信託のラインナップが 充実している「SBI証券」と「楽天証券」を比較! |
||||
| ◆マネックス証券 ⇒iDeCo詳細ページへ | ||||
| 運営管理手数料※(月額) | 手数料※ | 投資信託 | ||
| 加入時・企業型からの移換時 | 他の運営機関からの変更時 | |||
| 0円 | 0円 | 0円 | 27本 | |
| 【おすすめポイント】運営管理手数料が誰でも無料! インデックス型投信の信託報酬は最安水準! 運営管理手数料が誰でもずっと「無料」で、コスト面から最もお得な金融機関の1つ。投資信託の本数は27本と標準的だが、内容は充実。「eMAXIS Slim」シリーズなど信託報酬が最安水準のインデックス型投資信託が揃えられている。加えて、「ひふみ年金」「jrevive」など好成績のアクティブ型投信も豊富だ。「つみたてNISA」と「iDeCo」、どちらの制度が各個人の投資目的に適しているかアドバイスが受けられる「つみたてNISA・iDeCoシミュレーション」が便利。「e-iDeCo」に対応しており、氏名・住所や引落口座などの変更手続きがオンラインで申請可能だ。 |
||||
| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・One DC 国内株式インデックスファンド(信託報酬:0.154%) ・eMAXIS Slim先進国株式インデックス(信託報酬:0.09889%) |
||||
| 【関連記事】 ◆【マネックス証券のiDeCo、手数料・メリットは?】 運営管理手数料と加入時手数料が誰でも無料でお得!超低コスト&好成績の投資信託27本をラインナップ! |
||||
| ◆楽天証券 ⇒iDeCo詳細ページへ | ||||
| 運営管理手数料※(月額) | 手数料※ | 投資信託 | ||
| 加入時・企業型からの移換時 | 他の運営機関からの変更時 | |||
| 0円 | 0円 | 0円 | 36本 | |
| 【おすすめポイント】運営管理手数料が誰でも無料! 信託報酬の低い投信を多数ラインナップ! 運営管理手数料は残高を問わず誰でも0円で、コスト面から最もお得な金融機関の1つ。投資信託のラインナップは36本と豊富。信託報酬の低いインデックス型が揃っている。特に、2024年1月には超低コストで全世界や米国に投資できる「楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド」と「楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド」が、2025年5月には「楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド」が加わって魅力を増した。「MHAM日本成長株ファンド」など好成績のアクティブ型も用意。電話で問い合わせができる「個人型確定拠出年金(iDeCo)ダイヤル」は土日も受付を行っている。「e-iDeCo」に対応しており、氏名・住所や引落口座などの変更手続きがオンラインで申請可能だ。 |
||||
| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・楽天・プラス・S&Pインデックス・ファンド(信託報酬:0.077%) ・楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(信託報酬:0.0561%) ・楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド(信託報酬:0.198%) |
||||
| 【関連記事】 ◆【楽天証券のiDeCo、手数料・メリットは?】 運営管理手数料が誰でもずっと「無料」でお得!運用コストを抑えた投資信託を多数ラインナップ ◆「iDeCo」を始めるなら、おすすめ金融機関はココ! 運営管理手数料が無料になり、投資信託のラインナップが 充実している「SBI証券」と「楽天証券」を比較! |
||||
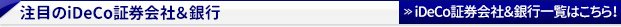
【松井証券のiDeCo】
誰でも無条件で口座管理料や各種手数料が無料!
投信の保有でポイントも貯まる⇒関連記事はこちら





![iDeCo(個人型確定拠出年金)おすすめ比較&徹底解説[2026年]](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/4/0/-/img_40016abb6bd0e6096770835bf5abf9ef21127.jpg)