ホンダ
関連ニュース
売上高が大きい会社ランキング2022【トップ5】ホンダ、三菱商事、NTTの序列は?
ダイヤモンド編集部,鈴木崇久
一つの財務指標に焦点を当て、知っているようで意外と知らない企業間の序列をお伝えする本ランキング企画。今回は、損益計算書(PL)の最も基本的な指標である「売上高」を取り上げ、全上場企業(金融業を除く)を対象にランキングを作成しました。

売上高が大きい会社ランキング2022【1000社完全版】
ダイヤモンド編集部,鈴木崇久
一つの財務指標に焦点を当て、知っているようで意外と知らない企業間の序列をお伝えする本ランキング企画。今回は、損益計算書(PL)の最も基本的な指標である「売上高」を取り上げ、全上場企業(金融業を除く)を対象にランキングを作成しました。

#2
トヨタ、ホンダ、日産で「EV部門分社」に動く企業は?電動化投資余力で切迫度を大胆予想!
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
仏ルノーが電気自動車(EV)部門の分社を表明した。株式市場でガソリン車の評価が凋落していることから、EV新会社の上場によって資金調達を有利に進めようという奇策を講じようとしているのだ。世界でガソリン車部門とEV部門を分離する動きが相次ぐ中、日系3社はどう動くのか。日系3社でEV分社に踏み切る切迫度が高い企業をキャッシュフロー計算書の分析により炙り出す。

トヨタが「流儀を曲げて」つかんだ過去最高決算、自動車“三重苦”は続く
ダイヤモンド・アナリティクスチーム,濵口翔太郎
コロナ禍が落ち着き始めたことで、市況も少しずつ回復しつつある。しかしビジネス界では、コロナショックから立ち直った企業と不調から抜け出せない企業とで明暗が分かれている。そこで、上場企業が発表した直近四半期の決算における売上高を前年同期と比べ、各業界の主要企業が置かれた状況を分析した。今回はトヨタ自動車、ホンダなどの「自動車」業界5社について解説する。

トヨタ“絶頂決算”でも今期は「2割減益」の理由、財務3表で解き明かすアキレス腱の正体
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
『週刊ダイヤモンド』6月25日号の第一特集は「決算書100本ノック!2022年夏版」です。シリーズ累計134万部を突破する人気企画がこの夏も帰ってきました!中でも人気なのが、ダイヤモンド編集部の業界担当記者が決算書を通してニュースを解説する事例集です。財務もニュースも分かる「決算書バイブル」をお届けします。

日産・三菱自の「ルノー支配論」が再燃、全社EVシフトで決断の時が迫る
佃 義夫
日産、三菱自が共同開発する軽自動車EVが5月発表された。だが、軽EVと同じタイミングで浮上したルノーによるEV事業の新会社化の構想に、業界がざわついている。ルノーはこの新会社に、日産と三菱の参画を要請している。

#10
トヨタ、ホンダ、日産が劇的円安・保護主義化でも「国内生産回帰」できない3つの理由
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
超円高に悲鳴を上げていた国内自動車メーカーが、今度は「円安の泥沼」にはまりつつある。円安は自動車メーカーにもたらす意外なデメリットとは。円安と保護主義化にもかかわらず、自動車メーカーの“国内生産回帰”が難しい理由についても詳しく解説する。

ウクライナ危機と脱炭素加速で需給ひっ迫、鉱物資源「枯渇リスク」に備えよ
新村直弘
ウクライナ危機をきっかけに、あらゆる商品価格が上昇している。各国はエネルギーの脱ロシア化を図り、脱炭素を加速させる狙いだ。これにより、脱炭素に欠かせない鉱物資源の価格が上昇するだけでなく、枯渇するリスクまで出てきそうだ。

ホンダ「3頭体制の次」の有力候補4人とは?文民統治”強化”で技術系人材は大ピンチ!
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
ホンダの三部敏宏社長をトップとする「3頭体制」がスタートした。新体制がスタートしたばかりで少々気が早いが、三部社長時代に頭角を表しそうな有力候補を大胆に予想してみた。「3頭体制の次」を睨んだ幹部候補4人の実名を明らかにする。

ホンダ電動化戦略でも「北米偏重」、盟友GMを差し置いて電池協業する企業とは?
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
ホンダの三部敏宏社長が就任してから1年。4月12日、満を辞して電動化戦略を発表した。その中身は電動化・ソフトウエア領域などに研究開発費8兆円を投じる野心的なものだ。ホンダの電動化戦略の全貌を解剖する。

ホンダ早期退職者2500人の衝撃、人材流出が多い「リストラ標的20拠点」が内部資料で判明
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
ホンダの早期退職プラン「ライフシフト・プラン(LSP)」の応募者が当初予定の2.5倍に相当する2500人に達していたことが分かった。ダイヤモンド編集部では、ホンダの人事関連資料を入手。LSP対象者を含む退職者約3000人の出身母体を洗い出し、特に人材流出の多い「リストラ標的20 拠点」を炙り出した。

ホンダの「脱自前主義」が鮮明化、GM・ソニーと提携ラッシュで生き残りへ
佃 義夫
ホンダと米GMが新たな提携を発表した。量販価格帯の新たなEVシリーズを共同開発し、2027年以降に全世界で発売していく。従来のホンダとGMの提携がさらに拡大することになる。
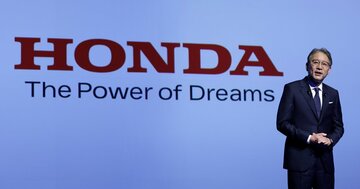
#6
台湾がEVで見出す「4つのビジネスチャンス」、半導体の次は自動車産業攻略へ
財訊
世界的に進むEV(電気自動車)化。この好機を商魂たくましい台湾企業はもちろん見逃さない。エンジン車の時代には自動車業界で優位に立つことのできなかった台湾企業が、EVの波で見いだす「四つのビジネスチャンス」とは。

トヨタは増益、スバルは減益予想…軒並み四半期減収の自動車業界で分かれた「明暗」
ダイヤモンド・アナリティクスチーム,笠原里穂
コロナ禍が3年目に突入し、多くの業界や企業のビジネスをいまだに揺さぶり続けている。その対応力の差によって企業の業績は、勝ち組と負け組の格差が拡大している。そこで、上場企業が発表した直近四半期の決算における売上高を前年同期と比べ、各業界の主要企業が置かれた状況を分析した。今回はトヨタ自動車、ホンダなどの「自動車」業界5社について解説する。

ウクライナ危機が「第3次オイルショック」となり得る理由、原油高騰はいつまで続くか
新村直弘
ロシアがウクライナに侵攻し、原油価格は急騰した。ウクライナ危機をきっかけに、エネルギー市場は、大きく構造変化が起きる可能性がある。ウクライナ危機は「第3次オイルショック」ともいえそうだ。

シベリア鉄道での日欧間物流を強化した矢先に軍事侵攻、日本通運らの対応は?
ダイヤモンド編集部
ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、シベリア鉄道ルートの物流がピンチだ。日欧間における「第3の輸送」として期待が高まっていたさなかの緊急事態に、日本通運などの物流大手、荷主らは対応に追われている。

ホンダ「55歳で退職金8000万円」大名リストラの中身、残っても地獄の管理職剥奪![話題のリストラ]
ダイヤモンド編集部
産業構造が激変する中、ホンダやフジテレビなど超優良とされてきた大企業でもリストラの嵐が吹き荒れています。そこで、これからの働き方のヒントにしてもらうため、「ダイヤモンド・プレミアム」で会員読者の反響が大きかったリストラ記事とその関連記事をお届けします。今回は過去2年間で有料会員獲得が多かったリストラ関連記事ランキング4位の『ホンダ「55歳で退職金8000万円」大名リストラの中身、残っても地獄の管理職剥奪!』と関連のおすすめ記事を取り上げます。
![ホンダ「55歳で退職金8000万円」大名リストラの中身、残っても地獄の管理職剥奪![話題のリストラ]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/2/d/360wm/img_2da32d0902000fdcd0aa982ce1f2ed17278666.jpg)
ホンダとソニーがEVで手を組んだ理由、車と電機のベンチャーが巨大タッグで攻勢
佃 義夫
ホンダとソニーグループがEV領域での提携を発表した。ベンチャー企業の走りとして高いブランド力を誇ってきた両社の提携に、大きな注目が寄せられている。

ホンダが「ソニーの下請け化」を意に介さず提携した裏事情、4月刷新EV部隊に懸念
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
ホンダとソニーグループが電気自動車(EV)分野で電撃提携した。異業種タッグの誕生にモビリティ業界は沸き立っているが、両社の損得を見積もるとソニーに軍配を上げる見方が大勢だ。それでもホンダが提携に突き進んだのはなぜなのか。ホンダのEV新組織が抱える悩みに迫る。

ホンダの「早期退職者数」「次のシニア放出策」判明!ソニー提携の裏で大リストラ断行中
ダイヤモンド編集部,浅島亮子
ソニーグループとの電撃提携が明らかになったホンダ。華やかな提携の裏では、シニア社員を放出する本気のリストラ策が断行されている。ダイヤモンド編集部の調べにより、昨春にアナウンスされていた早期退職制度「ライフシフト・プログラム」の全容と次なるシニア放出策が明らかになった。
