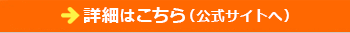アマゾンが高級スーパーマーケットの
「ホールフーズ」を買収
先週金曜日、アマゾン(ティッカーシンボル:AMZN)がホールフーズマーケット(ティッカーシンボル:WFM)を一株当たり42ドルで買収すると発表しました。買収総額は137億ドルです。
 アマゾン(AMZN)チャート/日足・6カ月(出典:SBI証券公式サイト)
アマゾン(AMZN)チャート/日足・6カ月(出典:SBI証券公式サイト)※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示
ホールフーズは、新鮮で安心できる生鮮食料品を売っている高級スーパーマーケットです。同社は、折からの自然食品ブームならびに裕福層のグルメ志向化のトレンドを背景に、近年急速に成長してきました。
 ホールフーズ(WFM)チャート/日足・6カ月(出典:SBI証券公式サイト)
ホールフーズ(WFM)チャート/日足・6カ月(出典:SBI証券公式サイト)※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示
日本にはホールフーズの店舗が無いので、イメージしにくいかもしれませんが、ちょうどスターバックス(ティッカーシンボル:SBUX)と同じような、消費者に熱烈に支持されているブランドです。
なぜアマゾンはホールフーズ買収に関して
きちんと説明しないのか
さて、この買収が発表された先週金曜日、ちょっとした当惑がウォール街に走りました。その理由は、アマゾンがこの買収に関するカンファレンス・コール(電話会議)を実施しなかったからです。
普通、アメリカでは、今回の買収くらいの大きなM&Aがあると、その買収の意図や合併後の業績に関する見通しなどを説明するカンファレンス・コールを急遽開催するのが常です。
しかしアマゾンは、そのような説明会を開催しなかったばかりか、買収に関するプレス・リリースも極めて簡潔で、ホールフーズ買収に絡めてどのような戦略を今後展開してゆくのかに関して一切説明がありませんでした。
アマゾンがその意図を一切説明しなかった理由は、これからアマゾンと実店舗を持つ小売店との間でいよいよ激しいバトルが始まるからだ、と解釈したウォール街関係者も多かったです。その戦いをするにあたって、アマゾンは自分の「手の内」を世間に晒すことを避けたというわけです。
ベンダーと良い関係を築いているホールフーズは
アマゾンにとって安い買い物
アマゾンがカンファレンス・コールを省略したもうひとつの理由は、普通なら、買収に際して資金調達をする必要からひとこと投資家に断りを入れる必要があるのですが、アマゾンの場合、買収資金の用立てにはぜんぜん困らない、ということによります。「投資家は、黙って俺についてこい!」というわけです。
アマゾン株は、株価収益率(PER)186倍で取引されており、仮に将来、アマゾンがホールフーズ買収のために転換社債を発行するような場合でも、極めて有利な条件で実行することが出来ます。言い換えれば、現在のアマゾンにとって、資金調達コストは問題にならないくらい低いのです。
むしろホールフーズを買収することにより、アマゾンが今後それを踏み台としていろいろ新しい展開が出来るようになれば、こんなに安い買い物はありません。
実際、ホールフーズはEBITDAマージンが8.6%あり、これは実店舗の小売業としてはかなり高い方に属します。つまり「しっかり儲かっている会社を買収する」わけです。
また、ホールフーズは、ローカルな農家などのベンダーとの関係を築いてきました。言い換えれば、安さだけで勝負するのではなく、新鮮さや安心感で勝負しているのです。このリレーションシップは、簡単に構築できるものではありません。
アマゾンが資金力にものを言わせて、これに匹敵するようなサプライチェインを構築しようと思っても、農家などのベンダーの側がそれに賛同するかどうかはわからないのです。その意味で、アマゾンはホールフーズ買収により、貴重なものを手に入れたと評価できると思います。
スーパーマーケットのビジネスは
普通のやり方では儲からない
ホールフーズの食料品売上高は157億ドルです。これは全米の食料品売上高の2%に過ぎません。つまり、未だ成長の余地はあるということです。しかも、ホールフーズは裕福層の客筋をつかまえているので、スーパーマーケットのビジネスでも、最も美味しいセグメントだけを相手にしているわけです。
実は、アメリカのスーパーマーケットのビジネスは競争がし烈であり、身売りや倒産が多いことで知られています。折から食料品はデフレ圧力に晒されており、事業規模が大きい会社だけが生き残る構図となっています。
その事業規模では、ウォルマート(ティッカーシンボル:WMT)が食料品売上高2,721億ドルと、他を圧倒しています。すると、いかにアマゾンでも、無益な消耗戦をウォルマートと戦うのは得策ではないのです。
アマゾンの今後の戦略は
ネット通販と実店舗の連携か
アマゾンは「実店舗を、すべてネット通販に置き換える」という未来図を予想していないと思います。もしそう考えているのなら、最近同社がやっているような実店舗の本社の出店など、やる意味がないからです。
つまり、実店舗は今後も絶滅することはなく、むしろ実店舗とネット通販の新しい連携のカタチを模索することにアマゾンは関心を持っているように見えます。
具体的には、ホールフーズの464の店舗は、主に裕福な都市部の便利なロケーションに展開しています。会社の帰りや昼休みのランチの時間に、ちょっと立ち寄ることが出来るわけです。
実際、ホールフーズは、デリカテッセンやベーカリーなどの売上が19%を占めており、単なるスーパーマーケットと言うよりは、ランチの時に立ち寄るトレンディーなレストランの性格を帯びています。とりわけ女性やミレニアル層(2000年代に成人した比較的若い層)に、このような利用のされ方をしています。
すると、アマゾンの顧客が、ネットで注文した商品を受け取る場所として、これほど最適な場所はありません。
アマゾンは「プライム」というメンバーシップを展開しており、6千万人を超えるメンバーが居ます。それらのメンバーに対して特別なサービスを提供するにあたって、ホールフーズの実店舗の拠点を持つことは、極めて有利です。
利便性とは、全ての商品を自宅で受け取ることを必ずしも意味しません。顧客の仕事や生活のルーチンの中で、いちばん便利な時間や場所で接点を持つことが大事なのです。
その意味で、アマゾンのホールフーズ買収は、「ドローンによるデリバリーなどより、遥かに脅威だ」とライバル企業は感じる事でしょう。
| 【今週のピックアップ記事!】 | |
| ■ | 日経平均株価の2017年7月中旬までの値動きをネット証券4社のエースアナリストがズバリ予想!アベノミクス後の高値、2万952円の突破なるか!? |
| ■ | 年収500万円以下のサラリーマンが、投資歴13年で資産1億5000万円、年間配当収入300万円を実現!成功のカギは「増配銘柄への投資」を発見したこと! |
【※米国株を買うならこちらの記事もチェック!】
⇒米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
【2026年2月1日時点】
「米国株」取扱数が多いおすすめ証券会社 |
| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約4900銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
|
【SBI証券のおすすめポイント】 |
|
| 【関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社! |
|
| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
| 【楽天証券おすすめポイント】 米国、中国(香港)、アセアン各国(シンガポール、タイ、マレーシアなど)と幅広い銘柄がそろっており、米国株の信用取引も利用可能! 指定の米国ETF15銘柄については買付手数料が無料で取引ができるのもお得。米ドル⇔円の為替取引が0円と激安! さらにNISA口座なら、米国株の売買手数料が完全無料(0円)。米国株の注文受付時間が土日、米国休場を含む日本時間の朝8時~翌朝6時と長いので、注文が出しやすいのもメリット。米国株式と米国株価指数のリアルタイム株価、米国株オーダーブック(板情報)、さらに米国決算速報を無料で提供。ロイター配信の米国株個別銘柄ニュースが、すぐに日本語に自動翻訳されて配信されるのもメリット。米国株の積立投資も可能。米国株の貸し出しで金利がもらえる「貸株サービス」も行っている。 |
|
| 【関連記事】 ◆【楽天証券おすすめのポイントは?】トレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!投資信託や米国や中国株などの海外株式も充実! ◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい! |
|
| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
| 【マネックス証券のおすすめポイント】 外国株式の取り扱い銘柄数はトップクラス! また、米国株の買付時の為替手数料が0円(売却時は1ドルあたり25銭)となるキャンペーンが長期継続しており、実質的な取引コストを抑えることができる。さらに、外国株取引口座に初回入金した日から20日間は、米国株取引手数料(税込)が最大3万円がキャッシュバックされる。米国ETFの中で「米国ETF買い放題プログラム」の対象22銘柄は、実質手数料無料(キャッシュバック)で買付が可能。米国株の積立サービス「米国株定期買付サービス(毎月買付)」は25ドルから。コツコツ投資したい人に便利なサービス。米国株は、時間外取引に加えて店頭取引サービスもあり日本時間の日中でも売買できる。しかもNISA口座なら、日本株の売買手数料が無料なのに加え、外国株(海外ETF含む)の購入手数料も全額キャッシュバックされて実質無料! 企業分析機能も充実しており、一定の条件をクリアすれば、銘柄分析ツール「銘柄スカウター米国株」「銘柄スカウター中国株」が無料で利用できる。 |
|
| 【関連記事】 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! |
|
| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約5000銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
| 【松井証券のおすすめポイント】 米国株の売買手数料は他の大手ネット証券と同水準なうえ、為替手数料は完全無料(0円)とお得!さらにNISA口座では、米国株の取扱手数料が無料に! 米国株でも信用取引が可能で手数料が業界最安水準。2025年7月から米国株のプレマーケットに対応し、日本時間18時(夏時間は17時)から取引が可能になったのもメリット。さらに投資情報ツール「マーケットラボ米国株」や専用の取引ツール、リアルタイム株価が無料、夜間での取引に便利な返済予約注文(IFD注文)、米国株専用ダイヤル「米国株サポート」や「株の取引相談窓口(米国株)」などが特徴となっている。また、米国株専用の「松井証券 米国株アプリ」は、リアルタイム株価の表示に加え、米国株の情報収集から資産管理、取引までスマホで対応可能だ。 |
|
| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |
|
| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約6300銘柄以上 | <現物・信用取引>約定代金の0.132%(上限22米ドル) |
| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国やカナダ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなどグローバルにサービスを展開するネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は業界トップクラス。売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(ただし売買手数料の上限は22米ドルと他社と同水準)。さらに、為替手数料が無料なので、米国株の売買コストのお得さでは頭ひとつ抜け出している。米国株に関するデータや情報も充実。最大上下60本の板情報や過去20年分の財務データ、大口投資家の売買動向など、銘柄分析に役立つさまざまな情報が無料で利用できる。24時間取引に対応しているので、日本時間の昼間にも売買が可能。1ドルから米国株を買うこともできる。取引アプリには対話型AIの「moomoo AI」を搭載。米国株の基礎知識から米国市場の動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、米国株初心者には力強い味方となるだろう。 |
|
| 【関連記事】 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |
|
| ※ 本記事の情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。 |