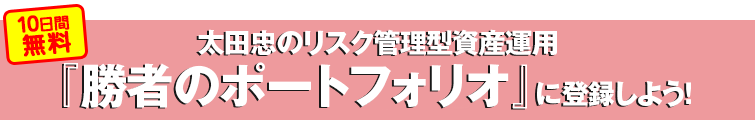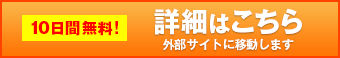相互関税発表で市場暴落。NYダウは3269ドル安、日経平均は3340円安
新年度入りした4月第1週。世界の株式市場は急落した。「米国解放の日」とトランプ大統領が称した4月2日水曜。米国の相手貿易国との相互関税を欧州連合(EU)20%、日本24%、中国34%などマーケットが想定していたよりも厳しい内容となった。世界経済悪化、貿易戦争勃発、インフレ懸念再燃といったネガティブな事象がマーケットでクローズアップされ、パニック売りを伴った大きな混乱となった。
トランプ大統領は相互関税を発表する演説において「今回の政策は非常にうまくいく」「米国の株式市場は上昇し、米国は繫栄する」と述べたが、週間での米国市場のパフォーマンスはNYダウが3269ドル下落(7.9%安)、ナスダックが1735ポイント下落(10.0%安)となり、ともに2020年3月以来の大きな下落を記録した。アップルも、アマゾンも、エヌビディアも、テスラも、JPモルガンも…主要企業が暴落の惨状を呈している。トランプ氏は現状をどのように見ているのだろうか? 関税政策によって最も被害を受けるのは他ならぬ米国である。
貿易赤字是正を目的に導入された相互関税率の計算方法はあまりにも稚拙
「貿易赤字を是正するため」とトランプ氏は言う。貿易赤字とは単に相手国との輸出入の差額がマイナスになっている状況である。取引先の国によって輸入する額は異なるし輸出する額も異なる。なぜなら相手国から必要なモノは異なり、相手国が必要とするモノは異なるからだ。米国人口は3.36億人。経済規模が大きいだけに輸入額が大きくなるのは当然であり、主要国との貿易収支は赤字になるのが普通である。私自身が理解に苦しむのは貿易赤字の是正のために「関税率」を使って解消しようとしている点だ。しかも、トランプ政権が発表した相互関税率は驚くべきことに、本来あるべきはずの計算方法ではないという点だ。
トランプ政権は「相手国が米国に課す付加価値税などの非関税障壁まで考慮し、米国の関税を同等の水準にまで引き上げる」ことを相互関税と言っているのだが、それぞれの国の関税措置を詳しく調べ、製品ごとに異なる複雑な関税率を一つひとつ一致させる必要がある。ところが、実際の計算方法は「相手国との貿易赤字額を米国への輸出額で割り、その数字を2で割る」という単純なものだ。例えば、中国を例に挙げると、2024年の対中貿易赤字額は2954億ドル(43兆円)、中国からの輸入額は4399億ドル(64兆円)。すなわち、中国の対米貿易黒字は輸出額の67%となる。これを2で割って「米国に課された関税は34%」とはじき出しているのだ。その34%を中国に相互関税として課すというものだ。
トランプ老人の大暴走によるシステマティックリスクに市場は極度の混乱
相互関税の定義はインチキだし、実行すればグローバルで取引している米国企業も大きな打撃を受ける。「今回の政策は非常にうまくいく」「米国の株式市場は上昇し、米国は繫栄する」と言うトランプ老人の大暴走ぶり。正気だろうか? いよいよ頭がおかしくなってきているのでは? と私は思う。もちろん、今回の相互関税はトランプ流に言えば「ビジネス」である。今後、政府間の交渉で関税引き下げがなされる可能性もありうる。状況が急展開することを考慮しておく必要がある。
話をマーケットに戻そう。最初の洗礼を受けた先週木曜日の東京市場は「ウワサで売って、さらにニュースで売る」展開となった。「日本に対しては24%の追加関税を課す」との報道で寄り付きからパニック売り。9時9分に1623円安まで下落して売り一巡後は徐々に戻す展開となり終値は989円安。ところが米国市場の急落を受けて金曜日はさらに下げが加速。13時56分には1476円安まで下落して徐々に戻して終値は955円安。米国発のシステマティックリスクに覆われており、マーケットに及ぼす度合いがマックスになっている。その仕業は先物市場で大暴れしているヘッジファンドだ。それによって現物市場の短期筋で信用取引の買いポジションを持つ個人投資家たちが投げ飛ばされ、現物株の投資家たちも振るい落とされているという構図である。
銀行株など多くのセクターがバーゲンセール状態。コロナ禍以来の商機
先週の下落で最も売られたセクターが銀行株である。木曜日が7%安、金曜日8%安といきなり年初来安値を更新した。「日銀の追加利上げが後ずれする」との思惑だがきわめて投機的な動きである。金曜日は銀行株指数にサーキットブレーカーが発動された。投機家は目先で稼ぐことしか考えていない。今後利上げされることは確実。現実とのギャップがあまりにもあり過ぎて投資チャンス満載となっている。
銀行株に限らず、あらゆるセクターがバーゲンセールで「ピンチはチャンス」状態だ。コロナショック当時を思い出させる展開である。「景気大減速で米連邦準備理事会(FRB)は大幅利下げ」というシナリオになれば、ようやく待ちに待った金融相場らしくなるのではないか、と私は考えている。
嵐去れば買戻しは起こるが、令和のブラックマンデーの時より戻りは鈍い
今のマーケットはシステマティックリスクで荒れているだけであり、嵐が過ぎ去れば大きな買戻しが起こる。ただし、今回は関税という経済政策が要因。昨年8月に起きた「令和のブラックマンデー」のようなマーケットイベントではないため、株価の戻りには時間がかかる可能性がある。だが、コロナショックと同様、相互関税ショックは意図的に作られた経済政策という点にも着目していただきたい。
「チャンスはピンチの顔をしてやって来る」というのが私の口癖だが、今回の急落を前向きに捉えていただきたい。マーケットの不安心理を表す恐怖指数をみると4月4日金曜時点で米国のVIX指数は45.31と2020年5月以来の高水準、日本のVI指数も35.58と高水準にある。これが何を意味しているのか考えていただきたい。
明日開催のセミナーは必聴。ピンチをチャンスに変える投資戦略を伝授!
さて、太田忠投資評価研究所とダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチ(DFR)がコラボレーションして投資助言を行っている「勝者のポートフォリオ」。毎週のメルマガ配信による運用の指南に加えて、2大特典として毎月のWebセミナー開催とスペシャル講義を提供している。
毎月恒例の株式投資Webセミナーを明日の4月9日水曜20時より開催する。テーマは『トランプ関税に惑わされるな、ピンチはチャンス』を予定している。10日間の無料お試し期間を使えば誰でも参加が可能。毎回の参加者が300名を超えるビッグイベントであるが、オープンな開催はしていないのでご注意願いたい。
動画によるスペシャル講義ではいよいよアンシステマティックリスク、すなわち個別銘柄リスクに関する詳細な講義がスタート。第2弾は「個別銘柄の株価の動きをスコア化する」「グロース株vsバリュー株の評価ポイント」。すでに講義動画はアップ済みである。
「個別銘柄の株価の動きをスコア化する」においては、株価がSリスク、USリスク、Mサイクルの3つの要因、さらにそれぞれが包含する多くの要素によって株価が動いていることを理解するのが目的である。スコア化することによって、常に泰然自若の投資家になっていただきたいと考えている。「グロース株vsバリュー株の評価ポイント」では、それぞれのカテゴリーにおいて投資の評価軸が異なることを再確認していただくのが目的。混同している方々が多いため詳しく解説している。
●太田 忠 DFR投資助言者。ジャーディン・フレミング証券(現JPモルガン証券)などでおもに中小型株のアナリストとして活躍。国内外で6年間にわたり、ランキングトップを維持した。現在は、中小型株だけではなく、市場全体から割安株を見つけ出す、バリュー株ハンターとしてもDFRへのレポート提供によるメルマガ配信などで活躍。
国内外で6年連続アナリストランキング1位を獲得した、
トップアナリスト&ファンドマネジャーが
個人投資家だからこそ勝てる
「勝者のポートフォリオ」を提示する、
資産運用メルマガ&サロンが登場!
老後を不安なく過ごすための資産を自助努力で作らざるを得ない時代には資産運用の知識は不可欠。「勝者のポートフォリオ」は、投資の考え方とポートフォリオの提案を行なうメルマガ&会員サービス。週1回程度のメルマガ配信+ポートフォリオ提案とQ&Aも。登録後10日間は無料!