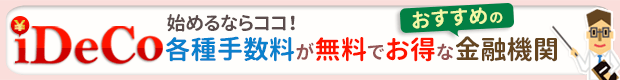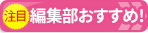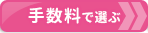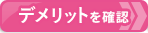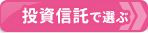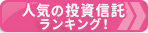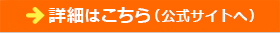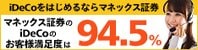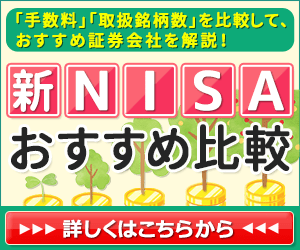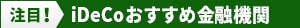「iDeCo」での投資は「バランス型ファンド」を
しっかり選んで「ほったらかし」にするのがおすすめ!
「iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)」で投資をスタートさせるとき、特に投資初心者ほど「今、人気のファンド(投資信託)はどれか」と考えてしまいます。しかし「iDeCo」で人気商品のランキングを調べることはあまりおすすめできません。というのも、「iDeCo」はファンドを次々乗り換えることには適していないからです。
そもそも、金融機関(運営管理機関)が「iDeCo」で取り扱う商品は、2018年5月以降は最大35本に限られています(現在は移行期間で、35本を超過しているところは今後5年以内に35本に減らすことになります)。長期の積み立てが前提の制度ということもあり、商品の入れ替えもあまり行われないでしょうし、自分好みのファンドが自分の選んだ金融機関に追加されるとは限りません。
もし買いたいファンドが自分の金融機関にない場合、金融機関そのものを変更する手もありますが、手続きに労力がかかる割に、ファンドを乗り換えたからといって効率的な売買になるとは限らないので、おすすめはできません。
しかも、頻繁にマーケットの状況をチェックし、売買の指図を行おうとすれば、仕事やプライベートのどこかを削ることになります。やりすぎれば日常生活の支障を来します。仕事でミスをやらかすかもしれません。
それに、「iDeCo」で投資に大きな労力を割いたところで、投資信託の売買は「翌日もしくは翌々日の基準価額での売却」「さらに数日後の購入」となるので、タイミングを狙った売買はほとんど不可能なのです。
掛金の上限があることから「iDeCo」での投資は金額ベースでもあまり大きくなりませんし、ファンドの見直しや入れ替えなど、投資に伴う負担は極力軽くする方向で考えるべきでしょう。
ということで、「iDeCo」での投資は、経済成長の平均点を確実に獲得する戦略(インデックス投資)で、可能な限りメンテナンスが不要な(つまりほったらかしにできる)商品を選ぶのがいいと思います。そして前回も解説したように、初心者でも1本でそれを実現できるのが「バランス型ファンド」です。
「iDeCo」では「バランス型ファンドをしっかり選び、基本的には長期保有」という「ほったらかし投資」をすることをおすすめします。
【※関連記事はこちら!】
⇒iDeCoを始めるために必要な4つのステップを解説! iDeCo口座を開設する金融機関の選び方、積立商品&掛金額の決め方など、具体的な手続きと注意点を紹介
バランス型ファンドなら資産配分もリバランスも
“お任せ”できて投資の労力が格段に減る!
それでは、「iDeCo」投資の選択肢として、バランス型ファンドを選ぶメリットは何でしょうか。
メリット1:「分散投資」が簡単に行える
まず第1に「バランス型ファンドは分散投資が容易である」という点です。株式、債券、国内、海外などの複数の資産に投資対象を分散するのは投資の基本です。理想的には、自分に合った資産配分(アセットアロケーション)になるように、それぞれの資産(アセットクラス)へ投資する投信を%単位で組み合わせていくのが最も効率的な方法になりますが、これは個人にとってはほとんど不可能でしょう。
例えば、国内株と外国株を何%ずつ組み合わせるのが効率的かは、プロの年金運用でも答えが出ない悩みです。特に個人においては、効率的な資産配分を行ううえで基礎となる「期待リターン」や「リスク」、「標準偏差」などの数値を得るのも簡単ではありません。金融機関などのウェブサイトでシミュレーションができるサービスもありますが、その前提が妥当なものか判断することすら難しいのです。
また、基礎数値を手に入れたとしても、個人にとって理想的なポートフォリオ(金融商品の組み合わせ)はひとりひとりのリスク許容度によって異なりますし、年齢や環境変化に応じてリスク許容度も変化します。それを検証するのも、個人にとっては困難です。
そこで解決策として、資金のうちどのくらいを安全資産にしてどのくらいを投資に回すか、すなわち「定期預金:投資金額」の割合だけは自分で決めて、バランス型ファンドを1本だけ買い、国内外にどのような分散投資を行うかのポートフォリオ作りは、バランス型ファンドに任せてしまうのが1つの有力な(そして現実的な)方法です。
そのほうが、思いつきでお手製ポートフォリオを作るよりはるかに労力は少なく、かつ効率的になる可能性が高いと考えられます。
【※関連記事はこちら!】
⇒iDeCoで失敗しない「資産配分」と「運用方法」を3つのステップで紹介! 定期預金と投資信託への適切な資産配分とおすすめの投資信託の種類とは?
メリット2:「リバランス」が簡単にできる
次のメリットは「バランス型ファンドはリバランスが不要である」という点です。
投資では、資産配分の比率を維持するのが、中長期的には合理的なやり方です。市場が上下に動いていくとき、「当初想定していた保有比率」に従って、値上がりしている資産(例えば株式)が高値になったときは部分的に売って利益確定を行います。同じ株式が値下がりしている時期にはむしろこれを買い増して、「保有比率」を維持することで結果として安値仕込みにつながります。これを繰り返し、リスクを一定に保ちつつ、運用収益の確保を目指します。
この投資行動は「リバランス」といわれて、プロの年金運用では一般的に行われるものですが、個人にとっては今まで実行が困難でした。しかしバランス型ファンドなら、投信の運用会社が自動的にリバランスを行ってくれます。
バランス型ファンドは、あらかじめ設定された投資比率を維持するように、運用の見直しが適宜行われるからです。仮に「国内株30%±3%」と設定されていれば、株価が上昇した場合は高くても33%に収まるよう株式保有割合を抑え、株価が下落している場合も27%より少なくならないように調整されます。
これも、個人が投資をコントロールする労力を減らしてくれることを意味します。
バランス型ファンドのデメリットも確認
ただし選び方次第で利用する価値は十分あり!
こうしたメリットがある一方で、もちろんバランス型ファンドにはデメリットもあります。注意点を確認しておきましょう。
デメリット1:単品のファンドより相対的に割高になる
複数の資産に投資を行う以上、単一の資産に投資をするファンドと比べて、運用コスト(信託報酬など)は割高になります。明確に割高であれば、バランス型ファンドの利用は避けるほうが合理的です。
ただ、低コストであることを採用の条件としてルール化した「つみたてNISA」のスタート以降、「iDeCo」のバランス型ファンドにも価格引き下げの波が押し寄せています。今や、かつての日本株インデックスファンド(信託報酬は年0.7%くらいが珍しくありませんでした)よりも低い運用コストで、国内外に分散投資が行えるようになっているのです。
例えば、信託報酬が年0.5%以下で国内外に分散投資されるバランス型ファンドであれば、これは十分に選択肢になり得るのではないかと思います。
デメリット2:完全に自分に合ったポートフォリオにはならない
バランス型ファンドは、典型的なポートフォリオ(資産の組み合わせ)を3タイプほど設定するのが一般的です。ファンド名で「積極型」「標準型」「安定型」と称したり、「75」「50」「25」のように株式の比率の数字でリスクの度合いを示したりすることがよくあります。
これは言い換えれば“オーダーメイド”ではなく、3タイプから自分の好みに近いものを選ぶ“レディメイド”型ということです。
とはいえ、スーツを買うとき完全オーダーメイドにする人は少数派でしょうし、完全オーダーメイドで食事を注文することもほとんどありません。レディメイドが便利で味もまあまあであれば(そして安ければ!)利用の余地はあると思います。
「iDeCo」で「ほったらかし投資」を実現する
バランス型ファンド選びの4つの条件
さて、「iDeCo」で買えるバランス型ファンドにもさまざまな種類があります。どんな条件で選ぶべきでしょうか。
条件1:「X資産均等」タイプはあえて選ばない
まず、最近人気の「4資産均等」「8資産均等」といった「X資産均等」ファンドは候補から外します。こうした配分は、投資理論にもとづく資産の効率的な組み合わせという観点からは合理的ではないからです。
例えば8資産均等ファンドで言うと、国内・先進国の株式・リート・債券および新興国の株式・債権の8つの資産に12.5%ずつ投資するわけですが、「不動産投資割合が25%もある」「海外への投資割合が62.5%もある」「実は日本国内株には12.5%しか投資していない」というようなことになります。これを聞いて「えっ?」と思う人は、実際の配分割合を確認していない、ということです。
条件2:「ターゲットデート」ファンドはあえて選ばない
「ターゲットデート」(「ターゲットイヤー」とも呼ばれます)のファンドは、若いうちはリスクを高めに設定し、運用のゴールが近づくとリスク資産の比率を引き下げる運用を行う投資商品です。年齢に応じたポートフォリオのリスク割合の修正まで自動化できるところに魅力があります。
ただ、信託報酬がやたら高いファンドが多いことと、60歳のゴールが近づいてリスク資産の割合を引き下げる(株式などを売却する)時期にもし市場の急落があると、損失確定を愚直にするだけになってしまう、という問題があります。
普通のバランス型ファンドで「ほったらかし投資」を続け、人生の一度だけ、50歳代のどこかで市場の急騰がやってきたときに、利益確定する──それくらいなら、個人の投資としても負担はあまり大きくないと思われます。したがって、ターゲットデートファンドも外したほうがいいでしょう。
【※関連記事はこちら!】
⇒50代から「iDeCo」を始めるメリットと注意点は?すでに「iDeCo」に加入している50代はいつ利益確定すべきか、60歳で後悔しないための運用戦略も解説!
条件3:株式投資比率が高いものを選ぶ
ここまでで残ったのは、資産配分(ポートフォリオ)が基本的に固定されたタイプの、一般的なバランス型ファンド(「スタティック型」と呼ばれることもある)でしょう。このとき、ポートフォリオが異なる3タイプほどがあったら、あえて「株式投資比率が一番高いもの」を選びます。
株式投資比率が低いバランス型ファンドは債券の割合を高くしていることが多いのですが、債券投資に期待される役割(利回りが低いが元本割れもしにくい)については、預貯金を保有することでカバーできます。つまり、「定期預金:バランス型ファンド」の組み合わせで資産全体の配分を行うのであれば、バランス型ファンドでわざわざ多くの債券を持つ必要はないのです。
株式投資比率が低いバランス型ファンドは、過半が債券運用になるため、「株価が20%も上がっているのにファンドは4%しか上がらない(株式投資比率20%の場合)」といったことになります。その割に、運用手数料(信託報酬)は債券部分も含めたファンド全体にかかります。
むしろバランス型ファンドには、「リスクはあるが期待リターンも高い」投資をしてもらうべきです。したがって、株式投資比率が高いファンドを選ぶことにします。
条件4:とにかく運用コストが低いものを選ぶ
ここまで商品性の条件で絞り込んできましたが、最後の、そして最重要の要素は運用コストです。
少なくとも、「信託報酬が年0.75%以下」(海外資産を組み入れたインデックス型ファンドの場合)という「つみたてNISA」の基準はクリアするべきです。「iDeCo」全体でインデックス型ファンドのコストが下がってきていることも考慮して、「信託報酬年0.5%以下」を条件としてみてはどうでしょうか。
4つの条件をクリアするおすすめのバランス型ファンドはこれ!
バランス型ファンドのラインナップで金融機関を選ぶのも手
4つの条件に合う「国内外に分散投資が行え、かつローコストで投資ができるバランス型ファンド」としては、例えば下記のような商品が挙げられます。最近では「iDeCo」のファンドを比較しながら、採用する金融機関(運営管理機関)もチェックできるサイトもあるので便利です。
「ファンド名」
信託報酬(年・税込)/「iDeCo」で取扱のある金融機関
「DCインデックスバランス(株式80)」
0.216%/SBI証券
「Smart-i 8資産バランス 成長型」
0.216%/りそな銀行(つみたてiDeCoプラン)
「DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)」
0.2376%/日本生命保険(Vプランα)
「三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金)」
0.2592%/京葉銀行、山梨中央銀行
「マイバランス70(確定拠出年金向け)」
0.2592%/イオン銀行、西日本シティ銀行
「マイバランスDC70」
0.2592%/野村證券、岩手銀行、琉球銀行
「三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)[マイパッケージ70]」
0.2592%/三井住友銀行(SMBC個人型プラン)、ジャパン・ペンション・ナビゲーター、荘内銀行、ジブラルタ生命保険
ここまでは年0.3%を切っておりかなりローコストのバランス型ファンドです。0.5%以下だとこのあたりも選択肢です。
「DCマイセレクション75」
0.3456%/岡三証券、三井住友信託銀行(プランN)
「DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型」
0.3456%/中央労働金庫
「ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド」
0.3934%/三井住友銀行(SMBC個人型プラン)
「DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)[宝船]」
0.405%/第一生命保険(Vプランα)
「野村世界6資産分散投信(DC)成長コース」
0.4212%/ゆうちょ銀行(Aプラン)
これらのファンドは取り扱う金融機関(運営管理機関)が限られており、口座管理手数料が無料の金融機関と必ずしも一致しないのが悩ましいところですが、「運用コストが安くて、国内外に分散投資したバランス型ファンド」をラインナップに採用していることを、金融機関選びの選択肢にするのも、一つの方法だと思います。
ぜひ検討の参考にしてみてください。
【※関連記事はこちら!】
⇒iDeCoの口座開設前に金融機関の「お得度」を計算! 「管理手数料+信託報酬」が割安な金融機関がわかる「計算式」で、iDeCoをもっとお得に活用しよう!
⇒「iDeCo」を始めるなら、おすすめ金融機関はココ!口座管理料が無料になり、投資信託のラインナップが充実している「SBI証券」と「楽天証券」を比較!
⇒「つみたてNISA」は、バランス型投資信託を1本だけ選べばOK! 国内と海外の4つの資産(株式+債券)に投資するバランス型投信の選び方と注意点を解説!
1995年株式会社企業年金研究所入社後、FP総研を経て独立。ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士、AFP)、1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)、消費生活アドバイザー。若いうちから老後に備える重要性を訴え、投資教育、金銭教育、企業年金知識、公的年金知識の啓発について執筆・講演を中心に活動を行っている。新刊『読んだら必ず「もっと早く教えてくれよ」と叫ぶお金の増やし方』(日経BP社)が好評発売中。
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
| 【2026年2月4日時点】 【iDeCoおすすめ証券会社&銀行 比較】 ※どの金融機関でiDeCo口座を開設した場合でも、別途、国民年金基金連合会へ支払う加入時手数料が2829円、国民年金基金連合会と信託銀行へ支払う手数料が合計171円(毎月)かかる。受取時は給付手数料440円(1回毎)を信託銀行に支払う。還付時には、国民年金基金連合会と信託銀行への還付時手数料として合計1488円(1回毎)がかかる。運営機関変更時の手数料は「他の金融機関から」変更の場合で、「他の金融機関に」変更する場合は4400円の手数料が発生する場合がある。下記の金額は掛金を拠出する場合(すべて税込)。 |
| ◆松井証券 ⇒iDeCo詳細ページへ | ||||
| 運営管理手数料※(月額) | 手数料※ | 投資信託 | ||
| 加入時・企業型からの移換時 | 他の運営機関からの変更時 | |||
| 0円 | 0円 | 0円 | 39本 | |
| 【おすすめポイント】「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」対象! 投資信託は39本と最多水準! 運営管理手数料は残高を問わず誰でもずっと無料。投資信託は2020年10月に11本から39本へと一気に拡充され、業界最多水準となった。具体的には、低コストで人気のインデックスファンドシリーズ「eMAXIS Slim」がずらりと並ぶほか、ターゲットイヤー型と呼ばれる「三菱UFJターゲット・イヤー・ファンド」、「セレブライフ・ストーリー」などの商品が新たに加わった。低コスト投信を厳選した上で、投資対象が広がった形だ。楽天・全世界株式インデックスファンド[楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)]や楽天・全米株式インデックスファンド[楽天・バンガード・ファンド(全米株式)]も取り扱う。投資信託の保有でポイントが貯まる「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」に、イデコで所有している投資信託もカウントされるのも嬉しい。ポイント還元を受けながらお得に投資を継続できる(毎月のエントリーが必要)。2025年11月からオンラインで申込手続きが完結する「e-iDeCo」に対応。氏名・住所や掛金額変更などのオンライン申請が可能になった。 |
||||
| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・One DC 国内株式インデックスファンド(信託報酬:0.154%) ・eMAXIS Slim先進国株式インデックス(信託報酬:0.09889%) |
||||
| 【関連記事】 ◆【松井証券のiDeCo、手数料・メリットは?】運営管理手数料と加入時手数料が誰でも無料でお得!信託報酬が最安クラスの投信が39本もラインナップ! |
||||
| ◆SBI証券 ⇒iDeCo詳細ページへ | ||||
| 運営管理手数料※(月額) | 手数料※ | 投資信託 | ||
| 加入時・企業型からの移換時 | 他の運営機関からの変更時 | |||
| 0円 | 0円 | 0円 | 37本 (セレクトプラン) |
|
| 【おすすめポイント】投資信託の品揃えが豊富! 運営管理手数料は誰でも無料! 運営管理手数料は誰でも0円。「セレクトプラン」は、ほとんどの投資対象で信託報酬が“最安”のインデックス型投信が揃えられており、バリエーションも豊富と、強力なラインナップになっている。人気のアクティブ型投信「ひふみ年金」や「ジェイリバイブ」も用意。2021年1月から申込み手続きを電子化。WEB申込フォームへの入力、必要書類のアップロードが可能になり、iDeCo口座開設の手続きが簡単になった。また、2025年10月からオンラインで申込手続きが完結する「e-iDeCo」に対応。氏名・住所や掛金額変更などのオンライン申請が可能になった。シミュレーションツール「DC Doctor」を提供しており、ポートフォリオ提案から将来予測の比較など、長期にわたるiDeCoの資産形成をサポートしてくれる。 |
||||
| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)(信託報酬:0.143%以内) ・SBI・全世界株式インデックス・ファンド[雪だるま(全世界株式)](信託報酬:0.1022%) |
||||
| 【関連記事】 ◆【SBI証券のiDeCo、手数料・メリットは?】 投信のラインナップが豊富!運営管理手数料は誰でもずっと無料! ◆「iDeCo」を始めるなら、おすすめ金融機関はココ! 運営管理手数料が無料になり、投資信託のラインナップが 充実している「SBI証券」と「楽天証券」を比較! |
||||
| ◆マネックス証券 ⇒iDeCo詳細ページへ | ||||
| 運営管理手数料※(月額) | 手数料※ | 投資信託 | ||
| 加入時・企業型からの移換時 | 他の運営機関からの変更時 | |||
| 0円 | 0円 | 0円 | 27本 | |
| 【おすすめポイント】運営管理手数料が誰でも無料! インデックス型投信の信託報酬は最安水準! 運営管理手数料が誰でもずっと「無料」で、コスト面から最もお得な金融機関の1つ。投資信託の本数は27本と標準的だが、内容は充実。「eMAXIS Slim」シリーズなど信託報酬が最安水準のインデックス型投資信託が揃えられている。加えて、「ひふみ年金」「jrevive」など好成績のアクティブ型投信も豊富だ。「つみたてNISA」と「iDeCo」、どちらの制度が各個人の投資目的に適しているかアドバイスが受けられる「つみたてNISA・iDeCoシミュレーション」が便利。「e-iDeCo」に対応しており、氏名・住所や引落口座などの変更手続きがオンラインで申請可能だ。 |
||||
| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・One DC 国内株式インデックスファンド(信託報酬:0.154%) ・eMAXIS Slim先進国株式インデックス(信託報酬:0.09889%) |
||||
| 【関連記事】 ◆【マネックス証券のiDeCo、手数料・メリットは?】 運営管理手数料と加入時手数料が誰でも無料でお得!超低コスト&好成績の投資信託27本をラインナップ! |
||||
| ◆楽天証券 ⇒iDeCo詳細ページへ | ||||
| 運営管理手数料※(月額) | 手数料※ | 投資信託 | ||
| 加入時・企業型からの移換時 | 他の運営機関からの変更時 | |||
| 0円 | 0円 | 0円 | 36本 | |
| 【おすすめポイント】運営管理手数料が誰でも無料! 信託報酬の低い投信を多数ラインナップ! 運営管理手数料は残高を問わず誰でも0円で、コスト面から最もお得な金融機関の1つ。投資信託のラインナップは36本と豊富。信託報酬の低いインデックス型が揃っている。特に、2024年1月には超低コストで全世界や米国に投資できる「楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド」と「楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド」が、2025年5月には「楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド」が加わって魅力を増した。「MHAM日本成長株ファンド」など好成績のアクティブ型も用意。電話で問い合わせができる「個人型確定拠出年金(iDeCo)ダイヤル」は土日も受付を行っている。「e-iDeCo」に対応しており、氏名・住所や引落口座などの変更手続きがオンラインで申請可能だ。 |
||||
| 【信託報酬が低いおすすめ投資信託】 ・楽天・プラス・S&Pインデックス・ファンド(信託報酬:0.077%) ・楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド(信託報酬:0.0561%) ・楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド(信託報酬:0.198%) |
||||
| 【関連記事】 ◆【楽天証券のiDeCo、手数料・メリットは?】 運営管理手数料が誰でもずっと「無料」でお得!運用コストを抑えた投資信託を多数ラインナップ ◆「iDeCo」を始めるなら、おすすめ金融機関はココ! 運営管理手数料が無料になり、投資信託のラインナップが 充実している「SBI証券」と「楽天証券」を比較! |
||||
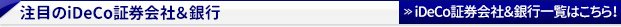
【松井証券のiDeCo】
誰でも無条件で口座管理料や各種手数料が無料!
投信の保有でポイントも貯まる⇒関連記事はこちら



![iDeCo(個人型確定拠出年金)おすすめ比較&徹底解説[2019年]](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/6/0/-/img_606e9a3f4984edef5c34375ab475d3ac23627.gif)

![iDeCo(個人型確定拠出年金)おすすめ比較&徹底解説[2026年]](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/4/0/-/img_40016abb6bd0e6096770835bf5abf9ef21127.jpg)