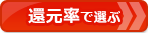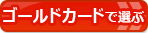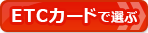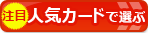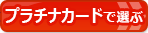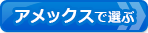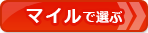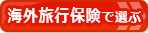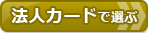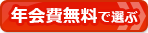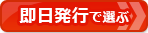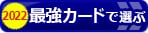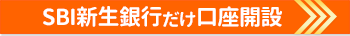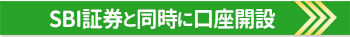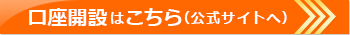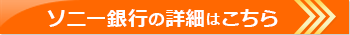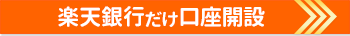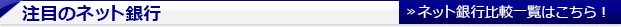2018年には、大規模な自然災害が数多く発生しました。6月の大阪府北部地震、7月の西日本豪雨や相次ぐ台風による被害、さらに9月には、北海道胆振東部地震も発生。これらの災害の影響により、いまだに普段の生活を取り戻せずにいる方も少なくありません。被害に遭われた皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。
このように大規模な災害が立て続いて起こると、大切な資産であるマイホームを守りたい、という意識が、普段より強くなるものでしょう。その一環として、「火災保険」や「地震保険」といった、住宅まわりの損害保険のことが気になっている人も多いかもしれません。
そこで今回は、マイホームを守る一助になりうる、最新の損害保険事情を解説していきます。
「火災保険」の補償期間が30年以上だったのは昔の話!
今は10年ごとに「火災保険」の見直しが必要な時代に
まずは、基本の「火災保険」から。復習しておくと、火災保険とは、火災などによる「建物」や「動産」の被害を補償する保険を指します。動産とは、建物の中にある家具などの家財のこと。火災保険では、建物だけを補償の対象とするか、建物と動産を補償の対象とするか、契約時に選択できるのが普通です。
商品設計や契約の仕方にもよりますが、火災だけでなく落雷や風水害、さらには水漏れ、盗難といった、幅広い災害や事故による被害を補償してくれる火災保険もあります。
昨今、「保険の見直し」という言葉が浸透し、生命保険や医療保険を見直す人は増えていますが、火災保険に関しては、最初に加入したまま、見直すことなく放置している人も多いのではないでしょうか。
しかし、火災保険も少しずつ変化しています。ここ最近でとりわけ大きな変化と言えるのは、2015年10月から、10年超の長期契約が不可になったこと。それ以前は、最長36年間補償が続く火災保険が販売されており、マイホームを買って長期で住宅ローンを組んだ人は、セットで長期契約の火災保険に加入するのが一般的でした。
なぜ、補償期間が短縮されたかといえば、自然災害の発生件数が増え、さらに被害の規模の予測も難しくなっていることが背景にあるようです。
今後、火災保険を見直すタイミングが増えることになるわけですが、その際に重要なのは、複数の火災保険をきちんと比較して検討することです。保険商品のラインナップや内容はずっと同じではなく、後からどんどんいい商品が出てくることもあります。深く考えず、同じ商品に継続して加入し続けていると、損をしてしまうかもしれません。
また、「ずいぶん前に家を買って、補償期間36年の火災保険に加入して、保険料も一括で支払ってあるから、満期になるまではこのままでいいでしょ」などと思っている人もいるはずです。
しかし、場合によっては、見直しをして新しい火災保険に入り直したほうが、求めている補償に合う可能性もあります。たとえば、最近の火災保険は被害に遭ったら、再度建て直しができる「新価(再調達価額)」を基準に保険金を計算するものが主流です。古い保険には、建築からの経過年数分の価値を割り引いた、「時価」を基準に保険金を請求する商品もあるため、自分が加入しているプランがどちらなのかを把握しておくことも大切です。
ちなみに、保険料を一括で全納した場合でも、火災保険を中途解約すると、残りの補償期間の分については払い戻されます。
「地震保険」は火災保険とセットで加入する保険!
未加入の人も多いが、住環境によっては加入を検討しよう!
続いて、「地震保険」に話を移します。地震保険とは、地震や噴火などで引き起こされた被害(※地震などに起因する火災の被害も含む。通常の火災保険では、地震による火災の被害は補償されない)について、補償してくれる保険です。
地震保険は単独で加入することができず、必ず火災保険とセットで加入することになっています。補償額は、火災保険の補償額の30~50%の範囲内で、任意で設定する仕組みです(建物は5000万円、動産は1000万円が上限)。
保険会社によって、保険料が大幅に異なる火災保険と違い、地震保険は国と損害保険会社が共同で運営しているものなので、どの保険会社で契約しても、補償内容や保険料は同一。保険料は居住地や建物の構造などによって変動し、補償期間は最長で5年契約となります。1年更新も可能です。
地震保険は、未加入の人も多いのが現状です。2017年度のデータによると、地震保険に加入している世帯の割合は、63%となっています(※損害保険料率算出機構の「当該年度に契約された火災保険(住宅物件)契約件数のうち、地震保険を付帯している件数の割合」より)。
火災保険も任意加入ですが、賃貸に住む場合は原則として加入が義務付けられていますし、住宅ローンを借りるときには、銀行から加入を義務付けられることもあります。これに対し、地震保険は火災保険のように加入を強制されることはないので、前述のような割合にとどまっているのでしょう。
なぜ、この地震大国に住みながら、地震保険に加入しない人が多いのか。それは、地震保険にはいくつかのデメリットがあるからです。
まずは、保険料が高いこと。また、実際に地震で被害を受けた際、補償の基準となる判定に不透明感があることも指摘されています。さらに、補償上限が火災保険の補償額の半分なので、必要十分な補償が受けられない可能性があることなども、地震保険のデメリットと言われています。
だからといって、加入するか、しないかは判断の分かれるところ。たとえば、オール電化の耐震性の高いタワーマンションに住んでいる場合は、地震によってある程度の被害は受けるにしても、地震由来の火災に見舞われるリスクは比較的低いと考えられるため、地震保険の必要性は低くなります。
しかし、木造一戸建て・住宅密集地に住んでいる場合は、地震による火災のリスクも高くなるため、地震保険への加入を前向きに検討したほうがいいかもしれません。1995年の阪神・淡路大震災の際には、今よりもっと地震保険の加入率が低く、住居が焼け落ちても保険金を受け取れない人が大勢いた、という事実を忘れてはいけません。
2019年1月には、保険料の改定(※多くの地域で値上げ)が予定されています。地震保険の保険料は、地震の発生リスクの度合いに応じて決められています。値上げされるということは、地震の発生リスクが高くなっている(と判断されている)ことを示しています。こうした状況を踏まえて、改めて地震保険の要・不要を検討する必要があるでしょう。
一般的な火災保険には、自分で特約をつけなければ
「水災補償」がセットされていない場合があるので注意!
2018年は、ことのほか台風が多かったため、風水害の不安を感じている人も多いと思われます。
まず、台風や竜巻などの「風害(風災)」ですが、これは補償内容がごくシンプルな火災保険でも、補償対象に含まれていることが多くなっています。加入している火災保険の契約を確認してみましょう。
一方で、洪水や高潮、土砂崩れなどの「水害(水災)」は、シンプルな火災保険だとカバーされない場合が多いです。保険で備えるのであれば、火災保険に水災補償を付帯するのが一般的です。
水災補償には「建物のみを補償するもの」「動産のみを補償するもの」「両方を補償するもの」の3通りがあります。一般的な支払い要件は、「建物または家財それぞれの時価の30%以上の損害」「床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水による損害」といったものです。
補償対象を絞り、なおかつ支払い要件を厳しくすれば、保険料を安くすることができます。しかし、絞り込みすぎると、いざというときに補償の対象外となるリスクがあるので、保険料と補償のバランスを勘案しながら、契約内容を検討したいところです。河川の近くに居住しているなど、水災のリスクが高いと考えるならば、手厚い補償のほうが安心感は得られます。
なお、居住地区のリスクについては、自治体が公表している「ハザードマップ」で確認しておくようにしましょう。近年は、災害の規模が大きくなっており、従来の常識が通用しないような豪雨被害なども起きています。そのため、昔のハザードマップを1回確認して終わりでは、あまり意味がありません。通常、ハザードマップは度々更新されているはずなので、こまめに新しいものを確認するといいでしょう。
家財の補償は「請求し忘れ」に要注意!
月100円台で安心が買える「個人賠償責任保険」にも注目
火災保険には、災害だけでなく、賠償事故に備えるための特約もセットで申し込めるのが一般的です。
たとえば「家財」の破損に関連する特約をつけると、うっかり壊してしまった家具や家電、カメラなどの買い替え費用まで、保険でカバーできます。たとえば、「小さい子どもがテレビにおもちゃを投げつけて壊してしまった」「落雷で家電が壊れてしまった」「敷地内に保管していた自転車が盗まれてしまった」「誤って眼鏡を割ってしまった」などの場合も、家財の補償を頼ることができます。
補償の対象が広い分、保険料はやや高いので、加入の是非は判断が分かれるところ。ただ、加入しているにもかかわらず、補償の範囲を明確に理解していないおかげで、保険金の請求をしそびれているケースがかなり多いようなので、その点は注意しましょう。
また、自転車の盗難保険に加入している場合など、家財の特約と補償内容が重複しているケースも散見されます。これでは保険料のムダ払いになってしまうので、見直しが必要になります。
そのほか、自分や家族が、他人にケガをさせたり、他人の持ち物を壊すなどして損害を与えてしまったりしたとき、保険金が出る「個人賠償責任保険」もポピュラーな特約です。たとえば、「自転車で人にケガをさせてしまった」「ペットが他人にケガを負わせてしまった」「買い物中、手に取った商品を誤って壊してしまった」「ベランダから誤って物を落とし、下にいた人にケガを負わせてしまった」など、誰もが日常で直面しそうな一大事に支えとなってくれるのがメリットです。
保険料は月100円台程度で加入でき、保険金は億単位で出るタイプがほとんどなので、安心を買うと思って加入するのがおすすめです。ただし、集合住宅に居住している場合、管理組合で共用部分に火災保険をかけているときには、居住者全員が個人賠償責任保険を利用できることもあるので、管理組合の規約などをきちんと確認しましょう。
また、個人賠償責任保険は、クレジットカードの付帯保険として加入しているケースも多いものです。こちらも、加入状況を確認のうえで、補償のかぶりがないように注意してください。
さて、今回は主に住宅まわりの損害保険について解説しました。損害保険は、身近で重要な存在であるわりに、補償内容や範囲などを理解するのが意外と難しいのかもしれません。ぜひ、これを機に加入している保険の確認や、必要な補償の見直しをしてみてください。
(取材/麻宮しま)
【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】
⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
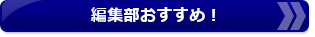 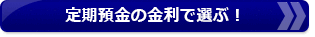 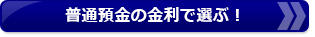 |
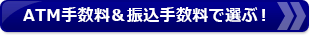 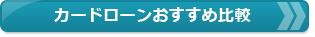 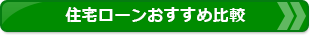 |
| 【2026年2月16日時点】 ■編集部おすすめのネット銀行はこちら! |
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆SBI新生銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.50% (※1) |
0.85% (※2) |
1.00% | 1.20% |
| 【SBI新生銀行のおすすめポイント】 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用すると普通預金金利が0.50%に大幅アップ! しかも「SBIハイパー預金」を利用すると「ステップアッププログラム」のステージが最上位の「ダイヤモンド」になり、提携コンビニATMの出金手数料が何回でも無料、他行あて振込手数料が月10回まで無料になる特典なども受けられてお得! ちなみに「SBIハイパー預金」を利用したからといって、投資などをする必要はないので安心しよう。そのほか、新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」なら、3カ月もの定期預金の金利が大幅アップ! また、他行からの振込入金などで現金がもらえる「キャッシュプレゼントプログラム」もお得。 ※1 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用した場合の金利。※2 新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【SBI新生銀行の金利・手数料・メリットは?】SBI証券との口座連携「SBIハイパー預金」の利用で、普通預金金利アップ&振込手数料が月10回まで無料! |
|||
| ◆あおぞら銀行 BANK ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.75% (※1) |
1.25% (※2) |
1.10% | 1.30% |
| 【あおぞら銀行 BANKのおすすめポイント】 普通預金金利は業界トップクラスなうえに、ほかのネット銀行とは違って「証券会社の口座と連携する」や「給与の振込口座に設定する」といった条件もなく好金利が適用されるのがメリット! また、コンビニATMでは出金手数料が発生してしまうが、郵便局やファミリーマートなどに設置されている「ゆうちょ銀行ATM」なら365日いつでも手数料無料なほか、他行あて振込手数料も月9回まで無料でお得! ※1 100万円を超えた分の普通預金は金利0.50%の適用。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「BANK The Giftスペシャル定期(BANK新規口座開設者限定)」適用時の金利。なお、期間中であっても募集総額が500億円に達した時点で取り扱い終了。 |
|||
| 【関連記事】 ■【あおぞら銀行 BANKの金利・手数料・メリットは?】普通預金金利が「定期預金レベル」でお得! ゆうちょ銀行ATMなら、週末でも出金手数料が無料に! |
|||
|
|
|||
| ◆ソニー銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.30% | 1.00% (※1) |
0.75% | 0.85% |
| 【ソニー銀行のおすすめポイント】 外貨に強いネット銀行。Visaデビット付きキャッシュカードの「Sony Bank WALLET」なら海外事務手数料が0円なので、海外での買い物がクレジットカードよりお得! 優遇プログラム「Club S」のステージなどにより、ATM出金手数料は月4回~無制限で無料、他行あて振込手数料は最大月11回まで無料! 毎月無料で決まった金額を、他行から手数料無料で入金できる「おまかせ入金サービス」も便利。 ※1 2026年3月1日までの期間限定キャンペーン「円定期特別金利」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【ソニー銀行の金利、手数料、メリットは?】外貨に強いネット銀行。Visaデビット搭載のSony Bank WALLETならクレジットカードよりお得に海外ショッピングが可能 ■「ソニー銀行」の顧客満足度調査の評価はなぜ高い? 手数料や金利で突出したメリットが見当たらなくてもなぜかユーザーから支持されている理由はどこだ!? |
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆東京スター銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.70% (※1) |
1.10% (※2) |
1.00% (※3) |
0.305% |
| 【東京スター銀行のおすすめポイント】 東京スター銀行を給与(バイトやパートも含む)または年金の受取口座に指定すると、普通預金金利が「0.30%⇒0.70%」に大幅アップするのが大きなメリット! さらに、コンビニATMの出金手数料は、月8回までなら24時間365日いつでも無料なので使いやすい。また、通常の定期預金のほか「スターワン1週間円預金」など、お得な金融商品を数多くラインナップ。 ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①東京スター銀行を給与振込や年金受取の口座に指定、②資産運用商品を300万円以上保有かつNISA口座保有&投資信託を購入。※2 新規に口座開設した人限定の「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」適用時の金利。※3「スターワン円定期預金プラス(インターネット限定)」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【東京スター銀行の金利・手数料・メリットは?】「ATM手数料」や「振込手数料」がお得なネット銀行。さらに、給与振込で普通預金金利が大幅にアップ! |
|||
| ◆auじぶん銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.51% (※1) |
1.05% (※2) |
0.61% | 0.71% |
| 【auじぶん銀行のおすすめポイント】 通常の普通預金金利は年0.31%だが、「三菱UFJ eスマート証券」または「SBI証券」と口座を連携すると+年0.10%、「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%、「au PAY アプリ」と口座を連携すると+年0.05%と、これらの条件を達成することで普通預金金利が年0.41%に! そのほか「じぶんプラス」のステージに応じて、コンビニATMでの出金手数料が最大月15回まで無料、他行あて振込手数料も最大月15回まで無料になるのも魅力! ※1 以下の①~③の条件をすべて達成した場合の金利。通常は年0.31%。①「au PAY アプリ」とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.05%。②「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%。③三菱UFJ eスマート証券またはSBI証券とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.10%。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「冬の1年もの特別金利キャンペーン」適用時の金利。au・UQ mobileユーザーの場合は+0.20%相当の現金がもらえる。 |
|||
| 【関連記事】 ■【auじぶん銀行の金利・手数料・メリットは?】KDDIの子会社なのでauユーザーには特におすすめ! 他行あて振込み手数料が最高で月15回まで無料に! ■auじぶん銀行は、振込手数料やATM出金手数料が最大で月15回まで無料!「じぶんプラス」のリニューアルでPontaポイントも貯まるようになり、さらにお得に! |
|||
| ◆楽天銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.38% (※1) |
0.40% | 0.60% | 0.70% |
| 【楽天銀行のおすすめポイント】 「楽天証券」との口座連動サービス「マネーブリッジ」を利用すれば、普通預金金利が最大0.38%に大幅アップ! しかも、楽天証券の申し込みページから「楽天証券の口座+楽天銀行の口座」を同時に開設できるので、普通預金金利が高金利な「マネーブリッジ」の利用も簡単! また、「マネーブリッジ」を利用しても特に投資をする必要はないので、とりあえず楽天証券の口座も開設して、楽天銀行の普通預金だけ利用してもOK! ※1「楽天証券」保有者の「マネーブリッジ」適用時。300万円を超えた分の普通預金は金利0.32%の適用。 |
|||
| 【関連記事】 ■【楽天銀行の金利・手数料・メリットは?】楽天証券との口座連動により普通預金金利がアップ!振込や口座振替などで「楽天ポイント」も貯まる! |
|||
|
|
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆UI銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.50% (※1) |
1.25% (※2) |
0.60% | 0.65% |
| 【UI銀行のおすすめポイント】 UI銀行は、2022年に東京きらぼしフィナンシャルグループが新たに開業した銀行で、1年~5年もの定期預金の金利はネット銀行の中でもトップクラスに高いのが魅力! また、コンビニATMの出金手数料は最大で月20回まで無料、他行あて振込手数料も最大で月20回まで無料でお得! ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①給与を「はたらくサイフ(普通預金)」で受けとった場合。②年金を「まもりのサイフ(普通預金)」で受け取った場合。③女性限定の「女神のサイフ(普通預金)」を利用した場合。※2 2026年5月31日までに新規口座開設した人向けの「4周年記念 新規口座開設者限定!定期預金キャンペーン」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■UI銀行は「高水準の金利&お得な手数料」でおすすめのスマホ特化型デジタルバンク!「東京きらぼしフィナンシャルグループ」から誕生した「UI銀行」の魅力を解説! ■【UI銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金&普通預金の金利にこだわる「スマホ特化」の銀行! 他行あて振込手数料が最大で月20回まで無料 |
|||
| ◆SBJ銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 最大0.30% (※1) |
1.35% (※2) |
1.40% (※2) |
1.45% (※2) |
| 【SBJ銀行のおすすめポイント】 ほかのネット銀行と比べても、定期預金金利の高さはトップクラス! さらに、セブン-イレブン(セブン銀行)やミニストップ(イオン銀行)、ファミリーマート(E-net)のATMなら、出金手数料が最低でも月10回まで無料でお得なほか、他行あて振込手数料も最低で月5回まで無料なので、月に何回も振込をする人にもおすすめ! ※1 通常の0.20%分の利息に加えて、月内の最低残高(上限1000万円)に対して0.10%分の追加利息を受け取れる「普通預金プラス」の場合。※2 新規口座開設者限定の「はじめての定期預金<はじめくん>」の場合。 |
|||
| 【関連記事】 ■SBJ銀行が業界No.1水準の“定期預金金利”や“手数料の安さ”を維持できる理由とは?「外資系の銀行に預金しても大丈夫?」という疑問や不安をSBJ銀行に直撃! ■【SBJ銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金がお得で、魅力的な商品も多い外資系銀行。ATM手数料や他行あて振込手数料の安さもメリット! |
|||
| ◆イオン銀行(イオンカードセレクト保有者) ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.22% (「イオン銀行Myステージ」の 「ゴールドステージ」の場合) |
0.45% | 0.45% | 0.70% |
| 【イオン銀行のおすすめポイント】 「イオン銀行Myステージ」で「ゴールドステージ」になれば、普通預金金利が0.22%に! しかも「イオンカードセレクト」で年間50万円以上を利用するなど、一定の条件を達成すると入手できる年会費無料のゴールドカード「イオンゴールドカードセレクト」を保有すれば、無条件で「ゴールドステージ」に到達できる特典が2024年3月にスタート。「ゴールドステージ」になれば、イオン銀行ATMの手数料は24時間いつでも何回でも無料なのはもちろん、他行ATMの入出金手数料と他行あて振込手数料がそれぞれ月3回まで無料になってお得! ※1 2026年2月11日までの期間限定キャンペーン「冬の定期預金キャンペーン」適用時(期間内にイオンカードセレクトに申し込んだ場合の金利)。 |
|||
| 【関連記事】 ■【イオン銀行の金利・手数料・メリットは?】イオン銀行利用者は「イオンカードセレクト」が必須!普通預金金利などがアップしてさらにお得に使える! ■イオンカードを作るなら「イオンカードセレクト」が一番お得! WAONチャージでのポイント2重取り&イオン銀行で預金金利が優遇されやすくなる特典も! |
|||
| ※ 100万円を預けた場合の2026年2月16日時点の金利(年率、税引前)。金利は税引き前の年利率であり、利息には20.315%(国税15.315%〈復興特別所得税含む〉+地方税5%)の税金がかかります。また、最新の金利は各銀行の公式サイトをご確認ください。 | |||