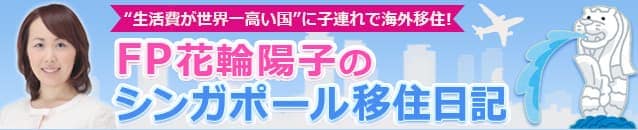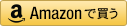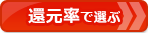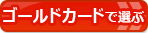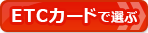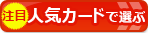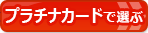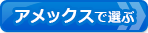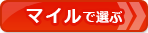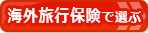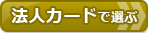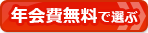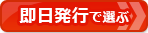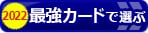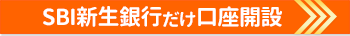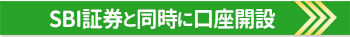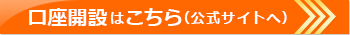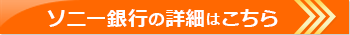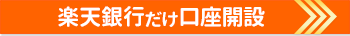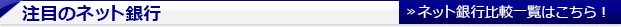ファイナンシャル・プランナーの花輪陽子です。
ここ数年、日本の保険業界では「外貨建て保険」が大ヒット商品になっています。「外貨建て保険」とは、契約者が支払った保険料を、保険会社が外貨で運用する商品のことで、年金保険や終身保険など、将来的に保険金や解約返戻金が戻ってくる貯蓄型の保険です。
現在、日本で販売されている「円建て保険」の場合、「予定利率」(保険会社が契約者に約束する運用利回り)が低水準で、「返礼率」(支払った保険料に対して、解約時にどれだけお金が受け取れるか、という割合)も低くなっているので、貯蓄型の「円建て保険」にはほとんど旨味がありません。
これに対して、「外貨建て保険」の中には「予定利率」が高水準で、「返礼率」も高く、魅力的な商品もあります。そのうえ、貯蓄型の「円建て保険」と比較すると、多少保険料も安い傾向にあることから、「投資は怖いけど、リスクを抑えながら資産を有効活用したい」という層を中心に、人気が集まっているのです。
ただし、最近になって日本のメディアでは、頻繁に「外貨建て保険」のリスクが取り沙汰されるようになりました。ということは、人気と裏腹に、実は「外貨建て保険」は危険性の高い商品なのでしょうか? そこで今回は「外貨建て保険」の実情や注意点、加えて、私が住んでいるシンガポールの「外貨建て保険」についても解説します。
「外貨建て保険」には為替変動リスクがある!
コストが高く、内訳や仕組みが不透明なのも問題点
まず、「円建て保険」と比べた場合、「外貨建て保険」に特有のリスクがあるのは事実です。主なリスクは以下の2つです。
(1)米ドルなどの外貨で運用されるため、為替差損が生じる場合がある
(2)円から外貨に換えて運用し、また外貨を円に戻すことで「為替手数料」が発生する。さらに、為替手数料以外にも何かとコストがかかるが、あまり明確に示されていない
最初に(1)の「米ドルなどの外貨で運用されるため、為替差損が生じる場合がある」という点から解説します。
日本で販売されている「外貨建て保険」の多くは、元本が保証されていますが、それはあくまで“運用する外貨建てでの元本が保証される”という意味です。つまり、為替の動向次第では、円に戻したときに元本割れするリスクがあります。
この点をきちんと理解しないまま加入してしまう人が多いのか、「『外貨建て保険』は元本保証だと言われたのに、損をした!」といったクレームが相次いでいるそうです。理解しないまま加入した側にも問題がありますが、金融機関の販売員が、あまり金融リテラシーのない高齢者の方などに対し、十分な説明をせずに「外貨建て保険」を販売している点のほうが大問題でしょう。
続いて、(2)の「円から外貨に換えて運用し、また外貨を円に戻すことで『為替手数料』が発生する。さらに、為替手数料以外にも何かとコストがかかるが、あまり明確に示されていない」という点について。
通貨と通貨を交換すると、為替手数料が発生します。日本の「外貨建て保険」の場合、通常だと「円⇒外貨」「外貨⇒円」と2回の交換を行うことになりますが、このときの為替手数料が高い傾向にあります。
さらに、「外貨建て保険」では為替手数料以外にも、契約時手数料や運用手数料など、何かとコストが発生するのですが、多くの商品はコストの内訳が分かりづらく、ほとんどブラックボックスのような状態になっています。事前にどれだけコストがかかるか、はっきりわからない商品もあります。
以上をまとめると、「外貨建て保険」は高い利回りが期待できて、保険料がやや安い反面、為替リスクがあって、コストが高い商品と言うことができます。
リスクはあっても、このご時世で高い利回りは魅力的!
シンガポールや香港の「外貨建て保険」がお手本になる?
ここまでのところで、「『外貨建て保険』はやめておいたほうがよさそう」と思った方も多いかもしれませんね。ただ、私は「外貨建て保険=絶対NG」だとは考えていません。というのも、やはり「外貨建て保険」の利回りは魅力的だと思うからです。
主要な「外貨建て保険」の運用状況を見ると、リターンは3%前後です。ただ、コストなどを差し引いた後で実際に受け取れる利回りは、保険期間や保険料の支払い方、保険金の受け取り方によって変わりますが、おおむね1~2%弱になりそうです。あまり高いとは言えませんが、それでも預貯金の利回りに比べればマシです。
ちなみに、私が住むシンガポールや、金融先進都市の香港では、貯蓄型の保険を用いた資産運用がごく一般的です。シンガポールでは、公的年金制度だけで老後の生活を支えるのが難しいため、多くの人が若いときから貯蓄型の保険に加入するのです。
同じように、年金不安が広がっている日本でも、「貯蓄型の保険で老後に備えたい」というニーズは大きいでしょう。かといって、「円建ての保険」では満足な利回りを期待するのが難しいので、「外貨建て保険」で運用したいと考える人は、もっと増えるかもしれません。
現時点で、「外貨建て保険」には前述したように、いくつものデメリットがあるので、大いに改善の余地があります。しかし、保険会社がコスト面の問題などを解決することができれば、とても将来性があるとも感じます。
シンガポールでは外貨建ての金融商品がポピュラー
商品性のシンプルさ、コストのわかりやすさが普及の理由
ここからは、参考までにシンガポールの「外貨建て保険」について紹介します。
シンガポールでは貯蓄型の保険に加入している人が大勢います。もちろん、現地通貨であるシンガポールドル建ての保険に入るのがメインですが、富裕層の間では米ドル建ての保険に入っている人も多いです。株や投資信託などと違って、一定の運用リターンがあらかじめ明示されるところに魅力を感じる人が多いのは、日本と同じです。
シンガポールドル建てか、米ドル建てのいずれかを選択できる保険もあります。最近の数字だと、利回り(実行レート)はシンガポールドル建てが4%前後、米ドル建てが5%前後といったところで、富裕層の多くは米ドル建てを選択します。また、運用状況が良ければ利益が上乗せされる設計となっており、たとえば20年の運用で、元金を2倍程度に増やすことも期待できます。
ただし、シンガポールと日本では、いろいろ事情が異なる部分もあります。
まず、シンガポール人は外貨建て(主に米ドル建て)の金融商品に慣れています。シンガポールでは、以前から保険以外でも外貨建ての金融商品が充実しており、しかも為替手数料が日本と比較するとはるかに安いです。よって、保険だけでなく外貨預金や外債なども購入しやすい環境と言えます。
米ドル建ての保険に加入して保険金を受け取り、シンガポールドルに戻さずに米ドルのままで使う人もたくさんいます。たとえば、子どもを米国の大学で学ばせるために、米ドル建ての保険で資金を準備し、無事に進学できれば米ドルで保険金を受け取って、そのまま入学金や授業料を支払う、といった具合です。
シンガポールの貯蓄型の保険は、全体的に商品の仕組みがシンプルだという特徴もあります。日本では、一つの保険契約に特約を上乗せし、結果として契約内容が複雑になってしまうケースがよく見られますが、シンガポールではこのようなことはありません。一つの保険であれこれカバーするのではなく、一つの目的に合わせて一つの保険に入るのが普通だからです。
なお、シンガポールの貯蓄型の保険も、為替手数料以外のコストは高額です。その代わり、過去の運用リターンや経費率、保険契約にかかるコストの総額、契約者が受け取れる利回り、運用の内訳などが全てすべて明記されている点が、日本の「外貨建て保険」と異なります。そのため、やみくもにコストを吸い上げられる印象はなく、安心して加入することができるのです。
「外貨建て保険」に加入したい人は支払い方法や
為替手数料などに注目して、類似商品の比較検討を!
日本とシンガポールの「外貨建て保険」の違いが見えてきたでしょうか。
確約部分の利回りでは、日本で販売されている米ドル建て保険も、シンガポールで販売されている米ドル建て保険も、それほど大きな違いはありません。しかし、シンガポールに駐在している日本人に話を聞くと、現地の「外貨建て保険」に加入している人がたくさんいます。やはり、為替手数料の安さや期待リターンの面で、シンガポールの保険のほうが魅力的だ判断されているのでしょう。
今後、日本の「外貨建て保険」のコストがもっと明確化され、金融機関が徴収する為替手数料が安くなる日が来れば、状況は大きく変わってくると思います。なかなか道は険しそうですが、実現すれば「外貨建て保険」の加入者数はさらに膨れ上がるかもしれません。
もし、現段階でみなさんが日本の「外貨建て保険」に興味があるなら、利回りだけに注目するのではなく、リスクを理解したうえで、加入のタイミングや保険料の支払い方などを検討する必要があるでしょう
最も大きな問題は、保険料を支払うタイミングによる「為替変動リスク」です。一時払いで保険料を支払うタイプの保険だと、分割払いよりも保険料がディスカウントされ、リターンも大きくなる可能性がある反面で、為替変動リスクは大きくなります。月払いや年払いのタイプなら、為替リスクは分散できますが、保険料がやや割高になりますし、まとまった余裕資金がある場合、最初から全額を運用に回せずに、資金効率が悪化するというデメリットもあります。つまり、いずれにせよデメリットはあるのですが、為替変動リスクを抑えることを最優先するなら、一時払いは避けたほうがいいでしょう。
また、保険金の受け取り方にも気を配る必要があります。おすすめは、保険金を受け取るタイミングを選べる(保険金を据え置ける)商品を選んだり、米ドルのまま満期金を受け取り、タイミングを見計らって少しずつ両替したりすること。こうすることによって、保険金を受け取るときに「円高」で青ざめる、というリスクを回避できます。銀行の為替手数料はすべて横並びではないので、為替手数料が安いネット銀行などを選択するといいでしょう。
どんな金融商品にも、必ずメリットとデメリットはあります。「外貨建て保険」は否定されることも多い金融商品ですが、ご自身にとってメリットとデメリット、どちらが大きく感じられるか、改めて考えてみてください。
『少子高齢化でも老後不安ゼロ シンガポールで見た日本の未来理想図』(講談社プラスα新書)
経済成長率3.5%で、定年退職は67歳。人口減少に影響されない社会保障制度が完備され、優秀な外国人労働者を優遇し、なおかつ教育環境も高水準な国・シンガポール。日本もお手本にしたい、少子高齢化でも老後不安がゼロのシンガポールが実行している合理的で賢い政策を、現地在住のファイナンシャルプランナーならではの視点で紹介!
【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】
⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
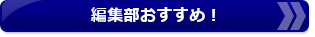 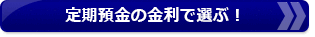 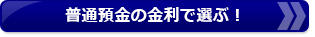 |
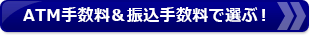 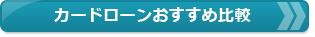 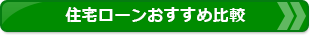 |
| 【2026年2月16日時点】 ■編集部おすすめのネット銀行はこちら! |
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆SBI新生銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.50% (※1) |
0.85% (※2) |
1.00% | 1.20% |
| 【SBI新生銀行のおすすめポイント】 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用すると普通預金金利が0.50%に大幅アップ! しかも「SBIハイパー預金」を利用すると「ステップアッププログラム」のステージが最上位の「ダイヤモンド」になり、提携コンビニATMの出金手数料が何回でも無料、他行あて振込手数料が月10回まで無料になる特典なども受けられてお得! ちなみに「SBIハイパー預金」を利用したからといって、投資などをする必要はないので安心しよう。そのほか、新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」なら、3カ月もの定期預金の金利が大幅アップ! また、他行からの振込入金などで現金がもらえる「キャッシュプレゼントプログラム」もお得。 ※1 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用した場合の金利。※2 新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【SBI新生銀行の金利・手数料・メリットは?】SBI証券との口座連携「SBIハイパー預金」の利用で、普通預金金利アップ&振込手数料が月10回まで無料! |
|||
| ◆あおぞら銀行 BANK ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.75% (※1) |
1.25% (※2) |
1.10% | 1.30% |
| 【あおぞら銀行 BANKのおすすめポイント】 普通預金金利は業界トップクラスなうえに、ほかのネット銀行とは違って「証券会社の口座と連携する」や「給与の振込口座に設定する」といった条件もなく好金利が適用されるのがメリット! また、コンビニATMでは出金手数料が発生してしまうが、郵便局やファミリーマートなどに設置されている「ゆうちょ銀行ATM」なら365日いつでも手数料無料なほか、他行あて振込手数料も月9回まで無料でお得! ※1 100万円を超えた分の普通預金は金利0.50%の適用。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「BANK The Giftスペシャル定期(BANK新規口座開設者限定)」適用時の金利。なお、期間中であっても募集総額が500億円に達した時点で取り扱い終了。 |
|||
| 【関連記事】 ■【あおぞら銀行 BANKの金利・手数料・メリットは?】普通預金金利が「定期預金レベル」でお得! ゆうちょ銀行ATMなら、週末でも出金手数料が無料に! |
|||
|
|
|||
| ◆ソニー銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.30% | 1.00% (※1) |
0.75% | 0.85% |
| 【ソニー銀行のおすすめポイント】 外貨に強いネット銀行。Visaデビット付きキャッシュカードの「Sony Bank WALLET」なら海外事務手数料が0円なので、海外での買い物がクレジットカードよりお得! 優遇プログラム「Club S」のステージなどにより、ATM出金手数料は月4回~無制限で無料、他行あて振込手数料は最大月11回まで無料! 毎月無料で決まった金額を、他行から手数料無料で入金できる「おまかせ入金サービス」も便利。 ※1 2026年3月1日までの期間限定キャンペーン「円定期特別金利」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【ソニー銀行の金利、手数料、メリットは?】外貨に強いネット銀行。Visaデビット搭載のSony Bank WALLETならクレジットカードよりお得に海外ショッピングが可能 ■「ソニー銀行」の顧客満足度調査の評価はなぜ高い? 手数料や金利で突出したメリットが見当たらなくてもなぜかユーザーから支持されている理由はどこだ!? |
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆東京スター銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.70% (※1) |
1.10% (※2) |
1.00% (※3) |
0.305% |
| 【東京スター銀行のおすすめポイント】 東京スター銀行を給与(バイトやパートも含む)または年金の受取口座に指定すると、普通預金金利が「0.30%⇒0.70%」に大幅アップするのが大きなメリット! さらに、コンビニATMの出金手数料は、月8回までなら24時間365日いつでも無料なので使いやすい。また、通常の定期預金のほか「スターワン1週間円預金」など、お得な金融商品を数多くラインナップ。 ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①東京スター銀行を給与振込や年金受取の口座に指定、②資産運用商品を300万円以上保有かつNISA口座保有&投資信託を購入。※2 新規に口座開設した人限定の「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」適用時の金利。※3「スターワン円定期預金プラス(インターネット限定)」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【東京スター銀行の金利・手数料・メリットは?】「ATM手数料」や「振込手数料」がお得なネット銀行。さらに、給与振込で普通預金金利が大幅にアップ! |
|||
| ◆auじぶん銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.51% (※1) |
1.05% (※2) |
0.61% | 0.71% |
| 【auじぶん銀行のおすすめポイント】 通常の普通預金金利は年0.31%だが、「三菱UFJ eスマート証券」または「SBI証券」と口座を連携すると+年0.10%、「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%、「au PAY アプリ」と口座を連携すると+年0.05%と、これらの条件を達成することで普通預金金利が年0.41%に! そのほか「じぶんプラス」のステージに応じて、コンビニATMでの出金手数料が最大月15回まで無料、他行あて振込手数料も最大月15回まで無料になるのも魅力! ※1 以下の①~③の条件をすべて達成した場合の金利。通常は年0.31%。①「au PAY アプリ」とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.05%。②「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%。③三菱UFJ eスマート証券またはSBI証券とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.10%。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「冬の1年もの特別金利キャンペーン」適用時の金利。au・UQ mobileユーザーの場合は+0.20%相当の現金がもらえる。 |
|||
| 【関連記事】 ■【auじぶん銀行の金利・手数料・メリットは?】KDDIの子会社なのでauユーザーには特におすすめ! 他行あて振込み手数料が最高で月15回まで無料に! ■auじぶん銀行は、振込手数料やATM出金手数料が最大で月15回まで無料!「じぶんプラス」のリニューアルでPontaポイントも貯まるようになり、さらにお得に! |
|||
| ◆楽天銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.38% (※1) |
0.40% | 0.60% | 0.70% |
| 【楽天銀行のおすすめポイント】 「楽天証券」との口座連動サービス「マネーブリッジ」を利用すれば、普通預金金利が最大0.38%に大幅アップ! しかも、楽天証券の申し込みページから「楽天証券の口座+楽天銀行の口座」を同時に開設できるので、普通預金金利が高金利な「マネーブリッジ」の利用も簡単! また、「マネーブリッジ」を利用しても特に投資をする必要はないので、とりあえず楽天証券の口座も開設して、楽天銀行の普通預金だけ利用してもOK! ※1「楽天証券」保有者の「マネーブリッジ」適用時。300万円を超えた分の普通預金は金利0.32%の適用。 |
|||
| 【関連記事】 ■【楽天銀行の金利・手数料・メリットは?】楽天証券との口座連動により普通預金金利がアップ!振込や口座振替などで「楽天ポイント」も貯まる! |
|||
|
|
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆UI銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.50% (※1) |
1.25% (※2) |
0.60% | 0.65% |
| 【UI銀行のおすすめポイント】 UI銀行は、2022年に東京きらぼしフィナンシャルグループが新たに開業した銀行で、1年~5年もの定期預金の金利はネット銀行の中でもトップクラスに高いのが魅力! また、コンビニATMの出金手数料は最大で月20回まで無料、他行あて振込手数料も最大で月20回まで無料でお得! ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①給与を「はたらくサイフ(普通預金)」で受けとった場合。②年金を「まもりのサイフ(普通預金)」で受け取った場合。③女性限定の「女神のサイフ(普通預金)」を利用した場合。※2 2026年5月31日までに新規口座開設した人向けの「4周年記念 新規口座開設者限定!定期預金キャンペーン」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■UI銀行は「高水準の金利&お得な手数料」でおすすめのスマホ特化型デジタルバンク!「東京きらぼしフィナンシャルグループ」から誕生した「UI銀行」の魅力を解説! ■【UI銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金&普通預金の金利にこだわる「スマホ特化」の銀行! 他行あて振込手数料が最大で月20回まで無料 |
|||
| ◆SBJ銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 最大0.30% (※1) |
1.35% (※2) |
1.40% (※2) |
1.45% (※2) |
| 【SBJ銀行のおすすめポイント】 ほかのネット銀行と比べても、定期預金金利の高さはトップクラス! さらに、セブン-イレブン(セブン銀行)やミニストップ(イオン銀行)、ファミリーマート(E-net)のATMなら、出金手数料が最低でも月10回まで無料でお得なほか、他行あて振込手数料も最低で月5回まで無料なので、月に何回も振込をする人にもおすすめ! ※1 通常の0.20%分の利息に加えて、月内の最低残高(上限1000万円)に対して0.10%分の追加利息を受け取れる「普通預金プラス」の場合。※2 新規口座開設者限定の「はじめての定期預金<はじめくん>」の場合。 |
|||
| 【関連記事】 ■SBJ銀行が業界No.1水準の“定期預金金利”や“手数料の安さ”を維持できる理由とは?「外資系の銀行に預金しても大丈夫?」という疑問や不安をSBJ銀行に直撃! ■【SBJ銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金がお得で、魅力的な商品も多い外資系銀行。ATM手数料や他行あて振込手数料の安さもメリット! |
|||
| ◆イオン銀行(イオンカードセレクト保有者) ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.22% (「イオン銀行Myステージ」の 「ゴールドステージ」の場合) |
0.45% | 0.45% | 0.70% |
| 【イオン銀行のおすすめポイント】 「イオン銀行Myステージ」で「ゴールドステージ」になれば、普通預金金利が0.22%に! しかも「イオンカードセレクト」で年間50万円以上を利用するなど、一定の条件を達成すると入手できる年会費無料のゴールドカード「イオンゴールドカードセレクト」を保有すれば、無条件で「ゴールドステージ」に到達できる特典が2024年3月にスタート。「ゴールドステージ」になれば、イオン銀行ATMの手数料は24時間いつでも何回でも無料なのはもちろん、他行ATMの入出金手数料と他行あて振込手数料がそれぞれ月3回まで無料になってお得! ※1 2026年2月11日までの期間限定キャンペーン「冬の定期預金キャンペーン」適用時(期間内にイオンカードセレクトに申し込んだ場合の金利)。 |
|||
| 【関連記事】 ■【イオン銀行の金利・手数料・メリットは?】イオン銀行利用者は「イオンカードセレクト」が必須!普通預金金利などがアップしてさらにお得に使える! ■イオンカードを作るなら「イオンカードセレクト」が一番お得! WAONチャージでのポイント2重取り&イオン銀行で預金金利が優遇されやすくなる特典も! |
|||
| ※ 100万円を預けた場合の2026年2月16日時点の金利(年率、税引前)。金利は税引き前の年利率であり、利息には20.315%(国税15.315%〈復興特別所得税含む〉+地方税5%)の税金がかかります。また、最新の金利は各銀行の公式サイトをご確認ください。 | |||