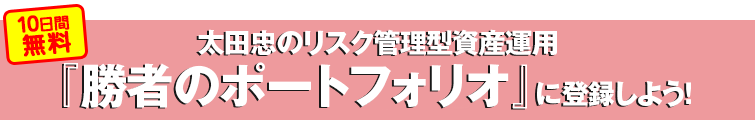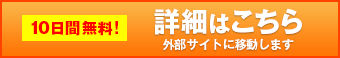米雇用統計の7月は市場予想に未達、5月と6月は大幅下方修正で市場急落
8月1日の米国市場。NYダウは一時800ドル近く下げ、S&P500やナスダック総合指数も大幅安。債券市場では米国債が買われて長期金利は前日比0.15%もの急激な低下が起こり4.22%となった。最近の金融市場において雇用統計の数字はほとんど攪乱要因になってなかったが、今回はマーケットを激しく揺さぶった。
7月の米雇用統計は7.3万人増と市場予想の10万〜11万人増を下回った。分野別では製造業が1.1万人減となり米トランプ政権が重視する製造業の雇用減は3カ月連続だ。これだけなら特に問題視されることはなかったはずだが、確報値として発表された5月分は14.4万人増から1.9万人増に、6月分は14.7万人増から1.4万人増へと大きく下方修正されてネガティブサプライズとなった。「足元の雇用はほとんど増えなくなっている」という現実を突き付けられたのだ。
トランプ大統領は大幅下方修正に憤慨し、あろうことか統計局長を解雇
さらに驚いたのはトランプ大統領の行動である。大幅な下方修正に憤慨して労働省のエリカ・マクエンタファー統計局長を解雇した。「彼女は選挙前に雇用統計を改竄し、カマラ・ハリスを勝たせようとした人物だ」と自身のSNSに投稿。自分の気に入らない事態が起こると、それに関係する人物を次々と切っていく暴君の姿をまたしても我々は見た。
そもそも雇用統計は速報値と確報値の振れ幅が大きい統計データである。速報値の発表時点においては全てのデータが回収されておらず、確報値との間に大きな誤差が生じることがある。特にコロナ禍においては混乱が生じ、たびたび過去データが大幅に修正された。
下方修正は連邦職員リストラや不安定な関税政策など自業自得の側面も
今回の下方修正はトランプ政権にも大きな要因がある。トランプ大統領の独断によって米連邦政府の大規模な職員リストラを実施。職員数は毎月1.5万人を超えるペースで減少しているのだ。企業においても、日々揺れ動く関税政策に身構えざるを得ず、積極的な採用に及び腰になっている。要するに雇用悪化はトランプ大統領の政策そのものに原因があるのではないか。自らを省みず、統計局長を解任しても何の解決策にもならない。
トランプ大統領の怒りの矛先は米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長にも及んだ。「遅すぎる男のジェロームは引退させるべきだ」とSNSに書き込み、従来からの批判を繰り返した。
7月の米連邦公開市場委員会(FOMC)は5会合連続で政策金利を据え置いた。パウエル議長は「関税の影響はなお不透明」「次回9月会合での利下げは決めていない」と早期利下げに慎重な姿勢を崩さなかった。ところが内情はFRB内で亀裂が生じていた。ボウマン副議長とウォラー理事の2人が利下げを求めて反対票を投じた。地区連銀の総裁ではなく、FRB本部の理事が複数で反対に回るのは1993年12月以来となる32年ぶりの異例の事態だった。マーケットコンセンサスは「年内に利下げ再開」だが、今回の会合ではその兆候を垣間見ることができた、と前回コラムで述べた通りである。
今回の雇用統計ショックはバッドニュース、それともグッドニュース?
その答えは、初動こそ株式市場は大幅安となったが、明らかにグッドニュースである。何故か? 今回の雇用統計ショックは金融相場を加速させる十分なインパクトを持っているからだ。日本を含めて世界の株式市場の方向性を決めるのはFRBの金融政策である。FRBは昨年9月にようやく0.50%の利下げを開始し、11月と12月は連続で0.25%ずつ利下げした。その結果、5.25%~5.50%だった政策金利はたった4ヶ月間で4.25%~4.50%の水準まで下がった。だが、今年に入ってからは一度も利下げを行っていない。利下げが再開されて中休みの状態から脱却すれば、本来の金融相場らしい動きが出てくる。非常に重要なイベントになる。
フェドウオッチでは9月の利下げ確率は雇用統計発表後に30%台から90%近くにまで急上昇。ウォール街の合言葉は「FRBに逆らうな」から「FRBを疑え」に変化しつつある。そして注目されるのが8月21日〜23日に開催される毎年恒例のジャクソンホール会議でのパウエル議長の講演だ。パウエル氏は過去に「利上げ」を示唆して市場を混乱させた前例がある。今回の雇用統計ショックを受けても利下げに慎重な姿勢は変わらないのか。経済データを検証しつつ会合ごとに金融政策を決めていく方針を常に唱えてきたが、今回はかなり厳しいデータが出た。ハト派的な意味合いの言い回しが使われれば、市場への影響は強くなるだろう。
景気や企業業績悪化の兆候も出れば金融緩和を迫られ株価上昇の原動力に
雇用悪化に加え、景気や企業業績が悪化する兆候も出てくれば金融緩和を一段と推進する必要があり、株価上昇のエンジンとなる。前回の金融相場が到来したコロナショックでは景気悪化と企業業績悪化が強烈でFRBはゼロ金利政策を取らざるを得なかった。赤字決算が続出する中で株価がどんどん上昇するという現象が見られたのは記憶に新しい。
雇用統計ショックを受けて、8月4日の日本市場でも寄り付き直後に日経平均株価が一時900円超も下げる場面があったが、結局は508円安と下げ渋った。『日経平均終値4万290円。「令和のブラックマンデー」再来は回避』と題する記事が掲載された日経電子版。どうして今回の雇用統計ショックを昨年8月5日の令和のブラックマンデーを引き合いに解説するのか私には全く理解不能である。令和のブラックマンデーが起きたのは逆業績相場。今回の雇用統計ショックが起きたのは金融相場。似ても似つかぬマーケット局面の出来事でありおかしな論調だ。読者の不安を煽るような悪意のある記事と私には映る。署名記事だが、マーケットのことを分かっていない人が都合よく書くとデタラメな記事が出来上がる典型例。こういう報道のされ方がメディアには多いので、気をつけていただきたい。
Webセミナーを8月13日に開催。快進撃の秘密と今後の投資戦略を伝授
さて、太田忠投資評価研究所とダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチ(DFR)がコラボレーションして投資助言を行っている「勝者のポートフォリオ」は快進撃が続いている。2021年10月のサービス開始以来、7月31日時点で累計パフォーマンスは+103.6%、昨年来+59.3%、年初来+20.6%と全ての期間においてマーケットを圧倒している。マーケット分析力と個別銘柄選択力で「市場に打ち克つ」を実践している成果が大きく出ていると自負している。
 「勝者のポートフォリオ」の設定来パフォーマンスの推移と主要指数との比較
「勝者のポートフォリオ」の設定来パフォーマンスの推移と主要指数との比較
「勝者のポートフォリオ」は日本株を中心とした個人投資家向けの投資助言サービス。毎週のマーケット解説・投資戦略のメルマガ配信に加え、毎月恒例のWebセミナーの開催と投資のスキルアップを目的とするスペシャル講義を提供している。
Webセミナーでは、日米の金融政策や景気動向、最近ではトランプ関税政策といったホットな話題を取り上げながら現状の投資戦略や株価上昇が期待できる銘柄の話、さらには参加者からの全ての質問に答えるQ&Aコーナーを設け、毎回約2時間半のロングランとなっている。毎回300名を超える参加者で盛り上がる投資のヒントが満載のセミナーだ。
次回のWebセミナーを8月13日(水)20時より開催する。テーマは『日経平均4万円回復で新局面、金融相場で資産を増やす最も効果的方法とは?』。株式市場は上昇しているのに資産運用がうまくいっていない個人投資家が多いとの印象を受ける。「どういう運用をすれば資産運用がうまくいくのか」を知りたい人はご参加いただきたい。10日間の無料お試し期間を使えば誰でも参加可能。有料会員はアーカイブ録画をいつでも視聴できる。
スペシャル講義は投資スキルを身につけることを目的に62本もの講義動画をリリース。個人投資家にとって必須のリスク管理、運用力を上げるためのマーケットサイクル投資法、恐怖指数の活用、システマティックリスクの対処法、ヘッジファンドの実態…など詳しく解説している。ぜひとも参考にしていただきたい。
●太田 忠 DFR投資助言者。ジャーディン・フレミング証券(現JPモルガン証券)などでおもに中小型株のアナリストとして活躍。国内外で6年間にわたり、ランキングトップを維持した。現在は、中小型株だけではなく、市場全体から割安株を見つけ出す、バリュー株ハンターとしてもDFRへのレポート提供による「勝者のポートフォリオ」メルマガ配信などで活躍。
※この連載は、ワンランク上の投資家を目指す個人のための資産運用メルマガ『勝者のポートフォリオ』で配信された内容の一部を抜粋・編集の上お送りしています。メルマガに登録すると、メルマガ配信の他、無料期間終了後には会員専用ページで「勝者のポートフォリオ」や「ウオッチすべき銘柄」など、具体的なポートフォリオの提案や銘柄の売買アドバイスなどがご覧いただけます。原則毎月第一木曜夜は、生配信セミナーを開催。
国内外で6年連続アナリストランキング1位を獲得した、
トップアナリスト&ファンドマネジャーが
個人投資家だからこそ勝てる
「勝者のポートフォリオ」を提示する、
資産運用メルマガ&サロンが登場!
老後を不安なく過ごすための資産を自助努力で作らざるを得ない時代には資産運用の知識は不可欠。「勝者のポートフォリオ」は、投資の考え方とポートフォリオの提案を行なうメルマガ&会員サービス。週1回程度のメルマガ配信+ポートフォリオ提案とQ&Aも。登録後10日間は無料!