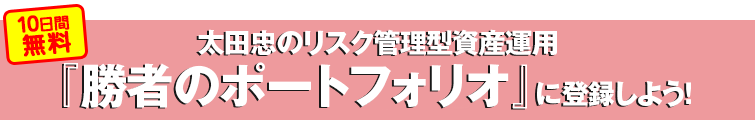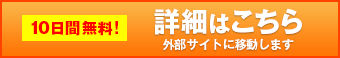FOMCが0.25%の利下げを決定。日経平均株価は初の4万5000円を突破
日経平均株価はついに初の4万5000円突破、持たざるリスクが鮮明に―。
9月17日から2日間に渡り開催された米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果が発表された。昨年12月以来6会合ぶりとなる利下げを決定。利下げ幅は事前予想通りの0.25%となり、米国の政策金利は4.00%~4.25%のレベルに低下した。
この日の米国市場は結果公表後にNYダウは一時500ドルを超える急騰ぶりを示したものの、その後は上げ幅を縮小して下げに転じる場面が見られた。結局は260ドル高の4万6018ドルにて終了し、短時間での乱高下ぶりだった。その主因はヘッジファンドによる投機的売買である。グローバル・マクロ、CTA(商品投資顧問)といった顔馴染みに加え、イベント・ドリブン型の投機家たちがここぞとばかりに高速取引で利ザヤを稼ぐ投資手法を繰り出した。私が常々言っている「日々の価格の動きはノイズ」「ノイズを生み出しているのは“うる星★やつら”ならぬ“うぜぇ★やつら”」である。
彼らは「価格の変動こそ収益の機会」との前提に立ち、大量マネーやレバレッジの力を借りて自ら価格変動を起こし、それに追随してくる投機家たちをダシにして一本取ろう、というのが戦略である。日本市場では日経平均先物を使った取引が典型的であるが、米国市場でも同様の手法が連日繰り広げられている。
米国では年内に2回の利下げが行われ、政策金利は3.5~3.75%の水準に
今回のFOMCでは利下げの他に大きな注目点があった。それはFOMCの参加メンバーによる今後の政策金利の見通し、すなわちドットチャートの公表である。2025年は今回の利下げを含めてあと2回の利下げが行われ、年末には合計0.75%金利が低下。政策金利は3.50%~3.75%の水準になるとの見方が示された。3カ月ごとに見直されるが、前回の6月に公表したドットチャートでは「2025年に合計0.50%の利下げ」との前提だったため、利下げ幅は拡大。だが、「2026年の利下げは0.25%」との新たな見通しが期待外れの結果になった。これにより、債券市場では10年債が売られて利回りは前日より0.06%上昇の4.09%となった。
「利下げされたのに、どうして債券利回りは上昇するのか?」との疑問を持たれた投資家の方も多いのではないかと思う。先回りして債券を多めに買い込んでいた投資家が「期待外れ」を理由に持ち高調整のための債券売りを行ったのである。こうした事情にも精通していないと「えっ、何で?」とマーケットの動向が理解できないだろう。
4月のトランプ関税ショックで売った大手投信は目も当てられない状況に
NYダウ260ドル高の流れを受けて、9月18日の日本市場では日経平均が名実ともに初の4万5000円台乗せとなり、513円高の4万5303円にて引けた。4月のトランプ関税ショックというシステマティックリスクにおいて3万1136円まで下落していたのがウソのようだ。金融相場におけるシステマティックリスクは投資家をたびたび惑わせ「売ってはいけない場面で売る」という間違った投資行動を誘発しやすい。個人投資家のみならず機関投資家でも、ちゃんとした意識を持っていないと間違った行動に出る。5月6日のコラム「トランプ関税ショックに収束の兆し、システマティックリスクを乗り越えて」で大手投信のさわかみ投信についてコメントした。4月30日付け日経新聞で彼らは次のような全面広告を打った。
「現金比率を高めて、次の株価急落時に徹底的に買い向かいます」
「短期的にうまく立ち回るのではなく、長期的な視野で臨んでいきましょう」
これを受けて私は述べた「さわかみ投信は直近10年間のどの期間をとってもマーケットと同業他社に対して著しくボロ負け」「長期的な視野ならうまくいく、とハッタリをかましているのは大きな問題」「長期的なパフォーマンスは短期成績の積み重ねであり、短期的にうまくいっていない投信が長期的なパフォーマンスなど出せるはずもない」と。
大手メディアの報道で散見される金融相場への間違った認識に騙されるな
売ってはいけない場面で現金比率を一気に19.5%にまで高めた戦略は明らかに間違いである。「運用成績の悪いファンドはパフォーマンス悪化を恐れて株を売る」「反発局面でマーケットに追随することは難しく、今後もマーケットに負け続ける可能性が高い」「次の株価急落時に徹底的に買い向かいますとまで宣言しているが、次の株価急落時って果たしていつなのだろうか?」と述べた通りであり、今や日経平均は4万5000円台。マーケットに対してさらにボロ負けしている。同じ業界人として、プロとして恥ずかしい失態である。
もうひとつの違和感はメディアによる金融相場への間違った認識である。個人投資家の皆さんには日頃から「日経新聞のマーケット解説は真に受けない方がいいですよ」と話している。9月のWebセミナーでも取り上げた話題だ。9月7日の『史上最大級の不確実性バブル 株式市場の変調に備えを』(日経QUICKニュース編集委員 永井洋一)や9月18日の『日経平均株価、初の4万5000円台 消える「日本株ディスカウント」』((今堀祥和、ニューヨーク=竹内弘文)などがその典型例である。日経新聞は日本の株式市場の上昇が気に入らないようだ。欧米市場に比べてトップパフォーマーになったのも気に食わないらしい。金融相場本来のあるべき姿のマーケットに対してネガティブなバイアスのかかった情報を発信している。こういうメディアの論調にはダマされてはいけない。
金融相場は株価が最も上昇する相場。バリュエーションの拡大を楽しもう
そもそも金融相場はマーケットサイクルにおいて最も株価が上昇する相場だ。最も稼げる相場であり、最もテンバガーが生まれる相場、そして最もバリュエーションが拡大する相場のことを指す。だから、株価上昇に対して誤った解釈で警鐘を鳴らすのは間違っている。バリュエーションの拡大を楽しみつつ、バリュエーションがどこまで拡大するかを見極めるのが大事である。これは、来たるべき業績相場への備えとしてとても重要なことだ。「景気が良くない」が故の金融緩和でマーケットが上昇する金融相場に対し、好景気で業績好調なのに株価下落が往々にして見られるのが業績相場だ。この「業績」相場というのがクセ者で、個人投資家たちが最も被害を受けるのが業績相場だ。果たして皆さんは、分かっているだろうか?
さて、太田忠投資評価研究所とダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチ(DFR)がコラボレーションして投資助言を行っている「勝者のポートフォリオ」はおかげさまで快進撃が続いている。2021年10月にサービス開始以来、9月16日時点で累計パフォーマンスは+120.4%、昨年来+72.4%、年初来+30.6%とすべての期間においてマーケット指標を圧倒している。マーケット分析力と個別銘柄選択力で「市場に打ち克つ」を実践している成果が大きく出ているものと自負している。
 「勝者のポートフォリオ」の設定来パフォーマンスの推移と主要指数との比較
「勝者のポートフォリオ」の設定来パフォーマンスの推移と主要指数との比較
金融相場の波に乗るのは今からでも遅くない。セミナー録画を視聴しよう
「勝者のポートフォリオ」は日本株を中心とした個人投資家向けの投資助言サービスだ。毎週のマーケット解説・投資戦略のメルマガ配信に加え、毎月恒例のWebセミナー開催とスキルアップを目的とするスペシャル講義を提供している。
Webセミナーでは米連邦準備理事会(FRB)や日銀の金融政策、日米の景気動向、あるいは最近ではトランプ関税政策といったホットな話題を取り上げながら現状の投資戦略や株価上昇が期待できる個別銘柄の話、さらには参加者からのすべての質問に答えるQ&Aコーナーを設けて毎回2時間半ものロングランとなっている。毎回300名を超える参加者で盛り上がり、投資のヒントが満載である。
9月10日(水)20時より開催したセミナーのテーマは『FRBの利下げ再開で本格的金融相場到来へ』。株式市場は上昇しているのに資産運用がうまくいっていない個人投資家が多いとの印象を受ける。「どういう運用をすれば資産運用がうまくいくのか」を知りたい新規参加者も多かった。すでにアーカイブ録画が視聴可能であり、有料会員になればいつでも視聴できる。
スペシャル講義は投資スキルを身につける場として62本もの講義動画をリリースしている。個人投資家に必須のリスク管理、運用力を上げるためのマーケットサイクル投資法、恐怖指数の活用、システマティックリスクの対処法、ヘッジファンドの実態…など詳しく解説している。ぜひとも参考にしていただきたい。
●太田 忠 DFR投資助言者。ジャーディン・フレミング証券(現JPモルガン証券)などでおもに中小型株のアナリストとして活躍。国内外で6年間にわたり、ランキングトップを維持した。現在は、中小型株だけではなく、市場全体から割安株を見つけ出す、バリュー株ハンターとしてもDFRへのレポート提供による「勝者のポートフォリオ」メルマガ配信などで活躍。
国内外で6年連続アナリストランキング1位を獲得した、
トップアナリスト&ファンドマネジャーが
個人投資家だからこそ勝てる
「勝者のポートフォリオ」を提示する、
資産運用メルマガ&サロンが登場!
老後を不安なく過ごすための資産を自助努力で作らざるを得ない時代には資産運用の知識は不可欠。「勝者のポートフォリオ」は、投資の考え方とポートフォリオの提案を行なうメルマガ&会員サービス。週1回程度のメルマガ配信+ポートフォリオ提案とQ&Aも。登録後10日間は無料!