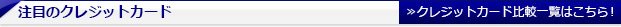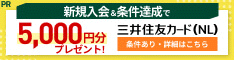今回は、普及が進む「キャッシュレス決済」について、改めて解説したいと思います。このところ「キャッシュレス決済」が幅広い世代に浸透し、「以前は『現金決済派』だったけれど、すっかり『キャッシュレス決済派』に転向した」という人も増えました。
復習しておくと、「キャッシュレス決済」とは、現金以外の決済手段で支払いをすることを指しています。具体的には、クレジットカード、電子マネー、デビットカード、スマホのコード決済などが、「キャッシュレス決済」の代表的な手段です。今や、現金以外の決済手段を持たない人は、少数派になっているかもしれませんね。
ただ、「キャッシュレス決済」は種類が多いため、どれを選ぶのが自分にとってベストなのか、結局よくわからない状態のまま、とりあえず手元にあるクレジットカードなどを使い続けている人も多そうです。そこで、ここからは「キャッシュレス決済」の現状や種類を整理するとともに、どんな人にどんな「キャッシュレス決済」が適しているのか考えていきましょう。
【※関連記事はこちら!】
⇒「キャッシュレス決済」おすすめ比較!「PayPay」や「LINE Pay」「楽天ペイ」など、主要な「スマホ決済」の還元率や利用可能なコンビニ、最新のキャンペーン情報を紹介!
決済の手段は「接触型」「非接触型」「コード決済」の3種類
それぞれのメリット・デメリットを紹介!
近年の「キャッシュレス決済」の普及を決定的に後押ししたのは、政府主導の「キャッシュレス・消費者還元事業」です。中小・小規模事業者が運営する店舗で「キャッシュレス決済」をした場合、最大5%の還元が受けられるというもので、2019年10月の消費税の増税に伴って施行されました。
【※関連記事はこちら!】
⇒「キャッシュレス決済」すると“2~5%”が還元される「ポイント還元事業」の中身を専門家がやさしく解説!「クレカ」や「スマホ決済」のお得なキャンペーン情報も
「キャッシュレス・消費者還元事業」は、増税による国民の負担の軽減に加え、東京オリンピックを見据えて決済の効率性を高めることで、インバウンド消費を喚起することを目的としていました。そのため、当初の期限は“東京オリンピック開催直前の2020年6月末まで”とされていたのですが、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う東京オリンピックの開催延期を受けて、延長される可能性が出てきています。同時に、還元率をアップすることなども議論されているようですが、2020年4月2日現在、先行き不透明な状況です。
ちなみに、今回の新型コロナウイルスの感染拡大の影響から、世界的に「キャッシュレス決済」の注目度は上がっています。不特定多数の人が触る現金に対して、衛生面を問題視する人が増えたからです。日本でも、同様の考えから「キャッシュレス決済」を選択する人は、確実に増えているものと思われます。
そんな「キャッシュレス決済」の種類ですが、「手段」と「お金を使うタイミング」という2つの視点で、9つに分類することができます。
| ■「キャッシュレス決済」は「手段」と「タイミング」で分類できる | ||||
| 決済のタイミング | ||||
| 前払い (プリペイド) |
即払い | 後払い (ポストペイ) |
||
| 決 済 手 段 |
接触型 (カード) |
●プリペイドカード (QUOカードなど) ●国際ブランド付き プリペイドカード |
●デビットカード (J-Debit) ●国際ブランド付き デビットカード |
●クレジットカード |
| 非接触型 (カード・スマホ) |
●電子マネー (Suica、WAON、 nanacoなど) |
●国際ブランド付き デビットカード (コンタクトレス決済 対応のもの) |
●Apple Pay ●電子マネー (VISAタッチやiD、QUICPay など、クレジットカードに 電子マネー) |
|
| コード決済 (スマホ) |
「LINE Pay」などは 銀行で事前にチャージ して前払いできる |
「J-Coin Pay」などは 銀行口座に紐付ける ことで即払いできる |
「楽天ペイ」などは クレジットカードに 紐付けて後払いできる |
|
| ※2020年4月2日時点。サービスによっては複数の手段を提供する場合もあり、連携対象次第で区分けが変わることもある。上の表は一例を紹介したもの。 | ||||
まずは、決済の「手段」のほうから見ていきましょう。決済の「手段」は、カードリーダーに何らかの形で接触させることによって決済する「接触型」、電子マネーのように、カードリーダーにかざすだけでOKの「非接触型(カードだけでなく、電子マネーなどを取り込んだスマホをかざす決済も含む)」、そして、スマホに表示させたコードを読み取ってもらう、あるいは店頭で提示されたQRコードを読み込むことで決済する「コード決済」があります。
「接触型」「非接触型」「コード決済」には、それぞれメリットとデメリットがあります。具体的には以下のとおりです。
「接触型」のメリット⇒長く使われてきた方法なので支払いの操作がわかりやすい。大手企業の運営する店舗などを中心に、使える場所が比較的多い。
「接触型」のデメリット⇒作りやすいので数が増えがち。スマホ決済ではないため、鞄から財布を探してカードを取り出す、といった手間からは解放されない(スマホカバーにカードを入れて使うなどの解決策はある)。
「非接触型」のメリット⇒操作性に優れている。基本的にお店の人にカードやスマホを渡さずに済むので、セキュリティの面でも安心感が強い。
「非接触型」のデメリット⇒店舗がカードを読み取れるリーダーを備えていないと使えない。また、スマホに電子マネーなどを取り込む場合、iPhoneだと“7”以降、Androidだと「おサイフケータイ」の機能付きの端末が必要となり、一定以上のスペックが求められる。また、端末ごとに対応サービスが若干異なる(iPhoneだとSuica、iD、QUICPay、Master、JCBなどに対応。AndroidだとSuica、WAON、nanaco、PASMOなどに対応)。よって、端末と非接触の対応サービスの組み合わせを把握する必要があり、最初の設定を難しく感じる可能性がある。
「コード決済」のメリット⇒コードを表示したり、読み取ったりするだけで使えて、高スペックなスマホでなくても利用できる。店舗の側からすると、導入の手間やコストが限定的なため、小規模な店舗でも導入しやすいのも特徴。
「コード決済」のデメリット⇒コードを表示させたり読み込んだりと、操作性はやや煩雑。使える場所がまだ限られているため、家庭の支払いのすべてを集約することは難しい。
【※関連記事はこちら!】
⇒「キャッシュレス・ポイント還元事業」でお得度がアップするクレジットカードの“還元上限額”や“還元方法”をまとめて解説! 消費増税後にお得になるカードとは?
決済のタイミングは「前払い」「即払い」「後払い」の3種類
それぞれのメリット・デメリットを紹介!
続いて、決済の「タイミング」ごとの特性を解説します。決済の「タイミング」は、事前にチャージした分だけお金が使える「前払い」、使ったらその都度、銀行口座からお金が落ちる「即払い」、一定期間に使った分のお金が、後でまとめて引き落とされる「後払い」があります。「接触型」で言うなら、「前払い」はプリペイドカード、「即払い」はデビットカード、「後払い」はクレジットカードとなります。
「前払い」「即払い」「後払い」のメリット・デメリットは以下のとおりです。
「前払い」のメリット⇒使い過ぎを予防できる。予算の管理をしやすい。
「前払い」のデメリット⇒いちいちチャージするのが面倒(オートチャージの設定ができる場合もあるが、この場合、結局使いすぎる恐れがある)。不正利用があった場合、いったんは自分の残高を失うことになる(カード会社から補償が受けられる場合でも、いったん支払って、後から返金される)。
「即払い」のメリット⇒使い過ぎを予防できる。
「即払い」のデメリット⇒銀行にお金がないときは使えない。不正利用があった場合、いったんは自分の残高を失うことになる(カード会社から補償が受けられる場合でも、いったん支払って、後から返金される)。
「後払い」のメリット⇒好きなときにお金を使いやすい。不正利用があった場合、引き落とし前に発覚することが多いため、一時的にでも自分の残高を失わずに済む。
「後払い」のデメリット⇒浪費を招きがち。借金が嫌いな人には不向き。
【※関連記事はこちら!】
⇒「クレジットマスター」を使ったクレジットカードの不正利用の手口や仕組みを解説! 他人のカード番号やセキュリティコード、有効期限を割り出す方法とは!?
「キャッシュレス決済」の初心者の人は
固定費をクレジットカードで支払うところから開始!
「キャッシュレス決済」の「手段」や「タイミング」ごとのメリット・デメリットを押さえたうえで、ここからはどんな人にどんな「キャッシュレス決済」が向いているか、具体的に考えていきたいと思います。
まず、「まだまだ現金決済が中心で、クレジットカードは持っているものの、あまり使わない」というような、「キャッシュレス決済」の初心者の場合。おすすめしたいのは、ひとまず手持ちのクレジットカードを、固定費の支払いに活用するところから始めることです。水道光熱費や通信費などを口座振替やコンビニ払いにしている場合は、クレジットカード払いに切り替えることを検討してみましょう。
ただし、口座振替にすることで割引が適用されている場合は、クレジットカード払いにしてクレジット会社のポイントをもらうのと、どちらがお得か計算してみてください。家族が多いなどの理由で、水道光熱費が1ヶ月5000円以上など、比較的高額になる場合は、クレジット会社によるポイントの還元率が1%以上の高還元カードを使うと、口座振替よりクレジットカード払いのほうが得する可能性が高くなります。
【※関連記事はこちら!】
⇒【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出! 全8部門の“2023年の最優秀カード”を詳しく解説!
現金払いを好む人は、「とにかく借金がイヤ」という場合が多いようです。それなら、普段の買い物においてはクレジットカードではなく、「前払い」や「即払い」タイプの決済手段を活用したいところ。具体的には、電子マネーなどのプリペイドカードや、デビットカードなどです。これらは、あらかじめチャージした金額や、口座に入っているお金しか使うことができないため、予算を管理しやすいのが特徴。もちろん、使った金額に応じてポイントも貯まり、店によってはキャッシュレス・消費者還元事業による還元も受けられるため、現金決済よりお得です。
ただ、プリペイドカードやデビットカードは固定費の支払いに使えないケースが多いため、固定費はクレジットカード、普段の買い物はプリペイドカードやデビットカードという具合に、使い分けるのがおすすめです。
「コード決済」初心者は身近で使えるもの一種類を選ぼう
中上級者なら複数利用してキャンペーンで得するのも◎
続いて、「クレジットカードや電子マネーは日常的に使っているけど、話題の『PayPay』などのコード決済もちょっと気になっている」というような、「キャッシュレス決済」をすでに取り入れている(ただし、最新の情報にはちょっと疎い)人の場合。この層は特に多いと思われますが、クレジットカードや電子マネーを日常的に使っていて、特に不便を感じていないのであれば、早急に新たな「キャッシュレス決済」を始める必然性はないでしょう。原則として、決済の手段は少数に絞っておいたほうが、お金の管理がしやすいものだからです。
「コード決済」は派手なキャンペーンのおかげで、特別お得なイメージがあるかもしれませんが、キャンペーン時のお得さは、ずっと継続するわけではありません。よって、ほかの「キャッシュレス決済」を普段から活用できているなら、「コード決済」にこだわる必然性はないでしょう。
とはいえ、今後「コード決済」はさらに普及していくと見られているので、興味があるなら、今のうちから始めるのも手ではあります。ひと口に「コード決済」と言っても、前払いタイプや即払いタイプ、後払いタイプと別れていて、仕組みが同一ではないので、最初から複数の「コード決済」に挑戦するのではなく、よく行く近所の店で導入されているものを一つ選んで始めてみるといいですね。
【※関連記事はこちら!】
⇒「スマホ決済」の専門家がおすすめするのは「楽天ペイ」と「d払い」の2つ!「スマホ決済」初心者が始めやすく、クレジットカードを紐づければ還元率が大幅アップ!
最後に、「ポイント還元率を気にしてクレジットカードなどを選んでおり、すでにコード決済も活用している」というような、「キャッシュレス決済」の中上級者の場合。特に今のスタイルを変える必要はありませんが、お金の情報にアンテナを張って、家計もしっかり管理できているのであれば、“決済手段は少数に絞る”という原則からあえて外れて、複数の「コード決済」を活用してみるのもよさそうです。「PayPay」や「楽天ペイ」、「LINE Pay」などの「コード決済」は、いずれもキャンペーンに意欲的であり、上手に使い分ければお得に買い物を楽しむことができるからです。
 オトクカレンダーには、「コード決済」のキャンペーン情報のほか、さまざまな提携店舗などのお得情報が掲載される。
オトクカレンダーには、「コード決済」のキャンペーン情報のほか、さまざまな提携店舗などのお得情報が掲載される。
どの「コード決済」がいつキャンペーンをやっているかを押さえるためには、オンライン家計簿サービスを提供している「Zaim」が一般に公開している「オトクカレンダー」が役に立ちます。「オトクカレンダー」を見れば各種「コード決済」のキャンペーン情報が一目瞭然。さらに、この「オトクカレンダー」を自分のGoogleカレンダーにインストールすると、より一層情報を拾いやすくなります。
ただ、キャンペーンをしていると、それほど必要のないものに対して「キャンペーンでお得だし、ま、いいか」とお金を使いがち。あくまで、欲しいものが先にあって、支払うときにどれが有利かを考える、というのが正しい順番なので、「キャッシュレス決済」の中上級者であっても、この大原則を忘れないようにしてください。
(取材/元山夏香)
【※関連記事はこちら!】
⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!
⇒定期預金の金利が高い銀行ランキング![2020年・夏]金利がメガバンクの100倍の「あおぞら銀行」など、「夏のボーナス」は高金利でお得な銀行に預けよう!
⇒まだ「つみたてNISA」を始められない人が抱えがちな“8つの疑問”をわかりやすく解説! 金融機関&投信の選び方や「iDeCo」との併用方法などにズバリ回答!
【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】
⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
【2026年2月16日時点・最新情報】
|
||||
| 還元率 | 年会費 (税込) |
ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |
カード フェイス |
◆三井住友カード(NL) |
||||
| 0.5~7.0% | 永年無料 | VISA Master |
iD |
 |
| 【三井住友カード(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない「ナンバーレス(NL)」なのが特徴(カード番号はアプリで確認可能)。通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※)する! さらに、獲得できる「Vポイント」は、さまざまな他社ポイントに交換できるほか、「1ポイント=1円分」としてカード利用額に充当できるなど、ポイントの汎用性が高いのも魅力! ※セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |
||||
| 【関連記事】 ◆「三井住友カード(NL)」は年会費無料+高還元+最短10秒発行の“三拍子”が揃ったおすすめカード!「対象コンビニ&飲食店で最大7%還元」特典は利用価値あり! ◆「三井住友カード(NL)」は、年会費無料&対象コンビニや飲食店で還元率7%のお得なクレジットカード!カード情報を記載していないのでセキュリティも抜群 |
||||
◆JCB CARD W(ダブル) |
||||
| 1.0~10.5% (※1) |
永年無料 | JCB | QUICPay |
 |
| 【JCB CARD W(ダブル)のおすすめポイント】 18歳~39歳以下の人だけが申し込める、年会費無料のうえに通常還元率1%のお得な高還元クレジットカード!(40歳以降も継続して保有可能)さらに「J-POINTパートナー」の「ポイントアップ登録」をすれば、マクドナルドやスターバックス、バーミヤン、ジョナサン、ドミノ・ピザ、吉野家などで10.5%還元になるうえに(※2)、Amazon.co.jpやセブン‐イレブンなどでも2%還元になるなど(※3)、さまざまな加盟店で高還元でポイントが貯まってお得! ※1 還元率は交換商品により異なる。※2「スターバックス カード」へのオンライン入金・オートチャージ、Starbucks eGift 、モバイルオーダーが対象で、店舗での利用分・入金分は対象外。※3 一部のセブン‐イレブンでは対象外。 |
||||
| 【関連記事】 ◆「JCB CARD W」は「楽天カード」などとほぼ同じ、年会費無料+還元率1~10.5%のJCBの入門カード!Amazonやスタバをよく利用する20~30代は注目! ◆「JCB CARD W」は、年会費無料で還元率1%以上のお得な高還元クレジットカード!「JCB CARD W」のメリット・デメリットを他のカードと比較して検証! ◆JCB CARD W(ダブル)のメリットを解説!「年会費無料」「常に還元率1.0%以上」「ポイントの使い勝手が良い」と三拍子そろった高還元クレジットカード! |
||||
◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |
||||
| 0.3~1.5% (※1) |
3万9600円 | AMEX | - |
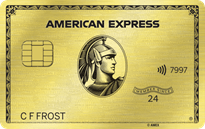 |
| 【アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードのおすすめポイント】 日本で最初に発行されたゴールドカード「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」の後継カードだけに、ステータス&付帯サービスは最高レベルで、カードが金属製という特別感もあって、一般的なゴールドカードとはケタ違い。たとえば、年間200万円(税込)以上を利用してカードを継続保有すると、国内40カ所以上の高級ホテルに無料宿泊できる「フリー・ステイ・ギフト」は、もはや一般的なプラチナカードすら凌駕するレベルの特典だ。さらに、高級レストランを2人以上で利用すると1人分が無料になる「ゴールド・ダイニング by 招待日和」や、世界1300カ所以上の空港ラウンジを年2回まで無料で利用できる「プライオリティ・パス」、最高補償額1億円の「海外旅行傷害保険」が付帯するなど、もはや「ゴールドカード」の枠組みを大きく飛び越えている。また、家族カードは2人目まで年会費無料でお得(3人目以降は年1万9800円・税込)。 ※貯まるポイントをマイルに交換した場合。1マイル=1.5円換算。 |
||||
| 【関連記事】 ◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードは“プラチナ”を超える“ゴールド”! 日本初のゴールドカードを受け継ぐ「新生ゴールド」を解説! ◆【アメリカン・エキスプレス・カードを一覧で比較】アメックスが発行する15枚のカードの年会費や特典、還元率を比較して、自分にピッタリの1枚を探そう! ◆アメックスの新規入会キャンペーンをまとめて紹介!「アメリカン・エキスプレス」の入会特典で、ポイントやマイルをお得に獲得しよう! |
||||
| 還元率 | 年会費 (税込) |
ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |
カード フェイス |
◆三井住友カード ゴールド(NL) |
||||
|
0.5~7.0% |
5500円 (ただし、年100万円以上の 利用で次年度から永年無料) |
VISA Master |
iD |
 |
| 【三井住友カード ゴールド(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない“ナンバーレス(NL)”のゴールドカード。年会費5500円(税込)だが、年間100万円を利用すると(※1)、次年度から年会費が“永年無料”になるうえに、1万ポイントが「継続特典」としてもらえるのが大きな魅力! さらに、通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード ゴールド(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※2)するなど、ポイントも貯まりやすくてお得! ※1 対象取引などの詳細は、三井住友カードの公式サイトで要確認。※2 セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |
||||
| 【関連記事】 ◆「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年100万円以上を使うと年会費が“永年無料”に! コンビニで7%還元、空港ラウンジや旅行保険などの特典も付帯してお得! ◆三井住友カード ゴールド(NL)のメリット・デメリットを解説! 同じく“実質”年会費が無料の「エポスゴールドカード」と付帯サービスなどを比較して魅力を解剖! |
||||
◆三菱UFJカード |
||||
| 0.5~7.0% (※1) |
永年無料 | VISA JCB Master AMEX |
- |
 |
| 【三菱UFJカードのおすすめポイント】 通常還元率は0.5%だが、セブン‐イレブンなどのコンビニのほか、オーケー、松屋、ピザハットオンライン、くら寿司、スシローなどでの利用分は還元率7%にアップするほか(※1)、カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定するなどの参加条件を満たしたうえで「MDCアプリのログイン」や「三菱UFJ銀行の住宅ローンの利用」といった条件を達成すると、対象店舗での利用分が最大20%グローバルポイント還元に!(※2)しかも、カードの利用で獲得できる「グローバルポイント」は、スマートフォンアプリ「MDCアプリ」を利用することで、さまざまなギフトカードに“即時交換”できるのもメリット! ※1 セブン‐イレブンや松屋などでは還元率7%。対象店舗によってはアメリカン・エキスプレスのカードは優遇対象外(予告なく内容を変更または終了する場合あり)。「1ポイント=5円相当」の商品に交換した場合の還元率。Apple PayはQUICPayでの利用が対象(Apple PayとQUICPayはMastercardまたはVisaのみ利用可能)。※2「カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定」「MDCアプリからエントリー」という2つの参加条件を満たすと、ポイントアップ条件の達成状況に応じて対象店舗での還元率が最大20%にアップ(AMEXブランドのみ一部加盟店が最大20%ポイント還元の対象外。最大20%ポイント還元には利用金額の上限など、各種条件・留意事項あり。詳細は遷移先の公式サイトを要確認)。 |
||||
| 【関連記事】 ◆「オーケー」「オオゼキ」「東武ストア」などのスーパーでも7%還元になる「三菱UFJカード」は主婦にもおすすめ! コンビニや飲食店だけでなくスーパーでもお得! |
||||
◆楽天カード |
||||
| 1.0~3.0% | 永年無料 | VISA JCB Master AMEX |
楽天Edy (楽天Edyへの チャージ分は 還元率0.5%) |
 |
| 【楽天カードのおすすめポイント】 楽天市場や楽天ブックス、楽天トラベルを利用している人はもちろん、楽天ユーザー以外にもおすすめの「年会費無料&高還元」クレジットカードの代表格。通常還元率は1.0%だが、楽天市場や楽天ブックスでは最低でも還元率が3.0%以上に! また、「楽天ポイントカード」や電子マネーの「楽天Edy」との併用で、楽天グループ以外でも還元率は1.5~2.0%以上になる! ゴールドカードの「楽天プレミアムカード」も格安の年会費で「プライオリティ・パス」がゲットできてコスパ最強! |
||||
| 【関連記事】 ◆【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2023年の最優秀カード”を詳しく解説!(最優秀メインカード部門) ◆「楽天ポイント」のお得な貯め方を解説!【2024年版】「楽天カード+楽天銀行+楽天証券」など、楽天市場のSPUでお得にポイントが貯まるサービスを活用しよう! |
||||