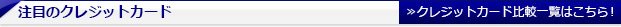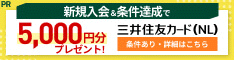人が亡くなると、遺族はさまざまな手続きに追われることになり、しばらくは故人を偲ぶ間もないほど慌ただしくなる――とは、よく耳にする話です。とはいえ、具体的にどんな手続きが発生するのか、断片的にしか知らない人も多いのではないでしょうか。
かくいう私自身、つい最近まで遺族の大変さは噂に聞くばかりで、実体験したことがありませんでした。ところが、先日、実父が亡くなり、母をサポートして各種手続きを引き受けることに。いざ取り組んでみると、遺族が行わなければならない手続きは、たしかに山のようにあり、噂に違わぬ大変さでした。
ファイナンシャル・プランナーという仕事柄、私にある程度のノウハウがあったことに加え、父は比較的シンプルな生活スタイルで、手続きすべき事案がそれほど多くなかったにもかかわらず、一段落するまでに要した期間は約3週間。これでも短いほうで、手続きすべき事案が多い場合など、家族が亡くなって1年以上経過して、ようやく落ち着いた――といったケースも珍しくないようです。
家族が亡くなって気持ちが落ち着かないなかで、手続きに忙殺されると、心も体も弱り切ってしまうかもしれません。元気なときはあまり考えたくないことですが、生前から自分たちの死後のことについて家族で話し合い、できる準備はしておくのが望ましいでしょう。
そこで今回は、家族が亡くなったときにどんな手続きがあるかをリストアップするとともに、手続きをスムーズに進めるため、生前から準備しておけることを紹介します。
家族が亡くなったら必要な手続きをリストで紹介!
葬儀後からは、解約・名義変更などの手続きが山積みに!
人が亡くなると、すぐさま手続きラッシュがスタートします。父が亡くなってから、わが家(もっとも近しい遺族は母・私を含む子ども3人)で行った手続きを時系列順に並べると、以下のようになります。
【家族が亡くなってから行った手続きの一覧】
①「死亡届」「死亡診断書」「火葬許可申立書」を役所に提出⇒「火葬許可書」の発行
②火葬⇒「埋葬許可書」の発行
③父の利用していた銀行、カードと引き落とし先、自宅を管轄する法務局のリスト化⇒必要書類の概要を確認
④各人の必要な公的書類の取り寄せ
⑤健康保険証の返却、埋葬費申請、払い済み保険料の返金申請
⑥未支給年金、遺族年金の申請など
⑦金融機関への相続手続き申請、通信会社への契約変更など
⑧自宅所有権移転登記
順に説明していきましょう。
まず、家族が亡くなったら、臨終に立ち会った医師、あるいは死亡を確認した医師から、「死亡診断書(死体検案書)」を交付してもらいます。役所に提出する「死亡届」は、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)という体裁になっているため、必然的に同時に提出することになります。また、一緒に「火葬許可申立書」も提出します。火葬の許可がないと荼毘に付すことができないため、これらの一連の手続きは、極力速やかに進めなければなりません。
わが家の場合もそうでしたが、一般的に死亡届や火葬許可申立書などの提出は、葬儀社が代行してくれることが多いようです。ただでさえ家族が亡くなって混乱しているなか、遺族は葬儀の打ち合わせをしたり、葬儀に向けて親戚や故人の友人・知人に連絡したりと、やることが山積みです。葬儀社は、葬儀前後の手続きのプロなので、頼れるところは頼ってしまっていいと思いますし、わからないことは何でも質問するといいでしょう。
リストの③以降は、葬儀が終わってからの手続きです。
真っ先に取り掛かったのが、父の利用していた金融機関やカード会社、公共料金を始めとする各種引き落とし先、法務局(不動産の所有権移転の登記をするため)など、連絡をとらなければならない相手をリスト化することでした。
口座の名義人が亡くなったときは、遺族がその旨を金融機関に連絡しなければなりません。連絡をすると、すぐにその口座は凍結されます。逆に、連絡をしなければ口座が凍結されないことも多いですが、故人の口座のお金を無断で使うと、相続上の問題に発展し、場合によっては使い込みの疑いをかけられるため、避けてください。
クレジットカードも同様で、遺族がクレジットカード会社に連絡をしなければ、故人のカードが自動的に解約されることは、通常はありません。ただ、名義人以外が勝手に使うのは規約違反にあたりますし、故人名義の銀行口座のお金を使う場合と同様、相続上の問題に発展しかねないので好ましくありません。
故人名義で毎月引き落としになっていた公共料金や携帯電話代、インターネット利用料などは、名義や支払い方法の変更、あるいは解約などの手続きが必要になります。場合によっては、故人がサブスクのサービスを色々と利用していて、遺族がそれを把握できていないことも。故人がどんなことにお金を使っていたかよくわからないときは、通帳やカード利用明細などを確認する手間も生じます。
手続きで必要になる戸籍謄本などの原本は使い回せる!
費用の節約のためにも、必要書類の情報を整理しよう
父が亡くなってからわが家で行った手続きを、もう一度以下に紹介しておきます。
【家族が亡くなってから行った手続きの一覧】
①「死亡届」「死亡診断書」「火葬許可申立書」を役所に提出⇒「火葬許可書」の発行
②火葬⇒「埋葬許可書」の発行
③父の利用していた銀行、カードと引き落とし先、自宅を管轄する法務局のリスト化⇒必要書類の概要を確認
④各人の必要な公的書類の取り寄せ
⑤健康保険証の返却、埋葬費申請、払い済み保険料の返金申請
⑥未支給年金、遺族年金の申請など
⑦金融機関への相続手続き申請、通信会社への契約変更など
⑧自宅所有権移転登記
③にあるように、連絡すべき関係各所のリストができたら、解約や名義変更などの手続きをするうえで、どんな書類が必要かを確認していきます。ネットで調べられる場合もありますが、わからないときは電話をして聞くのが早いです。手続きをする都度、どんな書類が必要か調べるよりは、一気に調べて一気に集めたほうが効率的です。
手続きをするうえで必要になったおもな書類は、以下のとおりです。
【各種手続きで必要になった書類一覧(※わが家の場合。ケースごとに変わります)】
①被相続人(父)に関する書類:生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本)・住民票の除票・死亡診断書・年金証書・固定資産税評価証明書
②代表的な相続人(母)に関する書類:戸籍謄本・印鑑証明書・住民票・年金証書
③その他の相続人(子)に関する書類:戸籍謄本・印鑑証明書(※わが家では使いませんでしたが、住民票が必要になることもよくあります)
ほとんどの手続きで必要になったのが「戸籍謄本(除籍謄本)」です。亡くなった人の“生まれてから亡くなるまで”の戸籍謄本(除籍謄本)を取得していくと、結構な数になるケースもよくあります。発行には、通常の戸籍謄本で1通450円、除籍謄本(改製原戸籍謄本)で1通750円の手数料がかかるほか、遠方から取り寄せるときには郵送費もかかるため、「必要書類を1セット揃えるだけで、数千円もかかってビックリ」といった状況になりがちです。
手続き時に提出した戸籍謄本などの原本は、手続き終了後に返却してもらえる場合がほとんどです。返却のタイミングは提出先によって異なる(その場で返してもらえることもあれば、後日郵送のこともある)ので、関係各所に必要書類について確認するとき、原本をどのタイミングで返却してもらえるかも確認するのがベスト。すぐ返却されるところから順に手続きをしていけば、書類を使い回せるので、費用を節約できます。
書類を集めたら、後は順々に提出していきます。⑤の健康保険関係の手続きは、亡くなった日から14日以内(国民健康保険の場合)に行うことになっているほか、⑥の年金関係の手続きも、なるべく速やかに行うことが求められるので、忘れないように注意しておく必要があります。
生前から金融機関や引落とし先などの情報をリスト化しておくと、
遺族の負担を大幅に減少させることができる!
以上、家族が亡くなってから遺族が行う一連の手続きを、大まかに紹介しました。
わが家の場合、父は生活スタイルがシンプルだったうえに、父名義の金融機関や支払先などの情報は、母が漏れなく把握していました。そのため、かなり効率的に、短期間で作業を進めることができたわけですが、それでも終わってみての感想は「本当に大変だった」というもの。複雑な相続などの手続きが発生するケースなどでは、なおさら大変なことになるのは間違いないでしょう。
また、最近はネット銀行やネット証券を利用していたり、ネットでさまざまなサブスクのサービスを利用していたりする人も多いはずです。そして、それを家族に伝えていないケースもあるかもしれません。
パソコンやスマホの中にすべての情報があって、それらのパスワードを自分自身しかわからないようにしている場合、その人が突然亡くなったら、遺族が途方に暮れるリスクがあります。ネット銀行などのID・パスワードも、遺族がわからない場合は、やはり余計な手間が発生することになるでしょう。
こうした“デジタル遺品”のことも考えると、自分が「どんな金融機関を使っていて、ID・パスワードは何か」「クレジットカードは何を使っているか」「どんな引き落としがあるか」といった情報は、遺された家族が見つけやすい形で、生前のうちにリスト化しておいたほうがよさそうです。紙に書いておくのもいいですし、パソコンやスマホの中にデータを保存するなら、パソコン、スマホのパスワードをどこかに明記しておくといいかもしれません。
こうした準備を進めつつ、使っていないクレジットカードを整理したり、保険の内容を確認したりするのもおすすめです。手間はかかりますが、遺族の不安を解消し、安心感を得ることにもつながると思いますので、ぜひ挑戦してみてください。
(取材/元山夏香)
一級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士。会社員だった26歳のとき、貯蓄80万円でありながら自宅用としてマンションを衝動買い。物件価格以外にも費用がかかることを知り、あわててお金の勉強と貯蓄を開始。年間貯蓄額を一年で6倍まで増やす。その後、自身の体験を活かしてマンション販売会社に転職。年間売上一位の実績を上げる。2013年、ファイナンシャル・プランナーとして独立。著書は『超ど素人がはじめる資産運用』(翔泳社)、『デキる女は「抜け目」ない』(あさ出版)、『ケチケチせずにお金が貯まる法見つけました!』(王様文庫)など多数。日常の記録にお金の情報を織り交ぜる「FUROUCHI vlog」を更新中⇒https://www.youtube.com/c/FUROUCHIvlog/
【※関連記事はこちら!】
⇒【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2022年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2022年の最優秀カード”を詳しく解説!
⇒【定期預金の金利を徹底比較!】定期預金金利の高さで選ぶ!おすすめネット銀行ランキング!
⇒まだ「つみたてNISA」を始められない人が抱えがちな“8つの疑問”をわかりやすく解説! 金融機関&投信の選び方や「iDeCo」との併用方法などにズバリ回答!
【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】
⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
【2026年2月1日時点・最新情報】
|
||||
| 還元率 | 年会費 (税込) |
ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |
カード フェイス |
◆三井住友カード(NL) |
||||
| 0.5~7.0% | 永年無料 | VISA Master |
iD |
 |
| 【三井住友カード(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない「ナンバーレス(NL)」なのが特徴(カード番号はアプリで確認可能)。通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※)する! さらに、獲得できる「Vポイント」は、さまざまな他社ポイントに交換できるほか、「1ポイント=1円分」としてカード利用額に充当できるなど、ポイントの汎用性が高いのも魅力! ※セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |
||||
| 【関連記事】 ◆「三井住友カード(NL)」は年会費無料+高還元+最短10秒発行の“三拍子”が揃ったおすすめカード!「対象コンビニ&飲食店で最大7%還元」特典は利用価値あり! ◆「三井住友カード(NL)」は、年会費無料&対象コンビニや飲食店で還元率7%のお得なクレジットカード!カード情報を記載していないのでセキュリティも抜群 |
||||
◆JCB CARD W(ダブル) |
||||
| 1.0~10.5% (※) |
永年無料 | JCB | QUICPay |
 |
| 【JCB CARD W(ダブル)のおすすめポイント】 18歳~39歳の人だけが申し込める、年会費無料のうえに通常還元率1%のお得な高還元クレジットカード!(40歳以降も継続して保有可能)さらに「ORIGINAL SERIESパートナー加盟店」の「ポイントアップ登録(無料)」をすれば、Amazonやセブン‐イレブンなどでは還元率2%、スターバックスでは「スターバックスカード」へのチャージで還元率5.5%、「Starbucks eGift」の購入で還元率10.5%に! ※還元率は交換商品により異なる。 |
||||
| 【関連記事】 ◆「JCB CARD W」は「楽天カード」などとほぼ同じ、年会費無料+還元率1~10.5%のJCBの入門カード!Amazonやスタバをよく利用する20~30代は注目! ◆「JCB CARD W」は、年会費無料で還元率1%以上のお得な高還元クレジットカード!「JCB CARD W」のメリット・デメリットを他のカードと比較して検証! ◆JCB CARD W(ダブル)のメリットを解説!「年会費無料」「常に還元率1.0%以上」「ポイントの使い勝手が良い」と三拍子そろった高還元クレジットカード! |
||||
◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |
||||
| 0.3~1.5% (※1) |
3万9600円 | AMEX | - |
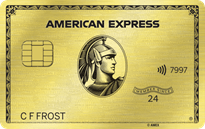 |
| 【アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードのおすすめポイント】 日本で最初に発行されたゴールドカード「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」の後継カードだけに、ステータス&付帯サービスは最高レベルで、カードが金属製という特別感もあって、一般的なゴールドカードとはケタ違い。たとえば、年間200万円(税込)以上を利用してカードを継続保有すると、国内40カ所以上の高級ホテルに無料宿泊できる「フリー・ステイ・ギフト」は、もはや一般的なプラチナカードすら凌駕するレベルの特典だ。さらに、高級レストランを2人以上で利用すると1人分が無料になる「ゴールド・ダイニング by 招待日和」や、世界1300カ所以上の空港ラウンジを年2回まで無料で利用できる「プライオリティ・パス」、最高補償額1億円の「海外旅行傷害保険」が付帯するなど、もはや「ゴールドカード」の枠組みを大きく飛び越えている。また、家族カードは2人目まで年会費無料でお得(3人目以降は年1万9800円・税込)。 ※貯まるポイントをマイルに交換した場合。1マイル=1.5円換算。 |
||||
| 【関連記事】 ◆アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カードは“プラチナ”を超える“ゴールド”! 日本初のゴールドカードを受け継ぐ「新生ゴールド」を解説! ◆【アメリカン・エキスプレス・カードを一覧で比較】アメックスが発行する15枚のカードの年会費や特典、還元率を比較して、自分にピッタリの1枚を探そう! ◆アメックスの新規入会キャンペーンをまとめて紹介!「アメリカン・エキスプレス」の入会特典で、ポイントやマイルをお得に獲得しよう! |
||||
| 還元率 | 年会費 (税込) |
ブランド | 電子マネー対応 (ポイント付与対象) |
カード フェイス |
◆三井住友カード ゴールド(NL) |
||||
|
0.5~7.0% |
5500円 (ただし、年100万円以上の 利用で次年度から永年無料) |
VISA Master |
iD |
 |
| 【三井住友カード ゴールド(NL)のおすすめポイント】 券面にカード番号が記載されていない“ナンバーレス(NL)”のゴールドカード。年会費5500円(税込)だが、年間100万円を利用すると(※1)、次年度から年会費が“永年無料”になるうえに、1万ポイントが「継続特典」としてもらえるのが大きな魅力! さらに、通常還元率は0.5%と一般的なクレジットカードと同等だが、スマートフォンに「三井住友カード ゴールド(NL)」を登録して「Visaのタッチ決済」や「Mastercardタッチ決済」を利用、またはモバイルオーダーで支払えば、セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルド、サイゼリヤ、バーミヤンなど、対象のコンビニや飲食店では還元率7%に大幅アップ(※2)するなど、ポイントも貯まりやすくてお得! ※1 対象取引などの詳細は、三井住友カードの公式サイトで要確認。※2 セブン‐イレブン、ローソン、マクドナルドなどの対象のコンビニ・飲食店で、スマートフォンでのVisaのタッチ決済やMastercardタッチ決済、またはモバイルオーダーを利用すると7%還元(「1ポイント=1円相当」のポイントや景品などに交換した場合の還元率(通常獲得ポイント分を含む)。一部店舗および一定金額を超える支払いでは指定の決済方法を利用できない場合、または指定のポイント還元にならない場合あり。カード現物のタッチ決済、iD、カードの差し込み、磁気取引による決済は7%還元の対象外。Google PayやSamsung WalletではMastercardタッチ決済は利用不可。スマホのタッチ決済の対象店舗とモバイルオーダーの対象店舗は異なる。詳しくはサービス詳細ページを要確認。) |
||||
| 【関連記事】 ◆「三井住友カード ゴールド(NL)」は、年100万円以上を使うと年会費が“永年無料”に! コンビニで7%還元、空港ラウンジや旅行保険などの特典も付帯してお得! ◆三井住友カード ゴールド(NL)のメリット・デメリットを解説! 同じく“実質”年会費が無料の「エポスゴールドカード」と付帯サービスなどを比較して魅力を解剖! |
||||
◆三菱UFJカード |
||||
| 0.5~7.0% (※1) |
永年無料 | VISA JCB Master AMEX |
- |
 |
| 【三菱UFJカードのおすすめポイント】 通常還元率は0.5%だが、セブン‐イレブンなどのコンビニのほか、オーケー、松屋、ピザハットオンライン、くら寿司、スシローなどでの利用分は還元率7%にアップするほか(※1)、カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定するなどの参加条件を満たしたうえで「MDCアプリのログイン」や「三菱UFJ銀行の住宅ローンの利用」といった条件を達成すると、対象店舗での利用分が最大20%グローバルポイント還元に!(※2)しかも、カードの利用で獲得できる「グローバルポイント」は、スマートフォンアプリ「MDCアプリ」を利用することで、さまざまなギフトカードに“即時交換”できるのもメリット! ※1 セブン‐イレブンや松屋などでは還元率7%。対象店舗によってはアメリカン・エキスプレスのカードは優遇対象外(予告なく内容を変更または終了する場合あり)。「1ポイント=5円相当」の商品に交換した場合の還元率。Apple PayはQUICPayでの利用が対象(Apple PayとQUICPayはMastercardまたはVisaのみ利用可能)。※2「カード代金の支払口座を三菱UFJ銀行に設定」「MDCアプリからエントリー」という2つの参加条件を満たすと、ポイントアップ条件の達成状況に応じて対象店舗での還元率が最大20%にアップ(AMEXブランドのみ一部加盟店が最大20%ポイント還元の対象外。最大20%ポイント還元には利用金額の上限など、各種条件・留意事項あり。詳細は遷移先の公式サイトを要確認)。 |
||||
| 【関連記事】 ◆「オーケー」「オオゼキ」「東武ストア」などのスーパーでも7%還元になる「三菱UFJカード」は主婦にもおすすめ! コンビニや飲食店だけでなくスーパーでもお得! |
||||
◆楽天カード |
||||
| 1.0~3.0% | 永年無料 | VISA JCB Master AMEX |
楽天Edy (楽天Edyへの チャージ分は 還元率0.5%) |
 |
| 【楽天カードのおすすめポイント】 楽天市場や楽天ブックス、楽天トラベルを利用している人はもちろん、楽天ユーザー以外にもおすすめの「年会費無料&高還元」クレジットカードの代表格。通常還元率は1.0%だが、楽天市場や楽天ブックスでは最低でも還元率が3.0%以上に! また、「楽天ポイントカード」や電子マネーの「楽天Edy」との併用で、楽天グループ以外でも還元率は1.5~2.0%以上になる! ゴールドカードの「楽天プレミアムカード」も格安の年会費で「プライオリティ・パス」がゲットできてコスパ最強! |
||||
| 【関連記事】 ◆【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2023年の最優秀カード”を詳しく解説!(最優秀メインカード部門) ◆「楽天ポイント」のお得な貯め方を解説!【2024年版】「楽天カード+楽天銀行+楽天証券」など、楽天市場のSPUでお得にポイントが貯まるサービスを活用しよう! |
||||