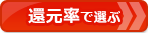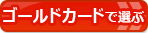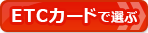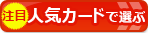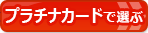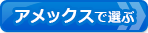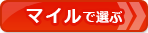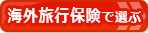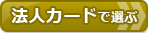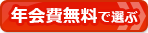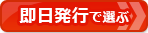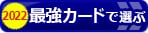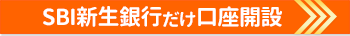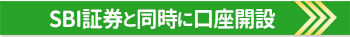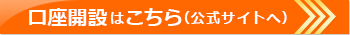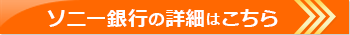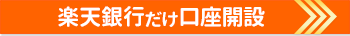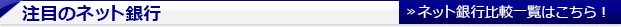2018年は食卓に欠かせない食品・飲料が値上げされている!
今回は「食費」の節約がテーマです。
近年、さまざまな食品の価格が、じわじわと上昇しています。単純に商品価格が上がるだけでなく、価格はそのままでも内容量が減る形で、値上げが行われる例も増えています。その一方で、サラリーマンの給与水準は、大幅に上昇しているわけではないので、多くの家庭において「エンゲル係数(消費支出に占める食費の割合)」が高くなってきている、との指摘もあります。
【※「食費の節約」の関連記事はこちら!】
⇒食費の節約で目指すのは、世帯月収の15%以内!予算の決め方、使い方から買い物に行く前の準備まで簡単に実行できる、具体的な食費節約のコツを伝授!
⇒食費を大幅に減らすことができた簡単な節約術とは?多忙な人、自炊をしない人でもネットスーパーを活用することで、便利に、簡単に節約できる!
それでは、具体的にどんな食品が値上げされているのでしょうか。一例は、以下のとおりです。
【2018年に値上げされた(または、これから値上げ予定の)食品】
●小麦粉
●冷凍食品(冷凍うどん、お好み焼き、たこ焼き)
●パックご飯
●米菓
●納豆
●アイスクリーム
●ヨーグルト
●ビール
●ワイン
●コーヒー
どれも生活に欠かせない食品・飲料ばかりですが、多くの人にとって、特にインパクトが大きいのは「小麦粉」の値上げではないでしょうか。すでに、この6~7月から値上げされており、当然ながら、パンなどの小麦粉を使う製品も、値上げの対象となっています。
ちなみに、パン以外にもコーヒーやヨーグルト、納豆といった、朝の食卓に上りやすい食品・飲料が、軒並み値上げされているのも特徴的です。いつのまにか“普段の朝食”がコスト高になってしまった、というご家庭も急増しているかもしれません。
お酒好きの人にとっては、ビールやワインの値上げも痛手でしょう。なかでも、ワイン価格の上昇は顕著です。原材料価格の高騰や世界的なワイン価格の上昇を背景として、この4月よりサントリーなどの大手メーカーが、輸入ワインや国産ワインの一部を、従来より3~6%値上げしています。
「天丼てんや」など、外食産業も続々と値上げを実施!
こうした値上げは、もちろん外食産業にも多大な影響を及ぼしており、すでに提供メニューの値上げに踏み切っている企業もあります。たとえば、天丼てんやでは、2018年1月から主力商品を値上げしていますが、その理由として原材料価格の高騰、人件費の高騰、物流コストの上昇を挙げています。
【※関連記事はこちら!】
⇒ケンタッキーフライドチキンが30%オフになる日は?毎月○日に天丼てんや、丸亀製麺で得する方法と年1回の天下一品、ロッテリアのお得な日にも注目!
天丼てんやが値上げの理由として挙げている「原材料価格の高騰、人件費の高騰、物流コストの上昇」という3つの要素は、いずれも一時的なものではなく、長期的に続いていくものと見なされています。つまり、今後も原則として、値上げ基調は続いていくことが予想されるのです。
さらには、2019年10月から消費税の引き上げも予定されており、家計にのしかかる重圧は、ますます強まることになります。
こうした状況を踏まえると、現時点で「食費が高いと感じている」「まだあまり節約しているとは言えず、削りどころがありそう」という人は、何らかの対策を講じたほうがいいでしょう。
出費の把握と予算決めをして、買い物の仕方を調整してみよう
それでは、これから食費を節約するにあたって、まずは何から始めればいいのでしょうか?
基本的な話になりますが、「月々の食費の予算」を決めておらず、食費に毎月いくら使っているかわかっていない場合は、出費を把握することが先決です。食材を買ったら必ずレシートをもらい、金額をノートや手帳などに書きとめ、1カ月にどれくらい使っているか把握したほうがいいでしょう。必ずしも、きっちり家計簿をつけなくてもOKです。
1カ月間で使っている金額が大体わかったら、そこから“守れそうな予算”を設定します。まったく節約せずに月8万円なのだとしたら、節約を意識して7万5000円の予算に食費を収める――といった具合です。予算を余裕で守れるようになったら、少しずつ厳しめに予算設定を変更していくといいでしょう。
予算を守るにあたって重要なのは、これまた当たり前の話ですが、ムダなものを買わないことです。買った食材は、必ず使い切るように心掛けたいもの。しかし、これができていない人はかなり多いようで、日本における“食品ロス(食べ残しなど)”は膨大な量に及びます。その量がどれくらいかと言えば、国民1人ひとりが毎日「ご飯1杯分程度」の食材をムダにしているのと、大体同じくらいなのだそうです。
経験則ですが、食材をムダにしがちな人は、日頃からまとめ買いをしているケースが多いと感じます。週末にまとめ買いをしたり、宅配システムやネットスーパーなどを利用してまとめ買いをしたりする人は、今の時代、多数派だと思われます。
しかし、まとめ買いをして食材をムダなく使い切るためには、高い計画性が求められます。また、冷蔵庫を上手に整理整頓するスキルも必要です。冷蔵庫がパンパンになるほど買い物をして、庫内に何が入っているか忘れてしまい、結果的に食材をダメにしてしまった、という経験がある人も多いのではないでしょうか。
定期的な宅配も、とりわけ共働きなどで食事の予定が変わることの多い家庭では、予定どおりに食材を消費できないこともありがち。毎回、使いきれない食材が出てしまう場合は、その宅配システムが生活に合っていない可能性が高いので、いったん止めることを検討したほうがベターでしょう。
まとめ買いをやめてしょっちゅう買い物に行くのは大変ですが、目先で必要なものだけを買う方式にすれば、冷蔵庫に空きスペースができて、食材の管理は格段にしやすくなるはずです。
ほかにも、食費のムダをなくすためにできる工夫はあります。
「チラシアプリ」の活用で安売り情報をチェック!
まず、いつも買い物する場所から見直してみましょう。
たとえば、会社帰りなどに、ついコンビニに立ち寄って、お菓子や飲み物などを買ってしまう人も少なくないかもしれません。しかし、コンビニは原則としてモノを定価で売るところ。同じものが、大型スーパーなら割安価格で買える例は多いです。コンビニやデパ地下、一部の高級スーパーなどでは、基本的に買い物しない、といったルールを決めてみるのもいいかもしれません。
また、各種アプリを活用するのもおすすめです。
たとえば、「トクバイ」というアプリは、地元のスーパーやドラッグストアなどの特売情報をチェックできる優れもの。買い物に出かける前に、事前にチェックする習慣にすると、お得に買い物ができます。
また、「Shufoo!」は、近所のスーパーなどのチラシをチェックできるアプリで、こちらもやはり特売情報をキャッチするのに便利。会員登録して利用するごとにポイントを貯めることができます。
 チラシアプリ「トクバイ」とチラシサイト「Shofoo!」は、ともに近所のスーパーやドラッグストアなどのお得情報をチェックできて、食費節約に頼れる存在。
チラシアプリ「トクバイ」とチラシサイト「Shofoo!」は、ともに近所のスーパーやドラッグストアなどのお得情報をチェックできて、食費節約に頼れる存在。拡大画像表示
スーパーのプライベートブランドや冷凍食品に注目
いつも買っている定番品を見直してみるのもおすすめです。誰しも、納豆はこのブランド、牛乳はこのブランドなどと、こだわっているものがあるのではないかと思いますが、それをPB(プライベートブランド)製品に替えることで、節約できる場合があります。
セブンアンドアイホールディングスの「セブンプレミアム」やイオンの「トップバリュ」など、大手スーパーのオリジナルPB製品は、メーカー製品(ナショナル・ブランド)に比べると価格が安く設定されています。これは、問屋を通さず直接小売店が買い取り、商品パッケージにロゴを入れて、特別な宣伝をかけないといった企業努力のなせる業です。
PB製品というと、品質が気になる人も多いようですが、メーカー製品に企業ロゴをつけたOEM製品も多く、実質的にクオリティはメーカー製品と遜色ありません。
また、食品購入の際にぜひ選択肢に入れたいのが、冷凍食品です。ひと口に冷凍食品といっても、小麦粉を多く使う冷凍うどんやお好み焼き、たこ焼きなど、一部商品は値上がり傾向にありますが、ここでおすすめしたいのは、冷凍ブロッコリーやスライス玉ねぎなどの冷凍野菜です。
日常的に料理をする方は、業務用の安売りスーパーなどで、冷凍野菜の大型パックをぜひチェックしてみてください。冷凍野菜というと、洗浄やカットなどの下処理がされているぶん、割高なイメージを持つ人も多いですが、実際には生野菜よりも安くつくものもたくさんあります。保存がきくため、野菜が高い時期に上手に取り入れると、食費を安く抑えつつ、十分に野菜を摂ることができます。
「ふるさと納税」で食品をお得にゲットする手も!
今や常識になりつつありますが、「ふるさと納税」を活用するのも、楽しくムリなくできる食費の節約方法としておすすめです。
ふるさと納税では、日頃なかなか買わないぜいたく品を返礼品として受け取る人も多いですが、節約という観点で考えるなら、おすすめは「お米」です。寄付する日を調節し、毎月お米が届くようにすれば、家計に占めるお米代を大幅に減らすことも可能です。
【※関連記事はこちら!】
⇒【ふるさと納税】お米がもらえる自治体ランキング!(2018年度版)人気の「お米」がもらえる自治体を比較して、コスパ最強のおすすめの自治体を発表!
また、前述したように、ビールやワインなどのお酒、アイスクリームなども値上がりしているので、お酒をよく飲む人やデザート好きな人も、ふるさと納税を活用してみるといいでしょう。
【※関連記事はこちら!】
⇒【2017年度版】お得な「ふるさと納税」ランキング~ビール編~特産品でもらえる「ビール」で得する自治体は?
家族の健康や日々の生活の満足度に直接関わるだけに、食費はただ節約して安く抑えればいいというものではありません。情報をチェックして、できるだけ底値で購入すること、無理やムダのない献立で食品ロスを防ぐことを意識して、おいしくお得に食費を節約することを心がけてください。
(取材/麻宮しま)
【※「ふるさと納税」するなら、このサイトがお得!】
⇒ふるさと納税の8大関連サイトを徹底比較!最も便利なサイトはどこ?取扱い自治体数や特典は?ザイがおすすめするサイトはここだ!
【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】
⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
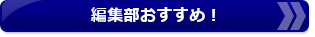 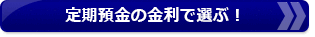 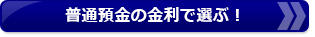 |
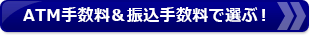 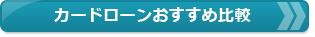 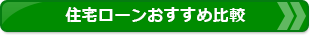 |
| 【2026年2月16日時点】 ■編集部おすすめのネット銀行はこちら! |
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆SBI新生銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.50% (※1) |
0.85% (※2) |
1.00% | 1.20% |
| 【SBI新生銀行のおすすめポイント】 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用すると普通預金金利が0.50%に大幅アップ! しかも「SBIハイパー預金」を利用すると「ステップアッププログラム」のステージが最上位の「ダイヤモンド」になり、提携コンビニATMの出金手数料が何回でも無料、他行あて振込手数料が月10回まで無料になる特典なども受けられてお得! ちなみに「SBIハイパー預金」を利用したからといって、投資などをする必要はないので安心しよう。そのほか、新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」なら、3カ月もの定期預金の金利が大幅アップ! また、他行からの振込入金などで現金がもらえる「キャッシュプレゼントプログラム」もお得。 ※1 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用した場合の金利。※2 新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【SBI新生銀行の金利・手数料・メリットは?】SBI証券との口座連携「SBIハイパー預金」の利用で、普通預金金利アップ&振込手数料が月10回まで無料! |
|||
| ◆あおぞら銀行 BANK ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.75% (※1) |
1.25% (※2) |
1.10% | 1.30% |
| 【あおぞら銀行 BANKのおすすめポイント】 普通預金金利は業界トップクラスなうえに、ほかのネット銀行とは違って「証券会社の口座と連携する」や「給与の振込口座に設定する」といった条件もなく好金利が適用されるのがメリット! また、コンビニATMでは出金手数料が発生してしまうが、郵便局やファミリーマートなどに設置されている「ゆうちょ銀行ATM」なら365日いつでも手数料無料なほか、他行あて振込手数料も月9回まで無料でお得! ※1 100万円を超えた分の普通預金は金利0.50%の適用。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「BANK The Giftスペシャル定期(BANK新規口座開設者限定)」適用時の金利。なお、期間中であっても募集総額が500億円に達した時点で取り扱い終了。 |
|||
| 【関連記事】 ■【あおぞら銀行 BANKの金利・手数料・メリットは?】普通預金金利が「定期預金レベル」でお得! ゆうちょ銀行ATMなら、週末でも出金手数料が無料に! |
|||
|
|
|||
| ◆ソニー銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.30% | 1.00% (※1) |
0.75% | 0.85% |
| 【ソニー銀行のおすすめポイント】 外貨に強いネット銀行。Visaデビット付きキャッシュカードの「Sony Bank WALLET」なら海外事務手数料が0円なので、海外での買い物がクレジットカードよりお得! 優遇プログラム「Club S」のステージなどにより、ATM出金手数料は月4回~無制限で無料、他行あて振込手数料は最大月11回まで無料! 毎月無料で決まった金額を、他行から手数料無料で入金できる「おまかせ入金サービス」も便利。 ※1 2026年3月1日までの期間限定キャンペーン「円定期特別金利」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【ソニー銀行の金利、手数料、メリットは?】外貨に強いネット銀行。Visaデビット搭載のSony Bank WALLETならクレジットカードよりお得に海外ショッピングが可能 ■「ソニー銀行」の顧客満足度調査の評価はなぜ高い? 手数料や金利で突出したメリットが見当たらなくてもなぜかユーザーから支持されている理由はどこだ!? |
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆東京スター銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.70% (※1) |
1.10% (※2) |
1.00% (※3) |
0.305% |
| 【東京スター銀行のおすすめポイント】 東京スター銀行を給与(バイトやパートも含む)または年金の受取口座に指定すると、普通預金金利が「0.30%⇒0.70%」に大幅アップするのが大きなメリット! さらに、コンビニATMの出金手数料は、月8回までなら24時間365日いつでも無料なので使いやすい。また、通常の定期預金のほか「スターワン1週間円預金」など、お得な金融商品を数多くラインナップ。 ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①東京スター銀行を給与振込や年金受取の口座に指定、②資産運用商品を300万円以上保有かつNISA口座保有&投資信託を購入。※2 新規に口座開設した人限定の「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」適用時の金利。※3「スターワン円定期預金プラス(インターネット限定)」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【東京スター銀行の金利・手数料・メリットは?】「ATM手数料」や「振込手数料」がお得なネット銀行。さらに、給与振込で普通預金金利が大幅にアップ! |
|||
| ◆auじぶん銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.51% (※1) |
1.05% (※2) |
0.61% | 0.71% |
| 【auじぶん銀行のおすすめポイント】 通常の普通預金金利は年0.31%だが、「三菱UFJ eスマート証券」または「SBI証券」と口座を連携すると+年0.10%、「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%、「au PAY アプリ」と口座を連携すると+年0.05%と、これらの条件を達成することで普通預金金利が年0.41%に! そのほか「じぶんプラス」のステージに応じて、コンビニATMでの出金手数料が最大月15回まで無料、他行あて振込手数料も最大月15回まで無料になるのも魅力! ※1 以下の①~③の条件をすべて達成した場合の金利。通常は年0.31%。①「au PAY アプリ」とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.05%。②「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%。③三菱UFJ eスマート証券またはSBI証券とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.10%。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「冬の1年もの特別金利キャンペーン」適用時の金利。au・UQ mobileユーザーの場合は+0.20%相当の現金がもらえる。 |
|||
| 【関連記事】 ■【auじぶん銀行の金利・手数料・メリットは?】KDDIの子会社なのでauユーザーには特におすすめ! 他行あて振込み手数料が最高で月15回まで無料に! ■auじぶん銀行は、振込手数料やATM出金手数料が最大で月15回まで無料!「じぶんプラス」のリニューアルでPontaポイントも貯まるようになり、さらにお得に! |
|||
| ◆楽天銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.38% (※1) |
0.40% | 0.60% | 0.70% |
| 【楽天銀行のおすすめポイント】 「楽天証券」との口座連動サービス「マネーブリッジ」を利用すれば、普通預金金利が最大0.38%に大幅アップ! しかも、楽天証券の申し込みページから「楽天証券の口座+楽天銀行の口座」を同時に開設できるので、普通預金金利が高金利な「マネーブリッジ」の利用も簡単! また、「マネーブリッジ」を利用しても特に投資をする必要はないので、とりあえず楽天証券の口座も開設して、楽天銀行の普通預金だけ利用してもOK! ※1「楽天証券」保有者の「マネーブリッジ」適用時。300万円を超えた分の普通預金は金利0.32%の適用。 |
|||
| 【関連記事】 ■【楽天銀行の金利・手数料・メリットは?】楽天証券との口座連動により普通預金金利がアップ!振込や口座振替などで「楽天ポイント」も貯まる! |
|||
|
|
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆UI銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.50% (※1) |
1.25% (※2) |
0.60% | 0.65% |
| 【UI銀行のおすすめポイント】 UI銀行は、2022年に東京きらぼしフィナンシャルグループが新たに開業した銀行で、1年~5年もの定期預金の金利はネット銀行の中でもトップクラスに高いのが魅力! また、コンビニATMの出金手数料は最大で月20回まで無料、他行あて振込手数料も最大で月20回まで無料でお得! ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①給与を「はたらくサイフ(普通預金)」で受けとった場合。②年金を「まもりのサイフ(普通預金)」で受け取った場合。③女性限定の「女神のサイフ(普通預金)」を利用した場合。※2 2026年5月31日までに新規口座開設した人向けの「4周年記念 新規口座開設者限定!定期預金キャンペーン」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■UI銀行は「高水準の金利&お得な手数料」でおすすめのスマホ特化型デジタルバンク!「東京きらぼしフィナンシャルグループ」から誕生した「UI銀行」の魅力を解説! ■【UI銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金&普通預金の金利にこだわる「スマホ特化」の銀行! 他行あて振込手数料が最大で月20回まで無料 |
|||
| ◆SBJ銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 最大0.30% (※1) |
1.35% (※2) |
1.40% (※2) |
1.45% (※2) |
| 【SBJ銀行のおすすめポイント】 ほかのネット銀行と比べても、定期預金金利の高さはトップクラス! さらに、セブン-イレブン(セブン銀行)やミニストップ(イオン銀行)、ファミリーマート(E-net)のATMなら、出金手数料が最低でも月10回まで無料でお得なほか、他行あて振込手数料も最低で月5回まで無料なので、月に何回も振込をする人にもおすすめ! ※1 通常の0.20%分の利息に加えて、月内の最低残高(上限1000万円)に対して0.10%分の追加利息を受け取れる「普通預金プラス」の場合。※2 新規口座開設者限定の「はじめての定期預金<はじめくん>」の場合。 |
|||
| 【関連記事】 ■SBJ銀行が業界No.1水準の“定期預金金利”や“手数料の安さ”を維持できる理由とは?「外資系の銀行に預金しても大丈夫?」という疑問や不安をSBJ銀行に直撃! ■【SBJ銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金がお得で、魅力的な商品も多い外資系銀行。ATM手数料や他行あて振込手数料の安さもメリット! |
|||
| ◆イオン銀行(イオンカードセレクト保有者) ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.22% (「イオン銀行Myステージ」の 「ゴールドステージ」の場合) |
0.45% | 0.45% | 0.70% |
| 【イオン銀行のおすすめポイント】 「イオン銀行Myステージ」で「ゴールドステージ」になれば、普通預金金利が0.22%に! しかも「イオンカードセレクト」で年間50万円以上を利用するなど、一定の条件を達成すると入手できる年会費無料のゴールドカード「イオンゴールドカードセレクト」を保有すれば、無条件で「ゴールドステージ」に到達できる特典が2024年3月にスタート。「ゴールドステージ」になれば、イオン銀行ATMの手数料は24時間いつでも何回でも無料なのはもちろん、他行ATMの入出金手数料と他行あて振込手数料がそれぞれ月3回まで無料になってお得! ※1 2026年2月11日までの期間限定キャンペーン「冬の定期預金キャンペーン」適用時(期間内にイオンカードセレクトに申し込んだ場合の金利)。 |
|||
| 【関連記事】 ■【イオン銀行の金利・手数料・メリットは?】イオン銀行利用者は「イオンカードセレクト」が必須!普通預金金利などがアップしてさらにお得に使える! ■イオンカードを作るなら「イオンカードセレクト」が一番お得! WAONチャージでのポイント2重取り&イオン銀行で預金金利が優遇されやすくなる特典も! |
|||
| ※ 100万円を預けた場合の2026年2月16日時点の金利(年率、税引前)。金利は税引き前の年利率であり、利息には20.315%(国税15.315%〈復興特別所得税含む〉+地方税5%)の税金がかかります。また、最新の金利は各銀行の公式サイトをご確認ください。 | |||