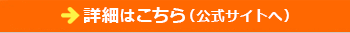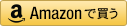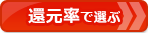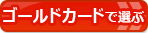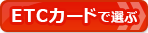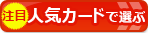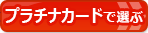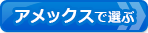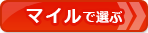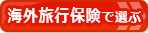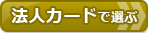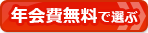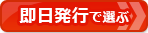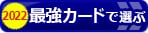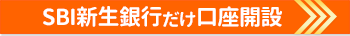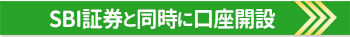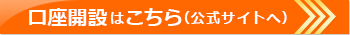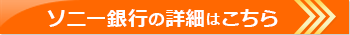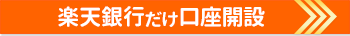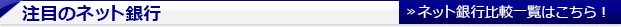みなさんは、日頃の買い物の際に、何で支払いをしていますか? 私自身は、クレジットカードか、後ほど詳しく紹介する「LINE Payカード」をメインで使用しています。現金決済の頻度は、それほど高くありません。
最近は、常に現金のみで決済するという人は、少数派になっていると思いますが、それでも「クレジットカードはどうしても好きになれない」という人は一定数存在しています。これまでに、「その場で支払いが完結する現金決済が好き」「借金は何となくイヤ」「口座にある以上にお金を使ってしまいそうで、使いすぎが怖い」「クレジットカード払いだと、家計簿がつけづらい」などの意見を、何度となく耳にしたこともあります。
私自身、「借金がイヤ」「使いすぎが怖い」などの気持ちのいずれも、わからないわけではありません。しかし、だからといって支出の大半を現金決済(固定費は銀行引き落とし)のみに頼っていると、損してしまいます。
それでは、クレジットカードが苦手な人は損をし続けるしかないのか? といえば、答えはNOです。今は、クレジットカード以外にも、お得な決済手段が続々と登場しているからです。それらの決済手段を利用すれば、ポイント還元などで得することができ、しかも借金をする必要もありません。
それでは、現金決済、クレジットカード決済以外におすすめの決済方法をいくつか挙げてみましょう。
①電子マネーを使う
現金、クレジットカード以外の決済手段として、もっとも普及しているのが、電子マネーです。電子マネーにもさまざまな種類があります。「Suica」や「nanaco」「WAON」「楽天Edy」などは、いわゆるプリペイド式の電子マネーなので、事前にチャージする必要があります。チャージした金額の分だけ、現金の代わりに使えます。
そのほか、「iD」や「QUICPay」といった電子マネーも有名ですが、これらはポストペイ式、つまりクレジットカードと同じく、利用金額を後払いする方式になっています。少額の買い物の際、サインレスで決済できる点が便利ですが、そもそも借金が嫌いな人には向いていません。
電子マネーは、自分がよく利用する店舗などで使えるものを選択するのが一番です。電子マネーの種類によってポイント還元率は異なりますが0.5~1%程度が一般的です。
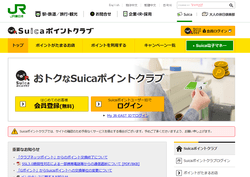 Suicaポイントクラブは、無記名のSuicaカードでは登録できない。
Suicaポイントクラブは、無記名のSuicaカードでは登録できない。拡大画像表示
なお、これは余談ですが、電子マネーの「Suica」は、事前にポイントプログラムに登録しておかないとポイントが貯まっていきません。ところが、実際には知らずに利用している人も多いようです。
というのも、「Suica」の発行枚数は5000万枚を超えていますが、「Suicaポイントプログラム」の会員数は、2015年4月時点でようやく200万人を突破した程度。つまり、「Suica」を利用しているものの、「Suica」を利用して貯まるポイントをドブに捨てている「Suica」ユーザーがかなり多いのです。「Suica」を利用している人は一度、確認してみてください。
電子マネー決済の話に戻りましょう。電子マネーを複数所有している場合、各電子マネーのアプリをダウンロードし、スマホで使えるようにすると便利です。iPhoneでは電子マネーのアプリを利用できませんが、Androidのスマホであれば「モバイルSuica」と「nanaco」と「楽天Edy」などのアプリを1台で利用できます。
私はiPhoneユーザーなので、電子マネーのアプリは使えていませんが、ポイントカードはアプリを利用しています。「Tポイント」「Ponta」「楽天スーパーポイント」「dポイント」という4大共通ポイントカードもアプリになっています。電子マネーにしろ、共通ポイントにしろ、カードをすべて持ち歩くとなると財布がかさばってしまうので、できる限りこうしたアプリを活用したいところです。
ちなみに、ポイントカードのアプリは、時々ログアウトしてしまったり、ディスプレイの明るさで読み込みがうまくいかない場合があります。私の利用環境だと、楽天スーパーポイントカードはすでにお財布に入れなくてもアプリで持ち歩きできる状態ですが、カードを手放してアプリに切り替える場合は、移行期間を設けた方がより安心だと覚えておいてください。
②ブランドデビットカードを使う
デビットカードとは、店頭で利用すると、すぐに使ったお金が銀行口座から引き落とされる決済ツールのこと。クレジットカードのように気軽に使えますが、決済はリアルタイムなので銀行の口座残高以上に利用することはできず、借金にはなりません。
デビットカードには、一部の限られた店舗などで手持ちの銀行キャッシュカードをそのまま使える「Jデビット」と、VISAやJCBの加盟店ならどこでも利用できる「ブランドデビット」の2種類があります。「Jデビット」は使える場所がわかりづらく、あまり普及していないのが実状なので、おすすめは「ブランドデビット」のほうです。
今のところ、「ブランドデビット」は「VISAデビット」が主流で、最近「JCBデビット」もちょこちょこ見かけるようになりました。「VISAデビット」はVISAの、「JCBデビット」はJCBの加盟店でそれぞれ利用できます。
「ブランドデビット」は、券面に「VISA」などと書かれているので、一見するとクレジットカードのように見えます。また、使い勝手もクレジットカードとほとんど変わりません。しかし、「年齢15歳以上」などの最低限の条件をクリアすれば、無審査で発行してもらえるのが魅力です。
クレジットカードが嫌いな人でも、海外旅行時など、クレジットカードの必要性を感じる場面はあるでしょう。「ブランドデビット」なら基本的に海外でも利用可能なので、一枚持っておくと非常に便利だと思います。
「ブランドデビット」のポイント還元率は0.3~0.5%程度が普通ですが、「楽天デビットカード(JCB)」のように還元率が1%というものも出てきました。これまでポイントの面ではクレジットカードに負けていたデビットカードですが、1%の還元率ならもはやクレジットカードと比較しても遜色がありません。
クレジットカードは借金になるから苦手、と言う人はデビットカードを検討してみてはどうでしょうか?
(※関連記事はこちら!⇒「デビットカード」のメリット増加で普及なるか? スーパーなどのレジがATM代わりに使える「キャッシュアウト(預金引き出し)」解禁の意味)
③「LINE Payカード」を使う
 「LINE Payカード」はおなじみのLINEのキャラクターが目印。他にも何種類かのデザインから選択できる。
「LINE Payカード」はおなじみのLINEのキャラクターが目印。他にも何種類かのデザインから選択できる。
今、私が一番お気に入りの決済ツールが「LINE Payカード」です。クレジットカード以外の決済手段の中で、「LINE Payカード」は最強と言っても過言ではないでしょう。
「LINE Payカード」は、JCBと提携しているプリペイドカードです。事前にチャージしておけば、国内外のJCB加盟店であればどこでもクレジットカードのように利用できます。前述した「JCBデビット」と混同してしまいそうですが、「JCBデビット」は銀行口座から即時で引き落とされるのに対し、「LINE Payカード」はあくまでお金をチャージしてから使うプリペイド式です。
「LINE Payカード」はLINEのユーザーであれば、審査なしで誰でもLINEのアプリから申し込め、入会金も年会費も無料というハードルの低さも魅力です。
JCBブランドの店で利用できるプリペイドカードということで、「LINE Payカード」はブランドデビットと電子マネーのいいとこ取りをしたような存在と言えます。つまり、幅広い場所で利用できる上に、プリペイドなので際限なく使うことができず、比較的“使いすぎる可能性が少ない”のです。
そして、最大のメリットが還元率の高さです。「LINE Payカード」のポイント還元率は2%と、大半のクレジットカードより高い設定になっています(貯まるのは「LINE」ポイントです)。年会費無料でありながら、どこで使っても2%貯まるのはかなりありがたいですね。
私は、日常的に「LINE Payカード」を使っていますが、レストラン、スーパー、カフェ、ドラッグストアなど、大体どこでも利用できています。JCB加盟店は国内だけでも約900万店に及ぶため、日常的にはほとんど不自由を感じないのではないでしょうか。一部の公共料金や税金の支払いにも充てられるので、当初予想していたよりも使い道が広い印象です(ただし、基本的には公共料金の毎月自動引き落としには対応していません)。
そのため、今では「LINE Payカード」で支払えない固定費はクレジットカード払いにして(ちなみに、私のメインカードは、「楽天カード」と「ソラチカカード(ANA To Me CARD PASMO JCB)」、そして今は新規発行されていない「SoftBankカード」です) 、普段の買い物の支払いはほとんど「LINE Payカード」を活用しています。プリペイドカードだとしょっちゅうチャージするのが手間だと思われがちですが、銀行口座を登録しておけばオートチャージも可能です。
| ■楽天カード | ||
| 還元率 | 1.0~3.0% (通常時は還元率1.0%、楽天市場や楽天ブックス利用時は還元率3.0%に。なお、楽天市場・楽天ブックス利用時に獲得できる+1.0%分はポイント付与の翌月末までの期間限定ポイント) |
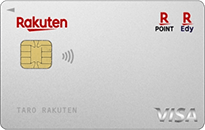 |
| 発行元 | 楽天カード | |
| 国際ブランド | VISA、Master、JCB、AMEX | |
| 年会費 | 永年無料 | |
| 家族カード | あり(年会費無料) | |
| ポイント付与対象の 電子マネー |
楽天Edy(還元率0.5%) | |
| 関連記事 | ◆【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】「おすすめクレジットカード」を2人の専門家が選出!全8部門の“2023年の最優秀カード”を詳しく解説!(メインカード部門) ◆「楽天カード」の4券種の中で、もっとも得するカードを選ぶ方法をカード専門家が解説! ゴールド、プレミアム、ブラックの特典を比較して最適な券種を選ぼう |
|
| 楽天カードへの新規入会&利用でポイントがもらえるキャンペーン中! | ||
貯まったLINEポイントは、LINEのサービスに利用できるほか、「LINE Payカード」にチャージできるので、また買い物の代金に充当できます。そのほか、「nanaco」や「Ponta」、「Amazonギフト券」などと交換もできるので、使い勝手はいいでしょう。ただ、交換レートが悪いポイントもあるので、私の一番のおすすめは「LINE Payカード」にチャージして使うことです。
ちなみに、LINEポイントの有効期限は、最後に取得した日から180日間と、やや短めです。継続的に使い続けていれば実質無期限になるので失効しないのですが、まったく使わないでいると半年ほどでそれまでのポイントがすべて失効するので注意しましょう。
その他の「LINE Payカード」で特徴的なのは、「LINE Payカード」所有者同士であれば、簡単に送金ができることです(事前に銀行口座の登録が必要です)。この機能を使えば、ワリカンが簡単になる点が便利です。
④プレミアム商品券を使う
さて、ここまではクレジットカード以外の決済ツールについて紹介してきました。最後にピックアップしたいのは、まったく毛色が異なる「プレミアム商品券」です。
 品川区のプレミアム商品券の見本。
品川区のプレミアム商品券の見本。拡大画像表示
「プレミアム商品券」とは、自治体が発行する額面よりお得な商品券のことで、地元のさまざまなお店で利用することができます。地元の商店街連合などが販売を手掛けていることも多いようです。販売方法は、どこかに並んで買うこともあれば、ネットで抽選のこともあります。
どれほどお得かについても、発行する自治体ごとに異なるのですが、多くは「1万円で買って、1万1000円分使える」というようなイメージでしょうか。上乗せ(プレミアム)分は10~20%程度が平均的です。なお、「プレミアム商品券」を購入できるのは、原則としてその自治体に居住しているか、勤務先がある、などの条件を満たしている人のみです。
2015年には、政府が地方創生の一環で補助金を出したため、全国の97%の自治体で「プレミアム商品券」が発行され、ちょっとしたブームになりました。2016年は、前年度に比べるとそこまでの注目度ではないのですが、お得であることに変わりはないので、知らなかった人はチェックしてみてもいいと思います。
「プレミアム商品券」の発行時期や、商品券一枚あたりの価格は自治体ごとに異なります。また、利用できる範囲も異なり、地元の商店街でしか使えないこともあれば、駅ビルやイトーヨーカドーなどのショッピングセンター、コンビニでの買い物も対象、という具合に、非常に利便性の高い商品券もあります。自分が買える自治体の商品券情報を調べてみましょう。
私の場合は、昨年文京区の「プレミアム商品券」を購入しましたが、発売日には長い列ができていました。1万円分(500円券×24枚=1万2000円)を購入したところ、受付の方に「それだけでいいの?」と驚かれました。たしかに、長時間並んで買うわけですから、用途を決めて5万円分、10万円分とまとめ買いした方が賢いと感じました。
購入した「プレミアム商品券」は、地元の商店街で使えるものでしたが、レストランやスーパーも対象になっていたので、使い道にはまったく困りませんでした。ただ、おつりが出ないので、比較的大きな買い物をするときなどに使うのがいいのかもしれません(とはいえ、大抵は500円券なので普通の買い物でも利用できます)。
おつりが出ないのはどの自治体の「プレミアム商品券」でも共通しているので、注意点の一つと考えておいたほうがいいでしょう。その他の注意点としては、商品券だからといってムダ遣いをしないことに尽きます。
商品券の形になっていると、現金よりもついムダ遣いしてしまう、という人も多いようです。よって、「プレミアム商品券」を入手する前に、「プレミアム商品券」で何を買うか、目的を決めておくといいでしょう。「地元のあの店で自転車を買う」「エアコンを買い換える」といった感じですね。
また、プレミアム商品券は、有効期限が半年程度と短い場合も多いので、買ったまま忘れてしまわないように注意が必要です。
さて、ここまでただ現金払いする以外の決済方法を紹介してきました。クレジットカードが苦手な人でも、取り入れられるものが多かったのではないかと思います。現金払い中心になっている人は、まず「LINE Payカード」の申し込みをしたり、自分の自治体の「プレミアム商品券」についてネットで調べたり、といったところから変化を起こしてみましょう。
(取材・構成/元山夏香)
『その節約はキケンです――お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか』(祥伝社)
●「家計簿」には大きな落とし穴がある!
●「固定費」を意識するとお金が貯まる
●底値より大事なのは「自分にとっての買い時」
●クレジットカード、メインとサブで差をつける……
「実は、ズボラな人ほどお金が貯まる」という節約の新常識を伝授!
【※還元率が高い「おすすめクレジットカード」はこちら!】
⇒【クレジットカードおすすめ比較】還元率の高さで選ぶ「おすすめクレジットカード」はコレだ! 高還元&年会費無料の12枚のカードを紹介!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
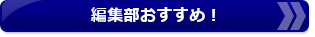 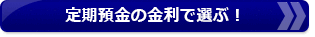 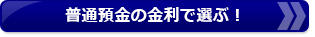 |
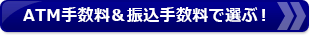 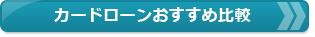 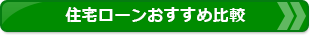 |
| 【2026年2月16日時点】 ■編集部おすすめのネット銀行はこちら! |
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆SBI新生銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.50% (※1) |
0.85% (※2) |
1.00% | 1.20% |
| 【SBI新生銀行のおすすめポイント】 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用すると普通預金金利が0.50%に大幅アップ! しかも「SBIハイパー預金」を利用すると「ステップアッププログラム」のステージが最上位の「ダイヤモンド」になり、提携コンビニATMの出金手数料が何回でも無料、他行あて振込手数料が月10回まで無料になる特典なども受けられてお得! ちなみに「SBIハイパー預金」を利用したからといって、投資などをする必要はないので安心しよう。そのほか、新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」なら、3カ月もの定期預金の金利が大幅アップ! また、他行からの振込入金などで現金がもらえる「キャッシュプレゼントプログラム」もお得。 ※1 SBI証券との口座連携サービス「SBIハイパー預金」を利用した場合の金利。※2 新規に口座開設した人限定の「スタートアップ円定期預金」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【SBI新生銀行の金利・手数料・メリットは?】SBI証券との口座連携「SBIハイパー預金」の利用で、普通預金金利アップ&振込手数料が月10回まで無料! |
|||
| ◆あおぞら銀行 BANK ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.75% (※1) |
1.25% (※2) |
1.10% | 1.30% |
| 【あおぞら銀行 BANKのおすすめポイント】 普通預金金利は業界トップクラスなうえに、ほかのネット銀行とは違って「証券会社の口座と連携する」や「給与の振込口座に設定する」といった条件もなく好金利が適用されるのがメリット! また、コンビニATMでは出金手数料が発生してしまうが、郵便局やファミリーマートなどに設置されている「ゆうちょ銀行ATM」なら365日いつでも手数料無料なほか、他行あて振込手数料も月9回まで無料でお得! ※1 100万円を超えた分の普通預金は金利0.50%の適用。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「BANK The Giftスペシャル定期(BANK新規口座開設者限定)」適用時の金利。なお、期間中であっても募集総額が500億円に達した時点で取り扱い終了。 |
|||
| 【関連記事】 ■【あおぞら銀行 BANKの金利・手数料・メリットは?】普通預金金利が「定期預金レベル」でお得! ゆうちょ銀行ATMなら、週末でも出金手数料が無料に! |
|||
|
|
|||
| ◆ソニー銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.30% | 1.00% (※1) |
0.75% | 0.85% |
| 【ソニー銀行のおすすめポイント】 外貨に強いネット銀行。Visaデビット付きキャッシュカードの「Sony Bank WALLET」なら海外事務手数料が0円なので、海外での買い物がクレジットカードよりお得! 優遇プログラム「Club S」のステージなどにより、ATM出金手数料は月4回~無制限で無料、他行あて振込手数料は最大月11回まで無料! 毎月無料で決まった金額を、他行から手数料無料で入金できる「おまかせ入金サービス」も便利。 ※1 2026年3月1日までの期間限定キャンペーン「円定期特別金利」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【ソニー銀行の金利、手数料、メリットは?】外貨に強いネット銀行。Visaデビット搭載のSony Bank WALLETならクレジットカードよりお得に海外ショッピングが可能 ■「ソニー銀行」の顧客満足度調査の評価はなぜ高い? 手数料や金利で突出したメリットが見当たらなくてもなぜかユーザーから支持されている理由はどこだ!? |
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆東京スター銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.70% (※1) |
1.10% (※2) |
1.00% (※3) |
0.305% |
| 【東京スター銀行のおすすめポイント】 東京スター銀行を給与(バイトやパートも含む)または年金の受取口座に指定すると、普通預金金利が「0.30%⇒0.70%」に大幅アップするのが大きなメリット! さらに、コンビニATMの出金手数料は、月8回までなら24時間365日いつでも無料なので使いやすい。また、通常の定期預金のほか「スターワン1週間円預金」など、お得な金融商品を数多くラインナップ。 ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①東京スター銀行を給与振込や年金受取の口座に指定、②資産運用商品を300万円以上保有かつNISA口座保有&投資信託を購入。※2 新規に口座開設した人限定の「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」適用時の金利。※3「スターワン円定期預金プラス(インターネット限定)」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■【東京スター銀行の金利・手数料・メリットは?】「ATM手数料」や「振込手数料」がお得なネット銀行。さらに、給与振込で普通預金金利が大幅にアップ! |
|||
| ◆auじぶん銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.51% (※1) |
1.05% (※2) |
0.61% | 0.71% |
| 【auじぶん銀行のおすすめポイント】 通常の普通預金金利は年0.31%だが、「三菱UFJ eスマート証券」または「SBI証券」と口座を連携すると+年0.10%、「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%、「au PAY アプリ」と口座を連携すると+年0.05%と、これらの条件を達成することで普通預金金利が年0.41%に! そのほか「じぶんプラス」のステージに応じて、コンビニATMでの出金手数料が最大月15回まで無料、他行あて振込手数料も最大月15回まで無料になるのも魅力! ※1 以下の①~③の条件をすべて達成した場合の金利。通常は年0.31%。①「au PAY アプリ」とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.05%。②「au PAY カード」の利用代金がauじぶん銀行の口座から引き落とされると+年0.05%。③三菱UFJ eスマート証券またはSBI証券とauじぶん銀行の口座を連携すると+年0.10%。※2 2026年2月28日までの期間限定キャンペーン「冬の1年もの特別金利キャンペーン」適用時の金利。au・UQ mobileユーザーの場合は+0.20%相当の現金がもらえる。 |
|||
| 【関連記事】 ■【auじぶん銀行の金利・手数料・メリットは?】KDDIの子会社なのでauユーザーには特におすすめ! 他行あて振込み手数料が最高で月15回まで無料に! ■auじぶん銀行は、振込手数料やATM出金手数料が最大で月15回まで無料!「じぶんプラス」のリニューアルでPontaポイントも貯まるようになり、さらにお得に! |
|||
| ◆楽天銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.38% (※1) |
0.40% | 0.60% | 0.70% |
| 【楽天銀行のおすすめポイント】 「楽天証券」との口座連動サービス「マネーブリッジ」を利用すれば、普通預金金利が最大0.38%に大幅アップ! しかも、楽天証券の申し込みページから「楽天証券の口座+楽天銀行の口座」を同時に開設できるので、普通預金金利が高金利な「マネーブリッジ」の利用も簡単! また、「マネーブリッジ」を利用しても特に投資をする必要はないので、とりあえず楽天証券の口座も開設して、楽天銀行の普通預金だけ利用してもOK! ※1「楽天証券」保有者の「マネーブリッジ」適用時。300万円を超えた分の普通預金は金利0.32%の適用。 |
|||
| 【関連記事】 ■【楽天銀行の金利・手数料・メリットは?】楽天証券との口座連動により普通預金金利がアップ!振込や口座振替などで「楽天ポイント」も貯まる! |
|||
|
|
|||
| 普通預金金利 (年率、税引前) |
定期預金金利(年率、税引前) | ||
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| ◆UI銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.50% (※1) |
1.25% (※2) |
0.60% | 0.65% |
| 【UI銀行のおすすめポイント】 UI銀行は、2022年に東京きらぼしフィナンシャルグループが新たに開業した銀行で、1年~5年もの定期預金の金利はネット銀行の中でもトップクラスに高いのが魅力! また、コンビニATMの出金手数料は最大で月20回まで無料、他行あて振込手数料も最大で月20回まで無料でお得! ※1 次の条件のうち“いずれか1つ”を達成した場合の金利。①給与を「はたらくサイフ(普通預金)」で受けとった場合。②年金を「まもりのサイフ(普通預金)」で受け取った場合。③女性限定の「女神のサイフ(普通預金)」を利用した場合。※2 2026年5月31日までに新規口座開設した人向けの「4周年記念 新規口座開設者限定!定期預金キャンペーン」適用時の金利。 |
|||
| 【関連記事】 ■UI銀行は「高水準の金利&お得な手数料」でおすすめのスマホ特化型デジタルバンク!「東京きらぼしフィナンシャルグループ」から誕生した「UI銀行」の魅力を解説! ■【UI銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金&普通預金の金利にこだわる「スマホ特化」の銀行! 他行あて振込手数料が最大で月20回まで無料 |
|||
| ◆SBJ銀行 ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 最大0.30% (※1) |
1.35% (※2) |
1.40% (※2) |
1.45% (※2) |
| 【SBJ銀行のおすすめポイント】 ほかのネット銀行と比べても、定期預金金利の高さはトップクラス! さらに、セブン-イレブン(セブン銀行)やミニストップ(イオン銀行)、ファミリーマート(E-net)のATMなら、出金手数料が最低でも月10回まで無料でお得なほか、他行あて振込手数料も最低で月5回まで無料なので、月に何回も振込をする人にもおすすめ! ※1 通常の0.20%分の利息に加えて、月内の最低残高(上限1000万円)に対して0.10%分の追加利息を受け取れる「普通預金プラス」の場合。※2 新規口座開設者限定の「はじめての定期預金<はじめくん>」の場合。 |
|||
| 【関連記事】 ■SBJ銀行が業界No.1水準の“定期預金金利”や“手数料の安さ”を維持できる理由とは?「外資系の銀行に預金しても大丈夫?」という疑問や不安をSBJ銀行に直撃! ■【SBJ銀行の金利・手数料・メリットは?】定期預金がお得で、魅力的な商品も多い外資系銀行。ATM手数料や他行あて振込手数料の安さもメリット! |
|||
| ◆イオン銀行(イオンカードセレクト保有者) ⇒詳細ページはこちら! | |||
| 0.22% (「イオン銀行Myステージ」の 「ゴールドステージ」の場合) |
0.45% | 0.45% | 0.70% |
| 【イオン銀行のおすすめポイント】 「イオン銀行Myステージ」で「ゴールドステージ」になれば、普通預金金利が0.22%に! しかも「イオンカードセレクト」で年間50万円以上を利用するなど、一定の条件を達成すると入手できる年会費無料のゴールドカード「イオンゴールドカードセレクト」を保有すれば、無条件で「ゴールドステージ」に到達できる特典が2024年3月にスタート。「ゴールドステージ」になれば、イオン銀行ATMの手数料は24時間いつでも何回でも無料なのはもちろん、他行ATMの入出金手数料と他行あて振込手数料がそれぞれ月3回まで無料になってお得! ※1 2026年2月11日までの期間限定キャンペーン「冬の定期預金キャンペーン」適用時(期間内にイオンカードセレクトに申し込んだ場合の金利)。 |
|||
| 【関連記事】 ■【イオン銀行の金利・手数料・メリットは?】イオン銀行利用者は「イオンカードセレクト」が必須!普通預金金利などがアップしてさらにお得に使える! ■イオンカードを作るなら「イオンカードセレクト」が一番お得! WAONチャージでのポイント2重取り&イオン銀行で預金金利が優遇されやすくなる特典も! |
|||
| ※ 100万円を預けた場合の2026年2月16日時点の金利(年率、税引前)。金利は税引き前の年利率であり、利息には20.315%(国税15.315%〈復興特別所得税含む〉+地方税5%)の税金がかかります。また、最新の金利は各銀行の公式サイトをご確認ください。 | |||