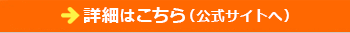中国政府がビットコイン取引所の閉鎖を検討?
先週金曜日、「中国政府が中国国内のすべてのビットコイン取引所の閉鎖を検討している」という記事が、中国の金融メディア「財新」に掲載されました。
それによると、2016年に中国人民銀行内に設置された仮想通貨ワーキング・グループが、このほど報告書を提出したのだそうです。現時点では、その報告書の内容は明らかになっておらず、その報告書の政策提言は、まだ検討中の段階であり決定ではありません。
このニュースとは別に、9月22には中国政府がICO(イニシャル・コイン・オファリング)、つまり新たな仮想通貨の発行を禁止する決定を下したということを「財新」が報じました。
【中国政府の決定】
・ICO⇒全面禁止
・ビットコイン取引所⇒閉鎖を検討中
最終的にどういう結論になるかは、これを書いている時点ではわかりませんが、中国政府が仮想通貨に対する規制を強化する方向に傾いている事は明白です。
中国のビットコイン取引所が閉鎖されても、
それはビットコインの死を意味しない
さて、ここで皆さんに理解して頂きたいことは「中国のビットコイン取引所が閉鎖されても、それはビットコインの死を意味しない」という点です。
ビットコインの取引に占める中国の割合が高いことは事実です。しかしビットコインは、取引所を通じなくても売り買いすることが出来ます。つまり、ビットコイン取引所が提供しているのはコンビニエンス(利便性)であり、「取引所が無くなると、ちょっと不便になる」というだけの事です。
ビットコインの仕組みである
「分散型通貨」の意味とは?
よく「ビットコインは分散型通貨だ」と言われます。今回のような事件があると、この「分散型通貨」の持つ意味をしっかり理解する必要が一段と高まります。そこでわかりやすいように噛み砕いて説明します。
ビットコインは「パスワードで保護された元帳」に例えられます。それでもまだイメージしにくいなら、ちょっと乱暴な例えになりますが、「エクセル・スプレッドシートのようなもの」を想像して頂ければ良いでしょう。
エクセル・スプレッドシートのような電子的な帳簿は、コピペや改ざんが簡単なので、何らかの方法でそのような不正ができないようにする工夫が必要です。
分散型通貨の意味は
「トラ・トラ・トラ」で理解しろ!
そこでビットコインが援用した不正防止の手法は、「ビットコインの売買があるたびに、広くその事実を世界に対して発信してしまう」というやり方です。希望する人は、だれでもその新しい取引が記帳された記録を入手することができ、それが正しいか吟味することが許されています。
この部分も、ちょっとわかりにくいと思うので、たとえ話で説明します。
第二次世界大戦初期は、まだ電信の周波数ホッピング(=周波数をこまめに変えること)技術が発達していなかったので、ワイヤレス通信は、味方だけでなく敵にも簡単に傍受されました。そのため、味方のコミュニケーションの内容を敵に知られないようにするためには、メッセージを暗号化する必要がありました。
真珠湾攻撃で奇襲に成功した場合、「トラ・トラ・トラ」というメッセージを使用することが事前に示し合わされていたのはその例です。
これと同じような感覚で、ビットコインの取引記録も、取引のたびごとに、世界中にばら撒かれているとイメージしてください。
すると、悪意を持ったユーザーが、その取引記録のひとつやふたつを改ざんしても、世界にばら撒かれた元帳のすべてを改ざんすることは、とうていムリなのです。
このように、ばら撒かれた状態を「ディストリビューテッド」、すなわち「分散している」と表現します。よく「ビットコインは分散型通貨だ」と形容されるわけですが、その意味するところは「ワイヤレス通信のように、誰にでも傍受できてしまう」ということです。
そして「ひとつ、その取引が純正かどうか、検証してやろう」と思う人は、誰でもそれを検査することが出来るのです。その検証作業を「マイニング」と言います。そのような検証作業をした結果、過半数の検証結果が「この取引は純正だ」と判断したら、その取引は正式に成立したことになります。
つまり、ビットコインの取引は、かならずしも株式市場のような取引所を介する必要は無いのです。
ビットコイン取引所は、
観光客目当ての「お団子屋」にすぎない
それではビットコイン取引所の意義は、何でしょうか?
私はこれを説明するときに、神社やお寺の前に自然発生的に出来る門前町、あるいは、お城の周辺に出来る城下町で説明することにしています。
つまり、ビットコインがお寺やお城であれば、そこへ集まってくる観光客目当ての旅籠屋(はたごや)やお団子屋が開業するわけです。
ビットコイン・エクスチェンジは「取引所」と訳されますが、それはあくまでも、民間が勝手にやっている私設の取引所です。また、ビットコイン・ウォレット会社というのもありますが、これは預かり所だと思えば良いでしょう。
これらは、いずれも仮想通貨の取引を便利にするための付帯的サービスに過ぎず、その意味において、ちょっと一息いれるお団子屋と変わらないのです。
つまり、中国政府がやっていることは「お団子屋のお取り潰し」に他なりません。門前町に出来たお団子屋を政府の意向で取り潰しにしたところで、それは周辺的かつ付帯的なサービスを取り押さえたに過ぎず、肝心のビットコインそのものを根絶させることにはならないのです。
ビットコインはひとつの国の意向に左右されない
真にグローバルな仮想通貨
すでにこれまでに説明してきたように、ビットコインには中心がありません。だからある国がビットコインを禁止したところで、取引が他の地域へ移るだけのことなのです。
もっと言えば、「お団子屋」や「旅籠屋」のサービスは、世界のどこでも出来るわけであり、それが中国である必要は無いのです。
さて、「お団子屋」や「旅籠屋」のサービスというと、スモール・ビジネスをイメージしてしまいますが、実は金融サービスというのは巨大な産業です。早い話、JPモルガン・チェースやゴールドマン・サックスだって「お団子屋の大きいやつ」に過ぎないのです!
世の中のあらゆるおカネは
「自由な方、自由な方へと流れる」
おカネの習性として、それは「自由な方、自由な方へと流れる」ことが知られています。すると、いま中国で仮想通貨ががんじがらめに規制され始めているということは、仮想通貨の付帯サービスを育もうとしている他の国々にとってチャンスです。
幸い、日本は世界でも最先端の仮想通貨法を整備しています。つまり日本政府の基本方針として「楽市楽座で、どんどん仮想通貨のお団子屋を出してオッケー!」ということが明示されているのです。
日本は、自動車メーカーなどは国際競争力がありますが、こと金融サービスになると国際競争力はありません。その証拠に、金融サービスの国際収支では日本は赤字です。
しかし仮想通貨では日本が世界に先行できる環境が整いつつあります。
そう考えると、今回の中国の仮想通貨に対する締め付け強化は、日本にとってまたとないチャンスかも知れないのです。
| 【今週のピックアップ記事!】 | |
| ■ | ビットコインの価格は5年後に「6倍以上」に上がる!? ビットコインETFの登場で、個人投資家中心の市場に機関投資家の莫大な資金が流入して一層活況になる! |
| ■ | 新仮想通貨「BAT」の売り出し成功は、証券会社が不要となる時代を暗示!「BAT」や「VALU」などブロックチェーン使用の新サービスが持つ意味とは? |
【※米国株を買うならこちらの記事もチェック!】
⇒米国株投資で注意が必要な「為替」と「税金」とは?「特定口座(源泉徴収あり)」か「NISA口座」で投資をして、口座内に「米ドル」を残さないのがポイント!
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
【2026年2月1日時点】
「米国株」取扱数が多いおすすめ証券会社 |
| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約4900銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
|
【SBI証券のおすすめポイント】 |
|
| 【関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社! |
|
| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
| 【楽天証券おすすめポイント】 米国、中国(香港)、アセアン各国(シンガポール、タイ、マレーシアなど)と幅広い銘柄がそろっており、米国株の信用取引も利用可能! 指定の米国ETF15銘柄については買付手数料が無料で取引ができるのもお得。米ドル⇔円の為替取引が0円と激安! さらにNISA口座なら、米国株の売買手数料が完全無料(0円)。米国株の注文受付時間が土日、米国休場を含む日本時間の朝8時~翌朝6時と長いので、注文が出しやすいのもメリット。米国株式と米国株価指数のリアルタイム株価、米国株オーダーブック(板情報)、さらに米国決算速報を無料で提供。ロイター配信の米国株個別銘柄ニュースが、すぐに日本語に自動翻訳されて配信されるのもメリット。米国株の積立投資も可能。米国株の貸し出しで金利がもらえる「貸株サービス」も行っている。 |
|
| 【関連記事】 ◆【楽天証券おすすめのポイントは?】トレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!投資信託や米国や中国株などの海外株式も充実! ◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい! |
|
| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約5100銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
| 【マネックス証券のおすすめポイント】 外国株式の取り扱い銘柄数はトップクラス! また、米国株の買付時の為替手数料が0円(売却時は1ドルあたり25銭)となるキャンペーンが長期継続しており、実質的な取引コストを抑えることができる。さらに、外国株取引口座に初回入金した日から20日間は、米国株取引手数料(税込)が最大3万円がキャッシュバックされる。米国ETFの中で「米国ETF買い放題プログラム」の対象22銘柄は、実質手数料無料(キャッシュバック)で買付が可能。米国株の積立サービス「米国株定期買付サービス(毎月買付)」は25ドルから。コツコツ投資したい人に便利なサービス。米国株は、時間外取引に加えて店頭取引サービスもあり日本時間の日中でも売買できる。しかもNISA口座なら、日本株の売買手数料が無料なのに加え、外国株(海外ETF含む)の購入手数料も全額キャッシュバックされて実質無料! 企業分析機能も充実しており、一定の条件をクリアすれば、銘柄分析ツール「銘柄スカウター米国株」「銘柄スカウター中国株」が無料で利用できる。 |
|
| 【関連記事】 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】「単元未満株」の売買手数料の安さ&取扱銘柄の多さに加え、「米国株・中国株」の充実度も業界最強レベル! |
|
| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約5000銘柄以上 | <現物取引>約定代金の0.495%(上限22米ドル)/<信用取引>約定代金の0.33%(上限16.5米ドル) |
| 【松井証券のおすすめポイント】 米国株の売買手数料は他の大手ネット証券と同水準なうえ、為替手数料は完全無料(0円)とお得!さらにNISA口座では、米国株の取扱手数料が無料に! 米国株でも信用取引が可能で手数料が業界最安水準。2025年7月から米国株のプレマーケットに対応し、日本時間18時(夏時間は17時)から取引が可能になったのもメリット。さらに投資情報ツール「マーケットラボ米国株」や専用の取引ツール、リアルタイム株価が無料、夜間での取引に便利な返済予約注文(IFD注文)、米国株専用ダイヤル「米国株サポート」や「株の取引相談窓口(米国株)」などが特徴となっている。また、米国株専用の「松井証券 米国株アプリ」は、リアルタイム株価の表示に加え、米国株の情報収集から資産管理、取引までスマホで対応可能だ。 |
|
| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは?】1日50万円以下の株取引は手数料0円(無料)! その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」! |
|
| ◆moomoo証券 ⇒詳細情報ページへ | |
| 米国株の取扱銘柄数 | 取扱手数料(税込) |
| 約6300銘柄以上 | <現物・信用取引>約定代金の0.132%(上限22米ドル) |
| 【moomoo証券のおすすめポイント】 米国やカナダ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなどグローバルにサービスを展開するネット証券。米国株には特に力を入れており、取扱銘柄数は業界トップクラス。売買手数料も大手ネット証券の4分の1程度だ(ただし売買手数料の上限は22米ドルと他社と同水準)。さらに、為替手数料が無料なので、米国株の売買コストのお得さでは頭ひとつ抜け出している。米国株に関するデータや情報も充実。最大上下60本の板情報や過去20年分の財務データ、大口投資家の売買動向など、銘柄分析に役立つさまざまな情報が無料で利用できる。24時間取引に対応しているので、日本時間の昼間にも売買が可能。1ドルから米国株を買うこともできる。取引アプリには対話型AIの「moomoo AI」を搭載。米国株の基礎知識から米国市場の動向、銘柄分析まであらゆる質問に答えてくれるので、米国株初心者には力強い味方となるだろう。 |
|
| 【関連記事】 ◆【moomoo証券のおすすめポイントを解説】米国株投資家には特におすすめの米国生まれのネット証券! プロレベルの高機能ツールやAIツールも魅力! |
|
| ※ 本記事の情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新の情報は各社の公式サイトでご確認ください。 |